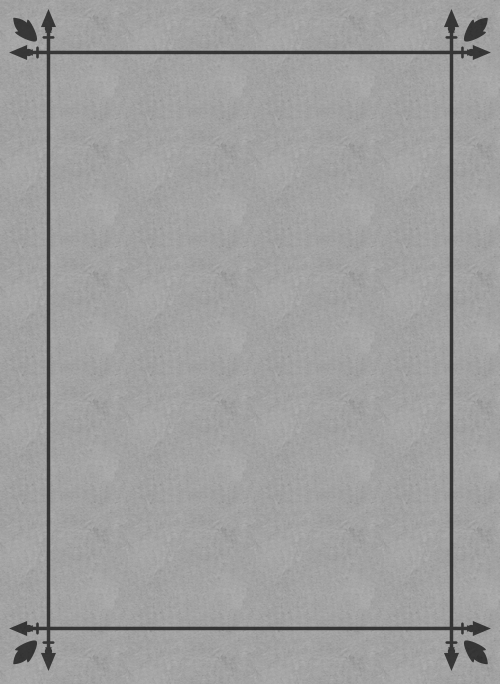「キリエさん、お疲れっす~……おや、そちらは?」
キリエさんに対して気軽に挨拶をした魔族は、背に生えた二対の羽をゆらめかせながら宙に浮いていた。
鋭い目つきでこちらを睨みつけている。
灰色の体色に小柄な体躯、特徴的にガーゴイルか?
文献で見たことがある。
確か、魔族の中では、人間界を空から偵察する役割を担っていたはずだ。
人間界でも度々目撃情報が出回ったりする。
「こちらは大切なお客様です。無礼は許しませんよ?」
「ほうほう。魔人のお客人っすな! こりゃまた珍しい」
ガーゴイルの魔族はぐっと近寄ってくると、下から上まで俺の全身をじっくりと凝視してきた。
殺意や悪意は感じないが、こんなにマジマジと見られると少し不気味に思える。
「ぶらぶらしていないで早く偵察へお行きなさい」
「相変わらずお堅いっすね……んじゃ、またな、魔人さんよ。オレッちはガーゴイルのアマンドだ。
目つきが悪く見えるのは生まれつきだから勘弁してくれよな。別に睨んでるわけじゃないからな~?」
ガーゴイルの魔族ことアマンドは、打って変わって朗らかな笑みを浮かべて手を振ってきた。
鋭い八重歯を見せて笑っており、先ほどまでの不気味さは消えてなくなっている。
「……なんなんだ」
俺は去り行くアマンドの背中を見ながら口にした。
父さんやキリエさんも魔族ではあるが、人間とよく似た容姿の魔族ではなく、魔族らしい外見の魔族は初見だった。
「ああ見えても、アマンドさんはガーゴイル偵察部隊の総隊長です。本人も言及しておられましたが、目つきが悪いのは生まれつきだそうなのであまりお気になさらず。基本的には誰にでも友好的な方ですし、ソロモンさんに危害を加えるようなことはないでしょう」
「魔族ってみんなあんな感じなんですか?」
人間の立場から考えると、キリエさんの言葉を鵜呑みにするのには無理があった。
俺が生まれるずっと前から、人間と魔族は憎しみ合う存在として認識されてきたし、それは今も変わっていないからだ。
「基本的に、魔族は人間への嫌悪感を殆ど抱いておりません。ですが、人間は私たち魔族の見た目が怖いのでしょう? なので、ソロモンさんのような両種の血を持つ存在は非常に希少なのです。
人間と魔族の今後のために必ず活躍する時が来るでしょう」
よくわからないが、想像していたような危険な展開にはならないような気がする。
むしろ、キリエさんとアマンドの様子を見た限りだと、人間同士よりもかなり落ち着いた会話だった。
冒険者は皆血の気が多く、一介のギルドの受付嬢やその辺にいる小さな子供だって、魔族やモンスターを殺せ殺せとうるさかった。
皆が魔王率いる魔族とモンスターを根絶やしにしようと躍起になっていたのをよく覚えている。例に漏れず、俺もその一人だった。
でも、何か違和感がある。
魔族である彼らはまるで気にも留めていないように思えた。
「……人間が一方的に恨んでいるだけで、魔族は人間と友好関係を築きたいってことか……まさかな」
俺は一つの結論に辿り着いたが、それはあまりにも人間が愚かで浅はかな生き物であることを露呈させるものだったので信じきれなかった。
もしかすると、人間が知らないだけで、両者の間には盛大な勘違いという名の深い溝があるのかもしれないな。
キリエさんに対して気軽に挨拶をした魔族は、背に生えた二対の羽をゆらめかせながら宙に浮いていた。
鋭い目つきでこちらを睨みつけている。
灰色の体色に小柄な体躯、特徴的にガーゴイルか?
文献で見たことがある。
確か、魔族の中では、人間界を空から偵察する役割を担っていたはずだ。
人間界でも度々目撃情報が出回ったりする。
「こちらは大切なお客様です。無礼は許しませんよ?」
「ほうほう。魔人のお客人っすな! こりゃまた珍しい」
ガーゴイルの魔族はぐっと近寄ってくると、下から上まで俺の全身をじっくりと凝視してきた。
殺意や悪意は感じないが、こんなにマジマジと見られると少し不気味に思える。
「ぶらぶらしていないで早く偵察へお行きなさい」
「相変わらずお堅いっすね……んじゃ、またな、魔人さんよ。オレッちはガーゴイルのアマンドだ。
目つきが悪く見えるのは生まれつきだから勘弁してくれよな。別に睨んでるわけじゃないからな~?」
ガーゴイルの魔族ことアマンドは、打って変わって朗らかな笑みを浮かべて手を振ってきた。
鋭い八重歯を見せて笑っており、先ほどまでの不気味さは消えてなくなっている。
「……なんなんだ」
俺は去り行くアマンドの背中を見ながら口にした。
父さんやキリエさんも魔族ではあるが、人間とよく似た容姿の魔族ではなく、魔族らしい外見の魔族は初見だった。
「ああ見えても、アマンドさんはガーゴイル偵察部隊の総隊長です。本人も言及しておられましたが、目つきが悪いのは生まれつきだそうなのであまりお気になさらず。基本的には誰にでも友好的な方ですし、ソロモンさんに危害を加えるようなことはないでしょう」
「魔族ってみんなあんな感じなんですか?」
人間の立場から考えると、キリエさんの言葉を鵜呑みにするのには無理があった。
俺が生まれるずっと前から、人間と魔族は憎しみ合う存在として認識されてきたし、それは今も変わっていないからだ。
「基本的に、魔族は人間への嫌悪感を殆ど抱いておりません。ですが、人間は私たち魔族の見た目が怖いのでしょう? なので、ソロモンさんのような両種の血を持つ存在は非常に希少なのです。
人間と魔族の今後のために必ず活躍する時が来るでしょう」
よくわからないが、想像していたような危険な展開にはならないような気がする。
むしろ、キリエさんとアマンドの様子を見た限りだと、人間同士よりもかなり落ち着いた会話だった。
冒険者は皆血の気が多く、一介のギルドの受付嬢やその辺にいる小さな子供だって、魔族やモンスターを殺せ殺せとうるさかった。
皆が魔王率いる魔族とモンスターを根絶やしにしようと躍起になっていたのをよく覚えている。例に漏れず、俺もその一人だった。
でも、何か違和感がある。
魔族である彼らはまるで気にも留めていないように思えた。
「……人間が一方的に恨んでいるだけで、魔族は人間と友好関係を築きたいってことか……まさかな」
俺は一つの結論に辿り着いたが、それはあまりにも人間が愚かで浅はかな生き物であることを露呈させるものだったので信じきれなかった。
もしかすると、人間が知らないだけで、両者の間には盛大な勘違いという名の深い溝があるのかもしれないな。