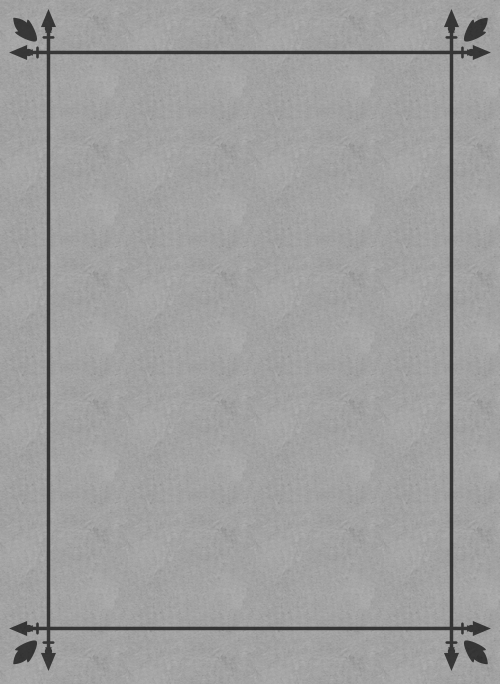目が覚めたら、全身を麻縄で縛り付けられていた。
背後の大木を軸にきつく縛られているからか全く身動きが取れない。
「おお、やっとお目覚めか。魔族野郎」
朧げな視界の中、眼前にはヘラヘラと笑うバリーがいた。
「……こ、ここは、森の中か?」
意識は虚ながらも、俺はこの場所がどこなのかを瞬時に理解していた。
「街の近くの森ん中だ。ここにはモンスターが出ねぇから人が殆ど来ねぇんだぜ? これがどういう意味かわかるか?」
「意味?」
反射的に聞き返したが、本当は心のどこかでわかっていた。
この森は静寂に包まれていて、人が来ることは殆どない。
おまけにこの中心の湖で何かを叫ぼうと、森の外へその声が届くことはない。
昨日来たばかりだからよくわかる。
「助けを呼んでも誰にも気づかれねぇってことだ!」
バリーは何の前触れもなく俺の腹に拳を叩き込んできた。
同時に、俺は声にもならない声を出して全身に脂汗をかく。
多分、肋骨が何本か折れた。
いつもはじわじわと痛ぶって楽しんでいるのに、今日は全く躊躇がない。
まるで、《《お気に入りのおもちゃに飽きた子供のようだ》》。
「苦しいか? 苦しいだろ? 苦しいって言えよ!」
「ぐる……じぃ……」
「ははははっ! もっとだ、もっと苦しめ! お前らもやっていいぞ!」
俺が苦悶の表情で言葉を口にしたのを見て満足したのか、バリーは酷く下品な高笑いを森に響かせると、上機嫌な様子で取り巻きたちに指示を出した。
気が付けば、壮絶なリンチに遭っていた。
縛り付けられていた麻縄からは解放されていたが、それは悪手でしかなかった。
腹を蹴られて地面を転がされ、仰向けになれば上からプレスされ、何も反応しないと更なる攻撃が襲いかかる。
俺が痛がる様子を見てとことん楽しんでいるようだった。
容赦ない暴力を受け続けた。
罵詈雑言を浴びせられながら、手も足も出せずに地面に打ちのめされた。
俺の身体はいつにも増して血だらけであり、立ち上がることもままならぬほど痛みに耐えながら、ただ生き延びることだけが頭によぎった。
「くはははははっ! ザマァねぇな!」
バリーと取り巻きの甲高い笑い声が俺の耳を刺し、俺の心には無念と絶望が滲む。
いつもならこれで終わる……いや、もっと早い段階で飽きられて終わっていたはずだ。
でも、今日は様子がおかしい。
全身の至る所の骨が折れているし、脳を揺さぶられてしまったのか意識を保つのすら精一杯だ。
おまけに出血量も多くて体が寒い。
呼吸もままならない。
これ以上続けると……俺は、確実に死ぬ。
「はっ! その顔、やっと気づいたか?」
バリーは膝を曲げて顔を近づけてきた。
「テメェは今日で死ぬんだよ。クソみたいな魔族の人生を、俺みたいなエリート貴族の手で終わらせられて幸せだろ?」
「し……ぬ?」
「父上に言われたんだ。そろそろ跡目を継がせるからお遊びは程々にしろってな。
近いうちに良いところの令嬢と見合いもあるしよ、そろそろ貴族らしく品行方正にシフトチェンジする頃合いってわけだ。だから、今日で苦しみから解放してやる。俺はいい奴だと思わないか?」
バリーは本当に自分が正しいことをしていると思っているのか、至って真剣な眼差しをこちらに向けてきた。
まるで意味不明な解釈を聞いた俺は思わず言葉を失うしかなかった。
とことんクズだ。
人間と魔族が対立している以上、魔人を差別する気持ちはわからなくもないが、それでも過剰にも程がある。
人殺しを正当化しているようにしか思えない。
でも、今の俺にはその言葉をぶつけることも憚られる。
口が開かないから言葉が出ない。今満足に動かせるのは視線だけだった。
誰か……俺を助けてほしい。
新たな門出を迎えさせてほしい。
どうか、どうか、どうか……お願いだから、誰でもいいから、俺のことを助けてください……
「……た……けて……」
俺は切実な想いを口にして大粒の涙で頬を濡らした。
そんな俺の姿を見下ろすバリーは背中から大剣を抜き払うと、鋒を俺の首元に突きつけて口角を上げた。
「情けねえ。結局、ザコは死に方も選べねぇ」
「っ……!」
もう終わりだ……俺は死を覚悟した。
刹那。
辺り一帯に強烈な突風が吹き荒れる。
湖の水面は静かに蠢き、森の中の木々はざわざわと不穏にゆらめく。
「ッ……なんだ?」
真っ先に気がついたバリーは周囲を見回して、異様なまでの空気感に警戒心を高めた。
それから僅か数秒後。
突如として、湖畔に何者かが現れる。
「何者だ!」
バリーと取り巻きは瞬時にその存在に体を向けて、各々の得物を即座に構えた。
「——あーあ、随分と酷いことをしてるね~」
虚な視界の中ではその顔はよく見えないが、声の主は女性のようだ。
辺りが凍りつきそうなほど冷めた声色だった。
「……頭に生えたそのツノ、魔族だな? 人間界で何してやがんだ。殺されに来たのか?」
魔族? 視界が朧げで全貌が見えない。
「はぁぁぁぁ……呆れた」
バリーは勢いのある脅しを口にしていたが、女性は大きな溜め息を吐くだけだった。
「……なんだてめぇ」
「私はそっちの彼に用があるだけ。争う気はないからどいてもらえる?」
「こんな雑魚に何の用だよ。こいつは穢れた混血種の魔人だぜ? それをわかってんのか?」
「もちろんわかってるよ」
女性は自身の胸に手を当てて答えると、満身創痍の俺のことを柔らかな瞳で一瞥してきた。
「じゃあ失せろ」
「無理。そっちこそ、退いてくれないなら……殺すよ?」
女性はさらに声を落としてより冷酷な雰囲気をその身に纏う。
しかし、バリーはそんなことなど気にするはずはなく、軽く笑い飛ばして取り巻きに攻撃を命じる。
「ははははっ! やれるもんならやってみろや! いくら魔族が相手とはいえ、こっちはBランク冒険者が何人もいるんだぜ!」
「……人間はどうして争いを好むんだろうね」
女性は瞬く間に取り巻きに囲まれたが、全く意に返さない。むしろ余裕綽々な口振りと表情だった。
でも、バリーたちはこれでもBランク冒険者だ。
いくらこの女性が強かろうと人数差は明白だし、真っ向から戦闘したら無事で済むとは思えない。
俺に用があるとか言っていたけど、早く逃げた方がいい。
魔族は身体能力が飛躍的に高くて魔法に長けているが、バリーたちを相手取るのは容易じゃないと思う。
「……に……げて……」
「逃げないよ。すぐ助けてあげるからね」
俺は途切れ途切れの言葉を懸命に振り絞った。
しかし、魔族の女性は一蹴して笑いかけてきた。
笑顔のままで《《虚空》》に手を伸ばすと、何もない空間から巨大な戦斧を取り出した。
「……亜空間にアクセスできる闇魔法を使えるってことは、マジもんの魔族だな。ここの出来損ないは何もできねぇみてぇだがよ」
バリーが指摘した通り、魔族は闇魔法を扱うことが知られている。
亜空間にアクセスしたのも闇魔法の一種だ。
女性は魔族で間違いない。
「口が減らないなら本当に殺しちゃうよ?」
「はっ! やれるもんならやってみやがれってんだ!」
「ふーん……威勢だけはいいんだね。でも、残念。人間には手を出しちゃいけないってパパに口酸っぱく言われてるから、殺すことはできないんだ」
女性は残念そうに首を横に振ると、瞬時に戦斧を構えて横薙ぎに振るった。
ギリギリ目で追えたが、視界がぼやけていてよく見えない。
「中々よく斬れるでしょ? 後ろの大木を横一線に真っ二つ……しかも、おまけにお仲間の武器と防具もバラバラにしちゃった。そうそう見られる光景じゃないと思うよ?」
「は?」
バリーは目の前の光景を見て素っ頓狂な声を漏らしたが、それは俺も同様だった。
そう。目の前では、取り巻きたちが手に持つ武器と身に纏う防具が見るも無惨に砕け散っていたのだ。
何をしたか全く見えなかった。
しかし、既に実力差ははっきりしていた。
「最後はあなただけ」
「ぐぅっ……クソがああああぁぁぁあああぁぁ——」
バリーは不快感たっぷりな表情を浮かべると、両手で握り込んだ大剣を構えて突進した。
格下の俺が言うこともでもないが、今のバリーは子供のようにしか見えなかった。
感情的で直情的で、単純な……いかにも余裕のある女性とは対照的だ。
「さよなら」
女性は迫り来るバリーの大剣をひらりと躱すと、ガラ空きになった背後から蹴りを叩き込んだ。
決して俊敏な動きではなかった。
でも、洗練されたその一撃は確実にバリーの意識を刈り取った。
「はぁーあ……ボスがやられちゃったわけだけど、まだやる? 武器と防具も粉々だけど?」
「くっ……今回は見逃してやる! 次会った時は覚悟しろ!」
女性がニヒルに笑いかけると、取り巻きたちはバリーを担いでそそくさと逃げ出した。
「……はは……ざまぁ、みやが……れ」
日頃から甘い蜜を吸って生きていた取り巻きたちが、情けなく敗走する姿を見るのは痛快だった。
性格が悪いと思われるかもしれないが、ここ一ヶ月の凄惨な日々が少しは晴れたような気がする。
「遅くなっちゃった。帰ろっか」
女性は亜空間に戦斧を収納すると、両手で俺のことを抱えて優しく微笑みかけてきた。
柔らかくて温かみのある肌は人間と変わらない。
見た目はツノが生えていて魔族そのものだが、それは魔族を虐げる理由にはならない。
「……」
俺は感謝を口をしようとした。
しかし、もはや意識を失う寸前だったこともあり、何も言葉を返せずに瞳を閉じてしまう。
もう死ぬのかもしれないな。
背後の大木を軸にきつく縛られているからか全く身動きが取れない。
「おお、やっとお目覚めか。魔族野郎」
朧げな視界の中、眼前にはヘラヘラと笑うバリーがいた。
「……こ、ここは、森の中か?」
意識は虚ながらも、俺はこの場所がどこなのかを瞬時に理解していた。
「街の近くの森ん中だ。ここにはモンスターが出ねぇから人が殆ど来ねぇんだぜ? これがどういう意味かわかるか?」
「意味?」
反射的に聞き返したが、本当は心のどこかでわかっていた。
この森は静寂に包まれていて、人が来ることは殆どない。
おまけにこの中心の湖で何かを叫ぼうと、森の外へその声が届くことはない。
昨日来たばかりだからよくわかる。
「助けを呼んでも誰にも気づかれねぇってことだ!」
バリーは何の前触れもなく俺の腹に拳を叩き込んできた。
同時に、俺は声にもならない声を出して全身に脂汗をかく。
多分、肋骨が何本か折れた。
いつもはじわじわと痛ぶって楽しんでいるのに、今日は全く躊躇がない。
まるで、《《お気に入りのおもちゃに飽きた子供のようだ》》。
「苦しいか? 苦しいだろ? 苦しいって言えよ!」
「ぐる……じぃ……」
「ははははっ! もっとだ、もっと苦しめ! お前らもやっていいぞ!」
俺が苦悶の表情で言葉を口にしたのを見て満足したのか、バリーは酷く下品な高笑いを森に響かせると、上機嫌な様子で取り巻きたちに指示を出した。
気が付けば、壮絶なリンチに遭っていた。
縛り付けられていた麻縄からは解放されていたが、それは悪手でしかなかった。
腹を蹴られて地面を転がされ、仰向けになれば上からプレスされ、何も反応しないと更なる攻撃が襲いかかる。
俺が痛がる様子を見てとことん楽しんでいるようだった。
容赦ない暴力を受け続けた。
罵詈雑言を浴びせられながら、手も足も出せずに地面に打ちのめされた。
俺の身体はいつにも増して血だらけであり、立ち上がることもままならぬほど痛みに耐えながら、ただ生き延びることだけが頭によぎった。
「くはははははっ! ザマァねぇな!」
バリーと取り巻きの甲高い笑い声が俺の耳を刺し、俺の心には無念と絶望が滲む。
いつもならこれで終わる……いや、もっと早い段階で飽きられて終わっていたはずだ。
でも、今日は様子がおかしい。
全身の至る所の骨が折れているし、脳を揺さぶられてしまったのか意識を保つのすら精一杯だ。
おまけに出血量も多くて体が寒い。
呼吸もままならない。
これ以上続けると……俺は、確実に死ぬ。
「はっ! その顔、やっと気づいたか?」
バリーは膝を曲げて顔を近づけてきた。
「テメェは今日で死ぬんだよ。クソみたいな魔族の人生を、俺みたいなエリート貴族の手で終わらせられて幸せだろ?」
「し……ぬ?」
「父上に言われたんだ。そろそろ跡目を継がせるからお遊びは程々にしろってな。
近いうちに良いところの令嬢と見合いもあるしよ、そろそろ貴族らしく品行方正にシフトチェンジする頃合いってわけだ。だから、今日で苦しみから解放してやる。俺はいい奴だと思わないか?」
バリーは本当に自分が正しいことをしていると思っているのか、至って真剣な眼差しをこちらに向けてきた。
まるで意味不明な解釈を聞いた俺は思わず言葉を失うしかなかった。
とことんクズだ。
人間と魔族が対立している以上、魔人を差別する気持ちはわからなくもないが、それでも過剰にも程がある。
人殺しを正当化しているようにしか思えない。
でも、今の俺にはその言葉をぶつけることも憚られる。
口が開かないから言葉が出ない。今満足に動かせるのは視線だけだった。
誰か……俺を助けてほしい。
新たな門出を迎えさせてほしい。
どうか、どうか、どうか……お願いだから、誰でもいいから、俺のことを助けてください……
「……た……けて……」
俺は切実な想いを口にして大粒の涙で頬を濡らした。
そんな俺の姿を見下ろすバリーは背中から大剣を抜き払うと、鋒を俺の首元に突きつけて口角を上げた。
「情けねえ。結局、ザコは死に方も選べねぇ」
「っ……!」
もう終わりだ……俺は死を覚悟した。
刹那。
辺り一帯に強烈な突風が吹き荒れる。
湖の水面は静かに蠢き、森の中の木々はざわざわと不穏にゆらめく。
「ッ……なんだ?」
真っ先に気がついたバリーは周囲を見回して、異様なまでの空気感に警戒心を高めた。
それから僅か数秒後。
突如として、湖畔に何者かが現れる。
「何者だ!」
バリーと取り巻きは瞬時にその存在に体を向けて、各々の得物を即座に構えた。
「——あーあ、随分と酷いことをしてるね~」
虚な視界の中ではその顔はよく見えないが、声の主は女性のようだ。
辺りが凍りつきそうなほど冷めた声色だった。
「……頭に生えたそのツノ、魔族だな? 人間界で何してやがんだ。殺されに来たのか?」
魔族? 視界が朧げで全貌が見えない。
「はぁぁぁぁ……呆れた」
バリーは勢いのある脅しを口にしていたが、女性は大きな溜め息を吐くだけだった。
「……なんだてめぇ」
「私はそっちの彼に用があるだけ。争う気はないからどいてもらえる?」
「こんな雑魚に何の用だよ。こいつは穢れた混血種の魔人だぜ? それをわかってんのか?」
「もちろんわかってるよ」
女性は自身の胸に手を当てて答えると、満身創痍の俺のことを柔らかな瞳で一瞥してきた。
「じゃあ失せろ」
「無理。そっちこそ、退いてくれないなら……殺すよ?」
女性はさらに声を落としてより冷酷な雰囲気をその身に纏う。
しかし、バリーはそんなことなど気にするはずはなく、軽く笑い飛ばして取り巻きに攻撃を命じる。
「ははははっ! やれるもんならやってみろや! いくら魔族が相手とはいえ、こっちはBランク冒険者が何人もいるんだぜ!」
「……人間はどうして争いを好むんだろうね」
女性は瞬く間に取り巻きに囲まれたが、全く意に返さない。むしろ余裕綽々な口振りと表情だった。
でも、バリーたちはこれでもBランク冒険者だ。
いくらこの女性が強かろうと人数差は明白だし、真っ向から戦闘したら無事で済むとは思えない。
俺に用があるとか言っていたけど、早く逃げた方がいい。
魔族は身体能力が飛躍的に高くて魔法に長けているが、バリーたちを相手取るのは容易じゃないと思う。
「……に……げて……」
「逃げないよ。すぐ助けてあげるからね」
俺は途切れ途切れの言葉を懸命に振り絞った。
しかし、魔族の女性は一蹴して笑いかけてきた。
笑顔のままで《《虚空》》に手を伸ばすと、何もない空間から巨大な戦斧を取り出した。
「……亜空間にアクセスできる闇魔法を使えるってことは、マジもんの魔族だな。ここの出来損ないは何もできねぇみてぇだがよ」
バリーが指摘した通り、魔族は闇魔法を扱うことが知られている。
亜空間にアクセスしたのも闇魔法の一種だ。
女性は魔族で間違いない。
「口が減らないなら本当に殺しちゃうよ?」
「はっ! やれるもんならやってみやがれってんだ!」
「ふーん……威勢だけはいいんだね。でも、残念。人間には手を出しちゃいけないってパパに口酸っぱく言われてるから、殺すことはできないんだ」
女性は残念そうに首を横に振ると、瞬時に戦斧を構えて横薙ぎに振るった。
ギリギリ目で追えたが、視界がぼやけていてよく見えない。
「中々よく斬れるでしょ? 後ろの大木を横一線に真っ二つ……しかも、おまけにお仲間の武器と防具もバラバラにしちゃった。そうそう見られる光景じゃないと思うよ?」
「は?」
バリーは目の前の光景を見て素っ頓狂な声を漏らしたが、それは俺も同様だった。
そう。目の前では、取り巻きたちが手に持つ武器と身に纏う防具が見るも無惨に砕け散っていたのだ。
何をしたか全く見えなかった。
しかし、既に実力差ははっきりしていた。
「最後はあなただけ」
「ぐぅっ……クソがああああぁぁぁあああぁぁ——」
バリーは不快感たっぷりな表情を浮かべると、両手で握り込んだ大剣を構えて突進した。
格下の俺が言うこともでもないが、今のバリーは子供のようにしか見えなかった。
感情的で直情的で、単純な……いかにも余裕のある女性とは対照的だ。
「さよなら」
女性は迫り来るバリーの大剣をひらりと躱すと、ガラ空きになった背後から蹴りを叩き込んだ。
決して俊敏な動きではなかった。
でも、洗練されたその一撃は確実にバリーの意識を刈り取った。
「はぁーあ……ボスがやられちゃったわけだけど、まだやる? 武器と防具も粉々だけど?」
「くっ……今回は見逃してやる! 次会った時は覚悟しろ!」
女性がニヒルに笑いかけると、取り巻きたちはバリーを担いでそそくさと逃げ出した。
「……はは……ざまぁ、みやが……れ」
日頃から甘い蜜を吸って生きていた取り巻きたちが、情けなく敗走する姿を見るのは痛快だった。
性格が悪いと思われるかもしれないが、ここ一ヶ月の凄惨な日々が少しは晴れたような気がする。
「遅くなっちゃった。帰ろっか」
女性は亜空間に戦斧を収納すると、両手で俺のことを抱えて優しく微笑みかけてきた。
柔らかくて温かみのある肌は人間と変わらない。
見た目はツノが生えていて魔族そのものだが、それは魔族を虐げる理由にはならない。
「……」
俺は感謝を口をしようとした。
しかし、もはや意識を失う寸前だったこともあり、何も言葉を返せずに瞳を閉じてしまう。
もう死ぬのかもしれないな。