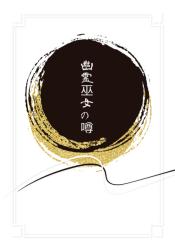二人は一瞬目だけで互いの顔を見合わせ、本当のことを言おうかどうしようかと迷っているようだった。青年が何か言おうと一度口を開いたが、すぐに閉口することになった。唐突に第三者の介入があったからだ。ドアを開けてまた誰か入って来る。
「気が付いたかしら」
心配そうな声音で入って来たのは、白衣を着た女性だった。ふわふわとしたクリーム色の短髪に緑の目、マシュマロを思わせる柔らかそうな体型と雰囲気。一目でこの女性が医師なのだと航汰には分かった。掛けている眼鏡をくい、と上げる仕草は何だかぎこちない。その姿に少女が少しだけ呆れたように言った。
「せんせぇ、やっぱ似合わないよ。その伊達眼鏡。止めたら?」
容赦の無い少女の指摘に先生と呼ばれた女性は、慌てたように訂正する。持っているバインダーをぎゅっと抱き締めたせいで、柔らかそうな胸がむにゅっと押し付けられた。
「そ、そんなこと無いわよ!? ミチルちゃん! 私は形から入るタイプなのっ!」
「あ、そう」
しかし、航汰にとってはそんなことはどうでも良く、再度三人に芽衣奈はどうしたのかと訊いた。
「で、芽衣奈はどうしたんですか?」
「あんたさ、何も覚えてないの?」
ポケットから棒付き飴を取り出し、包装を破って口に突っ込みながらミチルと呼ばれた少女は質問し返す。そのぶっきらぼうな物言いに女性が窘めた。
「こら、ミチルちゃん。彼は今、少し記憶を無くしてる状態だって言ったでしょ。無遠慮なこと言っちゃダメよ」
「それはせんせぇの見解だけど、本人にも確認しておいた方が良いでしょ。ここまできっと訳分かんなくて、混乱しっぱなしだと思うし」
「あのねえ、こっちからもいくつか君に質問しなくちゃいけなくて。でも、今は体を休めた方が良いよお。ここまで何か思い出せること、あるかなあ?」
終始朗らかな青年の言葉に航汰は今一度、冷静になった頭で考えてみる。確か、いじめの主犯達に学校まで呼び出されて、そこには芽衣奈がいて、それで――。
途方に暮れている航汰の様子に、三人共察したようだった。青年と席を交換した医師の女性が自己紹介から入った。
「初めまして、時風航汰くん。自分の名前は流石に覚えてる、わよね?」
「はい」
「私はここの医療室で治療を担当している天海真都梨よ。よろしくね。それで、こっちがあなたを保護した――」
「有明剛史だよお。よろしくねえ。みんなからはゴウって呼ばれてるよお」
「……御田美智瑠」
女性医師・真都梨に促されて、青年と少女がそれぞれ自己紹介する。剛史は名前に似合わず、非常に朗らかでのんびりとした口調の青年だ。髪はピンク色だが。美智瑠はぶっきらぼうな性格なのか、自己紹介も非常に簡素で愛想は無い。三人共が日本人に優しくない色合いをしているが、そんなことは気にせず、何だか毒気を抜かれた心持ちになり、彼も律儀に自己紹介を返した。
「僕は、時風航汰、です。七賀戸中学校に通ってます。あの、皆さんはどういう――」
「あ、その前に少し検査する時間を取ってもいいかな? 検査が終わったら、あなたの質問に答えつつ、ここを案内するつもりなの」
「は、はぁ……分かりました」
それから真都梨は美智瑠と剛史に部屋を出て行くように言うと、二人は僅かに渋々といった様子で従った。残った真都梨にいくつか質問をされた航汰は、正直に自分が覚えている範囲で答える。自分の名前、家族構成、友達の有無や顔、これまでの過去のこと。個人情報を簡単に他人に教えてしまっているという事実に、彼は何度か躊躇ったが、その度に真都梨は「私には守秘義務があるから、大丈夫。患者さんの情報はどこにも漏らさないわ」とにこやかに宣言してくれるので、まだどういった組織か見当も付かない状態でいくつか意味不明な質問もあったが、何故だか航汰は安心して質問に答えられた。
そうして、全ての質問に答え終わると、真都梨は真剣な面持ちで「断定はできないけど……」と前置きしてから診断結果を口にする。
「やっぱり一時的な記憶障害だと思うわ。過度なストレスに晒されて防衛本能が働いてる状態。記憶を取り戻すには個人差があるけれど、時間が要るの。今は焦らず、体と心を休めることが先決よ」
「はぁ……そうですか」
診断結果を聞いても、航汰にはまるで他人事のように聞こえた。あまりにも反応が薄い航汰に心底心配する真都梨だったが、記憶障害故に仕方のないことだと納得する。それを見澄ましたように美智瑠と剛史が戻ってきた。
「せんせぇ、終わった~?」
「ええ、終わったわ。二人共、話したいことがあるなら、なるべく手短にね。今の航汰くんは体を休ませた方が良いから」
「分かってるって。終わったら、声掛けるよ」
「はあい」
真都梨が退室した後、二人はまた航汰のベッド脇に来て興味津々といった様子で話しかけてくる。航汰が多少嫌そうな顔をしていてもお構いなしだ。
「ねぇねぇ、あんた。自分の右手、見てみたら? 面白いものが見れるかもよ?」
「右手……?」
美智瑠に言われて自分の右手を目の前で開いてみせる航汰。そこには掌の丁度、真ん中に何やら小さな縫い跡のようなものがある。と思った瞬間――
「うわ」
「にひひ」
にゅちっとその縫い跡のような部分が肉を少し開いて覗かせたのは、黄緑色の小さな目だった。猫目のように細長い瞳孔を動かし、周囲をきょろきょろと見回して、そのまま何事も無かったかのように閉じる様を見て、航汰は思わず小さく驚嘆の声を上げる。ここに来て初めて人間らしい反応をした航汰を見て何が嬉しいのか、美智瑠はしてやったりという笑みを浮かべた。
「面白いっしょ?」
「……なに、これ」
「あれえ? 真都梨ちゃんから聞いてない? それが航汰くんがここに運ばれて来た理由だってえ」
ふるふると首を左右に振る航汰を見て、二人は何か納得したように「あー」と意味の無い声を出す。口の中で棒付き飴をころころと転がしつつ、美智瑠が「後でまた説明されると思うけど」と前置きしてから簡単に説明する。
「それ、あんたが死なない限り、もう消えないから。後で『やだやだ』って泣き喚いても遅いからね」
「――どういうことですか?」
「教えてやんなーい。今ピーピー泣かれてもあたしら知らないしー」
「泣きませんよ」
一瞬、美智瑠は彼が負け惜しみで言っているのだと思ったが、実際の航汰の表情を見ると、それは違うと思い直す。
ベッドに横たわっている航汰は自身の掌を見つめながら、静かに涙を流していた。澱んだ目つきで一度も嗚咽することなく、ただ目元を透明な水滴が伝っていく。ある意味で異様な光景だったが、二人は引かなかった。むしろ、何か共感するところでもあるのか、妙に納得したような顔をしている。
「僕にはもう、何も無い。記憶が無くても、何となく感覚で分かります。もう今までの平和な日常には戻れない。何か、僕の中で一番大事なものを失ってしまった気がするから」
ぼろぼろと無感動に見える表情で涙を流す航汰に、それまでずっと黙って聞いていた美智瑠がもう見飽きたという顔で口を開く。
「そのうち思い出すことになるよ。嫌でもね。行こ、ゴウ」
「う、うん。それじゃあ、後でね。航汰くん」
どこか気まずい空気を漂わせつつ立ち上がり、そのまま部屋を出ようとする二人の背中に、か細い航汰の声が問いかける。
「あなた達も、僕と同じ、なんですか?」
その問いに足を止めた美智瑠は、ちらと航汰を一瞥してただ一言だけ残して行った。
「さぁね。教えてやんない」
静かに閉められるドアを少しの間見つめていた航汰だが、二人の足音が遠ざかり、後には何も聞こえなくなると、少し眠ろうと目を閉じた。
「気が付いたかしら」
心配そうな声音で入って来たのは、白衣を着た女性だった。ふわふわとしたクリーム色の短髪に緑の目、マシュマロを思わせる柔らかそうな体型と雰囲気。一目でこの女性が医師なのだと航汰には分かった。掛けている眼鏡をくい、と上げる仕草は何だかぎこちない。その姿に少女が少しだけ呆れたように言った。
「せんせぇ、やっぱ似合わないよ。その伊達眼鏡。止めたら?」
容赦の無い少女の指摘に先生と呼ばれた女性は、慌てたように訂正する。持っているバインダーをぎゅっと抱き締めたせいで、柔らかそうな胸がむにゅっと押し付けられた。
「そ、そんなこと無いわよ!? ミチルちゃん! 私は形から入るタイプなのっ!」
「あ、そう」
しかし、航汰にとってはそんなことはどうでも良く、再度三人に芽衣奈はどうしたのかと訊いた。
「で、芽衣奈はどうしたんですか?」
「あんたさ、何も覚えてないの?」
ポケットから棒付き飴を取り出し、包装を破って口に突っ込みながらミチルと呼ばれた少女は質問し返す。そのぶっきらぼうな物言いに女性が窘めた。
「こら、ミチルちゃん。彼は今、少し記憶を無くしてる状態だって言ったでしょ。無遠慮なこと言っちゃダメよ」
「それはせんせぇの見解だけど、本人にも確認しておいた方が良いでしょ。ここまできっと訳分かんなくて、混乱しっぱなしだと思うし」
「あのねえ、こっちからもいくつか君に質問しなくちゃいけなくて。でも、今は体を休めた方が良いよお。ここまで何か思い出せること、あるかなあ?」
終始朗らかな青年の言葉に航汰は今一度、冷静になった頭で考えてみる。確か、いじめの主犯達に学校まで呼び出されて、そこには芽衣奈がいて、それで――。
途方に暮れている航汰の様子に、三人共察したようだった。青年と席を交換した医師の女性が自己紹介から入った。
「初めまして、時風航汰くん。自分の名前は流石に覚えてる、わよね?」
「はい」
「私はここの医療室で治療を担当している天海真都梨よ。よろしくね。それで、こっちがあなたを保護した――」
「有明剛史だよお。よろしくねえ。みんなからはゴウって呼ばれてるよお」
「……御田美智瑠」
女性医師・真都梨に促されて、青年と少女がそれぞれ自己紹介する。剛史は名前に似合わず、非常に朗らかでのんびりとした口調の青年だ。髪はピンク色だが。美智瑠はぶっきらぼうな性格なのか、自己紹介も非常に簡素で愛想は無い。三人共が日本人に優しくない色合いをしているが、そんなことは気にせず、何だか毒気を抜かれた心持ちになり、彼も律儀に自己紹介を返した。
「僕は、時風航汰、です。七賀戸中学校に通ってます。あの、皆さんはどういう――」
「あ、その前に少し検査する時間を取ってもいいかな? 検査が終わったら、あなたの質問に答えつつ、ここを案内するつもりなの」
「は、はぁ……分かりました」
それから真都梨は美智瑠と剛史に部屋を出て行くように言うと、二人は僅かに渋々といった様子で従った。残った真都梨にいくつか質問をされた航汰は、正直に自分が覚えている範囲で答える。自分の名前、家族構成、友達の有無や顔、これまでの過去のこと。個人情報を簡単に他人に教えてしまっているという事実に、彼は何度か躊躇ったが、その度に真都梨は「私には守秘義務があるから、大丈夫。患者さんの情報はどこにも漏らさないわ」とにこやかに宣言してくれるので、まだどういった組織か見当も付かない状態でいくつか意味不明な質問もあったが、何故だか航汰は安心して質問に答えられた。
そうして、全ての質問に答え終わると、真都梨は真剣な面持ちで「断定はできないけど……」と前置きしてから診断結果を口にする。
「やっぱり一時的な記憶障害だと思うわ。過度なストレスに晒されて防衛本能が働いてる状態。記憶を取り戻すには個人差があるけれど、時間が要るの。今は焦らず、体と心を休めることが先決よ」
「はぁ……そうですか」
診断結果を聞いても、航汰にはまるで他人事のように聞こえた。あまりにも反応が薄い航汰に心底心配する真都梨だったが、記憶障害故に仕方のないことだと納得する。それを見澄ましたように美智瑠と剛史が戻ってきた。
「せんせぇ、終わった~?」
「ええ、終わったわ。二人共、話したいことがあるなら、なるべく手短にね。今の航汰くんは体を休ませた方が良いから」
「分かってるって。終わったら、声掛けるよ」
「はあい」
真都梨が退室した後、二人はまた航汰のベッド脇に来て興味津々といった様子で話しかけてくる。航汰が多少嫌そうな顔をしていてもお構いなしだ。
「ねぇねぇ、あんた。自分の右手、見てみたら? 面白いものが見れるかもよ?」
「右手……?」
美智瑠に言われて自分の右手を目の前で開いてみせる航汰。そこには掌の丁度、真ん中に何やら小さな縫い跡のようなものがある。と思った瞬間――
「うわ」
「にひひ」
にゅちっとその縫い跡のような部分が肉を少し開いて覗かせたのは、黄緑色の小さな目だった。猫目のように細長い瞳孔を動かし、周囲をきょろきょろと見回して、そのまま何事も無かったかのように閉じる様を見て、航汰は思わず小さく驚嘆の声を上げる。ここに来て初めて人間らしい反応をした航汰を見て何が嬉しいのか、美智瑠はしてやったりという笑みを浮かべた。
「面白いっしょ?」
「……なに、これ」
「あれえ? 真都梨ちゃんから聞いてない? それが航汰くんがここに運ばれて来た理由だってえ」
ふるふると首を左右に振る航汰を見て、二人は何か納得したように「あー」と意味の無い声を出す。口の中で棒付き飴をころころと転がしつつ、美智瑠が「後でまた説明されると思うけど」と前置きしてから簡単に説明する。
「それ、あんたが死なない限り、もう消えないから。後で『やだやだ』って泣き喚いても遅いからね」
「――どういうことですか?」
「教えてやんなーい。今ピーピー泣かれてもあたしら知らないしー」
「泣きませんよ」
一瞬、美智瑠は彼が負け惜しみで言っているのだと思ったが、実際の航汰の表情を見ると、それは違うと思い直す。
ベッドに横たわっている航汰は自身の掌を見つめながら、静かに涙を流していた。澱んだ目つきで一度も嗚咽することなく、ただ目元を透明な水滴が伝っていく。ある意味で異様な光景だったが、二人は引かなかった。むしろ、何か共感するところでもあるのか、妙に納得したような顔をしている。
「僕にはもう、何も無い。記憶が無くても、何となく感覚で分かります。もう今までの平和な日常には戻れない。何か、僕の中で一番大事なものを失ってしまった気がするから」
ぼろぼろと無感動に見える表情で涙を流す航汰に、それまでずっと黙って聞いていた美智瑠がもう見飽きたという顔で口を開く。
「そのうち思い出すことになるよ。嫌でもね。行こ、ゴウ」
「う、うん。それじゃあ、後でね。航汰くん」
どこか気まずい空気を漂わせつつ立ち上がり、そのまま部屋を出ようとする二人の背中に、か細い航汰の声が問いかける。
「あなた達も、僕と同じ、なんですか?」
その問いに足を止めた美智瑠は、ちらと航汰を一瞥してただ一言だけ残して行った。
「さぁね。教えてやんない」
静かに閉められるドアを少しの間見つめていた航汰だが、二人の足音が遠ざかり、後には何も聞こえなくなると、少し眠ろうと目を閉じた。