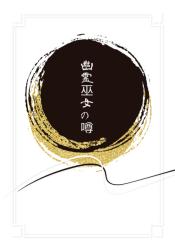芽衣奈に連れられるままバスに乗り、駅前のカラオケに連れて行かれる。最近できたばかりの新しい店で、夕方の六時までルーム料金が無料で利用できるとあって、学生に人気の店だ。
応対した店員は特に何の感情も見せぬまま、二人を個室に通し、航汰は芽衣奈の歌を聴いていた。自分で選んだのか、あまり記憶に無い烏龍茶をちびちび飲みながら、航汰は芽衣奈がノリノリで歌う流行の歌を聴く。芽衣奈は時々、こうして航汰を色んな場所に連れて行ってくれるが、その度に航汰は心から楽しめない自分を疎み、彼女に申し訳ない気持ちでいっぱいになっていくのだった。
五曲目が終わったところで、芽衣奈は一旦休憩を摂るらしく、航汰の隣に戻ってきてレモンスカッシュを一口飲んだ。素人ながらに咳払いをして喉の調子を見た後、「で、どう?」と期待に満ちた眼差しで航汰に訊いてきた。一瞬、何のことか分からなかった彼は、のろのろと彼女の方へ顔を向けて「どう、って?」と訊き返す。その鈍い反応に「もうっ」と少し拗ねてみせた芽衣奈は、身を乗り出して迫る。
「航汰、あんた今まで何聴いてたのよ。私の歌に決まってんじゃない」
「ごめん。流行の歌って、よく分からないから」
「ふぅ~ん。じゃあ、航汰が流行の歌知るのは、私の歌だけなんだ?」
「うん」
そう聞くと、芽衣奈はどこか嬉しそうに「えへへ」と笑い、「じゃあ、また歌うね」と上機嫌でまたマイクを持つ。それからまた二曲歌うと満足したのか、また隣に座ってレモンスカッシュを飲んだ。そこで何となく沈黙が流れ、航汰は以前からずっと持っていた疑問を訊いてみることにした。
「ねぇ、芽衣奈」
「なに?」
「芽衣奈はさ、なんで僕に構うの? いくら幼馴染みだからって、無理して僕と関わることなんてしなくていいんだよ。むしろ、僕と一緒にいると――」
「芽衣奈もどんな目に遭わされるか分からない」という心配の言葉は、他でもない芽衣奈の手によって吐露されることは無かった。ぐい、と手を引かれて航汰の頬に何か柔らかい感触がした。突然のことに驚き、何も反応できない航汰へ少し頬を赤らめた彼女は、優しく微笑んで続けた。
「こういうこと。私があんたに構う理由。ね? 今は応えて欲しいなんて言わないから。でも、いつか、教えてね」
まさか彼女が自分に対してそんな想いを抱えていたなんて、全く気が付いていなかった航汰は、何も言えずにただ頷くことしかできなかった。少ししてから漸く羞恥心が湧き起こり、航汰の顔が段々赤くなっていく。微かに幸せな気持ちが浮かんでくると同時に、恐怖が湧き起こる。もし、こんなことが周りに知れてしまったら、同級生達になんて知れてしまったら、芽衣奈がどうなるか分からない。あいつらだって、馬鹿ではないのだ。もし、彼女一人で対応し切れない事態が起きてしまったら、どうしよう。
どこかすっきりしたような、嬉しそうな表情で歌い続ける芽衣奈とは対照的に、航汰は青ざめて頭を抱えているのであった。
それから航汰の予想が的中するのにそう時間は掛からなかった。
芽衣奈とカラオケに行った翌日の放課後、さて帰ろうと下駄箱までやって来た彼に声を掛ける大人がいた。彼がそちらへ振り返ると、そこには副担任教師の来間直子が何やら大量のプリントを持って佇んでいた。彼女は申し訳なさそうに眉を下げて航汰に手伝って欲しいと言った。
「ごめんね、時風君。先生一人じゃ、ちょっと運ぶの大変で。少しだけ手伝ってくれる?」
彼女も教師という体面があるせいか、時々こうして口実を作っては航汰をいじめ連中から避難させてくれる。一瞬、今日は断ろうと思った航汰だが、端末にいじめ連中のリーダーから連絡が入り、放課後いつもの場所で待ってると簡潔なメッセージが届く。それを見て、あいつらが飽きて帰るまでやり過ごすことにした航汰は端末の電源を落とし、制服のポケットに突っ込んで来間からプリントを半分受け取った。
向かうは三階の資料室。プリントを紐綴じにした物を取り敢えず保存しておく為に持って行くようだ。移動中、特に話題も無いので、航汰はこの大量の資料は何かと訊いた。
「先生、この資料って何ですか?」
「ん? ああ、これはね。四年前の生徒さん達に関するものだったり、学校行事の記録なの。本当は劣化防止の為にファイルに入れるのが決まりなんだけど、うっかり在庫が無くなっちゃって。だから、一旦紐でくくって持っていくことになったのよ」
「量が多くてごめんね」とまた謝られる。それに「いいえ」と返して、航汰はぽつりと呟いた。
「いつも先生がこうやって色々口実を作ってくれて、僕を避難させてくれるの。正直、有り難いです。……とても」
少し照れながら告げられた素直な言葉に、来間は穏やかな笑みを浮かべて「そう? なら、良かった」と心底嬉しそうに笑った。慎重な足取りで階段を上り、資料室へ着くと、来間は先に入って窓際に置いてあるスチールの机へ資料を置いた。航汰もそれに倣って置く。来間はすぐ近くの棚を開けて、持ってきた資料を丁寧に積んだ。これを後二回はしなければいけないらしく、来間はもう一度「ごめんね」と謝った。
三階の資料室から屋上に繋がるドアまではそれなりに離れているが、いつ鉢合わせるとも限らない。なので、航汰は廊下へ出る時、必ず周囲に注意を払ってから出て行き、職員室から資料を持って来た時は、奴らの足音が聞こえてこないか、びくびくしながら上った。そんな彼の様子を見て、来間は必ず彼の前へ出て見張ってくれていた。
そんな調子で無事に全ての資料を運び終え、「じゃあ、帰ります」と出て行こうとした航汰を呼び止めた来間は、廊下に誰もいないことを資料室の引き戸に組み込まれている窓から確認して、ポケットから何かを取り出した。
「手を出してみて」
「? 何ですか?」
「ふふ、いいから」
言われるがままに航汰が手を出すと、来間はその掌に手の中の物を握らせた。「他の生徒さん達には内緒ね」と悪戯っ子のような笑みを見せる。そっと手の中にある物を見ると、それは個包装に入っているのど飴だった。さくらんぼ味と書かれた涼しげな文字を見て、航汰は不思議そうに来間を見返して言った。
「いいんですか? こういうの」
「だから、他の子には内緒なの」
「それ食べて元気出してね」と明るく言う来間に、航汰は上手く返せないながらも、大切そうにぎゅっと握り、ズボンのポケットへ入れた。
それから不思議とその日は誰にも絡まれることは無く、さっさと帰ろうと航汰は家路へ着く。帰り道でも不気味な程に、同級生達にも芽衣奈にも会わずに、無事に家へ辿り着くことができた。鞄から鍵を取り出して開けようとしたところで、何か予感のようなものを覚えた航汰だったが、気のせいだと思い、いつもと同じように鍵を開けて入った。
「ただいま」
まだ自分以外誰も帰ってきていないと分かりきっているが、一応帰って来たことを家に知らせる。リビングへは行かず、そのまま航汰は自室へ向かった。
自室に入ると鞄を適当に床へ放り、窓を少し開けてベッドへ仰向けに寝転んだ。外を見るのが億劫でいつも閉め切っているレースのカーテンが風に揺れる。透けたその先に見える夕陽が航汰は好きだった。町中をオレンジ色の光が照らし、毎日毎日これが最期の輝きだとでも言うかのように自身の全てを燃やし尽くすような琥珀色の自然光。彼がどんなに酷い目に遭っても、芽衣奈とこの夕陽だけはいつも優しかった。その陽を見つめていると、航汰の瞼は段々重くなっていった。
いつの間に眠っていたのか、次に航汰が目を開けた時は真っ暗だった。町の街灯が微かに差し込んでくる以外、光源は無い。車通りも少ない閑静な住宅街。両親はまだ帰って来ていないらしく、物音一つしない。そんな中で、唐突に彼の端末が鳴った。表示されている名前を見ると、芽衣奈からだった。
その名前を見た瞬間、何故か全身から血の気が引いたような感覚がして、航汰は顔面蒼白になり、一瞬電話に出ようかどうしようか躊躇した。嫌な予感がする、と彼は上体を起こした格好のまま、端末を眺めていた。予感はあるが、出ない訳にはいかない。液晶を出して通話ボタンをタップし、恐る恐る彼は画面を見つめた。
応対した店員は特に何の感情も見せぬまま、二人を個室に通し、航汰は芽衣奈の歌を聴いていた。自分で選んだのか、あまり記憶に無い烏龍茶をちびちび飲みながら、航汰は芽衣奈がノリノリで歌う流行の歌を聴く。芽衣奈は時々、こうして航汰を色んな場所に連れて行ってくれるが、その度に航汰は心から楽しめない自分を疎み、彼女に申し訳ない気持ちでいっぱいになっていくのだった。
五曲目が終わったところで、芽衣奈は一旦休憩を摂るらしく、航汰の隣に戻ってきてレモンスカッシュを一口飲んだ。素人ながらに咳払いをして喉の調子を見た後、「で、どう?」と期待に満ちた眼差しで航汰に訊いてきた。一瞬、何のことか分からなかった彼は、のろのろと彼女の方へ顔を向けて「どう、って?」と訊き返す。その鈍い反応に「もうっ」と少し拗ねてみせた芽衣奈は、身を乗り出して迫る。
「航汰、あんた今まで何聴いてたのよ。私の歌に決まってんじゃない」
「ごめん。流行の歌って、よく分からないから」
「ふぅ~ん。じゃあ、航汰が流行の歌知るのは、私の歌だけなんだ?」
「うん」
そう聞くと、芽衣奈はどこか嬉しそうに「えへへ」と笑い、「じゃあ、また歌うね」と上機嫌でまたマイクを持つ。それからまた二曲歌うと満足したのか、また隣に座ってレモンスカッシュを飲んだ。そこで何となく沈黙が流れ、航汰は以前からずっと持っていた疑問を訊いてみることにした。
「ねぇ、芽衣奈」
「なに?」
「芽衣奈はさ、なんで僕に構うの? いくら幼馴染みだからって、無理して僕と関わることなんてしなくていいんだよ。むしろ、僕と一緒にいると――」
「芽衣奈もどんな目に遭わされるか分からない」という心配の言葉は、他でもない芽衣奈の手によって吐露されることは無かった。ぐい、と手を引かれて航汰の頬に何か柔らかい感触がした。突然のことに驚き、何も反応できない航汰へ少し頬を赤らめた彼女は、優しく微笑んで続けた。
「こういうこと。私があんたに構う理由。ね? 今は応えて欲しいなんて言わないから。でも、いつか、教えてね」
まさか彼女が自分に対してそんな想いを抱えていたなんて、全く気が付いていなかった航汰は、何も言えずにただ頷くことしかできなかった。少ししてから漸く羞恥心が湧き起こり、航汰の顔が段々赤くなっていく。微かに幸せな気持ちが浮かんでくると同時に、恐怖が湧き起こる。もし、こんなことが周りに知れてしまったら、同級生達になんて知れてしまったら、芽衣奈がどうなるか分からない。あいつらだって、馬鹿ではないのだ。もし、彼女一人で対応し切れない事態が起きてしまったら、どうしよう。
どこかすっきりしたような、嬉しそうな表情で歌い続ける芽衣奈とは対照的に、航汰は青ざめて頭を抱えているのであった。
それから航汰の予想が的中するのにそう時間は掛からなかった。
芽衣奈とカラオケに行った翌日の放課後、さて帰ろうと下駄箱までやって来た彼に声を掛ける大人がいた。彼がそちらへ振り返ると、そこには副担任教師の来間直子が何やら大量のプリントを持って佇んでいた。彼女は申し訳なさそうに眉を下げて航汰に手伝って欲しいと言った。
「ごめんね、時風君。先生一人じゃ、ちょっと運ぶの大変で。少しだけ手伝ってくれる?」
彼女も教師という体面があるせいか、時々こうして口実を作っては航汰をいじめ連中から避難させてくれる。一瞬、今日は断ろうと思った航汰だが、端末にいじめ連中のリーダーから連絡が入り、放課後いつもの場所で待ってると簡潔なメッセージが届く。それを見て、あいつらが飽きて帰るまでやり過ごすことにした航汰は端末の電源を落とし、制服のポケットに突っ込んで来間からプリントを半分受け取った。
向かうは三階の資料室。プリントを紐綴じにした物を取り敢えず保存しておく為に持って行くようだ。移動中、特に話題も無いので、航汰はこの大量の資料は何かと訊いた。
「先生、この資料って何ですか?」
「ん? ああ、これはね。四年前の生徒さん達に関するものだったり、学校行事の記録なの。本当は劣化防止の為にファイルに入れるのが決まりなんだけど、うっかり在庫が無くなっちゃって。だから、一旦紐でくくって持っていくことになったのよ」
「量が多くてごめんね」とまた謝られる。それに「いいえ」と返して、航汰はぽつりと呟いた。
「いつも先生がこうやって色々口実を作ってくれて、僕を避難させてくれるの。正直、有り難いです。……とても」
少し照れながら告げられた素直な言葉に、来間は穏やかな笑みを浮かべて「そう? なら、良かった」と心底嬉しそうに笑った。慎重な足取りで階段を上り、資料室へ着くと、来間は先に入って窓際に置いてあるスチールの机へ資料を置いた。航汰もそれに倣って置く。来間はすぐ近くの棚を開けて、持ってきた資料を丁寧に積んだ。これを後二回はしなければいけないらしく、来間はもう一度「ごめんね」と謝った。
三階の資料室から屋上に繋がるドアまではそれなりに離れているが、いつ鉢合わせるとも限らない。なので、航汰は廊下へ出る時、必ず周囲に注意を払ってから出て行き、職員室から資料を持って来た時は、奴らの足音が聞こえてこないか、びくびくしながら上った。そんな彼の様子を見て、来間は必ず彼の前へ出て見張ってくれていた。
そんな調子で無事に全ての資料を運び終え、「じゃあ、帰ります」と出て行こうとした航汰を呼び止めた来間は、廊下に誰もいないことを資料室の引き戸に組み込まれている窓から確認して、ポケットから何かを取り出した。
「手を出してみて」
「? 何ですか?」
「ふふ、いいから」
言われるがままに航汰が手を出すと、来間はその掌に手の中の物を握らせた。「他の生徒さん達には内緒ね」と悪戯っ子のような笑みを見せる。そっと手の中にある物を見ると、それは個包装に入っているのど飴だった。さくらんぼ味と書かれた涼しげな文字を見て、航汰は不思議そうに来間を見返して言った。
「いいんですか? こういうの」
「だから、他の子には内緒なの」
「それ食べて元気出してね」と明るく言う来間に、航汰は上手く返せないながらも、大切そうにぎゅっと握り、ズボンのポケットへ入れた。
それから不思議とその日は誰にも絡まれることは無く、さっさと帰ろうと航汰は家路へ着く。帰り道でも不気味な程に、同級生達にも芽衣奈にも会わずに、無事に家へ辿り着くことができた。鞄から鍵を取り出して開けようとしたところで、何か予感のようなものを覚えた航汰だったが、気のせいだと思い、いつもと同じように鍵を開けて入った。
「ただいま」
まだ自分以外誰も帰ってきていないと分かりきっているが、一応帰って来たことを家に知らせる。リビングへは行かず、そのまま航汰は自室へ向かった。
自室に入ると鞄を適当に床へ放り、窓を少し開けてベッドへ仰向けに寝転んだ。外を見るのが億劫でいつも閉め切っているレースのカーテンが風に揺れる。透けたその先に見える夕陽が航汰は好きだった。町中をオレンジ色の光が照らし、毎日毎日これが最期の輝きだとでも言うかのように自身の全てを燃やし尽くすような琥珀色の自然光。彼がどんなに酷い目に遭っても、芽衣奈とこの夕陽だけはいつも優しかった。その陽を見つめていると、航汰の瞼は段々重くなっていった。
いつの間に眠っていたのか、次に航汰が目を開けた時は真っ暗だった。町の街灯が微かに差し込んでくる以外、光源は無い。車通りも少ない閑静な住宅街。両親はまだ帰って来ていないらしく、物音一つしない。そんな中で、唐突に彼の端末が鳴った。表示されている名前を見ると、芽衣奈からだった。
その名前を見た瞬間、何故か全身から血の気が引いたような感覚がして、航汰は顔面蒼白になり、一瞬電話に出ようかどうしようか躊躇した。嫌な予感がする、と彼は上体を起こした格好のまま、端末を眺めていた。予感はあるが、出ない訳にはいかない。液晶を出して通話ボタンをタップし、恐る恐る彼は画面を見つめた。