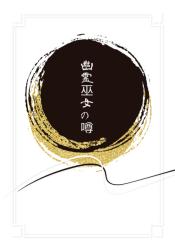風呂から上がってからも世話をしようとするステラを断ろうとしたが、「アストライア様は王女様ですので、相応しい香りを身に付けて頂きたいです」と押し切られてしまった。確かに、と私も納得してしまったというのもある。体を拭いた後、ステラが持ってきたらしい香油を体の背面に塗ってもらいながら、自分で自分の前面に塗る。種類は分からないけど、花の良い香りがする。薔薇に似た感じの香りだ。
「良い匂い。何ていう花の香り?」
「これはですね、ローゼスという花の香りですよ。樹国から取り寄せた天然物です」
「そうなんだ。・・・・・・ジュコク? って?」
「ああ、そうですね。この世界の国についても説明が必要ですよね」
ステラによる凄く簡単な説明によると、この世界は五つの国で構成されているのだという。それぞれ土地の特徴が全く違うことから火・水・地・木・金の国と呼ばれ、住んでいる種族も思想や文化も異なっている。この水の国は隣国の木の国と協力関係にあり、交易も盛んで、今使った香油も木の国から仕入れた物だそうだ。『樹国』という言い方は略称のようなもので、この世界に住んでいる者は皆日常的に使う名称らしい。
「そうなんだ。何だか複雑そうだね」
「――おそらく、今のアンナはアストライア様のお体ですから、先程あなたが危惧した通りのことはあると思います。申し訳ありませんが、アンナにもそれなりの知識や教養などを付けて頂くことになると思いますよ」
「……王女様として違和感無いようにってこと?」
「ええ。アイビー様も同じことをお考えだとは思いますが」
この国の王女様として振る舞い、決して魂が別人だと悟られないように。国の一端を担う立場の人間なのだから、それは当然だとは思っていたけれど、こうして改めて言われると不安ばかりが大きくなっていく。不安そうな顔をしていたのか、はっと気が付いたステラが「ごめんなさい」と謝る。
「ステラが謝ること無いよ?」
「いえ、本当は私があなたの不安を取り除かなければならないのに、逆に不安にさせるようなことを言ってしまいました。本当にごめんなさい」
「王族に負担を掛けるようなことをして、極刑に値します」と重々しい響きの言葉に心臓を直接掴まれたような心地がして、思わずステラの方へ振り返り、その肩を掴んだ。うわ、細い。掴まれたステラは驚いて手が止まり、私と目を合わせてくれた。
「そんな極端なこと言わなくても良いじゃない。今の私は王族でも何でも無いんだから」
「友達感覚で良いんだよ?」と続く筈だった言葉は、ステラが静かに首を振ることで遮られる。沈痛なようにも見える表情から、これは思ったよりずっと重いことなのだと感じてしまった。
「いいえ。いいえ、アンナ。魂はあなたでもそのお体とお立場は違うのです。今のあなたは水国の第三王女、アストライア様であらせられます。……本当にごめんなさい」
それは何に対しての謝罪なのか、私には分からなかった。この世界に呼んでしまったことに対して? 人違いをしたことに対して? それとも、『私(アンナ)』を否定したことに対して? それを訊くのは、何よりも怖かった。
体を拭き、香油を塗り、青いドレスに袖を通して鏡に映る私はすっかり異世界の王女様になった。金色の長い髪に薄紫色の目、手足は細くすらりと伸び、柔らかな胸は白く滑らかで形も良く、腹には余計な脂肪などついていない。理想的な体だ。でも、これは私のじゃない。それがどうしようもない程の疎外感と違和感を生んでいた。ステラに連れられてアイビーがいるだろうアストライアの部屋に案内される。日はすっかり昇ってもうすぐ朝食の時間になろうとしている、とステラが教えてくれた。その道すがら、ふと外を見てみたくなって、スカートの端を摘まんで歩きながら窓の方を見た。ガラスが填まっていない窓から見える景色は、やはり私の知らないものだった。
アストライアの部屋に戻ると、そこには依然としてアイビーがいた。そこで彼に「あれ?」と何か違和感を覚える。でも、その違和感の正体が掴めなくて、私は声に出すことはしなかった。彼は部屋に入って来た私を見ると、何故か暫し固まっていたけれど、私が「なに?」と声を掛けると、「な、何でもない」といつものしかめっ面に戻った。
「アストライア様と同じ香油か」
「ええ。私の方でできるだけアストライア様と同じ物をご用意致しました」
「ああ、それが良いだろう」
今、この人、匂い嗅いだ? と少し引いたけれど、下からふわりと舞い上がった香りになるほどと納得した。香油はおそらく、香水も兼ねているんだろう。ふとした時に香るのが何だか気分が上がる。ステラに促されて化粧台の前に座りつつ、ちょっとだけ機嫌が良くなって口元が緩むと、直ぐ様険しい顔をしたアイビーが「もっと賢そうな顔をしろ」と文句を言ってくる。それにまた気分を害されて私は鏡越しに彼を睨んだ。そんな私に意を介さず、彼は化粧台の引き出しからいくつかアクセサリーを出してきた。様々な色の宝石が填まったティアラや金のロケットペンダントに指輪。さすが王女様はアクセサリーも豪華だなんて考えていると、「動くなよ」と言って背後に立ったアイビーが一つずつ丁寧な手つきで付けてくれる。最初にロケットペンダント、次に指輪、最後にティアラを私の頭に載せると、彼の「こちらを向け」という命令で渋々彼と向かい合わせになるよう座り直す。向かい合うと、彼にぎゅっと両手を握られた。
「え? な、なに……?」
「そう身構えるな。いつもやっていることだ」
あんたら、いつも人目も憚らずにイチャついているのかと思ったけれど、違った。アイビーは手だけに集中しているようでこっちを見ていない。小さな声で何事かぶつぶつ呟いていたかと思うと、次第に彼の周りに小さな光が現れ始め、それは私がしている指輪に吸収されているようだった。それが一つ分終わると、その隣の指輪に移る。彼が何を言っているのか聞き取ろうと、私は耳を澄ませた。
「女神ヴィーナヴィアよ、この御方を蝕む毒から護り給え」
名前は分からないけど、黄色の石が填まっている指輪にその願いが光と共に込められる。それからも次々に宝石の一つ一つにアイビーは願いと共に光を込めていく。健康を願ったり、あんしじゅつ? から護ったり、怪我をしないよう願ったり、魅力的になるようにという願いまで込められていく。「いつもしている」という言葉が思い起こされ、私は次第に罪悪感に似たものを感じ始めていた。アイビーにとってアストライアは毎日こんなに願いを込める程の人で、本当に大事な人なのだと思い知らされる。本来、この祈りはアストライアへ捧げられるものだ。私じゃない。それを思うと、気持ちは鉛のように重くなった。
全ての祈りが終わるとアイビーは顔を上げ、「気分はどうだ?」と訊いた。特に異常は無いと答えると、彼は「そうか」と微笑む。その笑みが自分に向けてなのか、アストライアに向けてなのか、よく分からなくて私は何も言えない。その代わりに一度だけ頷くと同時に部屋の扉が三回ノックされた。
「おはようございます、アストライア様。朝食のご用意が出来ております」
扉越しに聞き慣れない声が掛けられ、返事をするべきなのか戸惑っていると、ステラが「アストライア様はまだもう少々ご準備がありますので、とお伝えください」と機転を利かせてくれた。扉の向こうの誰かはそう聞くと、「分かりました。では、ここで待たせて頂いても?」と返ってくる。その口振りからきっとステラより上の立場の人間だろうと思うが、彼女は引かずに「ありがとうございます」とだけ返した。
ステラに小声で礼を言うと、彼女はこちらへ向けてにっこりと微笑む。しかし、あまり時間は無いと呟いたアイビーは、私を立たせて耳元で囁いた。
「いつもこの時間は国王陛下・王妃陛下との朝食だ。お前には第三王女アストライア様として振る舞ってもらう。今、この御方の置かれている状況を話しておくから、頭に叩き込め」
正直、「無理!」と抵抗したかったけれど、有無を言わせない彼の表情に、私は覚悟を決めるしかなかった。
「良い匂い。何ていう花の香り?」
「これはですね、ローゼスという花の香りですよ。樹国から取り寄せた天然物です」
「そうなんだ。・・・・・・ジュコク? って?」
「ああ、そうですね。この世界の国についても説明が必要ですよね」
ステラによる凄く簡単な説明によると、この世界は五つの国で構成されているのだという。それぞれ土地の特徴が全く違うことから火・水・地・木・金の国と呼ばれ、住んでいる種族も思想や文化も異なっている。この水の国は隣国の木の国と協力関係にあり、交易も盛んで、今使った香油も木の国から仕入れた物だそうだ。『樹国』という言い方は略称のようなもので、この世界に住んでいる者は皆日常的に使う名称らしい。
「そうなんだ。何だか複雑そうだね」
「――おそらく、今のアンナはアストライア様のお体ですから、先程あなたが危惧した通りのことはあると思います。申し訳ありませんが、アンナにもそれなりの知識や教養などを付けて頂くことになると思いますよ」
「……王女様として違和感無いようにってこと?」
「ええ。アイビー様も同じことをお考えだとは思いますが」
この国の王女様として振る舞い、決して魂が別人だと悟られないように。国の一端を担う立場の人間なのだから、それは当然だとは思っていたけれど、こうして改めて言われると不安ばかりが大きくなっていく。不安そうな顔をしていたのか、はっと気が付いたステラが「ごめんなさい」と謝る。
「ステラが謝ること無いよ?」
「いえ、本当は私があなたの不安を取り除かなければならないのに、逆に不安にさせるようなことを言ってしまいました。本当にごめんなさい」
「王族に負担を掛けるようなことをして、極刑に値します」と重々しい響きの言葉に心臓を直接掴まれたような心地がして、思わずステラの方へ振り返り、その肩を掴んだ。うわ、細い。掴まれたステラは驚いて手が止まり、私と目を合わせてくれた。
「そんな極端なこと言わなくても良いじゃない。今の私は王族でも何でも無いんだから」
「友達感覚で良いんだよ?」と続く筈だった言葉は、ステラが静かに首を振ることで遮られる。沈痛なようにも見える表情から、これは思ったよりずっと重いことなのだと感じてしまった。
「いいえ。いいえ、アンナ。魂はあなたでもそのお体とお立場は違うのです。今のあなたは水国の第三王女、アストライア様であらせられます。……本当にごめんなさい」
それは何に対しての謝罪なのか、私には分からなかった。この世界に呼んでしまったことに対して? 人違いをしたことに対して? それとも、『私(アンナ)』を否定したことに対して? それを訊くのは、何よりも怖かった。
体を拭き、香油を塗り、青いドレスに袖を通して鏡に映る私はすっかり異世界の王女様になった。金色の長い髪に薄紫色の目、手足は細くすらりと伸び、柔らかな胸は白く滑らかで形も良く、腹には余計な脂肪などついていない。理想的な体だ。でも、これは私のじゃない。それがどうしようもない程の疎外感と違和感を生んでいた。ステラに連れられてアイビーがいるだろうアストライアの部屋に案内される。日はすっかり昇ってもうすぐ朝食の時間になろうとしている、とステラが教えてくれた。その道すがら、ふと外を見てみたくなって、スカートの端を摘まんで歩きながら窓の方を見た。ガラスが填まっていない窓から見える景色は、やはり私の知らないものだった。
アストライアの部屋に戻ると、そこには依然としてアイビーがいた。そこで彼に「あれ?」と何か違和感を覚える。でも、その違和感の正体が掴めなくて、私は声に出すことはしなかった。彼は部屋に入って来た私を見ると、何故か暫し固まっていたけれど、私が「なに?」と声を掛けると、「な、何でもない」といつものしかめっ面に戻った。
「アストライア様と同じ香油か」
「ええ。私の方でできるだけアストライア様と同じ物をご用意致しました」
「ああ、それが良いだろう」
今、この人、匂い嗅いだ? と少し引いたけれど、下からふわりと舞い上がった香りになるほどと納得した。香油はおそらく、香水も兼ねているんだろう。ふとした時に香るのが何だか気分が上がる。ステラに促されて化粧台の前に座りつつ、ちょっとだけ機嫌が良くなって口元が緩むと、直ぐ様険しい顔をしたアイビーが「もっと賢そうな顔をしろ」と文句を言ってくる。それにまた気分を害されて私は鏡越しに彼を睨んだ。そんな私に意を介さず、彼は化粧台の引き出しからいくつかアクセサリーを出してきた。様々な色の宝石が填まったティアラや金のロケットペンダントに指輪。さすが王女様はアクセサリーも豪華だなんて考えていると、「動くなよ」と言って背後に立ったアイビーが一つずつ丁寧な手つきで付けてくれる。最初にロケットペンダント、次に指輪、最後にティアラを私の頭に載せると、彼の「こちらを向け」という命令で渋々彼と向かい合わせになるよう座り直す。向かい合うと、彼にぎゅっと両手を握られた。
「え? な、なに……?」
「そう身構えるな。いつもやっていることだ」
あんたら、いつも人目も憚らずにイチャついているのかと思ったけれど、違った。アイビーは手だけに集中しているようでこっちを見ていない。小さな声で何事かぶつぶつ呟いていたかと思うと、次第に彼の周りに小さな光が現れ始め、それは私がしている指輪に吸収されているようだった。それが一つ分終わると、その隣の指輪に移る。彼が何を言っているのか聞き取ろうと、私は耳を澄ませた。
「女神ヴィーナヴィアよ、この御方を蝕む毒から護り給え」
名前は分からないけど、黄色の石が填まっている指輪にその願いが光と共に込められる。それからも次々に宝石の一つ一つにアイビーは願いと共に光を込めていく。健康を願ったり、あんしじゅつ? から護ったり、怪我をしないよう願ったり、魅力的になるようにという願いまで込められていく。「いつもしている」という言葉が思い起こされ、私は次第に罪悪感に似たものを感じ始めていた。アイビーにとってアストライアは毎日こんなに願いを込める程の人で、本当に大事な人なのだと思い知らされる。本来、この祈りはアストライアへ捧げられるものだ。私じゃない。それを思うと、気持ちは鉛のように重くなった。
全ての祈りが終わるとアイビーは顔を上げ、「気分はどうだ?」と訊いた。特に異常は無いと答えると、彼は「そうか」と微笑む。その笑みが自分に向けてなのか、アストライアに向けてなのか、よく分からなくて私は何も言えない。その代わりに一度だけ頷くと同時に部屋の扉が三回ノックされた。
「おはようございます、アストライア様。朝食のご用意が出来ております」
扉越しに聞き慣れない声が掛けられ、返事をするべきなのか戸惑っていると、ステラが「アストライア様はまだもう少々ご準備がありますので、とお伝えください」と機転を利かせてくれた。扉の向こうの誰かはそう聞くと、「分かりました。では、ここで待たせて頂いても?」と返ってくる。その口振りからきっとステラより上の立場の人間だろうと思うが、彼女は引かずに「ありがとうございます」とだけ返した。
ステラに小声で礼を言うと、彼女はこちらへ向けてにっこりと微笑む。しかし、あまり時間は無いと呟いたアイビーは、私を立たせて耳元で囁いた。
「いつもこの時間は国王陛下・王妃陛下との朝食だ。お前には第三王女アストライア様として振る舞ってもらう。今、この御方の置かれている状況を話しておくから、頭に叩き込め」
正直、「無理!」と抵抗したかったけれど、有無を言わせない彼の表情に、私は覚悟を決めるしかなかった。