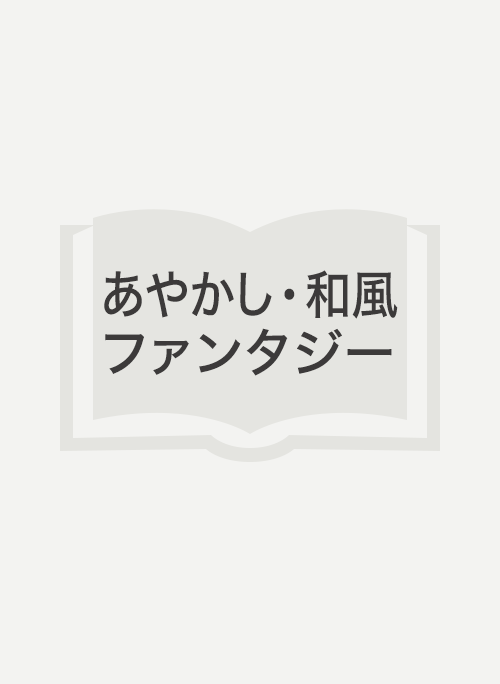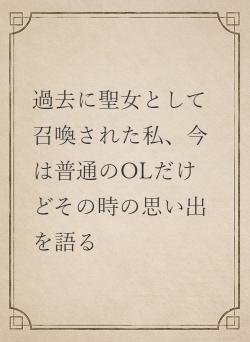あの日見た夜景は特別で
だから一生忘れられない
「ねっ、同窓会行くよね?」
日曜日の昼間、カフェで注文するなり友人はそう聞いた。
明るい店内と楽しげな音楽。
私はふかふかの椅子に手を置くと言った。
「……まあ、一応」
「一応ってなに! 美和来ないとやる気でないよー」
「まあ、出席で返事したよ」
私――有村美和は二十五歳。地方都市に住む普通のOLだ。いっしょにいるのは高校時代の友人・有紀。今日はふたりでカフェにきている。
「同窓会と言えばさぁ! 恭平もくるんじゃない?」
「…………くるかなー」
――斉藤恭平。
彼にもう一度会えるかも、というのは、私自身ずっと思っていることだった。
遠い遠い東京へ、行ってしまった彼。
彼と私は、高校時代の友人だった。
恭平は、頭の良い男の子だった。
柔らかな髪はくせっ毛で、長身で、それからよく笑った。
友人だった、といっても、遊びに出かけたことはない。
私と彼は高校一年生の時は同じクラスだったけれど、その時はあまり話さなかったし、それ以降同じクラスになったことがなかった。
そんな私たちの友情とは、期末テストの順位表が貼りだされるときだった。
期末テストの順位表は、廊下にずらりと貼り出される。
それを私が見に行くのは、順位が気になるからだけじゃなくて、恭平に会えるからだった。
「くっそー。期末試験の順位、国語だけ抜かれたな」
「恭平」
見ていると、やっぱり彼がきた。
恭平はいつも友人に囲まれていて、今日も三人でやってきていた。
彼は私の後ろに立つと、
「あとは俺の勝ちなんだけどなー」
「国語だけは負けたくないけど」
「美和強ぇえー」
「よく言うよ。あとは全部恭平の方が順位高いじゃん」
「ははっ」
恭平は少し笑うと、手でぽんと私の頭を叩いて廊下を歩き出す。
「なに?」
「がんばれよー」
ひらりと振られる手。そう言って彼は去って行く。
触れられた頭を押さえて、私はそれを見送る。
私と恭平は期末テストの順位を競うだけで、いっしょに出かけたこともない。けれど、テストの順位表が貼られるたびに話しかけてくれて、そのたびに嬉しくいて、でも上手く遊びには誘えなくて。彼が笑いながら去って行くたびに、照れてしまうのを隠すように「まったくもう」と自分の口がへの字になる。彼がそういったことをするのは私だけで、だから……もしかしたら、卒業式の日になにかあるんじゃないかと思ったけれど。
結局、私たちは何もなかったのである。
卒業後、恭平は親の転勤とともに東京の大学へと進学した。
両親揃って引っ越しということは……里帰りもないということで。
……そのまま東京の会社に就職したと聞く。
私のいる県は、地方都市だ。
東京からは新幹線で何時間もかかる。
――けれど、私は自分の県をそんなに田舎だとは思わない。
そりゃあ、関東に比べたらっていうのはあるけれど。
アーティストのライブで、たとえば『八大ツアー』くらいあるライブだったら入ってるし。
お店だって結構ある。
関東にある店も、チェーン店でさえあればだいたいはある。
会社もまあまあこんなもんかなというところへ入れたし……つまりは私は地元でそこそこ満足している。
ただ、――恭平は東京へと行ってしまった。
そのまま就職も向こうでってことは、やっぱり東京の方がいいってこと……なのかな。
私は、今でもあの頃のまま。どこへも行けない。
彼を追いかけるほどの関係にもなれず、……ただ、同窓会のハガキを毎日眺めているだけ。
「美和、恭平とは本当になにもなかったのー?」
「う、うん」
友人の有紀の声ではっとする。
そうだ、私、今カフェにいるんだ。
恭平は……モテていた、と思う。
でも彼は彼女を作らなかった。だからこそ、もしかしたら、なんて卒業式の日まで思っていたっけ。
私は、少し冷めたコーヒーを啜った。
そして迎えた同窓会の日。
仲の良い友達とは卒業後も会ったりしたけど、こうして同窓会としてみんなと会うのは初めてだ。
会場は、ホテルの中の小さなホールを貸し切っており、煌びやかで胸が高鳴る。
(恭平も、きてるのかな……)
そわそわして、頻繁に周りをキョロキョロとしてしまう。
今日のために、新しいワンピースドレスを着てきた。
適当に飲み物を貰い、口をつける。
すると、
「美和じゃん! 元気?」
「恭平……」
ぽんと頭に触れられた手。
そこには、大人になった恭平がいた。
スーツにネクタイ、髪はワックスでセットされていて――。
「ははっ。美和全然変わらないなー」
「恭平は……変わったね」
恭平は変わった。
元々格好良かったと思うけど……なんというか、都会っぽくなったっていうか……。垢抜けてるっていうか……。
思わずドキドキしてしまう。
「俺こっちくるの久しぶり! 卒業後全然これてなくて」
「だ、だよね。……東京どう?」
「楽しいよ」
「…………そっか」
そう、だろうな、って思っていた。
手に持ったジンジャーエールを、つつっと飲む。
グラスが空になってしまい、なんだか手元がそわそわしてしまう。
そんな私に、彼は言った。
「な、美和ー。工場夜景を見に行かないか?」
「……え?」
工場夜景?
「わっわっ……」
「しっかりつかまってろよー」
「うん……っ」
恭平のバイクの後ろに乗る。
バイクの二人乗り――タンデムデートってやつ?
こんなこと、私はもちろん初めてだ。
私は恭平の腰に恐る恐るしがみついている。
こんな……こんなっ。腰とか触っちゃっていいのっ?
夜の道路を、バイクで走る。
「これどうしたの?」と聞いたら「駅前のレンタルバイク」って返ってきた。そんな、普通同窓会ってタクシーとかでこない? もしくはレンタルでもレンタカーとか……。
っとは思ったけれど、バイクに乗っている恭平は似合っていた。……正直に言おう、格好良かった。
私のハンドバッグはバイクの椅子の中――メットインというらしい――に入れられ、代わりにそこからでてきたヘルメットを受け取った。
――同窓会が終わると、私たちは二次会には行かずに抜けてきた。それだけで、もしかしたら、という気持ちが膨らむ。
そして私たちは風を切って走っている。
しばらく走ると、海の近くにでた。
「わ……。すご……」
「どーだぁっ!? 綺麗だろ!!」
恭平が、風に負けないように大きな声で言う。
ここには、大きな――この街で一番大きな工場がある。
工場の明かりはオレンジで、光がたくさんあって、建物というか鉄骨やらタンクやらの高さもバラバラで、だから光がたくさんあった。私の会社の窓から漏れるLEDとは全然違う。
ずっとこの街にあったモノだけど――こうしてわざわざ夜景を見に来るのは初めてだ。
オレンジの光は綺麗で、それを恭平の背で見れるなんて、……なんだか不思議だ。
工場沿いの道路を、バイクは走る。
やがて坂道を上り、小高い公園の前でバイクは止まった。
「降りよ」
「あ、ありがと」
降りてヘルメットをとると、恭平がそれをさっと持っていってバイクにひっかけた。
同窓会のためにセットした髪型は崩れてしまったようだ。あわてて手ぐしで直す。
夜の公園は誰もいない。
蛍光灯は新しく、明るい。
私は公園に入ると、奥の方へと進んだ。
奥の方にはフェンスがあって、その金網にカシャンと指を掛ける。
公園は高いところにあって、下の方に工場夜景が広がっている。
恭平も近付いてきて、隣に並んだ。
「どう?」
「いいね。夜にこっちに来たの、初めてかも。通ったことはあるかもだけど、こうしてちゃんと見たことなかった」
「最近さー流行ってるらしいじゃん? テレビでさ、『写真家が結構撮りに来てる』ーとか見ると、こっちのこと思い出してたんだ」
「あー、ね。テレビとかでたまーにやってるよね」
ゴールデンタイムのテレビでも紹介されることがある。それは私も知っていた。
工場の高炉から、ボウ。ボウ! と火がでた。意外と大きな音で、ここまで音が届くんだ、と思った。
「……でも、なんで私?」
「んー。美和に久しぶりに、会えたから?」
「…………えっと……」
ねぇ、それって、どういう意味?
「俺、東京に行ったけど……美和のこと覚えてるよ。ずっとテストの順位競ってたよな。あの頃は楽しかったよなー!」
「う、うん……」
「順位表、女子ってあんま上位いなかっただろ? だから美和ってめずらしくてさ。しかもいっつも俺の順位の近くだっただろ? 負けたときは悔しかったなー」
「…………そうだね」
私の、今でも忘れられない思い出だ。
もしかして――恭平も、同じなの?
「工場夜景見に来れて良かったなー。一回は来てみたいって思ってたからさ」
「……え、もう、来ないの?」
「ははっ。俺、東京だからなー」
「…………そ、うだよね」
カシャンと恭平はフェンスにもたれた。
「……あのさ、美和」
「な、なに?」
恭平の顔が、伏し目がちになって、ドキッとする。
そんなことを思っていると、彼の口がゆっくり開いた。
「……俺、今度結婚するんだ」
「………………え?」
突然、何を言われたのか分からない。
風が吹いて、私の髪が揺れる。
「あのさ、会社の……上司の娘さんと、そういう話になって。まあ、そういうことでさ」
「まって……」
「だから、もうこっちには帰れないんだ」
「待ってよ」
声が、震える。
「ど、どうして今日、私を連れてきてくれたの……?」
「……俺、高校の時、美和のことが好きだった」
「……!」
「でも、言えなかった……。そんな意気地なしの俺でさ、ごめん」
「待って、恭平、なんで? そんな」
「美和」
恭平は、私の唇に指を添えた。
「美和のこと、『変わんないね』って言ったけど……綺麗になっててびっくりした」
「や、やめて……」
「美和、ごめん」
涙がでて、止まらなかった。
「どうして今そんなこと言うの? 私はこの街に住んでて、……この工場夜景とずっといっしょに生きていくのに!」
「綺麗な思い出に、なると思って」
「ならないよ……ばか……」
ただでさえ忘れられなかったのに。
馬鹿な恭平のせいで、私はさらに彼のことが忘れられなくなってしまった。