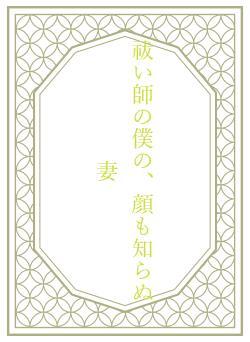お風呂から上がった彼女の髪はまだ濡れていて、乾かすために洗面所からドライヤーを持ってくる。
僕がソファで、床で足の間にちょこんと座った彼女の髪に温風を掛ける。
彼女は昔から面倒臭がりな所があって、髪が濡れたままでも気にしない。
でもそのままでは風邪をひくので、いつも僕がチェックして濡れていたら乾かしてあげるのだ。
髪がふわっと仕上がったのを見計らってドライヤーの電源をオフにすると、彼女は小さな欠伸を漏らす。
「眠い?寝室に行こうか」
「ううん…、まだ起きてる」
いつも寝ようとすると、彼女は嫌だと首を振る。
夜が近づくと、お互いに段々と沈んだ顔になるのを止められない。
寝てしまえば、彼女の記憶は消えるから。
一秒でも長く今日を覚えていたいのだと涙を流すんだ。
「忘れたく、ない…っ、もう何も、忘れたくないよっ」
僕はそんな彼女の背中をギュッと抱きしめて、安心させるために言葉を紡ぎ続ける。