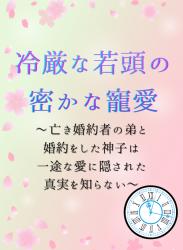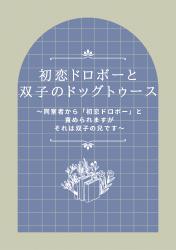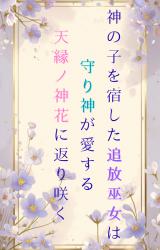「キサマには見えるのだな。この姿が」
「お前が思っているのとは違うかもしれないが。おれには蛍のように見えている。夜半、近くにいてくれたら丁度良さそうな光明だ」
「神を何だと思っている。それでも宮司の倅か」
「宮司の倅だからこそ、お前のことは一番分かっているつもりだ。暇そうに拝殿を覗きに来ていることも、伏せっていた幼きおれの見舞いに来てくれていたのもな」
「見舞いではない。キサマが寝込む度に親兄弟がここに快癒の頼みに来るから、気になって様子を見に行っていただけだ。今回はそこまで深刻なのかと」
この男が幼い頃、病に倒れる度に宮司である男の両親や男の兄たちが交互に本殿を訪れては、快復を神頼みしてきた。豊穣の神には病気快癒の力を持っていないので、そのような願い事をされても困惑するだけなのだが、毎度深刻そうな姿が気掛かりだったこともあり、男が眠る部屋に様子を見に行っていた。
世代を重ねる事に宮司や神主であっても、神やあやかしの存在を視認できる者が減っていた。この男もそうなのだろうと思っていたが、どうやら違ったらしい。神の姿を見たという者は数百年ぶりだったからか、あまり悪い気はしなかった。
「だが、お前のおかげでおれはこうして立派に成長できたのだ。病で伏せるおれの周囲を飛んでいただろう。蛍か不知火のように。この家に生まれていなかったら、とうとうその時が来たのだと勘違いするところだったぞ」
「失礼なことを言うな。様子を見に行っただけで何もしていない。快癒したのはキサマ自身の力だ」
「それでも病の苦しみと戦うおれにとっては一筋の光も同然だった。そんなお前に恩を返したいと思ったからこそ、神饌を捧げる役目を兄上たちから譲り受けたのだ。それなのにお前は頑なに婦女子が捧げた神饌でなければ受け取らぬという。男が捧げる神饌の何が気に入らないのだ」
「答える義理はない」
「おれはお前が心配なのだ。もしお前の力が弱まった原因がおれにあったとしたら、千古よりこの地で宮司を務めてきた先祖たちに顔向けが出来ない。この地で生きる者たちにも……。ここ数年不作が続き、商売も上手くいかぬ。この状態が続けば、いずれ人が離れ、誰も住む者がいない荒野となってしまう。そうなってからでは遅い。お前には力を取り戻して欲しい。かつての実りと豊かさを取り戻してくれないか。そのためなら、おれに出来ることは何でもしよう」
「何度も言わせるつもりか。キサマは何も関係ない。男が捧げる神饌を受け取らないのは美味くないからだ。食には質や見栄え以外に作り手も関係する。清らかな処女が手ずから用意したものなら味も信用に値するが、汚らしい男どもが用意したものなど、どんな味がするのか食えたものではない」
「衛生を心配しているのか。それなら神饌を用意する前には、必ず神社の神域から湧き出る清水で身体を清めている。我が家に代々伝わる古文書の内容に従っているぞ」
「不衛生という意味ではない。いや、それも大事だがそうではない! 邪心の権化とも言える飢えた獣以下の男に処女が用意する神饌以上の美味いものは用意できないと言っている」
「つまり、おれがこれまでお前に仕えてきた婦女子より美味なるものを用意できればいいのだな」
「そういう意味ではない!」
「お前は最初に言ったな。食には質や見栄え以外にも作り手が関係すると。婦女子が調理したから美味、男が調理したから不味とは限らない。これからの時代、そういった先入観は改めるべきだ。おれがそれを変えてやる」
男はそう宣言すると、靴を履いて帽子を被る。決意したかのように足早に去って行く男の背を見ながら神は独り言ちたのだった。
「何をしても無駄だ。考えが変わるわけがない。どうせアイツもすぐに諦めるだろう」
そんな神の目論みこそすぐに外れることになる。それは翌日の出来事であった。
「お前が思っているのとは違うかもしれないが。おれには蛍のように見えている。夜半、近くにいてくれたら丁度良さそうな光明だ」
「神を何だと思っている。それでも宮司の倅か」
「宮司の倅だからこそ、お前のことは一番分かっているつもりだ。暇そうに拝殿を覗きに来ていることも、伏せっていた幼きおれの見舞いに来てくれていたのもな」
「見舞いではない。キサマが寝込む度に親兄弟がここに快癒の頼みに来るから、気になって様子を見に行っていただけだ。今回はそこまで深刻なのかと」
この男が幼い頃、病に倒れる度に宮司である男の両親や男の兄たちが交互に本殿を訪れては、快復を神頼みしてきた。豊穣の神には病気快癒の力を持っていないので、そのような願い事をされても困惑するだけなのだが、毎度深刻そうな姿が気掛かりだったこともあり、男が眠る部屋に様子を見に行っていた。
世代を重ねる事に宮司や神主であっても、神やあやかしの存在を視認できる者が減っていた。この男もそうなのだろうと思っていたが、どうやら違ったらしい。神の姿を見たという者は数百年ぶりだったからか、あまり悪い気はしなかった。
「だが、お前のおかげでおれはこうして立派に成長できたのだ。病で伏せるおれの周囲を飛んでいただろう。蛍か不知火のように。この家に生まれていなかったら、とうとうその時が来たのだと勘違いするところだったぞ」
「失礼なことを言うな。様子を見に行っただけで何もしていない。快癒したのはキサマ自身の力だ」
「それでも病の苦しみと戦うおれにとっては一筋の光も同然だった。そんなお前に恩を返したいと思ったからこそ、神饌を捧げる役目を兄上たちから譲り受けたのだ。それなのにお前は頑なに婦女子が捧げた神饌でなければ受け取らぬという。男が捧げる神饌の何が気に入らないのだ」
「答える義理はない」
「おれはお前が心配なのだ。もしお前の力が弱まった原因がおれにあったとしたら、千古よりこの地で宮司を務めてきた先祖たちに顔向けが出来ない。この地で生きる者たちにも……。ここ数年不作が続き、商売も上手くいかぬ。この状態が続けば、いずれ人が離れ、誰も住む者がいない荒野となってしまう。そうなってからでは遅い。お前には力を取り戻して欲しい。かつての実りと豊かさを取り戻してくれないか。そのためなら、おれに出来ることは何でもしよう」
「何度も言わせるつもりか。キサマは何も関係ない。男が捧げる神饌を受け取らないのは美味くないからだ。食には質や見栄え以外に作り手も関係する。清らかな処女が手ずから用意したものなら味も信用に値するが、汚らしい男どもが用意したものなど、どんな味がするのか食えたものではない」
「衛生を心配しているのか。それなら神饌を用意する前には、必ず神社の神域から湧き出る清水で身体を清めている。我が家に代々伝わる古文書の内容に従っているぞ」
「不衛生という意味ではない。いや、それも大事だがそうではない! 邪心の権化とも言える飢えた獣以下の男に処女が用意する神饌以上の美味いものは用意できないと言っている」
「つまり、おれがこれまでお前に仕えてきた婦女子より美味なるものを用意できればいいのだな」
「そういう意味ではない!」
「お前は最初に言ったな。食には質や見栄え以外にも作り手が関係すると。婦女子が調理したから美味、男が調理したから不味とは限らない。これからの時代、そういった先入観は改めるべきだ。おれがそれを変えてやる」
男はそう宣言すると、靴を履いて帽子を被る。決意したかのように足早に去って行く男の背を見ながら神は独り言ちたのだった。
「何をしても無駄だ。考えが変わるわけがない。どうせアイツもすぐに諦めるだろう」
そんな神の目論みこそすぐに外れることになる。それは翌日の出来事であった。