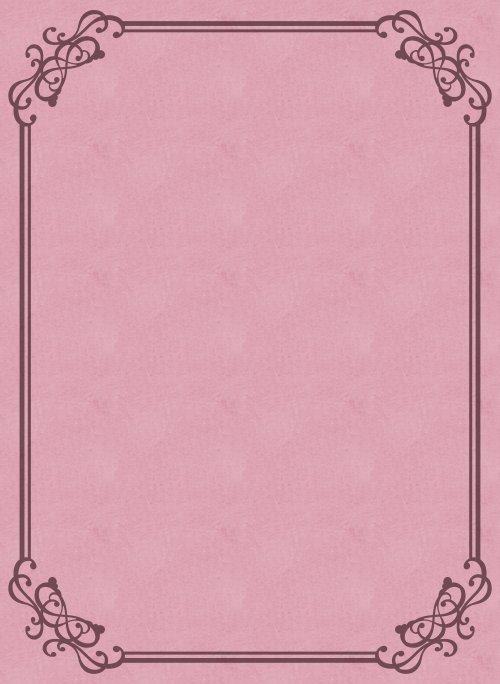梅雨が明けた初夏の夜のこと。
酷く心が沈んでいた僕は、薬を過剰摂取してたった少しの快楽に、心を委ねていた。
僕が過剰摂取するのは仕事で嫌なことがあった時とか、そういうんじゃない。
常に死にたい気持ちが漂っていて、いつも現実逃避の為にしてる。
でも今日は、そんなんじゃ気がすまなかった。
ふわふわと体が感じるうちに、なにか変化を起こしたかった。
いつもならこのまま寝てしまうところだが、今日は何故か外に出たくなった。
何故だろう、何かに引っ張られる感じがして、ちょっと自分が怖くなった。
支度をしながら、どこに行こうかと考えてみる。
「そうだ、海にでも行こうか」
咄嗟の思いつきで、僕は行動に移した。
スマホで海までの行き方を調べてから、財布とスマホをズボンの後ろポケットに入れて、僕は玄関のドアを開けた。
玄関の外は暗く、すっかりあたりは暗くなっていて、街は街頭に照らされていた。
アパートの通路にはカメムシが数匹いて、会社の関わりたくもない嫌な上司たちに思えてきて、刺激しないよう避けて階段をおりた。
ふらふらと何とか最寄りの駅について、電車が来るのを待つ。
30分に1本しか通らない電車は、ひとつ遅れると大変だ。
なんとか電車に乗りこみ、無人駅から乗った僕は電車の中で切符を買った。
田舎にある電車は無人駅というのをよく聞くが、僕の住んでる町も結構な田舎なんだろうなと、薄々感じとっていた。
こんな田舎にも、大きな病院がひとつあって、有名な先生がいるらしい。
僕の病は心から来るものだから専門外だろうな。
僕はこうして過剰摂取するほど追い込まれてるのが現状で、毎日同じことの繰り返しが苦しくて、上司に怒られては、またミスしての繰り返し。
なんにも使えない僕なんかいない方がいいんだろうな、って考えてしまう。
もっと僕に自信があれば、プラス思考ならば、落ち込まずにやる気出して仕事ができるんだろうか。
今の僕じゃ無理だ。
駅からしばらく歩いて海岸に着くと、砂浜に足を取られながらもふらふらと海の方向へ進んでいく。
すると、目の前には先客がいたようで、白いワンピースのような服を着た髪の長い女性がしゃがみこんでいた。
どうやら彼女は歌を口ずさみながら、砂浜に落ちている石や流木を拾っては海にポチョンと投げていた。
こちらに気付いたのか、彼女は後ろを振り返った。
「あ、こんばんは」
自然と挨拶をされて、こちらも慌てて「こんばんは」と返す。
特に喋ることもないのだが、僕は海に来て何がしたかったのか。
それは、ただ死にたかっただけだった。
海の中にフラフラの状態で入れば溺れると思った。
でもそれは、誰もいないのが前提のはなしで、助けを呼ばれちゃおしまいだ。
こんな田舎にすぐに来てくれる人なんているのかと疑問にも思うが、彼女がいるからには、死ぬことなんて不可能だろうと考えた。
第1発見者にさせるのも悪い気がしてくるし、何より彼女の方が貧弱そうに見える。
彼女の石を投げている手首を見ると、病院でつけるリストバンドがしてあった。
この人もしかして、夜中に抜け出してきたんじゃないかと、驚いた。
「青山病院から抜け出してきたんですか」
僕は咄嗟に聞いてしまった。
「…なんで、バレたんですか」
彼女は驚いた表情をしていた。
「腕のリストバンド、病院のですよね」
「あぁ…これね。そう、病院で付けられたやつ。気にしないで、気晴らしに来てるだけだから」
「そう、ですか…」
僕は気になって仕方がなかった。
それでも、喋るなと言わんばかりの重たい空気とは反対に、ひらひらと裾が踊っている白色のワンピースは、とても綺麗だった。
彼女の顔は、暗闇と過剰摂取のせいか視界が少しぼやけてあまり見えなかった。
そんな彼女は口を開いた。
「私ね、余命半年なの、本当は死にたくない」
とても重たい、言葉を。
「そうなんですね」
どんな表情をしているんだろう。
僕は何も言えなかった。
死にたいのに僕とは正反対の言葉、彼女は生きたいと思っている。
「私と交換してよ、こんな時間にふらふらと海に来て死ぬために来たんじゃないの?」
「僕の方もバレてましたか、交換できるぐらいならして欲しいです。でも、出来ないので、僕にはあなたの痛みもわかってあげられませんし、あなたには僕の心の痛みはわかってもらえるわけが無いと思ってます」
ちょっと言いすぎたかな。
「それが正論かぁ、君厳しいこと言うね、逆に面白いよ」
「面白く思われるためにこう生きてませんが」
「君はさ、なんで死にたいの?」
そう言いながら、彼女は砂浜に絵を描き始めた。
「普通に生きられないから、こんな世の中で、なんの楽しみもなく、働いて、働いて、休みなんて体が休まらなくて、人間関係に悩んで辛い思いをするから」
初対面の相手にぶちまけすぎだろうか。
「君、彼女いないでしょ」
「っは?…そりゃいませんけど、なんの関係があるんですか」
「彼女がいたら、また世界変わると思うな。あ、そうだ、私と付き合ってみない?私に人生預けてみてよ」
半年の命だから、どうなってもいいと思ってるんだろうか。
見ず知らずの僕と付き合おうだなんて。
「なんであんたなんかと」
「えー、こんな美少女が付き合おうって言ってるんだよ。余命半年だけど、悪い思いにはさせない!少なくとも、その自殺願望無くして欲しい」
彼女は、ハートを砂浜に描いていた。
「難しい話ですね」
「上見てよ、この綺麗な星空の下で出会えた私達は、一生の宝じゃない?今日の今この場でしか経験できないことだよ」
上を見上げると、確かに空にはたくさんの星と、綺麗な三日月が輝いていた。
「そうか、今日は三日月か」
「三日月に恋愛のお願いごとすると叶うって噂があるの知ってた?いまここで、私たちのお願いごとしてみようよ」
「僕はまだいいとは言ってないです」
「いいからいいから、目瞑って手合わせて」
そう言われ、言われるがままに従った。
死にたい気持ちなんて、彼女と話してるうちに忘れてしまっていた僕の心に気づいた後の願い事は、“彼女が幸せになれますように”だった。
「お願いしたよ」
目を開けてそう言うと、彼女はまだ真剣に祈っていた。
そんな彼女を見ると、綺麗にカールしたまつ毛は、女の子らしさを感じて、少しときめいた。
不覚にも、好意を少し抱いてしまっている僕の気持ちはなんなのか。
三日月を見て、これが恋の願い事が叶うというのはこういう事なのかと、考えた。
「ごめん、おわった?」
横で彼女が僕の顔をのぞき込むと、驚いて少し距離をとろうとすると、ふらついていたせいが、砂浜に足を取られ倒れそうになる。
「うわっっ」
「えっ」
彼女が僕の腕を掴み助けようとするが、僕は砂浜に倒れ、僕に乗っかるように彼女は覆い被さった。
「っ…いたたたっ…」
彼女と目が合って、僕たちは笑った。
「ふふっ、なにやってんだろうねわたしたち」
彼女とグッと距離が近くなったような気がして、緊張が緩んだ。
「ほんとだな」
彼女は怖いほど軽かった。
病気のせいなんだろうかと感じ取った。
僕たちは体制を直して、隣同士に座った。
そっと横目でリストバンドを見ると名前が書いてあった。
前田莉乃 、彼女の名前だろう。
夜空を見上げて、僕たちは喋った。
「神様はさ、見てるんだよ、君が死のうとしてることも、私が死にたくないって思ってることも、鉢合わせたのは神様なんだよ」
「そんなことあるかな」
「あったじゃん、現実で、起きてるじゃん、ここに私たちはいるそれだけで証明されてるよ、私たちを見つけてくれた神様に感謝しなきゃだね」
潮風が体にまとわりついて、少しベタベタとしていても、不思議と嫌じゃなかった。
「たしかにな。僕は出会えてよかったって今思えるよ」
「まだ、死にたい?」
彼女は心配そうに僕に聞いた。
「いや、そんな気持ち忘れてた、君のことで頭がいっぱいになってた」
「そんなまっすぐ言われたら照れくさいよ、よかった。出会えた価値があった。余命半年の私にも、できることがあったって思うと凄く嬉しい」
「まだ半年もあるじゃん、したいこと一緒にしようよ、今度は僕が手伝うよ」
「ほんとに?いいの?でも、半年しかないんだよ、最後も悲しませちゃうかもしれないよ」
「助けて貰ったお礼、今僕が君と一緒にいたいんだ」
この気持ちに嘘は無い。
心惹かれた彼女のために何かがしたい。
「じゃあ、一つお願いしていいかな?」
彼女は願い事を口にする。
「名前も知らない君だけど、私と半年間付き合ってほしい、恋愛の意味として」
僕は死にたい気持ちを無くしてくれた彼女に、恩返しがしたい。
一緒にいたい。
「僕にしかできないこと、手伝わせてもらいます。喜んで」
夜は明け、日の出を見ながら僕たちは半年と限られた契約を交わした。
酷く心が沈んでいた僕は、薬を過剰摂取してたった少しの快楽に、心を委ねていた。
僕が過剰摂取するのは仕事で嫌なことがあった時とか、そういうんじゃない。
常に死にたい気持ちが漂っていて、いつも現実逃避の為にしてる。
でも今日は、そんなんじゃ気がすまなかった。
ふわふわと体が感じるうちに、なにか変化を起こしたかった。
いつもならこのまま寝てしまうところだが、今日は何故か外に出たくなった。
何故だろう、何かに引っ張られる感じがして、ちょっと自分が怖くなった。
支度をしながら、どこに行こうかと考えてみる。
「そうだ、海にでも行こうか」
咄嗟の思いつきで、僕は行動に移した。
スマホで海までの行き方を調べてから、財布とスマホをズボンの後ろポケットに入れて、僕は玄関のドアを開けた。
玄関の外は暗く、すっかりあたりは暗くなっていて、街は街頭に照らされていた。
アパートの通路にはカメムシが数匹いて、会社の関わりたくもない嫌な上司たちに思えてきて、刺激しないよう避けて階段をおりた。
ふらふらと何とか最寄りの駅について、電車が来るのを待つ。
30分に1本しか通らない電車は、ひとつ遅れると大変だ。
なんとか電車に乗りこみ、無人駅から乗った僕は電車の中で切符を買った。
田舎にある電車は無人駅というのをよく聞くが、僕の住んでる町も結構な田舎なんだろうなと、薄々感じとっていた。
こんな田舎にも、大きな病院がひとつあって、有名な先生がいるらしい。
僕の病は心から来るものだから専門外だろうな。
僕はこうして過剰摂取するほど追い込まれてるのが現状で、毎日同じことの繰り返しが苦しくて、上司に怒られては、またミスしての繰り返し。
なんにも使えない僕なんかいない方がいいんだろうな、って考えてしまう。
もっと僕に自信があれば、プラス思考ならば、落ち込まずにやる気出して仕事ができるんだろうか。
今の僕じゃ無理だ。
駅からしばらく歩いて海岸に着くと、砂浜に足を取られながらもふらふらと海の方向へ進んでいく。
すると、目の前には先客がいたようで、白いワンピースのような服を着た髪の長い女性がしゃがみこんでいた。
どうやら彼女は歌を口ずさみながら、砂浜に落ちている石や流木を拾っては海にポチョンと投げていた。
こちらに気付いたのか、彼女は後ろを振り返った。
「あ、こんばんは」
自然と挨拶をされて、こちらも慌てて「こんばんは」と返す。
特に喋ることもないのだが、僕は海に来て何がしたかったのか。
それは、ただ死にたかっただけだった。
海の中にフラフラの状態で入れば溺れると思った。
でもそれは、誰もいないのが前提のはなしで、助けを呼ばれちゃおしまいだ。
こんな田舎にすぐに来てくれる人なんているのかと疑問にも思うが、彼女がいるからには、死ぬことなんて不可能だろうと考えた。
第1発見者にさせるのも悪い気がしてくるし、何より彼女の方が貧弱そうに見える。
彼女の石を投げている手首を見ると、病院でつけるリストバンドがしてあった。
この人もしかして、夜中に抜け出してきたんじゃないかと、驚いた。
「青山病院から抜け出してきたんですか」
僕は咄嗟に聞いてしまった。
「…なんで、バレたんですか」
彼女は驚いた表情をしていた。
「腕のリストバンド、病院のですよね」
「あぁ…これね。そう、病院で付けられたやつ。気にしないで、気晴らしに来てるだけだから」
「そう、ですか…」
僕は気になって仕方がなかった。
それでも、喋るなと言わんばかりの重たい空気とは反対に、ひらひらと裾が踊っている白色のワンピースは、とても綺麗だった。
彼女の顔は、暗闇と過剰摂取のせいか視界が少しぼやけてあまり見えなかった。
そんな彼女は口を開いた。
「私ね、余命半年なの、本当は死にたくない」
とても重たい、言葉を。
「そうなんですね」
どんな表情をしているんだろう。
僕は何も言えなかった。
死にたいのに僕とは正反対の言葉、彼女は生きたいと思っている。
「私と交換してよ、こんな時間にふらふらと海に来て死ぬために来たんじゃないの?」
「僕の方もバレてましたか、交換できるぐらいならして欲しいです。でも、出来ないので、僕にはあなたの痛みもわかってあげられませんし、あなたには僕の心の痛みはわかってもらえるわけが無いと思ってます」
ちょっと言いすぎたかな。
「それが正論かぁ、君厳しいこと言うね、逆に面白いよ」
「面白く思われるためにこう生きてませんが」
「君はさ、なんで死にたいの?」
そう言いながら、彼女は砂浜に絵を描き始めた。
「普通に生きられないから、こんな世の中で、なんの楽しみもなく、働いて、働いて、休みなんて体が休まらなくて、人間関係に悩んで辛い思いをするから」
初対面の相手にぶちまけすぎだろうか。
「君、彼女いないでしょ」
「っは?…そりゃいませんけど、なんの関係があるんですか」
「彼女がいたら、また世界変わると思うな。あ、そうだ、私と付き合ってみない?私に人生預けてみてよ」
半年の命だから、どうなってもいいと思ってるんだろうか。
見ず知らずの僕と付き合おうだなんて。
「なんであんたなんかと」
「えー、こんな美少女が付き合おうって言ってるんだよ。余命半年だけど、悪い思いにはさせない!少なくとも、その自殺願望無くして欲しい」
彼女は、ハートを砂浜に描いていた。
「難しい話ですね」
「上見てよ、この綺麗な星空の下で出会えた私達は、一生の宝じゃない?今日の今この場でしか経験できないことだよ」
上を見上げると、確かに空にはたくさんの星と、綺麗な三日月が輝いていた。
「そうか、今日は三日月か」
「三日月に恋愛のお願いごとすると叶うって噂があるの知ってた?いまここで、私たちのお願いごとしてみようよ」
「僕はまだいいとは言ってないです」
「いいからいいから、目瞑って手合わせて」
そう言われ、言われるがままに従った。
死にたい気持ちなんて、彼女と話してるうちに忘れてしまっていた僕の心に気づいた後の願い事は、“彼女が幸せになれますように”だった。
「お願いしたよ」
目を開けてそう言うと、彼女はまだ真剣に祈っていた。
そんな彼女を見ると、綺麗にカールしたまつ毛は、女の子らしさを感じて、少しときめいた。
不覚にも、好意を少し抱いてしまっている僕の気持ちはなんなのか。
三日月を見て、これが恋の願い事が叶うというのはこういう事なのかと、考えた。
「ごめん、おわった?」
横で彼女が僕の顔をのぞき込むと、驚いて少し距離をとろうとすると、ふらついていたせいが、砂浜に足を取られ倒れそうになる。
「うわっっ」
「えっ」
彼女が僕の腕を掴み助けようとするが、僕は砂浜に倒れ、僕に乗っかるように彼女は覆い被さった。
「っ…いたたたっ…」
彼女と目が合って、僕たちは笑った。
「ふふっ、なにやってんだろうねわたしたち」
彼女とグッと距離が近くなったような気がして、緊張が緩んだ。
「ほんとだな」
彼女は怖いほど軽かった。
病気のせいなんだろうかと感じ取った。
僕たちは体制を直して、隣同士に座った。
そっと横目でリストバンドを見ると名前が書いてあった。
前田莉乃 、彼女の名前だろう。
夜空を見上げて、僕たちは喋った。
「神様はさ、見てるんだよ、君が死のうとしてることも、私が死にたくないって思ってることも、鉢合わせたのは神様なんだよ」
「そんなことあるかな」
「あったじゃん、現実で、起きてるじゃん、ここに私たちはいるそれだけで証明されてるよ、私たちを見つけてくれた神様に感謝しなきゃだね」
潮風が体にまとわりついて、少しベタベタとしていても、不思議と嫌じゃなかった。
「たしかにな。僕は出会えてよかったって今思えるよ」
「まだ、死にたい?」
彼女は心配そうに僕に聞いた。
「いや、そんな気持ち忘れてた、君のことで頭がいっぱいになってた」
「そんなまっすぐ言われたら照れくさいよ、よかった。出会えた価値があった。余命半年の私にも、できることがあったって思うと凄く嬉しい」
「まだ半年もあるじゃん、したいこと一緒にしようよ、今度は僕が手伝うよ」
「ほんとに?いいの?でも、半年しかないんだよ、最後も悲しませちゃうかもしれないよ」
「助けて貰ったお礼、今僕が君と一緒にいたいんだ」
この気持ちに嘘は無い。
心惹かれた彼女のために何かがしたい。
「じゃあ、一つお願いしていいかな?」
彼女は願い事を口にする。
「名前も知らない君だけど、私と半年間付き合ってほしい、恋愛の意味として」
僕は死にたい気持ちを無くしてくれた彼女に、恩返しがしたい。
一緒にいたい。
「僕にしかできないこと、手伝わせてもらいます。喜んで」
夜は明け、日の出を見ながら僕たちは半年と限られた契約を交わした。