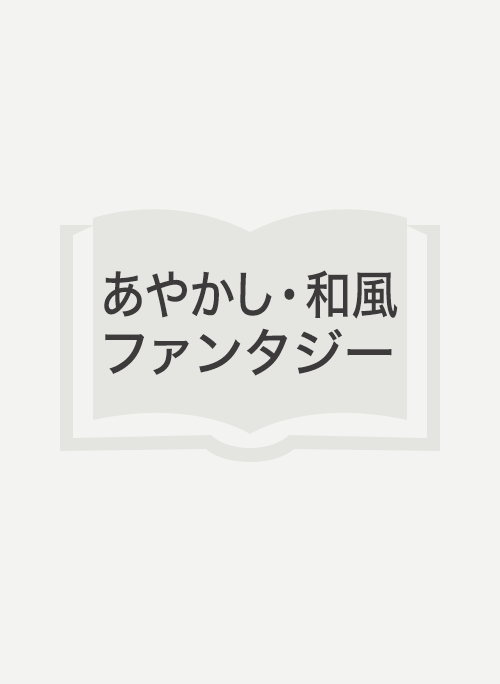「シオリ! ……シオリッ!」
彼の、必死にわたしを呼ぶ声がする。
彼の手が伸ばされて、――わたしはその手を取らなかった。
そしてわたしは、光に包まれた。
***
「お先に失礼します」
「会崎さん、おつかれー。タイムカードはもう押してあるからね」
「…………はい」
会社の事務所を出る。
事務所の入り口のタイムカードを、チラリと見る。
わたし――会崎汐梨のカードには、すでに退勤時間の打刻がしてある。
もちろん、わたしが押したのではない。
今は、夜の二十二時。……経理のおばさんが、二十時に全員のタイムカードを押している。
こんなことは、この会社では日常だ。
「……はぁ」
ため息をひとつこぼし、わたしは退勤した。
わたしは、かつて世界を救っていたことがある。
……今は普通のOLだけれど。
あれは、わたしがまだ高校生のだった時の話だ。
***
「救世主だ! 聖女が召喚されたぞ!」
「ん……」
まばゆい光がようやくやんで、わたしはこわごわと目を開ける。
「え……? ここ、って、……」
そこは――神殿だった。
まるで、漫画やアニメで見るような……そんな神殿だ。
日本人のわたしは、神殿や教会にあまり馴染みはないけれど、白を基調とした建物に、大きなステンドグラス、それから、白いベールをかぶった人々。
わたしの周りには、たくさんの人がいた。彼らは皆同じように白い服を着ていたけれど、その髪色は金髪や赤髪、青髪など……皆アニメの中のような姿をした人ばかりだった。
そしてわたしは、さっきまで着ていたセーラー服のままで、光る魔方陣の中央に座りこんでいたのだ。どうも、姿はそのままらしい。
(これって、異世界転移……ってやつ?)
すぐにそう思った。
「おお! 異世界からの聖女の召喚の儀式が成功したぞ!」
「これで世界は救われる!」
「え、えぇ……?」
「聖女様!」
困惑するわたしのもとへ、神官たちが駆け寄った。
その中に、一人だけ黒い格好をした人がいて、
「お前が聖女か。勇者パーティーへようこそ! 安心しろ、俺がお前を守ってやるからな!」
彼はニッと白い歯をのぞかせて笑いかけてくれた。
――それが、ライアスだった。
***
「ライアス!」
「シオリ! 援護を頼む!」
「……はい!」
わたしたちは勇者パーティーとして、各地へ赴いた。
魔王軍の進軍があると聞けばそこへ駆けつけ、何度も戦闘に赴いた。
わたしには、神官達が言うように聖なる力がちゃんとあって、
その力はこの世界のどんな光魔法よりも強く、浄化の力があった。
勇者パーティーはライアスと他の二人との四人組で、あとのふたりは盾役のデダニと、回復が得意な神官のメリーだった。
デダニが相手の攻撃を受けて、勇者のライアスが攻撃して、わたしの聖なる力で浄化して、メリーの力でパーティーメンバーの回復する。わたしたちは優れた勇者パーティーだった。
いつも先陣をきって戦うライアスの姿は凜々しく、黒髪の短髪に汗の雫が伝う。
キリリとした瞳は、勇者たる信念を持って、大剣をふるっていた。
わたしはいつしか、彼の姿に胸を高鳴らすことが増えていった。
***
ある日の午後。
わたしたちは出動要請がない日で、休養をとっていた。
わたしたち勇者パーティーは、この神殿で寝泊まりしている。
飲み物を持って、神殿の中庭のベンチへと腰掛ける。
明るい日差しの晴れた日で、わたしは「ふぅ」と息をはいた。
勇者パーティーの出動は多く、束の間の休息だ。
「よう、シオリ!」
「わ……。ライアス……!」
そこへ、ライアスがやってきた。
爽やかな黒髪と、明るい金色の瞳。
オフの日なので鎧は着ておらず、ラフな格好だ。
「シオリ、調子はどうだ?」
「大丈夫。ライアスはどう? こないだの戦闘、結構怪我も多かったよね?」
「ああ! メリーが治してくれたからな、大丈夫だ」
「……そう」
わたしは聖女だけれど、わたしの役目は魔物の浄化であって、仲間の傷を癒やす力ではない。
それは、神官のメリーの役目だった。
「シオリも、この世界にきてもうすぐ一年になるな。だいぶ慣れてきたか?」
「あ、うん。最初はびっくりしたけど、……大丈夫だよ。トイレとかお風呂もだいたい同じだったし」
「そっか! なにか困ったことはないか?」
「うーん。意外と大丈夫かも」
意外にも、この世界は居心地がいい。
それは――元いた世界よりも。
わたしの家は、母子家庭だった。
母は……忙しく働いているのかと思いきや、男の家にいることが多かった。
いつも機嫌が悪く、よくある『机の上にお金だけ』……というのもなく、お金もあまり渡してもらえなかった。
「女の子なんだから、節約料理くらい勝手にやるでしょ」
そう母が言っているのを聞いたことがある。
「シオリはいつも頑張ってくれてるよ。いつも本当にありがとうな!」
「う、うん……」
ライアスの言葉で、意識がもどる。
ライアスは、いつも優しい。
母はわたしのことを全然褒めてくれていなかったけれど、ライアスはいつもなにかと褒めてくれる。
だからわたしは、そんな彼の側にいれる今の世界の方が好きだ。
……いや、彼が、か……。
そんなことは言えない。
わたしは異世界からきた存在だし、これからも勇者パーティーとしてやっていかないといけないし、それに、それに……。
ううん、きっと、……言い訳を探しているだけ。
わたしは、ただただ、自分が傷つくのが……怖いのだ。
ライアスが言った。
「あのさ! 明日は祭りにでかけないか?」
「祭り?」
「あ、そうか。シオリはまだこの世界に来て一年経ってないから、知らないのか。明日は豊穣祭なんだ。街には美味しいものがたくさん並ぶぞ!」
「そうなんだ……! 行きたいな」
「じゃ、明日十時にここで待ち合わせな」
「う、うん……!」
祭り。……もしかして、ライアスとふたりきりだろうか?
それって、……デート?
そう考えた途端、
ドキン、と胸が鳴る。
「あのさっ、シオリ……!」
「な、なぁに、ライアス?」
「……明日、話があるんだ」
「……え?」
それって、
「あの、ライアス……」
「明日! 明日言うから!」
「……うん」
ライアスは頭をかきながら、小走りで帰っていった。
トクン。
胸が鳴る。
もしかして? 本当に?
わたしは、その日一日気が気ではなくて、ずいぶんと気がそぞろになってしまった。
(早く、明日にならないかな……)
勘違いだったら、怖い。
でも、もしかしたら……。
わたしの胸は、期待と不安とが入り混じ――期待の方が少しだけ勝っていた。
***