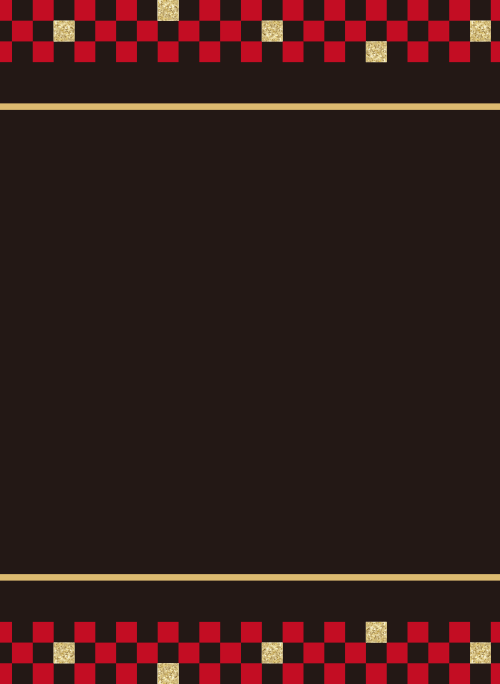「直上パス……あの開会式のとき、ずっと落とさず直上パス、し続けてたんですか?」
訳の分かんないことを聞いてしまった。
「?? あれ? 見てたと?」
「綺麗なフォームだなって……」
「俺も小学生ンときセッターやっとったけん」
「なんで……何で私がセッターだって知ってるんですか?」
「零華さんに……聞いとったけん……」
「え?」
零華先輩が、私のこと……何を言ったのだろう?
「『勝負所で私にトスを上げなかったバカなセッター』って笑いよった」
……あのときの……根に持ってるんですね……私のことしっかり覚えてるじゃない!
私はいつものスマイルスルー……いいえビタースマイルで応じる。
「菜々巳は~すっごく頭良いんだよ~」
「『バカ』の意味が違う」
「ゔ~どのバカ~?」
強く八千を見る。
「あたしはバカじゃない、ハチだ!」
「明日、零華さんとこと試合するっちゃろ?」
「あ、はい……」
九十九は八千と睦美の会話に笑っていながら、菜々巳に向けた言葉のときにはその笑みを捨てていた。
「俺、零華さんにトス上げとうてセッターになったとに、できん内に引っ越してもうた。やけん、あんたんことは気になっとった」
「…………」
『あんたんことは気になっとった』その言葉が独り歩きをする。……零華先輩の弱点……『もし零華先輩がスパイクするとき変な声を上げていることを知ったなら、彼は零華先輩に失望するだろうか?』『私のことをもっと見てくれるだろうか?』『もし彼が明日、試合を見に来たのなら、零華先輩は実力を発揮できないだろうか?』『私のバレー、見て欲しいな……』『イケメンがくれば八千のレシーブ反応速度が上がるし』
邪心が走る。いいえ、最後のは邪心じゃないわね。
「わたしも~菜々巳にトス上げてもらいたい~」
睦美の一言で目が覚める。
そんなんでもし試合に勝ったとして、それでいいのかしら? 勝ったからって、彼が私のことを好きになるなんて決まっていない。こんなんで勝ったってバレーボールに申し訳ない! 気持ちを利用して貶めたり、出し抜こうなんて……。
恋ってもっときれいな心かと思っていた……。
自分の中にこんなにも醜い心があったなんて信じられない、それを勝負と睦美に気付かされるなんて。
やっぱり私はバレーが好きだ。
暮れる日の光……判断に迷っていた街灯の明かりが突然辺りを照らしだす。
「私にも、居るんです。トスを上げたい人が」
私の言葉に彼は睦美をチラ見する。そして大きく息を一つ吐く。そのときには再び優しい笑顔に戻っていた。
「そっか……。あ、今んな零華さんにば内緒にしといて、な」
ポニーテールと呼ぶには低い位置で一本結びしてある髪を振り回すように私はそっぽを向いて、意地悪するふりをする。いいえ、本当は汚い心を除かれないように隠す意味合いの方が大きい。
「でもなんでセッター志望だった九十九さんは今、リベロを……」
「おっ? 古賀から電話や。あ、古賀って言うんなうちんキャプテンな」
そう言って電話の着信音を閉ざすようにポケットの奥へとねじ込むと私たちから距離を取り始める。再び影が彼をシルエットだけに変える
それでも彼がクルリと首を回したのが分かると、元気な声で手を振った。
「スパイカーを真に支えとーとはセッターやなか! レシーブだ。レシーブはセッターもアタッカーも助くんや……トスがでくるんな当たり前、思いっきりアタックでくるんも、スパイクフォローがありゃあこそ! バレーはレシーブこそ命や。あんたが2人んために頑張りや!」
同じリベロの八千にエールを送ると共に、私たち3人の繋がりを励ましてくれたと感じる。彼はその言葉を最後に去って行った。何しに来てたのかしら?
訳の分かんないことを聞いてしまった。
「?? あれ? 見てたと?」
「綺麗なフォームだなって……」
「俺も小学生ンときセッターやっとったけん」
「なんで……何で私がセッターだって知ってるんですか?」
「零華さんに……聞いとったけん……」
「え?」
零華先輩が、私のこと……何を言ったのだろう?
「『勝負所で私にトスを上げなかったバカなセッター』って笑いよった」
……あのときの……根に持ってるんですね……私のことしっかり覚えてるじゃない!
私はいつものスマイルスルー……いいえビタースマイルで応じる。
「菜々巳は~すっごく頭良いんだよ~」
「『バカ』の意味が違う」
「ゔ~どのバカ~?」
強く八千を見る。
「あたしはバカじゃない、ハチだ!」
「明日、零華さんとこと試合するっちゃろ?」
「あ、はい……」
九十九は八千と睦美の会話に笑っていながら、菜々巳に向けた言葉のときにはその笑みを捨てていた。
「俺、零華さんにトス上げとうてセッターになったとに、できん内に引っ越してもうた。やけん、あんたんことは気になっとった」
「…………」
『あんたんことは気になっとった』その言葉が独り歩きをする。……零華先輩の弱点……『もし零華先輩がスパイクするとき変な声を上げていることを知ったなら、彼は零華先輩に失望するだろうか?』『私のことをもっと見てくれるだろうか?』『もし彼が明日、試合を見に来たのなら、零華先輩は実力を発揮できないだろうか?』『私のバレー、見て欲しいな……』『イケメンがくれば八千のレシーブ反応速度が上がるし』
邪心が走る。いいえ、最後のは邪心じゃないわね。
「わたしも~菜々巳にトス上げてもらいたい~」
睦美の一言で目が覚める。
そんなんでもし試合に勝ったとして、それでいいのかしら? 勝ったからって、彼が私のことを好きになるなんて決まっていない。こんなんで勝ったってバレーボールに申し訳ない! 気持ちを利用して貶めたり、出し抜こうなんて……。
恋ってもっときれいな心かと思っていた……。
自分の中にこんなにも醜い心があったなんて信じられない、それを勝負と睦美に気付かされるなんて。
やっぱり私はバレーが好きだ。
暮れる日の光……判断に迷っていた街灯の明かりが突然辺りを照らしだす。
「私にも、居るんです。トスを上げたい人が」
私の言葉に彼は睦美をチラ見する。そして大きく息を一つ吐く。そのときには再び優しい笑顔に戻っていた。
「そっか……。あ、今んな零華さんにば内緒にしといて、な」
ポニーテールと呼ぶには低い位置で一本結びしてある髪を振り回すように私はそっぽを向いて、意地悪するふりをする。いいえ、本当は汚い心を除かれないように隠す意味合いの方が大きい。
「でもなんでセッター志望だった九十九さんは今、リベロを……」
「おっ? 古賀から電話や。あ、古賀って言うんなうちんキャプテンな」
そう言って電話の着信音を閉ざすようにポケットの奥へとねじ込むと私たちから距離を取り始める。再び影が彼をシルエットだけに変える
それでも彼がクルリと首を回したのが分かると、元気な声で手を振った。
「スパイカーを真に支えとーとはセッターやなか! レシーブだ。レシーブはセッターもアタッカーも助くんや……トスがでくるんな当たり前、思いっきりアタックでくるんも、スパイクフォローがありゃあこそ! バレーはレシーブこそ命や。あんたが2人んために頑張りや!」
同じリベロの八千にエールを送ると共に、私たち3人の繋がりを励ましてくれたと感じる。彼はその言葉を最後に去って行った。何しに来てたのかしら?