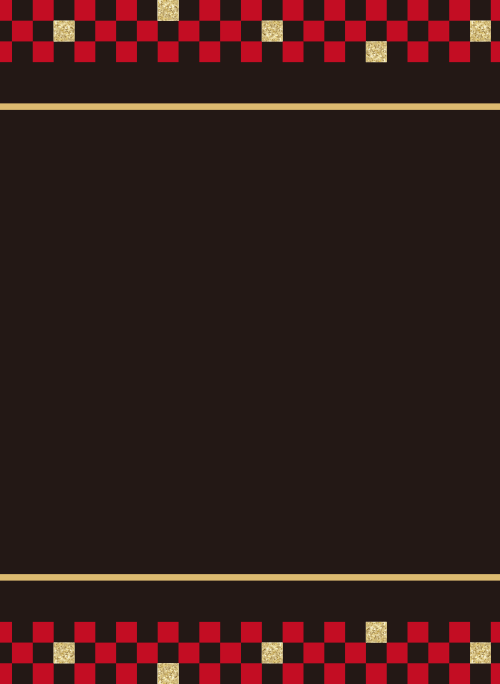「オーライ」
軽く手を挙げ、落ち着いて声を出して、落下点に入ったリベロはしっかり丁寧にセッターへとパスを上げる。セッターがボールの下へ入ったのなら、動き出す平安アタッカー陣。
レフト十色で勝負を決めに来るのであってもおかしくない場面。唯一のアンテナが拾ったのはど真ん中、三咲のクイック。
「11ッ!?」
咄嗟に唯一が声を張ってしまうほどの存在感。ファーストテンポで突っ込んでくる三咲のプレッシャーはゲスブロックでなくても思わず飛んでしまいたくなるほど気持ちを追い詰めてくる。
リードブロックは我慢のブロックだ。相手の挑発をスルーして、逸る気持ちを抑え、セッターの嘲笑を横目に、ボールが送られた方へ追いかける、そして……。
「クロス閉めて!」
ブロック3枚揃えた。これを決められたら負けだ、持して守り切る! しかしそれは相手側も同じ、精一杯を尽くし、十色がその重いスパイクを放つ。
***
十色は零華に負けたくなかった。
サーブもアンダーもオーバーも技術的な差はほとんどない、ジャンプ力、持久力、視野などのスキルも変わらない。体重、背丈、腕の長さ、体格の差も無いに等しい。肌の滑らかさ、髪の艶やかさ、目の大きさ、鼻の高さ、唇の色っぽさ、顔の大きさ、輪郭……そしてスパイクの決定力……そこに2人の差はあった。
十色は零華に負けたくない……十色は容姿の差がスパイクの威力の差だと、親を責めたりしたこともある……もう過去のことだ。
零華は初め、電気ロケッツというクラブチームに居た。環希が4年生のときの『全日本小学生大会』で東洋アローズと対戦。エースは十色。福岡最強の電気ロケッツの中でも零華は眩しいほどの才能を放っていた。
試合後しばらくして、父親の転勤で零華は東洋アローズに入団してきた。零華にとって奇跡の邂逅と言えた。一緒に練習をするようになって十色は気付かされた、自分は『環希のトスに助けられて零華に勝った』のだと。
十色は自分のスパイクを一段上に押し上げてくれる環希のトスを欲した。中学生では叶うことのなかった環希とコートに立つ時間。環希の病状が芳しくなくても、夢見た高校でのプレー。それなのに十色と同様に環希のトスを求めていた零華は、環希をあっさりと見限ってスカウトされた東京の学校に進学を決めた。
***
「抜けたッ!」
「チッ!」
十色のスパイクの破壊力は唯一パイセンの指が掛かりながらも、それを吹き飛ばして突き抜けた。ブロックを抜いたけれどもワンタッチでもある。
リードブロックは我慢のブロックだ……最後にスパイカーにその存在に舌打ちされる。スパイカーに睨まれ、セッターに嫌な顔をされる。ネットを挟んで
その前に立った人間が不快感を示せば示すほど自信が湧く。
ワンタッチされても尚、勢いのあるスパイク。それに立ち向かうのは八千。その勢いを適度に抜いて柔らかく上に曲線を描くボール……。
高さ300センチの打点から繰り出されたスパイクは、仮に時速100キロメートルで5メートルの距離でレシーブした場合、260グラムのバレーボールでは凡そ4.09重量キログラムの衝撃力となる。
つまりスパイクレシーブは2リットルのペットボトルを2本受けているのと同じこと。
八千……いつもありがとう。
軽く手を挙げ、落ち着いて声を出して、落下点に入ったリベロはしっかり丁寧にセッターへとパスを上げる。セッターがボールの下へ入ったのなら、動き出す平安アタッカー陣。
レフト十色で勝負を決めに来るのであってもおかしくない場面。唯一のアンテナが拾ったのはど真ん中、三咲のクイック。
「11ッ!?」
咄嗟に唯一が声を張ってしまうほどの存在感。ファーストテンポで突っ込んでくる三咲のプレッシャーはゲスブロックでなくても思わず飛んでしまいたくなるほど気持ちを追い詰めてくる。
リードブロックは我慢のブロックだ。相手の挑発をスルーして、逸る気持ちを抑え、セッターの嘲笑を横目に、ボールが送られた方へ追いかける、そして……。
「クロス閉めて!」
ブロック3枚揃えた。これを決められたら負けだ、持して守り切る! しかしそれは相手側も同じ、精一杯を尽くし、十色がその重いスパイクを放つ。
***
十色は零華に負けたくなかった。
サーブもアンダーもオーバーも技術的な差はほとんどない、ジャンプ力、持久力、視野などのスキルも変わらない。体重、背丈、腕の長さ、体格の差も無いに等しい。肌の滑らかさ、髪の艶やかさ、目の大きさ、鼻の高さ、唇の色っぽさ、顔の大きさ、輪郭……そしてスパイクの決定力……そこに2人の差はあった。
十色は零華に負けたくない……十色は容姿の差がスパイクの威力の差だと、親を責めたりしたこともある……もう過去のことだ。
零華は初め、電気ロケッツというクラブチームに居た。環希が4年生のときの『全日本小学生大会』で東洋アローズと対戦。エースは十色。福岡最強の電気ロケッツの中でも零華は眩しいほどの才能を放っていた。
試合後しばらくして、父親の転勤で零華は東洋アローズに入団してきた。零華にとって奇跡の邂逅と言えた。一緒に練習をするようになって十色は気付かされた、自分は『環希のトスに助けられて零華に勝った』のだと。
十色は自分のスパイクを一段上に押し上げてくれる環希のトスを欲した。中学生では叶うことのなかった環希とコートに立つ時間。環希の病状が芳しくなくても、夢見た高校でのプレー。それなのに十色と同様に環希のトスを求めていた零華は、環希をあっさりと見限ってスカウトされた東京の学校に進学を決めた。
***
「抜けたッ!」
「チッ!」
十色のスパイクの破壊力は唯一パイセンの指が掛かりながらも、それを吹き飛ばして突き抜けた。ブロックを抜いたけれどもワンタッチでもある。
リードブロックは我慢のブロックだ……最後にスパイカーにその存在に舌打ちされる。スパイカーに睨まれ、セッターに嫌な顔をされる。ネットを挟んで
その前に立った人間が不快感を示せば示すほど自信が湧く。
ワンタッチされても尚、勢いのあるスパイク。それに立ち向かうのは八千。その勢いを適度に抜いて柔らかく上に曲線を描くボール……。
高さ300センチの打点から繰り出されたスパイクは、仮に時速100キロメートルで5メートルの距離でレシーブした場合、260グラムのバレーボールでは凡そ4.09重量キログラムの衝撃力となる。
つまりスパイクレシーブは2リットルのペットボトルを2本受けているのと同じこと。
八千……いつもありがとう。