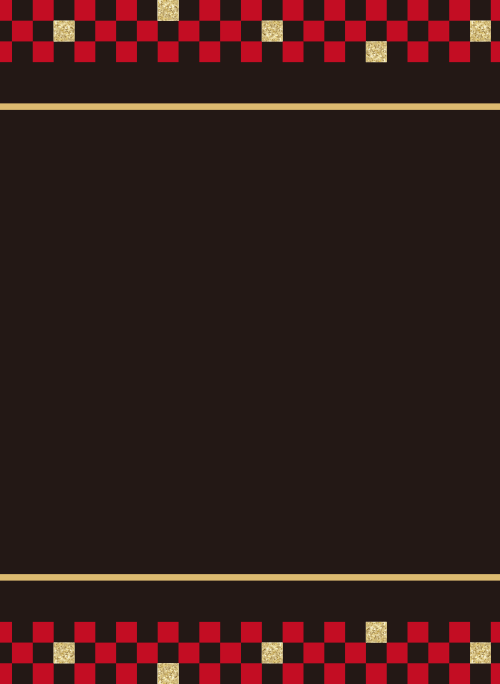「あーあ……練習では大分できるようになって来たんだけどなぁ」
五和がわざとらしく私の近くに寄って来たのなら、言い訳じみた言葉を吐く。それは自分への落としどころなのだろう……悔しくない訳がないのは勝負の世界に身を置く人間なら当たり前だ。負け惜しみの一つも言えないようじゃ次への一歩を踏み出せない。
「試合になると、咄嗟の場面になると出ちゃうものね、やっぱり」
「中々直せないから『癖』なんだよね」
「習慣になってて偏ってるんだから」
何も言葉を返せないでぎこちなさいっぱいのスマイルスルーの私の代りに、独りで話し続ける。顔を隠すようにタオルで汗を拭う。私はわざと視線をコートの白線にぶつけて固まる。
「あんたたちが入部してきて、あたし焦ってたんだよね」
「??」
思わず顔を上げると、バッチリ五和先輩と視線がぶつかってしまう。少し驚いた風の五和先輩は表情を戻すと再び語り出す。私は少しホッとして警戒にも似た緊張を解き、再び視線をさっきよりコートの少し遠い白線に落とした。
「視野の広さ、落下点に入るスピードが正確なフォームとミスのないトスを……あんた、目と……耳が良いのかな? 視野も広いのに、視覚に頼らないでも空間を把握する才能……あたしはトス回しであんたに勝てなかった」
びっくりして私は再び顔を五和先輩に向ける。以外にも五和先輩は笑っていた。五和先輩は目元の力を緩めて再び話し出す。
「目視に頼るあたしは、トスに速さを求め過ぎて雑になってしまった……変な癖が付いてしまった……」
「皆藤はあんたのトスに何だか依怙贔屓してるし」
「嫌われたくないんだと、さ」
睦美……バレーを辞めたってもう、友達から何一つ変わることなんてない。それだけの時間を一緒に過ごしてきたはずですよね。
「あたしたち今のセット、試されてたんだよね。春高を賭けたこの大事な試合であの監督、まったく勝負師と言うかなんて言うか……」
「試されてた?」
ようやく五和先輩の言葉に返事ができた私……私の反応を見てやっと五和先輩も胸を撫で下ろしたようだ。そんな気がした。
「皆藤は私のオープントスを打つこと、そのメンタルを。私は皆藤にバックトスを上げるときの癖を……」
「結果、あたしの媚びないトス回しをあんたが覚える方が勝利への近道、って判断されたみたい、監督は……」
「あたしもチームが勝ちたい、勝ち進みたい。だから教えといて上げる……」
初めて五和先輩と正対した気がした……。同じポジションを争ってきたからこそ、直視して来なかった私の弱い部分。私にもし、有能なセッターの後輩ができたとき、五和先輩のようにできるのであろうか? 1学年上の先輩、たったのこの1年が、この高校生という時代において、偉大な1年であることを思い知る。
「セッターだってスパイカーに『要求』したって良いってこと……スパイカーの力を引き出すってのは、言いなりになる事でも、従うことでもない。そこに信頼と敬意が有るか無いかだ」
「あんたはレシーブが乱れたとき『下手くそ』と思うのか? スパイカーがスパイクを外したとき、トスのせいにするのであれば、そんな奴はすぐに辞めさせた方がいい。高みへと押し上げるのは『慣れ合い』ではないよ」
バレーはボールを止めて一旦落ち着かせるなんてない、ましてや外に出して流れを切るなんてあり得ない。
6人それぞれが『どうすべきか』考えて動く、セッターはポジショニングなどから状況を汲み取りその最善手を模索する、たった3回のボールタッチ。
「あたしだって試合に出るのを諦めた訳ではないよ。あんたに負けないチーム1のサービスを打てるのはあたしなんだ……けどセッターは……セッターは司令塔なんだ。その自負を忘れるな、開菜々巳!」
そして勝負の第3セットが始まる。
五和がわざとらしく私の近くに寄って来たのなら、言い訳じみた言葉を吐く。それは自分への落としどころなのだろう……悔しくない訳がないのは勝負の世界に身を置く人間なら当たり前だ。負け惜しみの一つも言えないようじゃ次への一歩を踏み出せない。
「試合になると、咄嗟の場面になると出ちゃうものね、やっぱり」
「中々直せないから『癖』なんだよね」
「習慣になってて偏ってるんだから」
何も言葉を返せないでぎこちなさいっぱいのスマイルスルーの私の代りに、独りで話し続ける。顔を隠すようにタオルで汗を拭う。私はわざと視線をコートの白線にぶつけて固まる。
「あんたたちが入部してきて、あたし焦ってたんだよね」
「??」
思わず顔を上げると、バッチリ五和先輩と視線がぶつかってしまう。少し驚いた風の五和先輩は表情を戻すと再び語り出す。私は少しホッとして警戒にも似た緊張を解き、再び視線をさっきよりコートの少し遠い白線に落とした。
「視野の広さ、落下点に入るスピードが正確なフォームとミスのないトスを……あんた、目と……耳が良いのかな? 視野も広いのに、視覚に頼らないでも空間を把握する才能……あたしはトス回しであんたに勝てなかった」
びっくりして私は再び顔を五和先輩に向ける。以外にも五和先輩は笑っていた。五和先輩は目元の力を緩めて再び話し出す。
「目視に頼るあたしは、トスに速さを求め過ぎて雑になってしまった……変な癖が付いてしまった……」
「皆藤はあんたのトスに何だか依怙贔屓してるし」
「嫌われたくないんだと、さ」
睦美……バレーを辞めたってもう、友達から何一つ変わることなんてない。それだけの時間を一緒に過ごしてきたはずですよね。
「あたしたち今のセット、試されてたんだよね。春高を賭けたこの大事な試合であの監督、まったく勝負師と言うかなんて言うか……」
「試されてた?」
ようやく五和先輩の言葉に返事ができた私……私の反応を見てやっと五和先輩も胸を撫で下ろしたようだ。そんな気がした。
「皆藤は私のオープントスを打つこと、そのメンタルを。私は皆藤にバックトスを上げるときの癖を……」
「結果、あたしの媚びないトス回しをあんたが覚える方が勝利への近道、って判断されたみたい、監督は……」
「あたしもチームが勝ちたい、勝ち進みたい。だから教えといて上げる……」
初めて五和先輩と正対した気がした……。同じポジションを争ってきたからこそ、直視して来なかった私の弱い部分。私にもし、有能なセッターの後輩ができたとき、五和先輩のようにできるのであろうか? 1学年上の先輩、たったのこの1年が、この高校生という時代において、偉大な1年であることを思い知る。
「セッターだってスパイカーに『要求』したって良いってこと……スパイカーの力を引き出すってのは、言いなりになる事でも、従うことでもない。そこに信頼と敬意が有るか無いかだ」
「あんたはレシーブが乱れたとき『下手くそ』と思うのか? スパイカーがスパイクを外したとき、トスのせいにするのであれば、そんな奴はすぐに辞めさせた方がいい。高みへと押し上げるのは『慣れ合い』ではないよ」
バレーはボールを止めて一旦落ち着かせるなんてない、ましてや外に出して流れを切るなんてあり得ない。
6人それぞれが『どうすべきか』考えて動く、セッターはポジショニングなどから状況を汲み取りその最善手を模索する、たった3回のボールタッチ。
「あたしだって試合に出るのを諦めた訳ではないよ。あんたに負けないチーム1のサービスを打てるのはあたしなんだ……けどセッターは……セッターは司令塔なんだ。その自負を忘れるな、開菜々巳!」
そして勝負の第3セットが始まる。