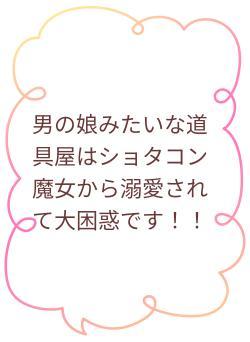「それで? ルカは虚空の海ってところを通って、この世界にやってきたって訳か?」
紫苑の理解が早い。
「うむ。虚空の海とは、キュアノスの世界の下の果てに広がる大雲海の事だ。そこに沈んだものは、二度と浮き上がることがないと言われておる。過去に小さな空島が落ちて沈んだことも有ったそうだ」
「キュアノスってのは、ルカがいた世界の事か?」
――いったい今どういう状況なのかな?
美兎は二人の会話にツッコミを入れず、聞き入れるのがやっとだった。
「そうじゃ。キュアノスは天空の世界とも呼ばれており、真っ青で広大な空に島や大地が浮かぶ世界だ。我がいた国は、大きな岩の島に鉄の城が乗った、スディーロスと呼ばれる国だった」
はたと美兎が顔を上げる。
「空に浮かぶ大きなお城? それ私見た!」
紫苑とルカがびっくりしたように少女の顔を見つめた。
「どこで!」
紫苑が美兎に飛び掛からんばかりの反応を見せる。ルカもわずかに体を前のめりにして美兎の言葉を待っている。
「その、ルカ君?が落ちてきたとき、雷がひどくて空一面が真っ黒な雲に覆われていたの。でも急に雨が止んだと思ったら、雲の裂け目から青空が出てきて。そしたら一瞬だけ雲の影から大きなヨーロッパみたいなお城が見えたの……」
「それだ、美兎! 雷って昨日のゲリラ豪雨だったときか……。クソっ、俺も見たかったな」
――悔しがる素振りは小学校の時と変わっていないね。
「そうすると、やはり我は虚空の海を抜けて、この地へと辿り着いてしまったと考えるのが筋か?」
ルカはボソボソと独り言ちながら、首を傾げたりしていたが、急に顔を上げると美兎のことを見つめた。
「娘よ。我がこの地に降り立ったとき、黄金の翼を持ってはいなかっただろうか? 虚空の海へ飛び込む寸前に、もぎ取られた我の翼を奪い返して、こう両の腕で抱えていたのだが?」
ルカが両手で抱き込むような仕草を見せる。
「ルカって翼が生えていたのか? それってもう天使じゃないか!」
「天使とやらは知らぬが、空人《そらびと》は一般的には左右一対の翼。王族方は三対の翼。我々のような戦士は二対四枚の翼を持って生まれてくるものだ」
「黄金の翼って程ではなかったけど…。確かに綺麗な羽は持っていたよ。でも、私が触れたら消えて無くなっちゃた……」
「なんと! 空人にとって翼は力の源。アレがなければ空を飛ぶことも難しいが……。鉄甲を纏うことぐらいは出来るだろうか?」
「鉄甲ってなんだ?」
紫苑が麦茶のコップを握り締めながら前のめりになる。
「鉄甲とは身に纏って防具にしたり、体が風に飛ばされぬよう重しの代わりに使用したりするものだ。ソナタ等も気が付いているだろうが、空人の体は非常に軽い。空を飛ぶ以上、強風に飛ばされる事もある。そう成らぬように、鉄甲を具現化し身に纏うのだ」
「今やって見ることは出来るのか?」
「やっても良いが、この世界の事がわからぬ故、重さに耐えきれなく床が抜けるかも知れんぞ?」
――あぁ、それは困る。いくら両親が不在とはいえ、留守を預かっている以上、無闇に家を壊されたくない。
「じゃあ外に出てみようか」
紫苑がそう言うと三人は立ち上がり庭へと出た。
「ホントに軽いんだな、風船みたいだ」
両脇の下に手を差し入れ、ルカのことを持ち上げる紫苑。
「今は翼の力を失っているからこんな姿だが、我の本来の背丈はソナタ等よりも遥かに高いぞ」
紫苑の手から抜け出たルカが空を見上げる。
「先ずは跳ねてみせようか」
そう言うとルカは一瞬屈んだ後、大きく跳ねた。
軽く二階建て住宅の屋根を超えた高さだろうか。まさに風船のようにゆっくりと地上に降りてくる。
――あっ、少し風に流されている。
ふわふわとそよ風に揺れながらルカは地上へと降りてきた。
「まぁ、こんな感じじゃ。見て解るように体が軽い分、わずかな風でも影響を受けてしまい易い。では鉄甲を出してみようかの」
ルカは少し屈むと、目をつぶりボソボソと何ごとかを呟き、両の拳を握り込んだ。
美兎と紫苑の二人は、息を呑んで成り行きを見守っている。
ルカの両手足がわずかに光ると、包むように鈍色の小手と脛当てが現れた。
「ふむ、やはり翼がないとこのぐらいが限界のようじゃな」
手足の様子を確認しながら少年は独り言ちた。
その姿を見て感嘆の声を漏らす美兎と紫苑。
――すっごい。なにこれ魔法?
思わず見とれている美兎と同じ感想を紫苑が口にする。
「すげぇ。魔法にしか見えねぇよな、美兎」
「魔法というものはよく知らぬが、空人であれば念じれば誰でも出来ることじゃ。これで体が重くなって風の影響は受けにくくなり、更にはこういう効果もある」
ルカは庭石に近づくと勢いよく殴りつけた。
「危ない!」
美兎の声よりも早く、ルカの拳が大きな庭石を真っ二つに砕く。
「すげっ……」
紫苑が唾を飲み込む音が聞こえる。
「シオンとやら、もう一度我のことを持ち上げてみるが良い」
紫苑は恐る恐るルカに近づくと、先程と同じように両手で持ち上げようとした。
「ぐっ、さっきより重くなっているな。持ち上がらなくはないけど、2~30キロぐらいはありそうだな」
「そうであろう、鉄甲を出すことによって重さと力を身につけることが出来るのだ」
「さっきみたいに飛ぶことが出来ない代わりに、力が増すって感じなのかな? なんか、どういう原理なのか全く理解できないけど」
美兎は首をすくめて、お手上げといった仕草をした。その手から包帯が少しめくれて垂れ下がった。
「そういえば、その包帯どうしたんだ? あちこち怪我だらけじゃんか」
――えー、いまさら? 気が付くの遅すぎない。
美兎は包帯を元通りに治すのを諦めて、くるくると丸めると、傷に貼ったガーゼが顔を出した。
「ほら、幅跳びで転んで盛大な擦り傷が……あれ?」
「無いじゃん」
美兎が傷を見せようとガーゼをめくると、そこに有ったはずの擦り傷が消えていた。
「えっ、待って? ほら、ガーゼには血も付いているし、ここに傷が有ったんだよ!」
美兎は慌てて肘の絆創膏を剥がしてみたが、そこにも傷はなかった。改めて体中をさすってみると、帰宅時にあれだけ感じていた、打ち身の痛みもすっかり無くなっていることに気が付いた。
――えっ、どういうこと?
困惑する美兎のことを二人の少年は首を傾げて見つめていた。
紫苑の理解が早い。
「うむ。虚空の海とは、キュアノスの世界の下の果てに広がる大雲海の事だ。そこに沈んだものは、二度と浮き上がることがないと言われておる。過去に小さな空島が落ちて沈んだことも有ったそうだ」
「キュアノスってのは、ルカがいた世界の事か?」
――いったい今どういう状況なのかな?
美兎は二人の会話にツッコミを入れず、聞き入れるのがやっとだった。
「そうじゃ。キュアノスは天空の世界とも呼ばれており、真っ青で広大な空に島や大地が浮かぶ世界だ。我がいた国は、大きな岩の島に鉄の城が乗った、スディーロスと呼ばれる国だった」
はたと美兎が顔を上げる。
「空に浮かぶ大きなお城? それ私見た!」
紫苑とルカがびっくりしたように少女の顔を見つめた。
「どこで!」
紫苑が美兎に飛び掛からんばかりの反応を見せる。ルカもわずかに体を前のめりにして美兎の言葉を待っている。
「その、ルカ君?が落ちてきたとき、雷がひどくて空一面が真っ黒な雲に覆われていたの。でも急に雨が止んだと思ったら、雲の裂け目から青空が出てきて。そしたら一瞬だけ雲の影から大きなヨーロッパみたいなお城が見えたの……」
「それだ、美兎! 雷って昨日のゲリラ豪雨だったときか……。クソっ、俺も見たかったな」
――悔しがる素振りは小学校の時と変わっていないね。
「そうすると、やはり我は虚空の海を抜けて、この地へと辿り着いてしまったと考えるのが筋か?」
ルカはボソボソと独り言ちながら、首を傾げたりしていたが、急に顔を上げると美兎のことを見つめた。
「娘よ。我がこの地に降り立ったとき、黄金の翼を持ってはいなかっただろうか? 虚空の海へ飛び込む寸前に、もぎ取られた我の翼を奪い返して、こう両の腕で抱えていたのだが?」
ルカが両手で抱き込むような仕草を見せる。
「ルカって翼が生えていたのか? それってもう天使じゃないか!」
「天使とやらは知らぬが、空人《そらびと》は一般的には左右一対の翼。王族方は三対の翼。我々のような戦士は二対四枚の翼を持って生まれてくるものだ」
「黄金の翼って程ではなかったけど…。確かに綺麗な羽は持っていたよ。でも、私が触れたら消えて無くなっちゃた……」
「なんと! 空人にとって翼は力の源。アレがなければ空を飛ぶことも難しいが……。鉄甲を纏うことぐらいは出来るだろうか?」
「鉄甲ってなんだ?」
紫苑が麦茶のコップを握り締めながら前のめりになる。
「鉄甲とは身に纏って防具にしたり、体が風に飛ばされぬよう重しの代わりに使用したりするものだ。ソナタ等も気が付いているだろうが、空人の体は非常に軽い。空を飛ぶ以上、強風に飛ばされる事もある。そう成らぬように、鉄甲を具現化し身に纏うのだ」
「今やって見ることは出来るのか?」
「やっても良いが、この世界の事がわからぬ故、重さに耐えきれなく床が抜けるかも知れんぞ?」
――あぁ、それは困る。いくら両親が不在とはいえ、留守を預かっている以上、無闇に家を壊されたくない。
「じゃあ外に出てみようか」
紫苑がそう言うと三人は立ち上がり庭へと出た。
「ホントに軽いんだな、風船みたいだ」
両脇の下に手を差し入れ、ルカのことを持ち上げる紫苑。
「今は翼の力を失っているからこんな姿だが、我の本来の背丈はソナタ等よりも遥かに高いぞ」
紫苑の手から抜け出たルカが空を見上げる。
「先ずは跳ねてみせようか」
そう言うとルカは一瞬屈んだ後、大きく跳ねた。
軽く二階建て住宅の屋根を超えた高さだろうか。まさに風船のようにゆっくりと地上に降りてくる。
――あっ、少し風に流されている。
ふわふわとそよ風に揺れながらルカは地上へと降りてきた。
「まぁ、こんな感じじゃ。見て解るように体が軽い分、わずかな風でも影響を受けてしまい易い。では鉄甲を出してみようかの」
ルカは少し屈むと、目をつぶりボソボソと何ごとかを呟き、両の拳を握り込んだ。
美兎と紫苑の二人は、息を呑んで成り行きを見守っている。
ルカの両手足がわずかに光ると、包むように鈍色の小手と脛当てが現れた。
「ふむ、やはり翼がないとこのぐらいが限界のようじゃな」
手足の様子を確認しながら少年は独り言ちた。
その姿を見て感嘆の声を漏らす美兎と紫苑。
――すっごい。なにこれ魔法?
思わず見とれている美兎と同じ感想を紫苑が口にする。
「すげぇ。魔法にしか見えねぇよな、美兎」
「魔法というものはよく知らぬが、空人であれば念じれば誰でも出来ることじゃ。これで体が重くなって風の影響は受けにくくなり、更にはこういう効果もある」
ルカは庭石に近づくと勢いよく殴りつけた。
「危ない!」
美兎の声よりも早く、ルカの拳が大きな庭石を真っ二つに砕く。
「すげっ……」
紫苑が唾を飲み込む音が聞こえる。
「シオンとやら、もう一度我のことを持ち上げてみるが良い」
紫苑は恐る恐るルカに近づくと、先程と同じように両手で持ち上げようとした。
「ぐっ、さっきより重くなっているな。持ち上がらなくはないけど、2~30キロぐらいはありそうだな」
「そうであろう、鉄甲を出すことによって重さと力を身につけることが出来るのだ」
「さっきみたいに飛ぶことが出来ない代わりに、力が増すって感じなのかな? なんか、どういう原理なのか全く理解できないけど」
美兎は首をすくめて、お手上げといった仕草をした。その手から包帯が少しめくれて垂れ下がった。
「そういえば、その包帯どうしたんだ? あちこち怪我だらけじゃんか」
――えー、いまさら? 気が付くの遅すぎない。
美兎は包帯を元通りに治すのを諦めて、くるくると丸めると、傷に貼ったガーゼが顔を出した。
「ほら、幅跳びで転んで盛大な擦り傷が……あれ?」
「無いじゃん」
美兎が傷を見せようとガーゼをめくると、そこに有ったはずの擦り傷が消えていた。
「えっ、待って? ほら、ガーゼには血も付いているし、ここに傷が有ったんだよ!」
美兎は慌てて肘の絆創膏を剥がしてみたが、そこにも傷はなかった。改めて体中をさすってみると、帰宅時にあれだけ感じていた、打ち身の痛みもすっかり無くなっていることに気が付いた。
――えっ、どういうこと?
困惑する美兎のことを二人の少年は首を傾げて見つめていた。