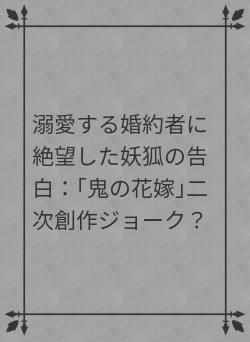1
お肉よりジャガイモの方が好きだった。だって、ママの同胞の「人間のお肉」なんて、「共食い」という言葉を知ってしまえば食べる気にもなれない。安い代用食品の「血のジャガイモ」と動物のお肉で十分だった。
不幸なことにか幸運なことにか、我が家は魔族伯爵の奴隷愛人である母とその娘の私。それなりに生活は出来たし、割り当てられて公私両面で支給される「高級食肉」は、近所や使用人の魔族たちにお裾分けで良い。それでご機嫌とり出来てお付き合いも円滑無難になるし、魔族の食事に犠牲にされる人間も僅かでも少なくて済むだろう。
「うちの子、ジャガイモやハーブティーの方が好きみたいで」
そんなふうに顔色を周囲の窺って話す母の声には、怯えと共に安堵の響きがあった。そうして「つつましい」生活をしていることで、嫉妬や憎悪を買わなくて済む。人肉は高級な食材だから下級の魔族たちからすれば、常時・大量には食べられない贅沢品でもある。妾腹とはいえ伯爵令嬢でしかも混血雑種の私であっても、普段の食べ物に下層魔族たちと同じようなジャガイモや獣肉ばかり食べていることで、周囲に憎まれる度合いは少なくて済むのだろうし。
魔族伯爵(中級の魔王)の父は「母親似で犬や猫のように金のかからない娘だ」と笑っていたが。父からすれば人間の奴隷女である母は、せいぜい犬や猫などの愛玩動物やペットと変わらなかったのだろう。でも、娘の私のことはそれなりには愛してくれたとは思うし、小さいときに私を膝に乗せて「肉入りのスープ」を自分の皿からスプーンで飲ませてくれたことは、一番古い記憶の一つだった。
きっと母からすれば、肉食獣の群れの中で生活する羊や兎と変わらない立場だったから、心の安まる暇もなかったに違いない。本当に母の味方なのは私だけだっただろう。混血の娘である私の食事の好みに安心して慰めを見いだし、それでも健康を心配して自分の乳房に針やナイフで傷つけて血を舐めさせてくれた。今でも傷だらけになった母の胸のことは良く覚えている。
2
負けず嫌いでプライドは高い方だったと思う(魔王伯爵の娘であることに秘かに誇りを持っていたことは否定できない)。だからマナーや態度と物腰の優雅さには拘ったし、剣術や魔術の訓練にも熱中した。
「まあ、あれでも私の娘だから」
よく剣術試合で好成績を残したり、成績が上位で父が嬉しそうだと、私も嬉しかった。少し恐れて距離を置きながらも全く嫌いなわけではなかったし、母の立場も守ってあげなくてはいけないと思っていたから。
母親の違う純粋魔族の兄弟や姉妹たちとも、適当には仲良くしていた。彼らは人間の母のことは奴隷や動物のように蔑んで見下したり無視していたが虐待まではしなかったし(魔王である伯爵家の圧倒的な優越感のせいなのか)、一応は実の姉妹である私にはさほど辛く当たらなかった。血縁者ゆえに弁護するようだが、同族同士での関係としては性格はけっして悪くなかったのかもしれない。混血雑種の変わり種とはいえ、それなりに優秀な私を「血統の良さの証」として喜んでいたのもあるだろうし、後継者争いの順位が問答無用で最低だから警戒されていなかった(むしろ兄弟姉妹の皆から、将来に最側近・片腕になりうる貴重な近親者と見られていた)。
本心を言えば、魔族であることや血筋と家柄だけで胡座をかいて満足しているような同族たちのことは軽蔑していた。数少ない親しい友人だったシェリーは下層魔族の出身だったけれども向上心の強い努力家で、頭も良かったから少し尊敬や共感して一目置いていたのだけれども、食事の好みや考え方が合わなくて最後には仲違いしてしまった。
3
それでも周囲の魔族の「同胞」たちに「舐められる」のは勘に触ったし(もちろん疎外感もあった)、健康上の必要もあって人間の生き血を飲むようになった。現実的な話として、優しい哀れな母が亡くなってからは、誰も新鮮な血を飲ませてくれない。だから自分で「狩る」しかないのだ。
それにサキにとっては心の中で「同胞であるはずの母を守ってくれずに虐待して、絶望と魔族への身売りに追いやった、無力で仁義のない人間たち」への恨みもあったから、感情的には意趣返しや当てつけでもあっただろう。人間たちはサキの母のことを「魔族に身売りした裏切り者」と陰口を叩いているようだったが、うち続く戦乱・治安崩壊と便乗した匪賊の跋扈で母がどんな酷い辛酸を舐めたかを知っていれば、「あなたたちなんかに母さんの何がわかるの?」「あんたらがゴミ弱者で信用も当てにもならないからでしょ、人間の同胞より魔族を頼られてる時点で面目丸潰れで自己責任だわ!」と言ってやりたかった。
だったら公私両面で支給される食用人肉を食べまくれば良いようなものだけれど、やっぱり母の同族の人間の命まで奪ってしまうやり方には拒否感や嫌悪感があった。食べるための「高級なお肉」が食卓にあるということは「そのために屠殺・解体された人間がいる」ということだから、あまりいい気分にはなれない(あまり美味しいとも思えなかった)。その点、少しばかり生き血を啜ったくらいだったら人間はそうは死なないのだからかえって気楽なものだったし、逃げて抵抗する人間をやり込めるのは娯楽遊戯のゲームでもある。
「私、お肉より新鮮な生き血を飲む方が好きなの」
そんなふうに言うと、兄弟姉妹たちは「魔族らしくなった」「ワイルドな嗜好」と、安心したように喜んでくれたものだった。父は本心を見透かしてなのか、「殺してその場で「血の生き肉」を食べたらもっと美味いかもしれんぞ」などと意地悪なことを言うものだから、「お肉は血抜きして熟成させた方が美味しいらしいですけど」と正論で言い返したら、生意気な娘の言い分に大笑いしていたものだ。
それから一番に素晴らしい利点は、血を吸って噛み跡をつけることで「獲物の宣言の印」になるために、他の魔族たちが勝手に殺すのは「マナー違反」になることだ。皮肉なことではあったけれども、サキに血を吸われていることで他の魔族による狩猟からは免れやすくなるので、実質的に庇護を与えているのと変わらない(多少気の強い魔族であっても伯爵令嬢には遠慮する)。
だから、わざと人間にとって犠牲者が多い危険地域である場所で、「可愛い」と感じた男の子や子供を狙うことが多かった。「守ってあげている」という力の満足感や優越感、そして「必ずしも危害を加えているだけではない」という自分自身への言い訳にもなっていた。
4
そうこうしているうちに、だんだんにサキの習性が「狩り場」の人間たちに知られてしまう。「優しい吸血鬼の綺麗なお姉さん」から血を吸われて勃起してしまうような少年たちが増えてきて、つい好奇心と悪戯心を起こしてしまった。人間とのセックスなんて魔族には割とよくある趣味ではあったし、インモラルでワルぶりたいお年頃でもあったから。
試しにズボンを下ろさせてしゃぶってみたら、これが予想外に楽しくて美味しくて。奥手だったはずのサキが性的興奮とエクスタシーに目覚めたのはそんなときで、何かが開花して吸血鬼というよりもサキュバスになってしまった。どうやら完全に性に合っていた。
お肉よりジャガイモの方が好きだった。だって、ママの同胞の「人間のお肉」なんて、「共食い」という言葉を知ってしまえば食べる気にもなれない。安い代用食品の「血のジャガイモ」と動物のお肉で十分だった。
不幸なことにか幸運なことにか、我が家は魔族伯爵の奴隷愛人である母とその娘の私。それなりに生活は出来たし、割り当てられて公私両面で支給される「高級食肉」は、近所や使用人の魔族たちにお裾分けで良い。それでご機嫌とり出来てお付き合いも円滑無難になるし、魔族の食事に犠牲にされる人間も僅かでも少なくて済むだろう。
「うちの子、ジャガイモやハーブティーの方が好きみたいで」
そんなふうに顔色を周囲の窺って話す母の声には、怯えと共に安堵の響きがあった。そうして「つつましい」生活をしていることで、嫉妬や憎悪を買わなくて済む。人肉は高級な食材だから下級の魔族たちからすれば、常時・大量には食べられない贅沢品でもある。妾腹とはいえ伯爵令嬢でしかも混血雑種の私であっても、普段の食べ物に下層魔族たちと同じようなジャガイモや獣肉ばかり食べていることで、周囲に憎まれる度合いは少なくて済むのだろうし。
魔族伯爵(中級の魔王)の父は「母親似で犬や猫のように金のかからない娘だ」と笑っていたが。父からすれば人間の奴隷女である母は、せいぜい犬や猫などの愛玩動物やペットと変わらなかったのだろう。でも、娘の私のことはそれなりには愛してくれたとは思うし、小さいときに私を膝に乗せて「肉入りのスープ」を自分の皿からスプーンで飲ませてくれたことは、一番古い記憶の一つだった。
きっと母からすれば、肉食獣の群れの中で生活する羊や兎と変わらない立場だったから、心の安まる暇もなかったに違いない。本当に母の味方なのは私だけだっただろう。混血の娘である私の食事の好みに安心して慰めを見いだし、それでも健康を心配して自分の乳房に針やナイフで傷つけて血を舐めさせてくれた。今でも傷だらけになった母の胸のことは良く覚えている。
2
負けず嫌いでプライドは高い方だったと思う(魔王伯爵の娘であることに秘かに誇りを持っていたことは否定できない)。だからマナーや態度と物腰の優雅さには拘ったし、剣術や魔術の訓練にも熱中した。
「まあ、あれでも私の娘だから」
よく剣術試合で好成績を残したり、成績が上位で父が嬉しそうだと、私も嬉しかった。少し恐れて距離を置きながらも全く嫌いなわけではなかったし、母の立場も守ってあげなくてはいけないと思っていたから。
母親の違う純粋魔族の兄弟や姉妹たちとも、適当には仲良くしていた。彼らは人間の母のことは奴隷や動物のように蔑んで見下したり無視していたが虐待まではしなかったし(魔王である伯爵家の圧倒的な優越感のせいなのか)、一応は実の姉妹である私にはさほど辛く当たらなかった。血縁者ゆえに弁護するようだが、同族同士での関係としては性格はけっして悪くなかったのかもしれない。混血雑種の変わり種とはいえ、それなりに優秀な私を「血統の良さの証」として喜んでいたのもあるだろうし、後継者争いの順位が問答無用で最低だから警戒されていなかった(むしろ兄弟姉妹の皆から、将来に最側近・片腕になりうる貴重な近親者と見られていた)。
本心を言えば、魔族であることや血筋と家柄だけで胡座をかいて満足しているような同族たちのことは軽蔑していた。数少ない親しい友人だったシェリーは下層魔族の出身だったけれども向上心の強い努力家で、頭も良かったから少し尊敬や共感して一目置いていたのだけれども、食事の好みや考え方が合わなくて最後には仲違いしてしまった。
3
それでも周囲の魔族の「同胞」たちに「舐められる」のは勘に触ったし(もちろん疎外感もあった)、健康上の必要もあって人間の生き血を飲むようになった。現実的な話として、優しい哀れな母が亡くなってからは、誰も新鮮な血を飲ませてくれない。だから自分で「狩る」しかないのだ。
それにサキにとっては心の中で「同胞であるはずの母を守ってくれずに虐待して、絶望と魔族への身売りに追いやった、無力で仁義のない人間たち」への恨みもあったから、感情的には意趣返しや当てつけでもあっただろう。人間たちはサキの母のことを「魔族に身売りした裏切り者」と陰口を叩いているようだったが、うち続く戦乱・治安崩壊と便乗した匪賊の跋扈で母がどんな酷い辛酸を舐めたかを知っていれば、「あなたたちなんかに母さんの何がわかるの?」「あんたらがゴミ弱者で信用も当てにもならないからでしょ、人間の同胞より魔族を頼られてる時点で面目丸潰れで自己責任だわ!」と言ってやりたかった。
だったら公私両面で支給される食用人肉を食べまくれば良いようなものだけれど、やっぱり母の同族の人間の命まで奪ってしまうやり方には拒否感や嫌悪感があった。食べるための「高級なお肉」が食卓にあるということは「そのために屠殺・解体された人間がいる」ということだから、あまりいい気分にはなれない(あまり美味しいとも思えなかった)。その点、少しばかり生き血を啜ったくらいだったら人間はそうは死なないのだからかえって気楽なものだったし、逃げて抵抗する人間をやり込めるのは娯楽遊戯のゲームでもある。
「私、お肉より新鮮な生き血を飲む方が好きなの」
そんなふうに言うと、兄弟姉妹たちは「魔族らしくなった」「ワイルドな嗜好」と、安心したように喜んでくれたものだった。父は本心を見透かしてなのか、「殺してその場で「血の生き肉」を食べたらもっと美味いかもしれんぞ」などと意地悪なことを言うものだから、「お肉は血抜きして熟成させた方が美味しいらしいですけど」と正論で言い返したら、生意気な娘の言い分に大笑いしていたものだ。
それから一番に素晴らしい利点は、血を吸って噛み跡をつけることで「獲物の宣言の印」になるために、他の魔族たちが勝手に殺すのは「マナー違反」になることだ。皮肉なことではあったけれども、サキに血を吸われていることで他の魔族による狩猟からは免れやすくなるので、実質的に庇護を与えているのと変わらない(多少気の強い魔族であっても伯爵令嬢には遠慮する)。
だから、わざと人間にとって犠牲者が多い危険地域である場所で、「可愛い」と感じた男の子や子供を狙うことが多かった。「守ってあげている」という力の満足感や優越感、そして「必ずしも危害を加えているだけではない」という自分自身への言い訳にもなっていた。
4
そうこうしているうちに、だんだんにサキの習性が「狩り場」の人間たちに知られてしまう。「優しい吸血鬼の綺麗なお姉さん」から血を吸われて勃起してしまうような少年たちが増えてきて、つい好奇心と悪戯心を起こしてしまった。人間とのセックスなんて魔族には割とよくある趣味ではあったし、インモラルでワルぶりたいお年頃でもあったから。
試しにズボンを下ろさせてしゃぶってみたら、これが予想外に楽しくて美味しくて。奥手だったはずのサキが性的興奮とエクスタシーに目覚めたのはそんなときで、何かが開花して吸血鬼というよりもサキュバスになってしまった。どうやら完全に性に合っていた。