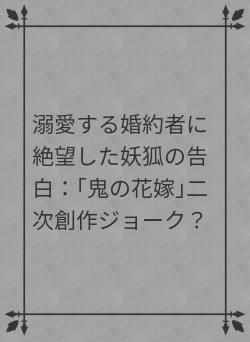1
旧魔王戦役の終結直後の監獄はどこでも、魔族シンパと連携・共謀して侵略幇助していた権力者・無法者で溢れかえっていたそうだ。
驚くべきことには、それなりに高級な社会的地位のある連中が大量に裏切っていたこと。彼らの場合には無責任行為やサボタージュを繰り返すだけで、人間側に多大な打撃を与え続けることができた。市参事会なども半分くらいは死刑や公職追放・資産没収などだったし、裁判官やら上級の学校の教授なども似たり寄ったりだったらしい。
まだ保身や迎合でもたいして悪意がない・罪が軽いと見做された者たちは流石に多くが免責されたが、それでも免職・降格・減給や「過失責任」で罰金などの嵐。それでも「幸運な部類」の大多数なのであった。
2
「ぎゃぐみょんとひゅーのはねー(学問というのはねえ)」
独房で、逮捕と破滅で気が狂った「元」教授がブツブツ言っている。玄妙と韜晦の巧みな話術と詭弁の論理学、それにデマや誤情報を混ぜたり重要情報を隠蔽するなどして、人々を騙したり混乱させるプロだった。
こんな奴らが他にも何千人といたのだから、恐ろしい話だった。
「おい、お前の番だ」
看守が軍事裁判の順番で呼びに来る。
「ひゃひゅひょ、ひょ?」
もうとっくに人間の言葉すら通じない先生。これまでも巧みな修辞学と論理学で世を欺き騙してきたのだが、今は動物か宇宙人のやり方でしらばくれる。
「だんあちゅ、なんでしゅねえ。じんけんとぎゃぐもんのそんげんへのぼーとくはゆるしゃれなひ! しゃがれうちぇろ、むちなていがきゅれきめ!」
(弾圧なんですねえ。人権と学問の尊厳への冒涜は許されない! 下がれ失せろ、無知な低学歴め!)
「何を言っているんだ、お前は! ラリってんのか、この詐欺野郎! いいから裁判だ、早く出ろ!」
頭を小突かれて、ロープを引っ張って引きずり出される。さながらヤドカリの如き執念で抵抗したが(有罪で死刑がわかりきっているので)、棍棒で殴られ蹴飛ばされて軍事法廷の場にまでついに連行される。引き攣った頬で笑うような狂人の表情を浮かべながら。
それから判決(死刑宣告)のために待っていたのは、およそ「低学歴」とは言えない人たちも多数だった。世の中には法律学校や神学校を出ている人間は幾らでもいるのだし、一定数は賢い連中もいる。いかに教授や博士を名乗って欺こうが、デタラメをやりまくればバレて当たり前だった。
死刑囚の最後の抵抗は、その場で脱糞してウンコ投げであった。
しかし、無駄だ。判決で発狂して暴れる囚人が多いのでとっくに対策はとられており、被告席の四方は強化ガラス張り(魔法強化され、見えない)。
それでも大便を両手に握りしめて、最後の抵抗の構えする。しかし、無駄だ。
「よし、死刑執行!」
裁判官が合図すると、刑務官がレバーを引っ張る。
すると、トゲのついた天井が落ちてきて、グチャリとゆっくり押し潰してしまうのだ。次に床が開いて臨死体験しながら、下の穴に落ちていく。
旧魔王戦役の終結直後の監獄はどこでも、魔族シンパと連携・共謀して侵略幇助していた権力者・無法者で溢れかえっていたそうだ。
驚くべきことには、それなりに高級な社会的地位のある連中が大量に裏切っていたこと。彼らの場合には無責任行為やサボタージュを繰り返すだけで、人間側に多大な打撃を与え続けることができた。市参事会なども半分くらいは死刑や公職追放・資産没収などだったし、裁判官やら上級の学校の教授なども似たり寄ったりだったらしい。
まだ保身や迎合でもたいして悪意がない・罪が軽いと見做された者たちは流石に多くが免責されたが、それでも免職・降格・減給や「過失責任」で罰金などの嵐。それでも「幸運な部類」の大多数なのであった。
2
「ぎゃぐみょんとひゅーのはねー(学問というのはねえ)」
独房で、逮捕と破滅で気が狂った「元」教授がブツブツ言っている。玄妙と韜晦の巧みな話術と詭弁の論理学、それにデマや誤情報を混ぜたり重要情報を隠蔽するなどして、人々を騙したり混乱させるプロだった。
こんな奴らが他にも何千人といたのだから、恐ろしい話だった。
「おい、お前の番だ」
看守が軍事裁判の順番で呼びに来る。
「ひゃひゅひょ、ひょ?」
もうとっくに人間の言葉すら通じない先生。これまでも巧みな修辞学と論理学で世を欺き騙してきたのだが、今は動物か宇宙人のやり方でしらばくれる。
「だんあちゅ、なんでしゅねえ。じんけんとぎゃぐもんのそんげんへのぼーとくはゆるしゃれなひ! しゃがれうちぇろ、むちなていがきゅれきめ!」
(弾圧なんですねえ。人権と学問の尊厳への冒涜は許されない! 下がれ失せろ、無知な低学歴め!)
「何を言っているんだ、お前は! ラリってんのか、この詐欺野郎! いいから裁判だ、早く出ろ!」
頭を小突かれて、ロープを引っ張って引きずり出される。さながらヤドカリの如き執念で抵抗したが(有罪で死刑がわかりきっているので)、棍棒で殴られ蹴飛ばされて軍事法廷の場にまでついに連行される。引き攣った頬で笑うような狂人の表情を浮かべながら。
それから判決(死刑宣告)のために待っていたのは、およそ「低学歴」とは言えない人たちも多数だった。世の中には法律学校や神学校を出ている人間は幾らでもいるのだし、一定数は賢い連中もいる。いかに教授や博士を名乗って欺こうが、デタラメをやりまくればバレて当たり前だった。
死刑囚の最後の抵抗は、その場で脱糞してウンコ投げであった。
しかし、無駄だ。判決で発狂して暴れる囚人が多いのでとっくに対策はとられており、被告席の四方は強化ガラス張り(魔法強化され、見えない)。
それでも大便を両手に握りしめて、最後の抵抗の構えする。しかし、無駄だ。
「よし、死刑執行!」
裁判官が合図すると、刑務官がレバーを引っ張る。
すると、トゲのついた天井が落ちてきて、グチャリとゆっくり押し潰してしまうのだ。次に床が開いて臨死体験しながら、下の穴に落ちていく。