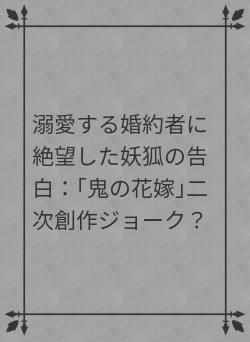3
いつかの、サキとの会話が脳裏をよぎる。
「人間もろくに食べないとか
おかしいよ。雑種だからしょーがないとか思わず、もうちょっと魔族のプライド持ったら? そんな風だからみんなからも舐められるんじゃん。あんただけじゃなくって魔族全部がさ」
「あら? 共食いしないと生きていけない方こそ「出来損ない」なんじゃないの?」
たしか、ずっと昔の子供の頃のことだった。
魔族といえども下層階級の出身だったシェリーは、雑種ハーフのサキとはよく一緒にいることが多かったように思う。伯爵の妾腹だから金がないわけでもないだろうに、主に下層階級魔族のための人肉代用食である「血のジャガイモ」などばかりを好んで食べていることもあって、親しみやすかったからだ。
当時のサキは痩せた女の子だった。人肉をあまり食べたがらないせいなのか発育が悪く、人間の母親がたまに乳房から血を飲ませていたらしい。
なんだか可哀想に思ったシェリーは、市場で買った食用の人肉を手料理のサンドイッチやシチューにして、何度もサキに勧めてみたことがある。けれどもサキは謝絶して食べようとせず、なんだか裏切られた気持ちになって、それから彼女とも疎遠になってシェリーはもっと孤独になった。
後にサキが「サキュバス」をやって人間の男たちの体液を飲んだり、もっと忌まわしいやり方で摂取していると人伝に聞いたときには、ショックで眩暈がして吐いてしまった。
「ねえ、あんた。あの噂って本当なの?」
「噂?」
「……あんたが、その、人間の男と」
駆けつけ、再会したサキはいくらか血色が良くなって、人間なら二十歳前ほどの美しい娘になっていた。
けれども安堵しつつも、シェリーの胸の中は罪悪感でいっぱいだった。「どうしてもっと熱心に人肉を勧めてあげなかったのか?」。上位の存在であるはずの魔族からすれば、人間との性行為は変態趣味でしかない(実際には多かったが、あくまでも「奴隷や玩具」が建て前なのだ)。特に魔族の女性が食事目的で精液乞食するのは屈辱的ですらある。
「やっぱり、身体の具合が辛かった? そんな片意地はらずに一緒にレストラン行こうよ! 今日くらいおごってあげるからさ!」
「人肉(ひとにく)?」
「うん! 美味しい店知ってるから」
「遠慮しとく。ジャガイモあるし、たまに補充してる」
そんな返事に、シェリーは口をへの字に曲げた。
「そんなことしてたら、お嫁にいけなくなるよ。サキは家柄も良いんだし美人じゃん! 雑種でも気にしなくたって、いい旦那さんとか愛人が見つかるでしょ?」
遠い小さな子供の頃。シェリーが転んで血が出た膝小僧を、サキが舐めてくれたことがある(友情を抱くようになったのはそれからだっただろうか?)。あの優しい舌と唇が下等な人間のオスのナニを咥えているというのは不愉快極まりない。
しかしサキはかぶりを左右にして、想像よりもずっと酷いことを言う。
「構わないわ。貴族とかお金持ちの奥さんになんかなったら、毎日人間を料理したり食べなきゃいけなくなるでしょ?」
「本当に?」
「うん。血のジャガイモ好きだし、母さんの手料理だったから。それに」
「それに、って?」
「よくスラムで人間の男の人を誘ってチューチューってね。とっても喜んでくれるしぃ。人間の男の子って、可愛いの。思春期くらいだと夢中になっちゃって凄い勢いで、この前はお尻に」
パンっ!
嬉々として話すサキの横っ面に、シェリーは考える前にビンタを張っていた。
「信じられないっ! 最低だわ!」
たとえ生まれが低く貧しくとも「正統派の魔族」として誇りや規範意識と上昇志向を持っているシェリーからすれば、サキは敗北主義者でしかなかった。しかも度し難い変態に堕ちてしまっているキチガイ女め。
4
その後で、シェリーは親しく親身になってくれている従兄に相談した。彼は騎士になっていて、貴族の男性にも何人か友人がいる。
「友達を助けてあげて欲しいんだ。美人だけど偏食とノイローゼでさ、それで身を持ち崩しそうになってて。でも悪い子じゃないから、どこかの貴族のお妾さんとかだったら、十分イケると思うよ。いっそ、私に紹介してくれてる人たちに、私と一緒に嫁いでも良いし」
従妹のシェリーから事情を聞いた従兄は、友人の貴公子たちとサキを輪姦レイプした。幸いにも彼女はまだ処女だったようだ。
シェリーは同伴して、ニヤニヤ笑ってそれを眺めていた。やはりサキのような上等な娘は、一流の魔族に囲われるべきだし、やっと友人も目を覚ますだろうと。
だから、事後に二人になってから勝利顔で告げた。
「それで、あの中で誰が気に入った? あいつらってエリートだし、従兄のアニキの友達だし。サキはお母さんは奴隷猿でも、伯爵の子供なんだし、いくらでも良い貰い手あるんじゃない?
あとで「処女を奪われた」って言ってやったら、もう正式に愛人にするしかなくなるよ。私も証人になってあげるからさ!」
「あなたがやったの?」
予想外にも、サキはひどく心を傷つけられた様子で(何故泣いていたのだろうか?)黙って立ち上がり、「あんたなんか大嫌い!」と呟いて立ち去ってしまう。シェリーは、人間にザーメン乞食する変態女にまで倫理観やプライドが落ちぶれたサキが、やや強引とはいえ降って湧いた「僥倖」に激怒するのが理解不能だった。
それが価値観の噛み合わない二人の喧嘩別れで、長い因縁の始まりだった。
5
やがて、鉄格子の向こうに忌まわしい人間の女たちが現れ、シェリーは現実に引き戻される。
彼女たちは日々に魔族の脅威と恐怖に怯え続け、本人が直接・間接の被害を受けたり、身内が犠牲になっている者も少なくない。ゆえに復讐心旺盛で陰険で残酷だった。
「おーい、魔族の便所女、生きてる? 男どもだけじゃお仕置きにならないかもだから、私たちが手伝ってあげに来たの。感謝しろっつーの!」
「そーよねー。どうせスキモノだし、悦んでるだけでしょ? 男って、ちょっと見た目がいい女には甘いからさぁ」
頷き合いながら獄中に入ってくる。シェリーは魔族ではあるのだけれども、人間の呪いで魔力を失っているのだった。
鎖がジャラジャラと引っ張られると、両腕で吊り下げられてしまう。手錠の鎖が天井の滑車につなげられているのだった。
「さぁて、今日はどうしようかしら?」
「じゃん! こんなの、持ってきましたあ!」
わざとらしいやり取りではしゃぐ復讐の女たち。
それは大きな凶悪なペンチだった。
「え? な、何を?」
「こうするのよっ!」
裸の乳首を摘まんで引っ張られ、抗弁しようとしたところをグチャリと挟み潰される。さらに引っ張る。
「あいたたた! やめて、千切れちゃう!」
「いいじゃない。どうせあんたは復活の魔術がかかってるから、千切れても元にもどるでしょ? れっつ、トライアル!」
「うううう! い、痛い! 痛いよぅ! ああああああああ! ああああ! 止めて止めて止めて、あああああああうううううううごおおおおおおおおおお!!」
グイグイと引っ張られ、乳首を潰されて血の出ている乳房が変形して伸びる。ブチッと引きちぎれたとき、シェリーは獣のような咆哮を地下牢全域に響くほどにほとばしらせていた。
その日、反対の乳首とクリトリスや陰唇も同じやり方で破壊された。内部組織まではみ出して引きずり出され悶絶してしまう。恒例となっている革紐を巻いた拳で顔面や胸腹・背中を数人がかりで何十回も殴られて、口にウジの湧いた馬糞を詰め込まれた。髪の毛に火をつけられて泣き叫ぶ。
それから乾いた血のこびりついた鞭で交代で三百回鞭打たれた。「今日はこれくらいにしておいてやるよ」と人間の女たちが「定期的な復讐・制裁・教育的指導」から立ち去ったときには、血塗れで赤い水溜まりに漏らした小水と汚物の臭いが漂っていた。シェリーは半ばは意識朦朧として、切れた唇から血を流して「やめて」「鬼」などとうわごとを呟いてブルブル震えていたようだ。
もしも彼女が邪神から特別な「復活・回復の魔法効果」を授かって付与されていなければ、さっさと絶命して楽になれたかもしれない。なまじっかあだになって、終わりなき虜囚と虐待の日々が続く。
翌日に男たちがズボンにテントを張ってやって来たときには、シェリーは心底にホッとした思いだった。「女たちからの虐待から一日二日は愛嬌満点でサービスも良い」ことは既に定説になっていた。
いつかの、サキとの会話が脳裏をよぎる。
「人間もろくに食べないとか
おかしいよ。雑種だからしょーがないとか思わず、もうちょっと魔族のプライド持ったら? そんな風だからみんなからも舐められるんじゃん。あんただけじゃなくって魔族全部がさ」
「あら? 共食いしないと生きていけない方こそ「出来損ない」なんじゃないの?」
たしか、ずっと昔の子供の頃のことだった。
魔族といえども下層階級の出身だったシェリーは、雑種ハーフのサキとはよく一緒にいることが多かったように思う。伯爵の妾腹だから金がないわけでもないだろうに、主に下層階級魔族のための人肉代用食である「血のジャガイモ」などばかりを好んで食べていることもあって、親しみやすかったからだ。
当時のサキは痩せた女の子だった。人肉をあまり食べたがらないせいなのか発育が悪く、人間の母親がたまに乳房から血を飲ませていたらしい。
なんだか可哀想に思ったシェリーは、市場で買った食用の人肉を手料理のサンドイッチやシチューにして、何度もサキに勧めてみたことがある。けれどもサキは謝絶して食べようとせず、なんだか裏切られた気持ちになって、それから彼女とも疎遠になってシェリーはもっと孤独になった。
後にサキが「サキュバス」をやって人間の男たちの体液を飲んだり、もっと忌まわしいやり方で摂取していると人伝に聞いたときには、ショックで眩暈がして吐いてしまった。
「ねえ、あんた。あの噂って本当なの?」
「噂?」
「……あんたが、その、人間の男と」
駆けつけ、再会したサキはいくらか血色が良くなって、人間なら二十歳前ほどの美しい娘になっていた。
けれども安堵しつつも、シェリーの胸の中は罪悪感でいっぱいだった。「どうしてもっと熱心に人肉を勧めてあげなかったのか?」。上位の存在であるはずの魔族からすれば、人間との性行為は変態趣味でしかない(実際には多かったが、あくまでも「奴隷や玩具」が建て前なのだ)。特に魔族の女性が食事目的で精液乞食するのは屈辱的ですらある。
「やっぱり、身体の具合が辛かった? そんな片意地はらずに一緒にレストラン行こうよ! 今日くらいおごってあげるからさ!」
「人肉(ひとにく)?」
「うん! 美味しい店知ってるから」
「遠慮しとく。ジャガイモあるし、たまに補充してる」
そんな返事に、シェリーは口をへの字に曲げた。
「そんなことしてたら、お嫁にいけなくなるよ。サキは家柄も良いんだし美人じゃん! 雑種でも気にしなくたって、いい旦那さんとか愛人が見つかるでしょ?」
遠い小さな子供の頃。シェリーが転んで血が出た膝小僧を、サキが舐めてくれたことがある(友情を抱くようになったのはそれからだっただろうか?)。あの優しい舌と唇が下等な人間のオスのナニを咥えているというのは不愉快極まりない。
しかしサキはかぶりを左右にして、想像よりもずっと酷いことを言う。
「構わないわ。貴族とかお金持ちの奥さんになんかなったら、毎日人間を料理したり食べなきゃいけなくなるでしょ?」
「本当に?」
「うん。血のジャガイモ好きだし、母さんの手料理だったから。それに」
「それに、って?」
「よくスラムで人間の男の人を誘ってチューチューってね。とっても喜んでくれるしぃ。人間の男の子って、可愛いの。思春期くらいだと夢中になっちゃって凄い勢いで、この前はお尻に」
パンっ!
嬉々として話すサキの横っ面に、シェリーは考える前にビンタを張っていた。
「信じられないっ! 最低だわ!」
たとえ生まれが低く貧しくとも「正統派の魔族」として誇りや規範意識と上昇志向を持っているシェリーからすれば、サキは敗北主義者でしかなかった。しかも度し難い変態に堕ちてしまっているキチガイ女め。
4
その後で、シェリーは親しく親身になってくれている従兄に相談した。彼は騎士になっていて、貴族の男性にも何人か友人がいる。
「友達を助けてあげて欲しいんだ。美人だけど偏食とノイローゼでさ、それで身を持ち崩しそうになってて。でも悪い子じゃないから、どこかの貴族のお妾さんとかだったら、十分イケると思うよ。いっそ、私に紹介してくれてる人たちに、私と一緒に嫁いでも良いし」
従妹のシェリーから事情を聞いた従兄は、友人の貴公子たちとサキを輪姦レイプした。幸いにも彼女はまだ処女だったようだ。
シェリーは同伴して、ニヤニヤ笑ってそれを眺めていた。やはりサキのような上等な娘は、一流の魔族に囲われるべきだし、やっと友人も目を覚ますだろうと。
だから、事後に二人になってから勝利顔で告げた。
「それで、あの中で誰が気に入った? あいつらってエリートだし、従兄のアニキの友達だし。サキはお母さんは奴隷猿でも、伯爵の子供なんだし、いくらでも良い貰い手あるんじゃない?
あとで「処女を奪われた」って言ってやったら、もう正式に愛人にするしかなくなるよ。私も証人になってあげるからさ!」
「あなたがやったの?」
予想外にも、サキはひどく心を傷つけられた様子で(何故泣いていたのだろうか?)黙って立ち上がり、「あんたなんか大嫌い!」と呟いて立ち去ってしまう。シェリーは、人間にザーメン乞食する変態女にまで倫理観やプライドが落ちぶれたサキが、やや強引とはいえ降って湧いた「僥倖」に激怒するのが理解不能だった。
それが価値観の噛み合わない二人の喧嘩別れで、長い因縁の始まりだった。
5
やがて、鉄格子の向こうに忌まわしい人間の女たちが現れ、シェリーは現実に引き戻される。
彼女たちは日々に魔族の脅威と恐怖に怯え続け、本人が直接・間接の被害を受けたり、身内が犠牲になっている者も少なくない。ゆえに復讐心旺盛で陰険で残酷だった。
「おーい、魔族の便所女、生きてる? 男どもだけじゃお仕置きにならないかもだから、私たちが手伝ってあげに来たの。感謝しろっつーの!」
「そーよねー。どうせスキモノだし、悦んでるだけでしょ? 男って、ちょっと見た目がいい女には甘いからさぁ」
頷き合いながら獄中に入ってくる。シェリーは魔族ではあるのだけれども、人間の呪いで魔力を失っているのだった。
鎖がジャラジャラと引っ張られると、両腕で吊り下げられてしまう。手錠の鎖が天井の滑車につなげられているのだった。
「さぁて、今日はどうしようかしら?」
「じゃん! こんなの、持ってきましたあ!」
わざとらしいやり取りではしゃぐ復讐の女たち。
それは大きな凶悪なペンチだった。
「え? な、何を?」
「こうするのよっ!」
裸の乳首を摘まんで引っ張られ、抗弁しようとしたところをグチャリと挟み潰される。さらに引っ張る。
「あいたたた! やめて、千切れちゃう!」
「いいじゃない。どうせあんたは復活の魔術がかかってるから、千切れても元にもどるでしょ? れっつ、トライアル!」
「うううう! い、痛い! 痛いよぅ! ああああああああ! ああああ! 止めて止めて止めて、あああああああうううううううごおおおおおおおおおお!!」
グイグイと引っ張られ、乳首を潰されて血の出ている乳房が変形して伸びる。ブチッと引きちぎれたとき、シェリーは獣のような咆哮を地下牢全域に響くほどにほとばしらせていた。
その日、反対の乳首とクリトリスや陰唇も同じやり方で破壊された。内部組織まではみ出して引きずり出され悶絶してしまう。恒例となっている革紐を巻いた拳で顔面や胸腹・背中を数人がかりで何十回も殴られて、口にウジの湧いた馬糞を詰め込まれた。髪の毛に火をつけられて泣き叫ぶ。
それから乾いた血のこびりついた鞭で交代で三百回鞭打たれた。「今日はこれくらいにしておいてやるよ」と人間の女たちが「定期的な復讐・制裁・教育的指導」から立ち去ったときには、血塗れで赤い水溜まりに漏らした小水と汚物の臭いが漂っていた。シェリーは半ばは意識朦朧として、切れた唇から血を流して「やめて」「鬼」などとうわごとを呟いてブルブル震えていたようだ。
もしも彼女が邪神から特別な「復活・回復の魔法効果」を授かって付与されていなければ、さっさと絶命して楽になれたかもしれない。なまじっかあだになって、終わりなき虜囚と虐待の日々が続く。
翌日に男たちがズボンにテントを張ってやって来たときには、シェリーは心底にホッとした思いだった。「女たちからの虐待から一日二日は愛嬌満点でサービスも良い」ことは既に定説になっていた。