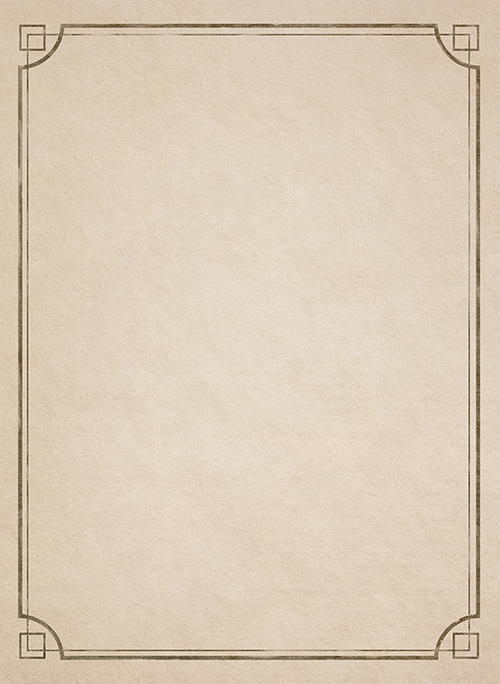行くよう伝えた。見張りは自分一人で継続するから、と。
だが、あかりは首を振った。そんなことまでしなくてもいいというのが、彼女の言い分だった。
夫妻が本物か偽物か、できるだけ早いうちにはっきりとさせたい渉はちょっとの間抵抗して見せたが、結局は空腹を理由に折れた。あかりの奢りで、二人は近くのファミレスで昼食を食べた。
食事が済んだ二人は、再び公園に戻り活動を再開させたが、日の暮れる時間まで成果と呼べるものは得られなかった。
どこかにいるカラスの鳴き声があたりに響いて、それを合図に渉はスマホで時刻を確認した。もうまもなく一八時という時間だった。
件のあの現実逃避をしているあかりとは違い、渉は悔しそうに歯を食いしばった。そして、何の変化も生まれなかった灰色の住宅を憎々しげに見つめた。
少年は見張りを継続したいと主張したが、依頼主であるあかりが首を振ったため、泣く泣く帰宅することになった。
そうして土曜日は、一日を無駄にしたと言う結論で帰着した。
渉は双眼鏡をあかりに返却し、帰路についた。ふと後ろを振り返ると、あかりがあの灰色の家に歩いていくのが見えた。
夕暮れの中をたった一人で進んでいく彼女の目的地は、信じられる者のいない空虚な箱だ。
あの箱の中には、あかりの両親を騙った連中が居座っている。まだ可能性の段階ではあるが、それは渉の心にどうしようもない苛立ちのような感情を抱かせる。
この件に関わるほどに、渉はあかりという少女の行く末を案じるようになっていった。
あかりは現在、孤独の中で生きている。本来であれば一番信用のできるはずの両親が、何者かに成り代わられたかもしれないのだから。
もし自分が同じ立場になったのなら、と渉は想像してみた。恐らく自分は、家族だけではなく、学校の友人も、教師も信じられなくなってしまうかも知れない。常に疑心暗鬼に陥って、まともに人間社会を生きていけないのではないかと思った。
あかりが背負っているのは、彼には重すぎるほどの重荷である。だからこそ、渉は彼女への協力を惜しまないのかも知れなかった。
しかし理由がどうであれ、行動には結果がつきものだ。その結果が文字通り全くのゼロなのだから、渉が良い気がしないのも当たり前なのかも知れない。
明日こそは、解決への手がかりを掴んでみせる。遠ざかっていく背中に、彼は心の中で誓った。
結果がどうであれ、解決のための糸口を見出さないことには彼のいる意味もないのだ。
決意を新たに、彼は問題の家に背を向けて歩き出した。その先には、彼が帰るべき家がある。
だが、あかりは首を振った。そんなことまでしなくてもいいというのが、彼女の言い分だった。
夫妻が本物か偽物か、できるだけ早いうちにはっきりとさせたい渉はちょっとの間抵抗して見せたが、結局は空腹を理由に折れた。あかりの奢りで、二人は近くのファミレスで昼食を食べた。
食事が済んだ二人は、再び公園に戻り活動を再開させたが、日の暮れる時間まで成果と呼べるものは得られなかった。
どこかにいるカラスの鳴き声があたりに響いて、それを合図に渉はスマホで時刻を確認した。もうまもなく一八時という時間だった。
件のあの現実逃避をしているあかりとは違い、渉は悔しそうに歯を食いしばった。そして、何の変化も生まれなかった灰色の住宅を憎々しげに見つめた。
少年は見張りを継続したいと主張したが、依頼主であるあかりが首を振ったため、泣く泣く帰宅することになった。
そうして土曜日は、一日を無駄にしたと言う結論で帰着した。
渉は双眼鏡をあかりに返却し、帰路についた。ふと後ろを振り返ると、あかりがあの灰色の家に歩いていくのが見えた。
夕暮れの中をたった一人で進んでいく彼女の目的地は、信じられる者のいない空虚な箱だ。
あの箱の中には、あかりの両親を騙った連中が居座っている。まだ可能性の段階ではあるが、それは渉の心にどうしようもない苛立ちのような感情を抱かせる。
この件に関わるほどに、渉はあかりという少女の行く末を案じるようになっていった。
あかりは現在、孤独の中で生きている。本来であれば一番信用のできるはずの両親が、何者かに成り代わられたかもしれないのだから。
もし自分が同じ立場になったのなら、と渉は想像してみた。恐らく自分は、家族だけではなく、学校の友人も、教師も信じられなくなってしまうかも知れない。常に疑心暗鬼に陥って、まともに人間社会を生きていけないのではないかと思った。
あかりが背負っているのは、彼には重すぎるほどの重荷である。だからこそ、渉は彼女への協力を惜しまないのかも知れなかった。
しかし理由がどうであれ、行動には結果がつきものだ。その結果が文字通り全くのゼロなのだから、渉が良い気がしないのも当たり前なのかも知れない。
明日こそは、解決への手がかりを掴んでみせる。遠ざかっていく背中に、彼は心の中で誓った。
結果がどうであれ、解決のための糸口を見出さないことには彼のいる意味もないのだ。
決意を新たに、彼は問題の家に背を向けて歩き出した。その先には、彼が帰るべき家がある。