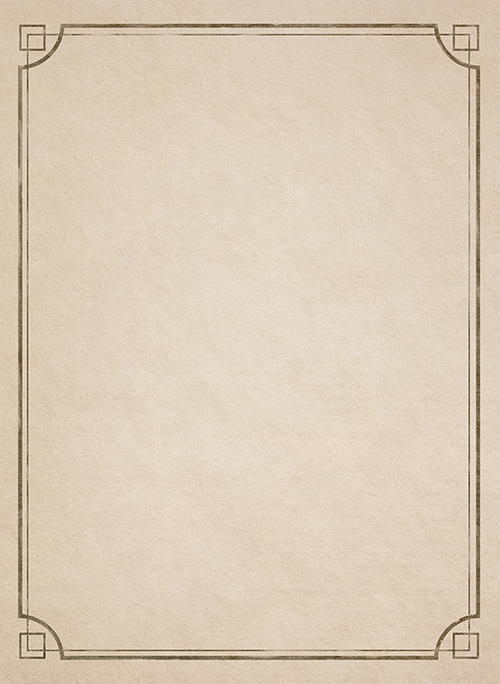「そういえば、僕って石嶺さんの家族の顔を知らないんだけど」
ある時点で、渉はそう言った。そして隣に座っているあかりの方を見やった。彼女は文庫本を一冊取り出して、のんびり読書をしているところだった。渉の声に反応して持ち上げた顔には、不思議そうな表情を浮かべている。
「どういう意味?」
「ほら、僕は石嶺さんの両親の顔を知らない。だから、今見張っているのが本当に石嶺さんの両親で間違いないのか、わかんないんだ」
「そういうことね。ちょっと待ってね」
あかりは画用紙でできた手作り感のあるしおりを本に挟み、自分の双眼鏡を手にして家のある方角を向いた。
視点をよく調節している気配があった。やがて双眼鏡から目を離して、一つ頷いてみせる。
「間違いなく、私のお父さんとお母さんよ。少なくとも顔はね」
「身長とか、体格も間違いない?」
あかりが頷いた。現在石嶺家でくつろいでいる二人は、本物で間違いないらしい。もちろん、中身がどうなのかは不明だ。それをこれからはっきりとさせるのだ。
渉が監視を再開させる。聴覚には子供達の元気な声が訴えかけ、視覚には落ち着いた休日の大人の姿が捉えられている。
何もかもが正反対の二つの情報を、渉はしっかりと別々のものとして受け取っていた。
聞こえる声が突然大きくなれば振り向くし、リビングで何やら動きがある際には、周りの人々を忘れたように双眼鏡を覗き込む。
目と耳とを使い分けながら過ごしているうち、時刻は一一時を少し過ぎた頃になっていた。
その頃には、渉の集中力も途切れかけ、子供達も皆一旦は家に帰宅していた。昼食の時間が近づいている。
「異常は何かあった?」
読んでいた本を閉じ、あかりが尋ねる。
渉は静かに首を振って言った。
「何もない。ずっとテレビを観て、お菓子を食べたりしているだけだよ。怪しい動きなんてちっともなかった」
「おかしいわね、てっきり油断してくれるものだと思っていたのに」
悔しがったり、焦ったりせずにあかりは呟いた。目の前の人がいなくなった砂場を見つめている。科学者が実験結果の報告を受けた
時のように、感情の波が一定になっているようだった。
現状をどうにか納得しようとしているんだ、と渉は思った。
「ねえ、石嶺さん、訊いていいかな」
彼はほとんど出し抜けにそう言った。あかりが視線を彼の方に持っていく。
「なに?」
ある時点で、渉はそう言った。そして隣に座っているあかりの方を見やった。彼女は文庫本を一冊取り出して、のんびり読書をしているところだった。渉の声に反応して持ち上げた顔には、不思議そうな表情を浮かべている。
「どういう意味?」
「ほら、僕は石嶺さんの両親の顔を知らない。だから、今見張っているのが本当に石嶺さんの両親で間違いないのか、わかんないんだ」
「そういうことね。ちょっと待ってね」
あかりは画用紙でできた手作り感のあるしおりを本に挟み、自分の双眼鏡を手にして家のある方角を向いた。
視点をよく調節している気配があった。やがて双眼鏡から目を離して、一つ頷いてみせる。
「間違いなく、私のお父さんとお母さんよ。少なくとも顔はね」
「身長とか、体格も間違いない?」
あかりが頷いた。現在石嶺家でくつろいでいる二人は、本物で間違いないらしい。もちろん、中身がどうなのかは不明だ。それをこれからはっきりとさせるのだ。
渉が監視を再開させる。聴覚には子供達の元気な声が訴えかけ、視覚には落ち着いた休日の大人の姿が捉えられている。
何もかもが正反対の二つの情報を、渉はしっかりと別々のものとして受け取っていた。
聞こえる声が突然大きくなれば振り向くし、リビングで何やら動きがある際には、周りの人々を忘れたように双眼鏡を覗き込む。
目と耳とを使い分けながら過ごしているうち、時刻は一一時を少し過ぎた頃になっていた。
その頃には、渉の集中力も途切れかけ、子供達も皆一旦は家に帰宅していた。昼食の時間が近づいている。
「異常は何かあった?」
読んでいた本を閉じ、あかりが尋ねる。
渉は静かに首を振って言った。
「何もない。ずっとテレビを観て、お菓子を食べたりしているだけだよ。怪しい動きなんてちっともなかった」
「おかしいわね、てっきり油断してくれるものだと思っていたのに」
悔しがったり、焦ったりせずにあかりは呟いた。目の前の人がいなくなった砂場を見つめている。科学者が実験結果の報告を受けた
時のように、感情の波が一定になっているようだった。
現状をどうにか納得しようとしているんだ、と渉は思った。
「ねえ、石嶺さん、訊いていいかな」
彼はほとんど出し抜けにそう言った。あかりが視線を彼の方に持っていく。
「なに?」