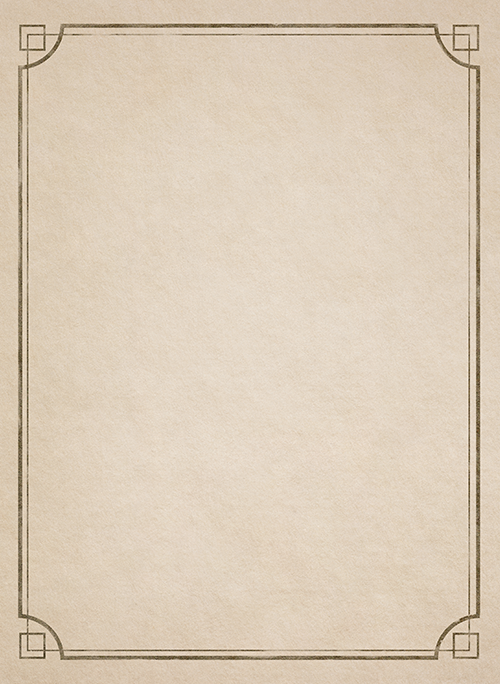いるんだね」と、あかりを極力不快にさせないような話し方をした。
疑問をぶつけられたあかりは、オレンジジュースを一口飲んで、その間に考えた答えを渉に聞かせてくれた。
「私、余裕がないことが嫌いなの。例えば、課題の提出期限が迫ってるとか、友達と大喧嘩した翌日とかね。考えなくちゃいけないことで頭をいっぱいにして、眠れないし、落ち着かない気分になる。そういうのって、すごく嫌い。考え込んだり心配をする時間って、勿体無いでしょ? できる限り、楽しいことだけの生活のほうがいいじゃない。だから、今回のこともできるだけ落ち着いて対処しようって思って、そのためには『なるべく気にしないようにする』のが正解だと思ったわけ。だから、他人事みたいな言い方になっちゃうのかも」
つまり、状況を意図的に過小評価しているのだ、と渉は思った。
あかりの今の状態というのは、言い換えるならばそれほどまでに追い詰められていることに他ならないだろう。
敢えて考えないようにする。
たとえ毎日顔を合わせる両親が別の人間であると確信を持っていても、その正体が全く不明であっても、できるだけ頭の中から排除する。考えてしまわないようにする。
彼女のしていることは、現実逃避なのだ。そんなものは毎日思った通りに続くわけがない。
違和感を感じるたびに、必死に言い聞かせるのは無理があるだろう。
バケツに入れ続けた水が溢れてくるように、感じないようにしていた不安と恐怖がある時点で傾れ込んでくるはずだ。
事態の収束はなるべく早い方が良い、と少年は意識のスイッチを切り替えた。
「それで、作戦って何の作戦を立てるの?」
目下の目標とは、作戦立案である。
あかりは顎を人差し指でトントンと叩きながら、天井を睨んだ。それから視点を渉に定めた。
「呉屋くん、ドラマとか観る?」
「時々」
「刑事ドラマって、いきなりかっこよく犯人を吹っ飛ばしたり、逮捕したりしないじゃない? もっと地道な捜査活動の末、犯人を追い詰めていくわよね」
「そうだね。聞き込みとか、張り込みとか頑張ってるイメージはある」
「私たちにもそういった活動って必要だと思うのよ」
「つまり、聞き込みとか、張り込みをするってこと?」
あかりは首を振った。
「そんなことしたって意味ないわよ。私たち家族はご近所付き合いなんてないし、張り込みをするにしたって、刑事さんが乗ってくるような車は持ってない」
疑問をぶつけられたあかりは、オレンジジュースを一口飲んで、その間に考えた答えを渉に聞かせてくれた。
「私、余裕がないことが嫌いなの。例えば、課題の提出期限が迫ってるとか、友達と大喧嘩した翌日とかね。考えなくちゃいけないことで頭をいっぱいにして、眠れないし、落ち着かない気分になる。そういうのって、すごく嫌い。考え込んだり心配をする時間って、勿体無いでしょ? できる限り、楽しいことだけの生活のほうがいいじゃない。だから、今回のこともできるだけ落ち着いて対処しようって思って、そのためには『なるべく気にしないようにする』のが正解だと思ったわけ。だから、他人事みたいな言い方になっちゃうのかも」
つまり、状況を意図的に過小評価しているのだ、と渉は思った。
あかりの今の状態というのは、言い換えるならばそれほどまでに追い詰められていることに他ならないだろう。
敢えて考えないようにする。
たとえ毎日顔を合わせる両親が別の人間であると確信を持っていても、その正体が全く不明であっても、できるだけ頭の中から排除する。考えてしまわないようにする。
彼女のしていることは、現実逃避なのだ。そんなものは毎日思った通りに続くわけがない。
違和感を感じるたびに、必死に言い聞かせるのは無理があるだろう。
バケツに入れ続けた水が溢れてくるように、感じないようにしていた不安と恐怖がある時点で傾れ込んでくるはずだ。
事態の収束はなるべく早い方が良い、と少年は意識のスイッチを切り替えた。
「それで、作戦って何の作戦を立てるの?」
目下の目標とは、作戦立案である。
あかりは顎を人差し指でトントンと叩きながら、天井を睨んだ。それから視点を渉に定めた。
「呉屋くん、ドラマとか観る?」
「時々」
「刑事ドラマって、いきなりかっこよく犯人を吹っ飛ばしたり、逮捕したりしないじゃない? もっと地道な捜査活動の末、犯人を追い詰めていくわよね」
「そうだね。聞き込みとか、張り込みとか頑張ってるイメージはある」
「私たちにもそういった活動って必要だと思うのよ」
「つまり、聞き込みとか、張り込みをするってこと?」
あかりは首を振った。
「そんなことしたって意味ないわよ。私たち家族はご近所付き合いなんてないし、張り込みをするにしたって、刑事さんが乗ってくるような車は持ってない」