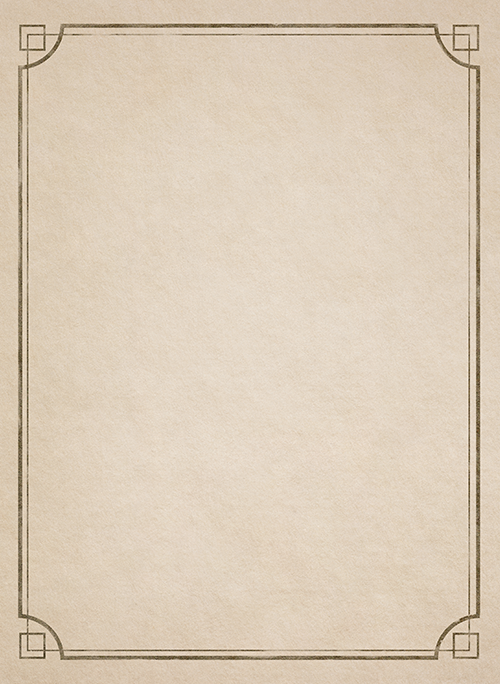本格的な調査開始は、一週間後となった。
渉とあかりの二人が、共にアルバイトに励んでいる学生だったためだ。
渉はコンビニ、あかりが喫茶店勤務だった。両者ともシフトの急な変更が効かない場所であったため、一度時間を置くことがどうしても必要だった。
シフト調整のための話し合いをするにあたり、二人は連絡先を交換した。渉にとって初めての異性の連絡先だった。
この日でどうだろうか、という話し合いが何度か持ち上がった後、二人はようやく時間を作り合流することができた。
金曜日の放課後、渉とあかりは学校の外で合流して、それから適当なファストフード店に寄った。夕方ということもあり、学生たちの入りが激しく、賑やかな空間だった。
向かい合って座った渉とあかりは、ひとまず注文した商品に手をつけた。渉はいつも注文しているハンバーガーのセットで、あかりはアップルパイとオレンジジュースの二つだけだった。
「一番に必要なものが何なのか、私なりに考えてみたの」
と、あかりが言った。渉は食事の手を止めて、彼女の話に耳を傾ける。
「まずは作戦よ、必要なものは。これがなくては、きっと私たちの動きをあの『偽物』たちに察知されるに違いないわ」
「もう偽物であることは確定したんだ」
渉は率直に感じたことを言ってみた。するとあかりは腕を組んで、厳粛な顔になった。まるで、話の筋を掴めていない子供を叱りつける大人みたいだ。
「ええ、間違い無いわ。図書室で話をした日にもう一度、改めて観察し直したのよ。そしたら余計に、お父さんとお母さんじゃないってことがはっきりとしたわ。浮き彫りになったと言えば良いのかな、とにかくそんな感じ」
食事を再開させながら、渉は頭の中で色々な考えを巡らせていた。
石嶺あかりは、どこか自分の置かれている状況を他人事のように考えている節があった。
この件に関して、両親という存在がもし本当に偽物だったとして、一番の被害を被るのはあかり自身であるはずなのだ。しかしその本人は、珍しい生き物を見つけた時のようにやけにあっさりとしている。
それを見つけたなら、あとはもう自分には関係がない。そう言っているようにも思えるのだ。
一週間前には、こんな態度ではなかった。もっと深刻で、自分ごととして事態を受け止めていたはずだ。何せ家族のことなのだから。だからこそ、ああやって渉のような、特に親しいわけでもない人物を頼ったのではないか。
渉は自分の抱いた疑問を、できる限りそのまま伝えた。「落ち着いて
渉とあかりの二人が、共にアルバイトに励んでいる学生だったためだ。
渉はコンビニ、あかりが喫茶店勤務だった。両者ともシフトの急な変更が効かない場所であったため、一度時間を置くことがどうしても必要だった。
シフト調整のための話し合いをするにあたり、二人は連絡先を交換した。渉にとって初めての異性の連絡先だった。
この日でどうだろうか、という話し合いが何度か持ち上がった後、二人はようやく時間を作り合流することができた。
金曜日の放課後、渉とあかりは学校の外で合流して、それから適当なファストフード店に寄った。夕方ということもあり、学生たちの入りが激しく、賑やかな空間だった。
向かい合って座った渉とあかりは、ひとまず注文した商品に手をつけた。渉はいつも注文しているハンバーガーのセットで、あかりはアップルパイとオレンジジュースの二つだけだった。
「一番に必要なものが何なのか、私なりに考えてみたの」
と、あかりが言った。渉は食事の手を止めて、彼女の話に耳を傾ける。
「まずは作戦よ、必要なものは。これがなくては、きっと私たちの動きをあの『偽物』たちに察知されるに違いないわ」
「もう偽物であることは確定したんだ」
渉は率直に感じたことを言ってみた。するとあかりは腕を組んで、厳粛な顔になった。まるで、話の筋を掴めていない子供を叱りつける大人みたいだ。
「ええ、間違い無いわ。図書室で話をした日にもう一度、改めて観察し直したのよ。そしたら余計に、お父さんとお母さんじゃないってことがはっきりとしたわ。浮き彫りになったと言えば良いのかな、とにかくそんな感じ」
食事を再開させながら、渉は頭の中で色々な考えを巡らせていた。
石嶺あかりは、どこか自分の置かれている状況を他人事のように考えている節があった。
この件に関して、両親という存在がもし本当に偽物だったとして、一番の被害を被るのはあかり自身であるはずなのだ。しかしその本人は、珍しい生き物を見つけた時のようにやけにあっさりとしている。
それを見つけたなら、あとはもう自分には関係がない。そう言っているようにも思えるのだ。
一週間前には、こんな態度ではなかった。もっと深刻で、自分ごととして事態を受け止めていたはずだ。何せ家族のことなのだから。だからこそ、ああやって渉のような、特に親しいわけでもない人物を頼ったのではないか。
渉は自分の抱いた疑問を、できる限りそのまま伝えた。「落ち着いて