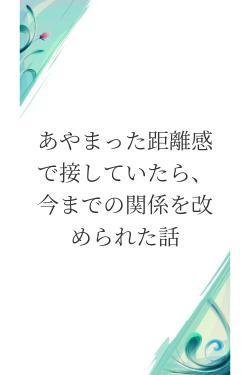窓枠のそばにより、着物が着崩れるのも気にせず。元・旦那様である清冬様は、長いキセルを手に持ったまま、入室した私に切れ長の瞳を寄こした。
「女将と花魁の手引きがなきゃ、お前を見つけるのは無理だった」
「え?」
「おう」とか「よう」もなく、もちろん「久しぶり」も「元気だったか」もない第一声は、歪んだ表情で吐き捨てられた。
「こんな薄暗い所に隠れやがって……随分と探したぞ」
「!」
清冬様が相変わらず不機嫌なことは理解できた。だけど、言われている言葉の意味がさっぱり分からない。
探す……探す?
清冬様が私を? どうして!?
あ、報復に来たとか? 私が全部の能力を取り返したから、怒ってるのだろうか。
「仕返しをしに来られたのですか?」
「は?」
「だって、そうでしょう……。能力ほしさに私を脅そうと、こんな所にまで」
ここまで言った時。カンッ、と高く大きく響く音――見ると、くわえていたキセルの灰を、清冬様が慣れた手つきで灰入れに落としていた。
「仕返し? 俺がそんな女々しい男だと思うか。見くびるな」
「……っ」
威圧感がすごい。雰囲気が、空気が――頬に傷が入る錯覚を覚えるほどの鋭さだ。
だけど……女々しい男って、今さらじゃないですか? 修行に出ると意気込んで三年。一度も帰らず、していたことと言えば「こっそり私の能力をとる」こと。しかも恩を仇で返すとはこのことで、能力が手に入れば私を用済みと言って、さっさと離縁。清冬様は実に女々しく、実に男らしくない。
視線を合わせず畳を見つめていると、清冬様が先に口を開いた。
「お前に伝えたいことがあって、ずっと探していたんだ」
「伝えたいこと?」
コトンとキセルを置き、体ごと私へ向き直る清冬様。私も近くへ寄り、お互い正座をして見つめ合った。
「俺がいない間、随分と親父を助けてくれたらしいな。お前が屋敷からいなくあった後ツツジから聞いた。感謝する」
「え……」
本当に、ほんとうに僅かだけど……清冬様は体を傾け目を伏せた。これはまさか……お辞儀? 驚愕な光景に開いた口が塞がらず固まっていると、清冬様は僅かに口角を上げる。
「お前のおかげで、親父も晩年は穏やかに過ごせたと聞く。眠った顔、すごく穏やかだったんだろう?」
「……はい。とてもきれいな寝顔のようでした」
「――ふっ、そうか」
「!」
その時、薄く笑った笑みが綺麗で、けれども儚くて。見た瞬間、唐突に三年間不在にされた「屋敷で一人ぼっちだった」日を思い出す。この人は、また遠くに行ってしまうのではないかと。既に何の縁もなくなった私だけど、これが情と言うものか――気づけば私の視線は、清冬様に釘付けになっていた。
「その顔は、睨んでいるのか?」
「……へ? あ、いえ……すみません。違います。見入っていただけです」
「見入る、か」
「……」
しまった。誤解を生む言い方をしてしまった。すぐに口を噤んだ私を、清冬様はしばらく興味深そうに眺める。しかし着物が擦れる音が聞こえたと同時に――いつ動いたか分からない俊足で、私の目の前に佇み、なおかつ顔を近づけた。
「ひっ!」思わぬ事態に頭が真っ白になる。それは清冬様が「怖い」というのもあるけれど、無駄に顔が整っているせいでもある。今まで子供としか接してこなかった私に、このくらいの年齢の男性は耐性がないのだ。
「な、なんですか……?」
「いや、随分と顔を厚く塗られたものだと思ってな」
ふっ、と嫌味っぽく笑う顔を見ると、少しだけ冷静になれる。今のが褒め言葉ではなく嫌味や皮肉の類ということは、さすがの私でも分かった。
清冬様のこういう「妙に子供っぽいところ」は、遊郭にいるというのに男女のあれこれを全く想像させない力があるから、経験不足な私にとっては重宝する。さっきまで赤面していた私の顔は、いつの間にか能面のような無表情に戻っていた。
「これくらい厚く塗らないと私は商品にならないみたいなので。見るに堪えかねるのであれば、早々に退席いたします」
「商品にならない? なら、ここの遣り手(やりて)ばあの目は節穴だ。花に花を添えても無意味だろ、魅力が半減するってもんだ」
「え……?」
今のって……もしかして褒められた? いや、まさかね――だけど少し喜んだ私がいるのか、手の内側がわずかに湿ってきた。決してバレまいと、膝の上で拳を強く握る。
しかし、そんな固い意志があっけなく崩れ去るのは――三秒後。
「で、ここからが本題だ。まずはコレを受け取れ」
「これは……?」
コレ――と言われて出されたのは、白いバラの花の束。今まで赤いバラは見たことあったけど、白なんて……こんな高級な代物、どこで手に入れたんだろう。さすが日登家だ。人脈と資金は潤っているわけか。
……そうじゃなくて。
「えっと……、この花束は?」
「お前にだ」
「わ、私に?」
なぜ? 私に渡す道理が分からない――戸惑ってなかなか花束を受け取らない私を見て「いらないなら捨てておけ」と、清冬様はバサリと投げた。花束が床にぶつかった瞬間、何枚かの花びらが千切れてしまう。あぁ、かわいそうに……。
「いくら腹が立ったからと言って……おやめください。花に罪はありません」
そっと拾い上げると、まるで花束が喜んだようにわずかに揺れた。例え清冬様からの頂き物といえど、やっぱり花を見ていると癒される。しかも、こんなに豪華な花束。何本あるんだろう、30本以上だろうか。
「……そんな顔もするんだな」
「え?」
「いや」
フイと顔を逸らしたかと思えば、再びキセル。なんと慌ただしく、落ち着かない人だろう。
「それで、どうして花束を? 私には受け取る理由がないのですが……」
「――……だ」
「え?」
ただでさえキセルをくわえていて聞き取りずらいのに、私がいる向きとは正反対の窓を向かれ、更に聞き取りずらかった。思わず聞き返すと――
「分からないのか鈍い奴め。男が花束を贈ると言ったら、求婚を申し込んでいるに決まっているだろう」
「え……」
え?
「す、すみません……よく聞こえなかったのですが」
「二度も言わん」
ピシャリと言われてしまい、仕方なく口を閉じる。と同時に、さっき言われたことを思い出した。聞き間違いでなければ、清冬様は……求婚を申し込んでいると言った。しかも、私に――?
「ど、どこか体調が悪いのですか?」
「は?」
「だって清冬様がこんなとち狂った事をされるなんて、ご病気以外に考えられません。すぐにツツジさんを呼んで、」
「――!」
その瞬間。パシッと私の腕が握られる。間髪入れずに引き寄せられ、なすすべなく傾いた私の体は、胡坐をかいた清冬様の足の上にあっけなく倒れてしまった。
「な、ななな、なにを……っ!」
「ツツジは呼ぶな、絶対だ」
「ど、どうして呼んではいけないのですか? 調子が悪いのならお屋敷で休まれないと、」
早口で喋る私を、顔を歪めて見下ろす清冬様。今度こそキセルをやめて、代わりに懐から扇子を取り出した。何をするかと思えば私の顔の前へ持ってきて、まるで「黙れ」と言わんばかりにバサリと扇を広げた。
「俺がここにいることはツツジには内緒だ。アイツを撒くのに、どれほど大変だったと思っているんだ」
「どうして内緒なんですか……?」
「お前は知られてもいいのか?」
言いながら、着物の切れ目から覗く私の足を、清冬様が閉じた扇子でなぞっていく。ゆっくり、じわじわと。まるで私を追い詰めるように。
「わ、私は商品ではなく医者として遊郭におります……ですので、そういう行為は禁止です」
「今のお前は俺が買っている。どうしようが俺の自由だろ? それに――」
両脇へ手を入れ、清冬様は簡単に私の体を持ち上げた。そして自分の足の上に私を座らせ、私たちはかつてない至近距離で見つめ合う。
「医者をしてるっていうなら好都合。さっき〝俺の調子が悪くないか〟と心配しただろ? なら診察してくれ。その間、俺はここで休ませてもらう」
「へ?」
「頼んだぞ」
窓に体を預け、目を瞑る清冬様。この状況で放置されても……困る。
「風邪ひきますよ、清冬様」
「すー――」
なんとなんと。清冬様はものの数秒で寝てしまった。仕方ないので、私が来ていた打掛(うちかけ)を清冬様の体にかける。その時……まじまじと、顔を見てしまった。だって清冬様があまりにも綺麗な顔をしてるから、本当に生きてるの?って不思議で不思議で。
「すー――」
「……生きてる。カッコイイのに、変な人」
ボソッと呟いた後、危なくないようキセルの道具を片付ける。清冬様が寝ているなら私は用済みだし、退室してもいいよね? 抜き足差し足で襖まで移動し取っ手に手を掛ける……その時。清冬様に乱暴に引き寄せられた時に、床へ落としてしまった花束へ目をやった。
――男が花束を贈ると言ったら、求婚を申し込んでいるということだ
「今さら何を……」
呆れて物も言えないとはこういう事で、浪漫たっぷりに高価な花束を贈られたところで昔の裏切りを許せるわけでもなく。それ以前に、求婚する真意が不透明すぎるが故に……不気味だ。何の目的があって、こんな事をするんだろうか。
「……でも、花に罪はない。か」
全開の花びらを見て、誰が捨て置くことが出来るだろう。清冬様に離縁されているため、捨てられる痛みというのは良く知っているつもりだ。だから、仕方ない。
「今回だけですからね」
花束を拾い上げ、今度こそ部屋を出る。すると今回の逢引きに手を貸したとみられる花魁姉さんとバッタリ出くわした。
「まぁまぁ、こんなにステキな花を貰っちゃって。あんたも隅におけないねぇ」
「姉さん、こんな事はこれっきりにしてくださいよ。私は医者なのですから」
恨み言を言うと、姉さんは「仕方ないじゃないか」と、紅のついた色のいい唇をキュッと引っ張った。
「末春という女に会いたいと、何日も熱心に通われちゃぁねぇ」
「え……?」
何日も、熱心に?
あの清冬様が、本当に?
「それに顔が大層イイだろ? 断り続けるなんて無理な話さね」
「もう。結局、絆されただけじゃないですか」
「ふふ、そう怒るな。堪忍しておくれ、末春」
「うぅ……」
末春という名前ではなく、別の名前で生きて行こうと思っていた。だけど……
――今日からお前の名は末春(みはる)だ
干扇様から頂いた名前を簡単に捨てることは出来ず、かといって春ノ助に戻ることも出来ず。現在も私は「末春」として生きている。
「そいで、お客さんは?」
「寝たので部屋に置いてきました」
「まったく鬼のような子だね、お前は」
ふふ、と綺麗な笑みを向けた花魁姉さんは、禿と一緒にいなくなった。「鬼のような子」なんて……失礼きわまりない。私がしてきたことよりも、清冬様の行いの方がよほど「鬼」だろうに。
「……あ、お風呂は朝にならないと入れないし。今日一日、ずっと化粧したままの顔でいるのはツライよ」
全ては清冬様が会いに来たせいで――と小言を呟き、部屋の前から通り過ぎる。そんな私の声を、声を潜めて聞く者が一名いた。
「……はっ」
もちろん清冬様だ。
「あの女、俺が寝ていると分かったら、サッサと出て行きやがった」
ジワジワ広げた扇子を、パシンと勢いよく畳む。その仕草には怒りが隠れている……かに思われたが。
「何も思ってないような顔をして、俺のことを褒めたな。まったく変な女だ」
――カッコイイのに、変な人
「ふっ。この打掛、また返しに来ないとな」
毒々しい笑みではなく、穏やかな笑顔を見せる清冬様。その顔を見ていたのは誰でもなく、私が残した打掛だけだった。