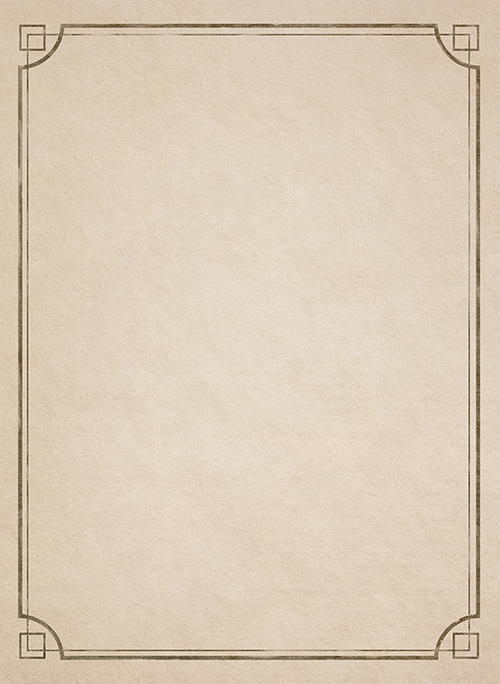僕の口からは、申し訳ございませんでしたの一言も出てこなかった。代わりに出てきたのは、瞳からこぼれ落ちそうな涙の粒だけだった。
泣いているところを見られたくないと思いながら頭を上げると、隣から状況に反した愉快な声が聞こえた。
「私、クレーム対応したのなんて初めて。あれで良かったのかな」
ふと見れば、石川梨沙が楽しそうに笑っていた。ウォータースライダーを滑ってきた後みたいな表情だった。
僕は消え入るような声で礼を言った。男性客に謝罪をし損なった分溜め込まれた力がその声に動員された。僕に残された力の結晶のようなものだ。
だがそれでも、蚊の鳴くような声だというのは自分でも理解できた。情けなくて、笑われても不思議はない声だと思った。
だが石川梨沙は、僕に優しく微笑みかけた。そして言った。
「しばらく、レジから離れて仕事をしましょう。店長に文句を言われない範囲で、楽な仕事を任せるわ」
彼女は僕を、店の裏方に回した。接客はせずに、物流業者から回ってきた商品の整理をするよう指示を出した。
やがて銀行から戻ってきた店長には、特に何も言われなかった。その後タイムカードを切るまで、僕はほとんどお客さんと同じ空間に立つことはなかった。
この出来事を境にして、石川梨沙は僕のことを守ったり、庇ったりし始めた。
僕のミスを自分のしたことだと言った。何かしらの事情で業務に乗り気でない時は、負担にならないような仕事を僕に任せてくれた。
彼女のおかげで僕は、釣り銭を間違えたあの一件以来、大した失敗もせずアルバイトを続けられた。彼女の助力によって、結果として高校を卒業するまで継続できたのだ。更に言うなら、時間の経過と共に、店長からも信頼を得るようにもなった。
全ては、石川梨沙のおかげだった。彼女がほぼ毎回のように同じシフトに入ってくれているおかげで、僕は安心して仕事に臨めたのだ。
だからといって、問題を全て彼女の責任にしたり、手を抜いたりはしなかった。僕は僕で、真剣に働いた。自分の力で過ちを繰り返すまいとしていたのだ。
それに、シフトが被らない日はある。曜日が被っていたとしても、時間帯が噛み合わないことだってある。そういう時に頼れるのが己の実力だけであることくらい、当時の僕でも十分わかっていた。
僕は僕なりに、必死に働いたのだ。そのおかげか、二年生になる頃には、一人だけでも十分にやっていけるだけの戦力として成長していた。石川梨沙の助けは、あまり必要とはしなくなっていた。
さらに時が経ち、彼女は僕より一年早く高校を卒業したのだが、コンビニのアルバイトは辞めなかった。店長から聞いた話では、進学も就職もしなかったらしい。僕は首を捻らないわけにはいかなかった。
泣いているところを見られたくないと思いながら頭を上げると、隣から状況に反した愉快な声が聞こえた。
「私、クレーム対応したのなんて初めて。あれで良かったのかな」
ふと見れば、石川梨沙が楽しそうに笑っていた。ウォータースライダーを滑ってきた後みたいな表情だった。
僕は消え入るような声で礼を言った。男性客に謝罪をし損なった分溜め込まれた力がその声に動員された。僕に残された力の結晶のようなものだ。
だがそれでも、蚊の鳴くような声だというのは自分でも理解できた。情けなくて、笑われても不思議はない声だと思った。
だが石川梨沙は、僕に優しく微笑みかけた。そして言った。
「しばらく、レジから離れて仕事をしましょう。店長に文句を言われない範囲で、楽な仕事を任せるわ」
彼女は僕を、店の裏方に回した。接客はせずに、物流業者から回ってきた商品の整理をするよう指示を出した。
やがて銀行から戻ってきた店長には、特に何も言われなかった。その後タイムカードを切るまで、僕はほとんどお客さんと同じ空間に立つことはなかった。
この出来事を境にして、石川梨沙は僕のことを守ったり、庇ったりし始めた。
僕のミスを自分のしたことだと言った。何かしらの事情で業務に乗り気でない時は、負担にならないような仕事を僕に任せてくれた。
彼女のおかげで僕は、釣り銭を間違えたあの一件以来、大した失敗もせずアルバイトを続けられた。彼女の助力によって、結果として高校を卒業するまで継続できたのだ。更に言うなら、時間の経過と共に、店長からも信頼を得るようにもなった。
全ては、石川梨沙のおかげだった。彼女がほぼ毎回のように同じシフトに入ってくれているおかげで、僕は安心して仕事に臨めたのだ。
だからといって、問題を全て彼女の責任にしたり、手を抜いたりはしなかった。僕は僕で、真剣に働いた。自分の力で過ちを繰り返すまいとしていたのだ。
それに、シフトが被らない日はある。曜日が被っていたとしても、時間帯が噛み合わないことだってある。そういう時に頼れるのが己の実力だけであることくらい、当時の僕でも十分わかっていた。
僕は僕なりに、必死に働いたのだ。そのおかげか、二年生になる頃には、一人だけでも十分にやっていけるだけの戦力として成長していた。石川梨沙の助けは、あまり必要とはしなくなっていた。
さらに時が経ち、彼女は僕より一年早く高校を卒業したのだが、コンビニのアルバイトは辞めなかった。店長から聞いた話では、進学も就職もしなかったらしい。僕は首を捻らないわけにはいかなかった。