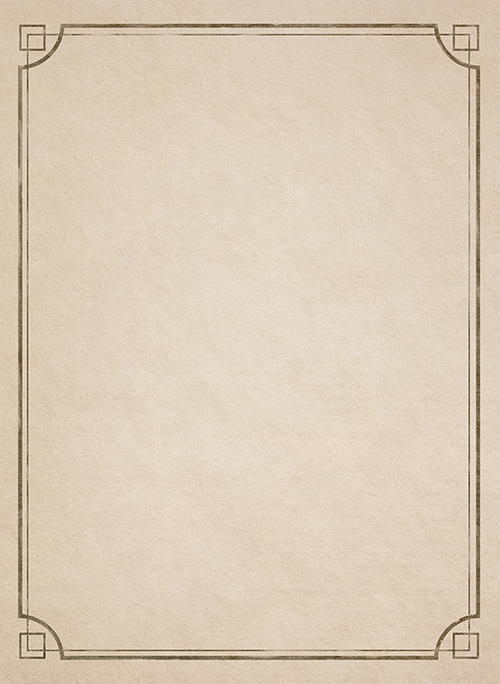か、と。
普段の僕のアルバイトは、こうした一連の不可思議な出来事を終えてから始まるのだが、そんな石川梨沙は、どうも僕のことを気に入っている節があるようだった。
具体的な日付は思い出せないが、まだ初めての給料をもらう前の頃だったはずだ。当時の僕といえば、例の店長の教育のせいで心身ともに疲労困憊といった様子だった。有り体に言えば、死んだ顔をして働いていた。
場所を移動する時には、この世を彷徨っている落武者みたいな格好で足を引きずって歩いた。
集中力などとうになくなり、どうしてこんな大変なことを自ら望んだのだろうかと後悔すらしていた。
限界に近い体力と精神状態だったので、ある時精算をした際のお釣りの金額を間違えてお客さんに渡してしまった。
本来なら一〇〇円であるはずのところを、五〇円玉一枚を渡した。僕もお客さんもそのことに気づかず、事態が発覚したのは三〇分ほどが経過した頃だった。
まだ購入して日が浅いだろうスーツを着た、若い男性が入ってきた。「さっきもこの顔を見たな」などとぼんやり考えている僕に、男性客が歩み寄ってきた。
表情からすぐに、すっかり忘れていた電気代の支払いをしに戻ってきたわけでも、タバコを購入するために再度入店したわけでもないというのが理解できた。
こみ上げる怒りを押し殺しているといった表情で、男性客は一言だけ僕に言った。
「お釣り、足りませんよ」
まだどうにか正気を保ち続けていた僕に、とどめを刺すような一言だった。全身の血の気が引いていくという感触を体験をしたのは、あれが初めてだった。
それまでも何度か注意を受けてきた僕だが、金銭でのミスをするのは前例のないこと。頭が真っ白になるという経験をしたのも、あの時が最初だ。
電池の切れかかったおもちゃみたいに口を開いたり閉じたりして、でも声は出せないでいる僕に、石川梨沙が助け舟を出してくれた。
「お客様、大変申し訳ありません。最近アルバイトとして採用された子でして、教育が足りていませんでした。不足分はすぐにお渡しいたします。ご不便をおかけしまして、誠に申し訳ございませんでした」
彼女は頭を下げてからレシートを男性客から受け取り、そこに記されていた金額を確認してから足りていなかった五〇円を手渡した。平身低頭の、謝罪の言葉と対応だった。まだ怒りがおさまっていないと言った様子で店から出ていく男性客の背中に向かって、彼女はもう一度頭を下げた。僕もそれに倣った。
普段の僕のアルバイトは、こうした一連の不可思議な出来事を終えてから始まるのだが、そんな石川梨沙は、どうも僕のことを気に入っている節があるようだった。
具体的な日付は思い出せないが、まだ初めての給料をもらう前の頃だったはずだ。当時の僕といえば、例の店長の教育のせいで心身ともに疲労困憊といった様子だった。有り体に言えば、死んだ顔をして働いていた。
場所を移動する時には、この世を彷徨っている落武者みたいな格好で足を引きずって歩いた。
集中力などとうになくなり、どうしてこんな大変なことを自ら望んだのだろうかと後悔すらしていた。
限界に近い体力と精神状態だったので、ある時精算をした際のお釣りの金額を間違えてお客さんに渡してしまった。
本来なら一〇〇円であるはずのところを、五〇円玉一枚を渡した。僕もお客さんもそのことに気づかず、事態が発覚したのは三〇分ほどが経過した頃だった。
まだ購入して日が浅いだろうスーツを着た、若い男性が入ってきた。「さっきもこの顔を見たな」などとぼんやり考えている僕に、男性客が歩み寄ってきた。
表情からすぐに、すっかり忘れていた電気代の支払いをしに戻ってきたわけでも、タバコを購入するために再度入店したわけでもないというのが理解できた。
こみ上げる怒りを押し殺しているといった表情で、男性客は一言だけ僕に言った。
「お釣り、足りませんよ」
まだどうにか正気を保ち続けていた僕に、とどめを刺すような一言だった。全身の血の気が引いていくという感触を体験をしたのは、あれが初めてだった。
それまでも何度か注意を受けてきた僕だが、金銭でのミスをするのは前例のないこと。頭が真っ白になるという経験をしたのも、あの時が最初だ。
電池の切れかかったおもちゃみたいに口を開いたり閉じたりして、でも声は出せないでいる僕に、石川梨沙が助け舟を出してくれた。
「お客様、大変申し訳ありません。最近アルバイトとして採用された子でして、教育が足りていませんでした。不足分はすぐにお渡しいたします。ご不便をおかけしまして、誠に申し訳ございませんでした」
彼女は頭を下げてからレシートを男性客から受け取り、そこに記されていた金額を確認してから足りていなかった五〇円を手渡した。平身低頭の、謝罪の言葉と対応だった。まだ怒りがおさまっていないと言った様子で店から出ていく男性客の背中に向かって、彼女はもう一度頭を下げた。僕もそれに倣った。