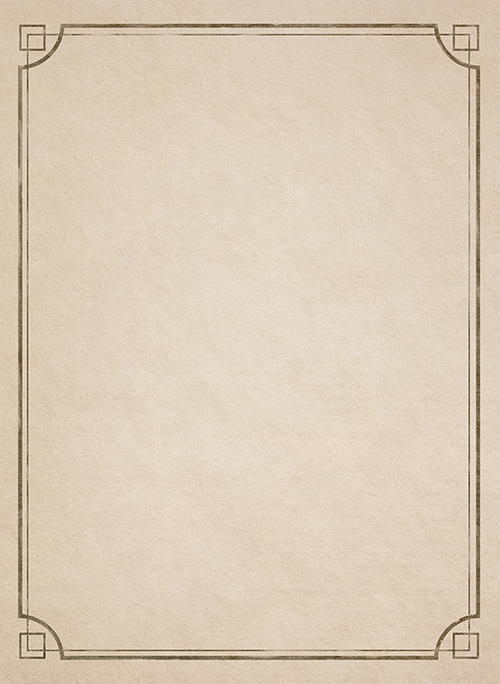としては、そんなふうには思っていませんでしたけど」
そう言いながら、僕は改ためて去年からの己の生活について、詳細に思い出してみた。
去年の三月に、石川梨沙は高校を卒業した。それに合わせて、彼女自身はアルバイトのシフトを変更した。就職も、進学もしなかった。
四月になってからは、あの野球部員がアルバイトとして働き始めた。彼の存在が、僕の自由をある程度抑止する存在となったのは、言うまでもない。僕は結局、野球部員の存在感に怯み、逃げるようにして嘘をでっち上げてシフトを減らし、よりにもよって野球部員にそのことをバラされた。ひとつ下の後輩だが、彼を好きになれるようなエピソードはどこを探してみても無かった。こうして夜勤へ移動するまで、彼と一緒に働くのをよく許容できたものだと我ながら思う。
信頼回復のため、真面目に出勤をしていたあたりまで思い出すと、不意にそこから先の記憶が曖昧になったことに気がついた。霧の中から手繰り寄せていたロープが想定より短かったみたいに、一本の連なりが唐突に断ち切られたのだ。ロープの先端を掴んで、僕は本来あるはずの続きについて思案した。すると前触れなく、昨日参加したばかりの卒業式に行き当たった。それよりも前の出来事を思い出そうとすると、二泊三日の北海道旅行が浮かんだ。更に前へ戻ろうとしたが、果たして旅行より前に僕の生活の中に何かがあっただろうか。
専門学校へオープンキャンパスに行った。高校では、教師たちにあれこれと進路についての話を聞かされた。担任の社会科の先生からは、当時クラスメイトの中で自分だけが受験に失敗したと言う話も聞かされた。それを別にすれば、あの頃、学校について語るに足るものは見当たらない。僕はほとんど、家と学校とここを決まった通りに周回するだけの生活を送っていたのでは無いか。
僕は目の前に座っている石川梨沙の目を見た。彼女の目は「ほら、言った通りでしょ」と僕に語りかけているようだった。これまでの僕の日常を、漏らすことなく全て把握しているとでも言わんばかりだった。
僕はほんの少し、顔をしかめた。言語化の難しい、どこまでも抽象的な不快感が体の内側で持ち上がったようだ。引き金となったのは、言うまでもなく石川梨沙だ。
言い表せない不快感を振り払おうと、僕は半ば無理やりに口を開いた。
「思い返せば、地味な毎日だったと思います。友達と遊ぶ機会も減りましたし。僕の一年は、起伏のない一年だったみたいだ。石川さんは、どうだったんですか? この一年、何か大きなことはありましたか?」
僕に問われて、彼女は腕組みをした。真剣に考え込んでいるようだった。そして彼女の様子を窺う限り、僕とあまり違いはないようだった。
「私も、特に何もないわ。卒業してからすぐに車の免許を取ったの。それ以外だと、特に何もない」
自分に言い聞かせるようにして、彼女は言った。
そう言いながら、僕は改ためて去年からの己の生活について、詳細に思い出してみた。
去年の三月に、石川梨沙は高校を卒業した。それに合わせて、彼女自身はアルバイトのシフトを変更した。就職も、進学もしなかった。
四月になってからは、あの野球部員がアルバイトとして働き始めた。彼の存在が、僕の自由をある程度抑止する存在となったのは、言うまでもない。僕は結局、野球部員の存在感に怯み、逃げるようにして嘘をでっち上げてシフトを減らし、よりにもよって野球部員にそのことをバラされた。ひとつ下の後輩だが、彼を好きになれるようなエピソードはどこを探してみても無かった。こうして夜勤へ移動するまで、彼と一緒に働くのをよく許容できたものだと我ながら思う。
信頼回復のため、真面目に出勤をしていたあたりまで思い出すと、不意にそこから先の記憶が曖昧になったことに気がついた。霧の中から手繰り寄せていたロープが想定より短かったみたいに、一本の連なりが唐突に断ち切られたのだ。ロープの先端を掴んで、僕は本来あるはずの続きについて思案した。すると前触れなく、昨日参加したばかりの卒業式に行き当たった。それよりも前の出来事を思い出そうとすると、二泊三日の北海道旅行が浮かんだ。更に前へ戻ろうとしたが、果たして旅行より前に僕の生活の中に何かがあっただろうか。
専門学校へオープンキャンパスに行った。高校では、教師たちにあれこれと進路についての話を聞かされた。担任の社会科の先生からは、当時クラスメイトの中で自分だけが受験に失敗したと言う話も聞かされた。それを別にすれば、あの頃、学校について語るに足るものは見当たらない。僕はほとんど、家と学校とここを決まった通りに周回するだけの生活を送っていたのでは無いか。
僕は目の前に座っている石川梨沙の目を見た。彼女の目は「ほら、言った通りでしょ」と僕に語りかけているようだった。これまでの僕の日常を、漏らすことなく全て把握しているとでも言わんばかりだった。
僕はほんの少し、顔をしかめた。言語化の難しい、どこまでも抽象的な不快感が体の内側で持ち上がったようだ。引き金となったのは、言うまでもなく石川梨沙だ。
言い表せない不快感を振り払おうと、僕は半ば無理やりに口を開いた。
「思い返せば、地味な毎日だったと思います。友達と遊ぶ機会も減りましたし。僕の一年は、起伏のない一年だったみたいだ。石川さんは、どうだったんですか? この一年、何か大きなことはありましたか?」
僕に問われて、彼女は腕組みをした。真剣に考え込んでいるようだった。そして彼女の様子を窺う限り、僕とあまり違いはないようだった。
「私も、特に何もないわ。卒業してからすぐに車の免許を取ったの。それ以外だと、特に何もない」
自分に言い聞かせるようにして、彼女は言った。