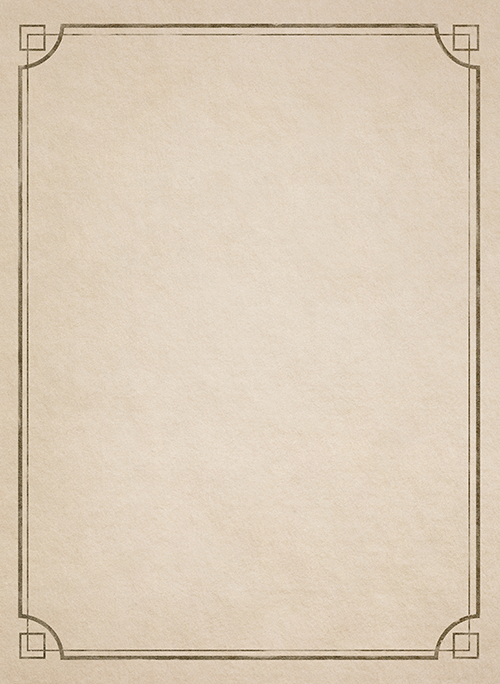●五月十二日(日曜)
忍は別の依頼人から「夫が会社仲間とのゴルフと称して職場の女性と会っているかもしれない」と先日相談を受け、その不倫調査で留守にしていた。
柊が一人店番をしていると外から例の甲高い音が響いて、柊も慌てて身構える。予想通りの女性が事務所に入ると、柊が先制攻撃を仕掛ける。
「あっあっ蒼樹さん! なんですか! 所長は今日」
「不倫調査なんでしょ。知ってる」
「……………………」
「ンな怖い顔で睨まないでよ。コンビニの前で会っただけだって、偶然。それよりほら、来客をおもてなししてよ、コンシェルジュさん」
蒼樹は「お土産もあるから」と、他県へ行った時に購入したご当地スイーツである栗のタルトを献上した。
柊が二人分のコーヒーを運び、柊は蒼樹の向かいに腰掛ける。蒼樹は足を組んで座っていた。
「柊ちゃん、彼に八つ当たりされたんだって?」
柊は突然フランクに下の名前でちゃん付けされて面食らったが、蒼樹が金曜夜の一件を知っていることに遅れて動揺した。
「道端でハスキー犬がションボリしてたから」
「所長、蒼樹さんにはなんでも話すんですね」
「いや、かなり無理強いして吐かせただけだから。最初本人も抵抗してたし。……まだ気にしてるの?」
「いえ、そもそも私が所長の指示を聞かなくて怒られただけなので。そのあと所長も私に気を遣って、外食に誘ってくださいましたし。お互い水に流して終わりましたよ」
「向こうはまだ気にしてるんじゃないかってクンクン鳴いてたわよ。『やけに優しいからまだ怯えてるんじゃないか』って」
「そんな風に見えたんでしょうか。いつものように過ごしていたつもりだったんですけど」
柊の顔が曇るので蒼樹も困り、一度タルトとコーヒーを口にした。
「昨日の調査って多分例の素行調査よね。赫碧症の」
柊がコクリと頷くと、蒼樹も納得したかのような顔をする。
「依頼人の方と恋人の男性を引き合わせて、所長が鞄を盗もうとする暴漢役で男性にわざと襲われたんですけど、依頼人の方、走って逃げてしまわれました」
そっか、と蒼樹は相づちを打つ。そのまま黙って柊の言葉を待った。
「所長もそれを気に病んでるんじゃないかと思って。
所長のやり方は間違っていたんでしょうか」
蒼樹がしばらく考え込んだので、しばし事務所に沈黙が流れる。彼女は組んだ足を元に戻してソファに深く腰掛けた。
「急にらしくないことやろうとして。適当に通り魔しときゃ良かったのに」
「最初は赫碧症かどうかの調査だけだったのに、素行調査まで依頼されたので。依頼人の方を守ろうとする姿を見たら、もしかしたら考え直してくれるかもって、そう思ったんでしょうね」
「登場人物全員幸せにならない結末になっちゃったのね。それも凹んでた理由か」
蒼樹は腕を頭の後ろで組んで「はあ~、甘いなあ伊泉寺くんは」とため息をつきながら天井を眺めた。話題に困った蒼樹が色々考えた末、あることを聞かせてやろうと閃く。
「そうだ。わたしと伊泉寺くんが知り合うきっかけになった人、有島さんのことを話してあげようか。どうせ伊泉寺くん、ロクに教えてないんでしょ」
確かに教えてもらっていなかったが、写真でしか知らない、柊とは面識もない女性なのだ。
忍が言おうとしないのも無理はないと思って、今まで彼女は自分から進んで話題にしようとは思わなかった。
「まあ、私も無理に聞こうとはしなかったので」
「あれ? あんま興味ない感じ?」
「あ、いえ。そうではないんですけど……。
有島さんのことを知るということは、昔の所長のことを知るということで、なんとなく所長が昔苦労されたんだなと窺い知ることができるだけに聞きづらいというか。
知りたくなかったんです」
蒼樹は「そっか」と一息つくと、
「じゃあ伊泉寺くんとは関係ない、わたしと有島さんの話にしよう」
と、提案するのだった。
「そう言えば、所長も蒼樹さんも有島さんつながりでしたね。でも有島さんが出て行かれるまで面識はなかったんですね」
「そうね。有島さんとは十五の頃出会ったの。当時わたしはクスリやってた非行少女で――」
予想もしていなかった告白に思わず柊も「え⁉︎」と口を挟んでしまった。流石に唐突すぎたかと指でぽりぽりと頬を掻く蒼樹だったが、構わず続ける。
「最初はね。きっかけは痩せるって言われて試してみたらみるみるうちに痩せちゃって、快楽にも目覚めてすっかり虜になっちゃったの。まあ胸まで萎んだのは痛かったけど。やってなかったら今もうちょっと巨乳だったのに」
蒼樹は自分の胸を不満げに見つめた。確かに大きいと呼べるサイズではないものの極端に小さいというわけでもなく、見る人が見れば彼女の美しいスタイルに釣り合う絶妙なサイズのように映るだろう。
「で、クスリ繋がりで徒党を組んで悪さやってるうちにいつのまにかヤクザと関わり合いになって、ちょっとしたアルバイトの見返りにクスリをタダでもらってたの。それまで必死にお金巻き上げてまで買ってたから、わたし向きのバイトの上にクスリもタダで手に入れてラッキー、って。
そこに有島さんが現れてキャットファイトした結果、わたしは有島さんの言うこと聞いてクスリからもヤクザからも手を引いてこうして社会復帰に成功したわけです」
「結構簡単にまとめましたが、ずっと乱用してたんですよね。禁断症状はどうだったんですか」
「そりゃ毎日地獄よ地獄。色んな施設梯子したし、精神も不安定になってまたクスリに手を出したくなると必ず降って湧いたように有島さんが様子見に来るの。本当敵わないったらありゃしない」
「以前主に薬物犯罪について追っているとお伺いしましたが、その時の体験が理由で?」
「まあそれもあるけど。将来経験者としてクスリが如何にヤバいかを世間に警鐘しとけよってシメられた。
それにほら、赫碧症の人がクスリやると、アレでしょ」
そう、確かに違法な薬物の摂取で赫眼するというのは一般常識だった。
「赫碧症の人はタダでさえ社会に溢れやすい上に、クスリで身体強化してヤクザの鉄砲玉に担ぎ上げられて、それでまたクスリ欲しくなってヤクザの言うこと聞いて……って悪循環なの。
それを止めるのがわたしの罪滅ぼしだって言われた」
蒼樹は感慨深げに忍のデスクを見つめる、忍ではなく、そこで座って働いていたであろう有島の姿を見たのだ。
今度は柊が話題を振る番で、前々から聞きたかったことを蒼樹に尋ねた。
「蒼樹さんは所長と二人でお仕事されてたんですよね、三ヶ月くらい」
「三ヶ月? …………あっ」
蒼樹は心の中で忍に謝罪した。今の反応で忍にウソをつかれたことに気づいた柊が冷めた目で蒼樹を見ている。
「本当はどのくらいなので?」
「半年くらい」
「ははあ……それは確かに一瞬ですねぇ…………」
蒼樹は最初こそ忍に申し訳なく思ったものの、彼が事務所に帰ってきたあとのことを想像するだけで爆笑しそうになったので特にフォローはしなかった。
「で。で、蒼樹さんもここでお手伝いをしてたんですよね。当時は大変でしたか?」
「大変なんてレベルじゃない。
雑務はもちろん、電話対応、来客対応、調査でカップルのフリする必要があるからってこっちの都合もお構いなく引っ張り出されたし。
今日中に作らないといけない書類あるのいつも忘れるからその度に教えてあげて、そういう日は家にも帰れず付き合わされて。
確定申告の時は最悪だった。素直に税理士に頼めば良いものを『自分でやる』って言い張った挙句に『あの領収書がない、書類がない』ってギリギリになって大騒ぎし始めて事務所中ひっくり返りそうになるくらい漁るに漁ってその時期はほとんど泊まり込み……
……わたしもあんま甘やかさずにたまには突っぱねるんだった」
「ほほっっ、ほっ、ほ、ほおう……?」
柊はもはや怒りを通り越して笑うしかなかった。蒼樹は蒼樹で「やべーおもしれー」と対岸の火事で、忍の行く末などお構いなしである。
「色々お手伝いを経験されたみたいで…………当然夜のお手伝いもしたことでしょうねえ………………」
「だから怖いって。そういう手伝いはしたことないって真面目に」
「所長も蒼樹さんも口裏合わせてウソつくんですから。信用なりません」
柊がぷいと拗ねるので流石の蒼樹も見かねて「ちょっと」と声をかけた。
「その点は彼本当に紳士だからね? 泊らせてもらった夜はいつも一階のソファ使って寝るし、誘ってみたこともあるけど固辞するし。一応本人の名誉の為に言っておいてあげるけど」
「証拠は?」
「悪魔の証明やめてくれる?」
「これはですね? 偶然! 偶然見つけたんですけど‼
物置部屋を掃除してたらいかがわしいグッズ……なんかこう、目隠し、しかもなんかいかにもプレイ用って感じなデザインのやつを見つけたんですけど、二人でこれを使って楽しんでたんじゃないんですか‼」
「じゃあ別の女と楽しむ時に使ったんじゃない」
「ウソつかないでくださーーい! だって所長、だって……」
「まあ億が一に調査のために必要になった説も捨てきれないよ?
探偵だし、潜入調査とかで色々買いそろえてるって言ってたし。
なんかその手の店に潜入するために必要になったんじゃない?」
「いや、そうは言っても………………潜入調査? その手の店に?」
夕方過ぎ。調査を終えた忍が柊へのご機嫌取りにケーキを買ってきたものの、事務所に戻るやいなやプレイ用目隠しを突きつけられると同時に、蒼樹の話で判明したあれやこれやの説明を求められた。ケーキはおろか夕飯どころではなく、事情聴取は深夜まで及んだという。
明け方になって、忍から蒼樹に抗議の電話が届いたのは言うまでもない。
忍は別の依頼人から「夫が会社仲間とのゴルフと称して職場の女性と会っているかもしれない」と先日相談を受け、その不倫調査で留守にしていた。
柊が一人店番をしていると外から例の甲高い音が響いて、柊も慌てて身構える。予想通りの女性が事務所に入ると、柊が先制攻撃を仕掛ける。
「あっあっ蒼樹さん! なんですか! 所長は今日」
「不倫調査なんでしょ。知ってる」
「……………………」
「ンな怖い顔で睨まないでよ。コンビニの前で会っただけだって、偶然。それよりほら、来客をおもてなししてよ、コンシェルジュさん」
蒼樹は「お土産もあるから」と、他県へ行った時に購入したご当地スイーツである栗のタルトを献上した。
柊が二人分のコーヒーを運び、柊は蒼樹の向かいに腰掛ける。蒼樹は足を組んで座っていた。
「柊ちゃん、彼に八つ当たりされたんだって?」
柊は突然フランクに下の名前でちゃん付けされて面食らったが、蒼樹が金曜夜の一件を知っていることに遅れて動揺した。
「道端でハスキー犬がションボリしてたから」
「所長、蒼樹さんにはなんでも話すんですね」
「いや、かなり無理強いして吐かせただけだから。最初本人も抵抗してたし。……まだ気にしてるの?」
「いえ、そもそも私が所長の指示を聞かなくて怒られただけなので。そのあと所長も私に気を遣って、外食に誘ってくださいましたし。お互い水に流して終わりましたよ」
「向こうはまだ気にしてるんじゃないかってクンクン鳴いてたわよ。『やけに優しいからまだ怯えてるんじゃないか』って」
「そんな風に見えたんでしょうか。いつものように過ごしていたつもりだったんですけど」
柊の顔が曇るので蒼樹も困り、一度タルトとコーヒーを口にした。
「昨日の調査って多分例の素行調査よね。赫碧症の」
柊がコクリと頷くと、蒼樹も納得したかのような顔をする。
「依頼人の方と恋人の男性を引き合わせて、所長が鞄を盗もうとする暴漢役で男性にわざと襲われたんですけど、依頼人の方、走って逃げてしまわれました」
そっか、と蒼樹は相づちを打つ。そのまま黙って柊の言葉を待った。
「所長もそれを気に病んでるんじゃないかと思って。
所長のやり方は間違っていたんでしょうか」
蒼樹がしばらく考え込んだので、しばし事務所に沈黙が流れる。彼女は組んだ足を元に戻してソファに深く腰掛けた。
「急にらしくないことやろうとして。適当に通り魔しときゃ良かったのに」
「最初は赫碧症かどうかの調査だけだったのに、素行調査まで依頼されたので。依頼人の方を守ろうとする姿を見たら、もしかしたら考え直してくれるかもって、そう思ったんでしょうね」
「登場人物全員幸せにならない結末になっちゃったのね。それも凹んでた理由か」
蒼樹は腕を頭の後ろで組んで「はあ~、甘いなあ伊泉寺くんは」とため息をつきながら天井を眺めた。話題に困った蒼樹が色々考えた末、あることを聞かせてやろうと閃く。
「そうだ。わたしと伊泉寺くんが知り合うきっかけになった人、有島さんのことを話してあげようか。どうせ伊泉寺くん、ロクに教えてないんでしょ」
確かに教えてもらっていなかったが、写真でしか知らない、柊とは面識もない女性なのだ。
忍が言おうとしないのも無理はないと思って、今まで彼女は自分から進んで話題にしようとは思わなかった。
「まあ、私も無理に聞こうとはしなかったので」
「あれ? あんま興味ない感じ?」
「あ、いえ。そうではないんですけど……。
有島さんのことを知るということは、昔の所長のことを知るということで、なんとなく所長が昔苦労されたんだなと窺い知ることができるだけに聞きづらいというか。
知りたくなかったんです」
蒼樹は「そっか」と一息つくと、
「じゃあ伊泉寺くんとは関係ない、わたしと有島さんの話にしよう」
と、提案するのだった。
「そう言えば、所長も蒼樹さんも有島さんつながりでしたね。でも有島さんが出て行かれるまで面識はなかったんですね」
「そうね。有島さんとは十五の頃出会ったの。当時わたしはクスリやってた非行少女で――」
予想もしていなかった告白に思わず柊も「え⁉︎」と口を挟んでしまった。流石に唐突すぎたかと指でぽりぽりと頬を掻く蒼樹だったが、構わず続ける。
「最初はね。きっかけは痩せるって言われて試してみたらみるみるうちに痩せちゃって、快楽にも目覚めてすっかり虜になっちゃったの。まあ胸まで萎んだのは痛かったけど。やってなかったら今もうちょっと巨乳だったのに」
蒼樹は自分の胸を不満げに見つめた。確かに大きいと呼べるサイズではないものの極端に小さいというわけでもなく、見る人が見れば彼女の美しいスタイルに釣り合う絶妙なサイズのように映るだろう。
「で、クスリ繋がりで徒党を組んで悪さやってるうちにいつのまにかヤクザと関わり合いになって、ちょっとしたアルバイトの見返りにクスリをタダでもらってたの。それまで必死にお金巻き上げてまで買ってたから、わたし向きのバイトの上にクスリもタダで手に入れてラッキー、って。
そこに有島さんが現れてキャットファイトした結果、わたしは有島さんの言うこと聞いてクスリからもヤクザからも手を引いてこうして社会復帰に成功したわけです」
「結構簡単にまとめましたが、ずっと乱用してたんですよね。禁断症状はどうだったんですか」
「そりゃ毎日地獄よ地獄。色んな施設梯子したし、精神も不安定になってまたクスリに手を出したくなると必ず降って湧いたように有島さんが様子見に来るの。本当敵わないったらありゃしない」
「以前主に薬物犯罪について追っているとお伺いしましたが、その時の体験が理由で?」
「まあそれもあるけど。将来経験者としてクスリが如何にヤバいかを世間に警鐘しとけよってシメられた。
それにほら、赫碧症の人がクスリやると、アレでしょ」
そう、確かに違法な薬物の摂取で赫眼するというのは一般常識だった。
「赫碧症の人はタダでさえ社会に溢れやすい上に、クスリで身体強化してヤクザの鉄砲玉に担ぎ上げられて、それでまたクスリ欲しくなってヤクザの言うこと聞いて……って悪循環なの。
それを止めるのがわたしの罪滅ぼしだって言われた」
蒼樹は感慨深げに忍のデスクを見つめる、忍ではなく、そこで座って働いていたであろう有島の姿を見たのだ。
今度は柊が話題を振る番で、前々から聞きたかったことを蒼樹に尋ねた。
「蒼樹さんは所長と二人でお仕事されてたんですよね、三ヶ月くらい」
「三ヶ月? …………あっ」
蒼樹は心の中で忍に謝罪した。今の反応で忍にウソをつかれたことに気づいた柊が冷めた目で蒼樹を見ている。
「本当はどのくらいなので?」
「半年くらい」
「ははあ……それは確かに一瞬ですねぇ…………」
蒼樹は最初こそ忍に申し訳なく思ったものの、彼が事務所に帰ってきたあとのことを想像するだけで爆笑しそうになったので特にフォローはしなかった。
「で。で、蒼樹さんもここでお手伝いをしてたんですよね。当時は大変でしたか?」
「大変なんてレベルじゃない。
雑務はもちろん、電話対応、来客対応、調査でカップルのフリする必要があるからってこっちの都合もお構いなく引っ張り出されたし。
今日中に作らないといけない書類あるのいつも忘れるからその度に教えてあげて、そういう日は家にも帰れず付き合わされて。
確定申告の時は最悪だった。素直に税理士に頼めば良いものを『自分でやる』って言い張った挙句に『あの領収書がない、書類がない』ってギリギリになって大騒ぎし始めて事務所中ひっくり返りそうになるくらい漁るに漁ってその時期はほとんど泊まり込み……
……わたしもあんま甘やかさずにたまには突っぱねるんだった」
「ほほっっ、ほっ、ほ、ほおう……?」
柊はもはや怒りを通り越して笑うしかなかった。蒼樹は蒼樹で「やべーおもしれー」と対岸の火事で、忍の行く末などお構いなしである。
「色々お手伝いを経験されたみたいで…………当然夜のお手伝いもしたことでしょうねえ………………」
「だから怖いって。そういう手伝いはしたことないって真面目に」
「所長も蒼樹さんも口裏合わせてウソつくんですから。信用なりません」
柊がぷいと拗ねるので流石の蒼樹も見かねて「ちょっと」と声をかけた。
「その点は彼本当に紳士だからね? 泊らせてもらった夜はいつも一階のソファ使って寝るし、誘ってみたこともあるけど固辞するし。一応本人の名誉の為に言っておいてあげるけど」
「証拠は?」
「悪魔の証明やめてくれる?」
「これはですね? 偶然! 偶然見つけたんですけど‼
物置部屋を掃除してたらいかがわしいグッズ……なんかこう、目隠し、しかもなんかいかにもプレイ用って感じなデザインのやつを見つけたんですけど、二人でこれを使って楽しんでたんじゃないんですか‼」
「じゃあ別の女と楽しむ時に使ったんじゃない」
「ウソつかないでくださーーい! だって所長、だって……」
「まあ億が一に調査のために必要になった説も捨てきれないよ?
探偵だし、潜入調査とかで色々買いそろえてるって言ってたし。
なんかその手の店に潜入するために必要になったんじゃない?」
「いや、そうは言っても………………潜入調査? その手の店に?」
夕方過ぎ。調査を終えた忍が柊へのご機嫌取りにケーキを買ってきたものの、事務所に戻るやいなやプレイ用目隠しを突きつけられると同時に、蒼樹の話で判明したあれやこれやの説明を求められた。ケーキはおろか夕飯どころではなく、事情聴取は深夜まで及んだという。
明け方になって、忍から蒼樹に抗議の電話が届いたのは言うまでもない。