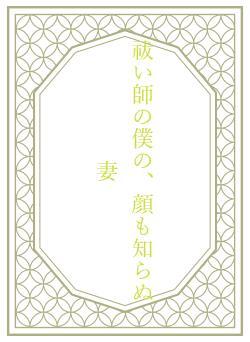「あいつはどうせ戦場で死ぬ。お前はこれまで通りここで使用人として働け」
「でも…」
「私に逆らう気か!」
私が言い募ろうとするのを遮って、父はいつものように怒鳴りつける。
「い、いえ…、そういうわけでは…」
「いいか、お前を名ばかりの貴族に嫁がせたのは、貴族の地位が欲しかったからだ。
あいつには病気の母親がいるんだ。
あいつは母親のための薬を私から手に入れたいがためにお前と結婚した。
その引き換えに、二人亡きあとは貴族の地位を私に譲ると契約書を書かせた。
お前の役目は二人が死ぬまで妻の座に収まることだ。分かったな?」
「…はい」
「分かったら掃除でもしてこい」
「はい、失礼いたします…」
頭を下げて父の書斎を後にする。
倉庫から掃除用具を持ってきて、まずは窓を拭き始めると、指先から冷えてきて冬の始まりを感じる。
これから本格的に寒くなるというのに戦いに行かなければいけないなんてと、顔も知らない夫の身を案じる。