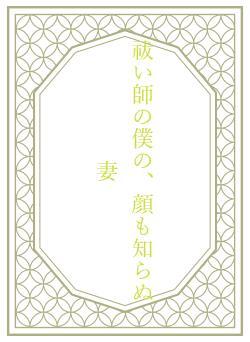「私たちは、本当に同時刻に死んだってこと…?」
「そうだよ。ねぇ、これって運命だと思わない?」
私には縁遠い言葉だが、このチャラ男はそう言ってあちこちで口説いてきたに違いない。
幽霊だという事実を受け入れ始めた頭で考えて、思わずジト目で彼を見てしまう。
それに、死んだ時間が同じだからってどうしてそうゆう考えになるのか理解不能だ。
「そんな目で見ないでよぉ。これは俺より先に逝った先輩幽霊に聞いたんだからぁ」
「…?」
「同じ場所の同じ時間で死んだ人は、来世で結ばれるって話」
「はぁ…?」
幽霊であることよりも信じがたくて、これこそ冗談だろうと彼を睨む。
と言っても、頬に熱が集まるのを感じているので睨む力は弱々しいかもしれない。
(そもそも幽霊に熱なんてあるのか)
自分で自分にツッコミを入れるが、それは置いておいて。