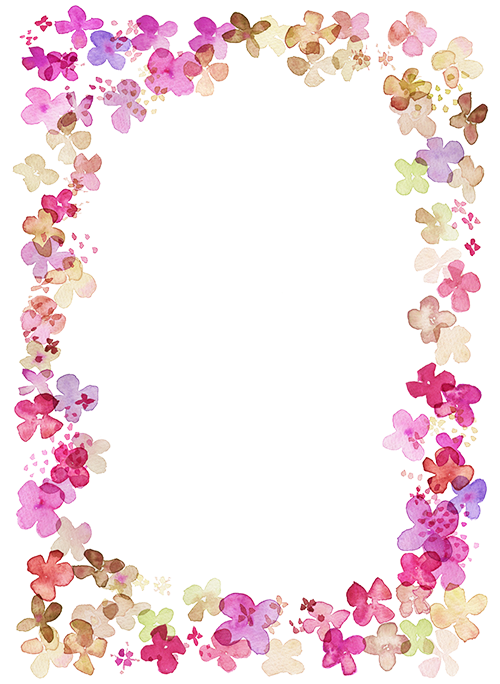春になって、私は英国へデニスのお墓参りに行くことに決めた。
飛行機は西に飛び続けて、私は沈まない太陽を見ていた。
私は薄暗い機内の窓の隙間から、微かにこぼれる光を覗き見て目を細める。
周りを見渡すと、乗客は皆目を閉じてぐったりしている。それにならって、私も硬い座席に背中を預けた。
目だけを窓の外にやると、やはりそこには消えることのない光の筋。
まだ着かない。沈まない太陽を見ていられる。
降りるために乗っているのに、降りないことをどこかで望んでいる自分は少しおかしい。
このまま永遠にデニスの死を信じないことも考えた。でも両親とリチャードに勧められて、私は英国へ旅に出る。
私はふと胸に手を当てて、そこに入っているものを思う。
お守りのように首に下げたパスポートケースに、デニスからの手紙が入っている。
……デニスが亡くなる数日前に書いて、亡くなってから私へ届いた手紙。
私は目を閉じてひとときの眠りに入っていく。
そこで、私は夢を見ていた。
そこに立ったとき、それは現実ではないとわかっていたけど、うれしかった。
懐かしい声で、彼は私に言う。
「久しぶりだね、智子」
目を開けたら、闇の中にデニスが立っていたから。
小柄で痩せた体躯で、だけどいつも通りしゃんと背を伸ばして彼はいた。作りものめいているほど整った顔立ちで、涼やかな灰緑の目で私を見ていた。
デニスは私の前に立って言う。
「元気でやっているかな。ちゃんと勉強している?」
夢でもいいからもう一度会いたいとずっと願っていた。ずっとみつめていたいと思う私に、デニスは言葉を続けた。
「今日は君が英国に来た時のために、少し紹介をしておこうと思ってね」
デニスの最後の手紙は、そうやって始まった。暗記できるほど繰り返し読んだから、ついに夢に出てきたのだろう。
デニスは少し顔を上げる。暗闇の中、無数の額縁が浮かび上がる。
次の瞬間、デニスは額縁の中の光景の一部になっていた。
「英国に来たら、まずコッツウォルズに行くといい。古き良き田舎が君を迎えてくれる」
霧雨の中にはちみつ色の壁の家々が立ち並ぶ。小川のほとりを、デニスはゆっくりと歩いていく。
「その近くに、オックスフォード。重厚な歴史のつまった石畳と聖堂、そして図書館がある」
額縁の中をデニスは渡る。灰色の荘厳な大学街を、目を閉じながら進む。
「ロンドンに来たら、博物館や美術館を見ておこう。大英博物館には世界中から集められた展示品が、ナショナルギャラリーには美の結集である無数の絵画が収められている」
迷宮のようなミュージアムが、額縁の中に浮かび上がっては移り変わる。
「ロンドン塔やセント・ポール大聖堂もぜひ足を運んでほしい。栄光のすぐ隣に影が見えるだろう」
宝石博物館の隣に血ぬられた監獄があるロンドン塔、炎の中に立ち竦むセント・ポール大聖堂が見えた。
「ウェストミンスターの鐘の音も、聞いてみてくれ。君はびっくりするかもしれないね」
澄んだ軽やかな鐘の音が、どこからか響いて来た。
「そして遺跡、ストーンヘンジ。僕が英国で一番好きな場所だ」
曇り空の下、永遠の緑のじゅうたんの上に立ち続ける石群を背景に、デニスは振り返る。
「でもこれらは英国のほんの一部でしかない。今更のような、ありふれた観光案内をしてしまったな」
デニスは額縁をくぐりぬけて降りてくる。
「君が見て、感じ取るものは、僕が紹介したものとはまるで違うかもしれない。君は失望するかもしれないし、もっと新鮮なものを感じるのかもしれない」
デニスは少しだけ気に入らなさそうに言う。
「僕はロンドンが好きじゃないが、今の英国の中心は間違いなくロンドンだ。それも一言付け加えておく」
英国の光景が絵画のように額縁に入って、私たちの周りを取り囲んでいた。
「いい旅になることを、心から祈る……」
デニスは宙に浮かぶ無数の光景を見回して、そして私に目を戻す。
「本当はここで手紙を終えるつもりだったが、最後まで逃げていてはいけない。やはり伝えなければいけないな」
真っ直ぐ私の方まで歩いて来て、デニスは半歩先で立ち止まる。
「この手紙が届く時には、僕はもういないと思う。僕が死んで少し落ち着いた頃に君へ送ってほしいと、家族に頼んであるから」
手を伸ばせば届くところにデニスはいる。けれど手を伸ばした瞬間に消えてしまうことも、私はわかっている。
「二つ、君に伝えたいことがある」
デニスは一度目を伏せてから話し始める。
「一つ目。僕は去って行く人間だから、君の時間を奪いたくない……と思っていたのだが、僕の中のずるい部分が反抗する。君に忘れられたくないと思ってしまう」
哀しいような調子で、デニスは告げる。
「だから、一度英国を訪れるまでは僕のことを覚えていてほしい。その後は、何もかも忘れてしまって構わない」
そんなことはできないよ、デニス。君のことは絶対に一生忘れない。
君がどこへ失せたって、それは変わらないんだ。
「もう一つは……」
そこでデニスは初めて困った様子を見せた。
「君はよく、僕のことがわからないと言っていたね」
表情の変わらないデニスには珍しく、目や口の端、頬、あちこちに困惑が現れた。
「わからなくて当然なんだよ。僕は君に近付くことをやめてしまったから」
完璧なほど整った表情を崩して、情けないような目をする。
「コミュニケーションは互いに近付いてようやく成立する。片方がどんなに近付いても、もう片方が逃げては通じない。君が僕のことを理解できなかったのは、僕のせいだ。すまない」
ため息をついて、デニスはついと目を上げる。
「でも君の考えていることは、僕に伝わっていたよ。君は一生懸命近付いてきてくれたから」
そっと微笑んでデニスは言う。
「君が僕のことを大切に思っていてくれたことも知っている。嬉しかった」
ううん。君が穏やかに私を見守ってくれていたことは、私も感じていたよ。
全部がわからなくても、それだけは何となく気づいていたんだ。
「君は誠実で、真面目な人だった。そして小さな反応でも感じ取る素直な心を持ってる」
デニスは私をみつめて告げる。
「……だからその素直な心を抱いて、これから先も生きていって」
瞳を揺らした私が見えているように、デニスは静かに諭す。
「大丈夫。君ならできるよ」
デニスの輪郭がぼやける。私は自分の目をこすったけど、デニスの姿は薄くなっていく。
「日本に来てよかった。君に会えてよかった。僕は幸せだった」
立ち竦んで、私はついデニスに向かって手を伸ばしていた。
「ありがとう。智子」
抱きしめたとき、デニスにはやはり体温を感じなかった。
けれどそっと、頬に手が触れたような感覚がした。一瞬だけ頬の上をデニスの手が動いた。
「君の友達、デニスより」
そうして、デニスは指先から私の中に消えて行った。
飛行機から降りて、私はヒースロー空港の通路を歩いていた。
たぶん私は迷子のような足取りで、到着ロビーに足を踏み入れたのだと思う。
でも次の瞬間、私の目を覚ますように強く抱きしめられた。
「……よく来てくれた」
この国でこんなことをする人を、私は一人しか知らない。
彼は私の背を叩いて、にじんだ声で言った。
「勇気も必要だったろう。よく、ここまで来たね……!」
私はその生きた者が持つ温もりに、ずっと凍り付いていた心がほどけ始める。
私はのろのろと彼の背に腕を回して、問いかけるように言った。
「リチャード、迎えに来て、くれたの……?」
リチャードは私を抱きしめたままうなずいて返す。
「うん。今度は僕が案内する番だ。どこへだって連れて行ってあげる」
ふいにリチャードは体を離して、私をのぞきこみながら言った。
「さあ、智子さん。行こうよ。……デニスが愛した国の隅々まで」
私はその明るい緑の瞳をみつめ返しながら、ゆっくりとうなずいた。
ねえ、リチャード。時間が許す限り、私に英国を見せて。
ここは宝石みたいな時間を抱いた土地だと、デニスに聞いているよ。
それでデニスが眠っているお墓に案内してほしい。
私はそこでデニスに、あの手紙の答えを返すつもりなんだ。
ありがとう、デニス。君のくれた時間は、私を照らしてくれる光だ。
……私はその光に顔を上げて、これからも先も生きていく。
飛行機は西に飛び続けて、私は沈まない太陽を見ていた。
私は薄暗い機内の窓の隙間から、微かにこぼれる光を覗き見て目を細める。
周りを見渡すと、乗客は皆目を閉じてぐったりしている。それにならって、私も硬い座席に背中を預けた。
目だけを窓の外にやると、やはりそこには消えることのない光の筋。
まだ着かない。沈まない太陽を見ていられる。
降りるために乗っているのに、降りないことをどこかで望んでいる自分は少しおかしい。
このまま永遠にデニスの死を信じないことも考えた。でも両親とリチャードに勧められて、私は英国へ旅に出る。
私はふと胸に手を当てて、そこに入っているものを思う。
お守りのように首に下げたパスポートケースに、デニスからの手紙が入っている。
……デニスが亡くなる数日前に書いて、亡くなってから私へ届いた手紙。
私は目を閉じてひとときの眠りに入っていく。
そこで、私は夢を見ていた。
そこに立ったとき、それは現実ではないとわかっていたけど、うれしかった。
懐かしい声で、彼は私に言う。
「久しぶりだね、智子」
目を開けたら、闇の中にデニスが立っていたから。
小柄で痩せた体躯で、だけどいつも通りしゃんと背を伸ばして彼はいた。作りものめいているほど整った顔立ちで、涼やかな灰緑の目で私を見ていた。
デニスは私の前に立って言う。
「元気でやっているかな。ちゃんと勉強している?」
夢でもいいからもう一度会いたいとずっと願っていた。ずっとみつめていたいと思う私に、デニスは言葉を続けた。
「今日は君が英国に来た時のために、少し紹介をしておこうと思ってね」
デニスの最後の手紙は、そうやって始まった。暗記できるほど繰り返し読んだから、ついに夢に出てきたのだろう。
デニスは少し顔を上げる。暗闇の中、無数の額縁が浮かび上がる。
次の瞬間、デニスは額縁の中の光景の一部になっていた。
「英国に来たら、まずコッツウォルズに行くといい。古き良き田舎が君を迎えてくれる」
霧雨の中にはちみつ色の壁の家々が立ち並ぶ。小川のほとりを、デニスはゆっくりと歩いていく。
「その近くに、オックスフォード。重厚な歴史のつまった石畳と聖堂、そして図書館がある」
額縁の中をデニスは渡る。灰色の荘厳な大学街を、目を閉じながら進む。
「ロンドンに来たら、博物館や美術館を見ておこう。大英博物館には世界中から集められた展示品が、ナショナルギャラリーには美の結集である無数の絵画が収められている」
迷宮のようなミュージアムが、額縁の中に浮かび上がっては移り変わる。
「ロンドン塔やセント・ポール大聖堂もぜひ足を運んでほしい。栄光のすぐ隣に影が見えるだろう」
宝石博物館の隣に血ぬられた監獄があるロンドン塔、炎の中に立ち竦むセント・ポール大聖堂が見えた。
「ウェストミンスターの鐘の音も、聞いてみてくれ。君はびっくりするかもしれないね」
澄んだ軽やかな鐘の音が、どこからか響いて来た。
「そして遺跡、ストーンヘンジ。僕が英国で一番好きな場所だ」
曇り空の下、永遠の緑のじゅうたんの上に立ち続ける石群を背景に、デニスは振り返る。
「でもこれらは英国のほんの一部でしかない。今更のような、ありふれた観光案内をしてしまったな」
デニスは額縁をくぐりぬけて降りてくる。
「君が見て、感じ取るものは、僕が紹介したものとはまるで違うかもしれない。君は失望するかもしれないし、もっと新鮮なものを感じるのかもしれない」
デニスは少しだけ気に入らなさそうに言う。
「僕はロンドンが好きじゃないが、今の英国の中心は間違いなくロンドンだ。それも一言付け加えておく」
英国の光景が絵画のように額縁に入って、私たちの周りを取り囲んでいた。
「いい旅になることを、心から祈る……」
デニスは宙に浮かぶ無数の光景を見回して、そして私に目を戻す。
「本当はここで手紙を終えるつもりだったが、最後まで逃げていてはいけない。やはり伝えなければいけないな」
真っ直ぐ私の方まで歩いて来て、デニスは半歩先で立ち止まる。
「この手紙が届く時には、僕はもういないと思う。僕が死んで少し落ち着いた頃に君へ送ってほしいと、家族に頼んであるから」
手を伸ばせば届くところにデニスはいる。けれど手を伸ばした瞬間に消えてしまうことも、私はわかっている。
「二つ、君に伝えたいことがある」
デニスは一度目を伏せてから話し始める。
「一つ目。僕は去って行く人間だから、君の時間を奪いたくない……と思っていたのだが、僕の中のずるい部分が反抗する。君に忘れられたくないと思ってしまう」
哀しいような調子で、デニスは告げる。
「だから、一度英国を訪れるまでは僕のことを覚えていてほしい。その後は、何もかも忘れてしまって構わない」
そんなことはできないよ、デニス。君のことは絶対に一生忘れない。
君がどこへ失せたって、それは変わらないんだ。
「もう一つは……」
そこでデニスは初めて困った様子を見せた。
「君はよく、僕のことがわからないと言っていたね」
表情の変わらないデニスには珍しく、目や口の端、頬、あちこちに困惑が現れた。
「わからなくて当然なんだよ。僕は君に近付くことをやめてしまったから」
完璧なほど整った表情を崩して、情けないような目をする。
「コミュニケーションは互いに近付いてようやく成立する。片方がどんなに近付いても、もう片方が逃げては通じない。君が僕のことを理解できなかったのは、僕のせいだ。すまない」
ため息をついて、デニスはついと目を上げる。
「でも君の考えていることは、僕に伝わっていたよ。君は一生懸命近付いてきてくれたから」
そっと微笑んでデニスは言う。
「君が僕のことを大切に思っていてくれたことも知っている。嬉しかった」
ううん。君が穏やかに私を見守ってくれていたことは、私も感じていたよ。
全部がわからなくても、それだけは何となく気づいていたんだ。
「君は誠実で、真面目な人だった。そして小さな反応でも感じ取る素直な心を持ってる」
デニスは私をみつめて告げる。
「……だからその素直な心を抱いて、これから先も生きていって」
瞳を揺らした私が見えているように、デニスは静かに諭す。
「大丈夫。君ならできるよ」
デニスの輪郭がぼやける。私は自分の目をこすったけど、デニスの姿は薄くなっていく。
「日本に来てよかった。君に会えてよかった。僕は幸せだった」
立ち竦んで、私はついデニスに向かって手を伸ばしていた。
「ありがとう。智子」
抱きしめたとき、デニスにはやはり体温を感じなかった。
けれどそっと、頬に手が触れたような感覚がした。一瞬だけ頬の上をデニスの手が動いた。
「君の友達、デニスより」
そうして、デニスは指先から私の中に消えて行った。
飛行機から降りて、私はヒースロー空港の通路を歩いていた。
たぶん私は迷子のような足取りで、到着ロビーに足を踏み入れたのだと思う。
でも次の瞬間、私の目を覚ますように強く抱きしめられた。
「……よく来てくれた」
この国でこんなことをする人を、私は一人しか知らない。
彼は私の背を叩いて、にじんだ声で言った。
「勇気も必要だったろう。よく、ここまで来たね……!」
私はその生きた者が持つ温もりに、ずっと凍り付いていた心がほどけ始める。
私はのろのろと彼の背に腕を回して、問いかけるように言った。
「リチャード、迎えに来て、くれたの……?」
リチャードは私を抱きしめたままうなずいて返す。
「うん。今度は僕が案内する番だ。どこへだって連れて行ってあげる」
ふいにリチャードは体を離して、私をのぞきこみながら言った。
「さあ、智子さん。行こうよ。……デニスが愛した国の隅々まで」
私はその明るい緑の瞳をみつめ返しながら、ゆっくりとうなずいた。
ねえ、リチャード。時間が許す限り、私に英国を見せて。
ここは宝石みたいな時間を抱いた土地だと、デニスに聞いているよ。
それでデニスが眠っているお墓に案内してほしい。
私はそこでデニスに、あの手紙の答えを返すつもりなんだ。
ありがとう、デニス。君のくれた時間は、私を照らしてくれる光だ。
……私はその光に顔を上げて、これからも先も生きていく。