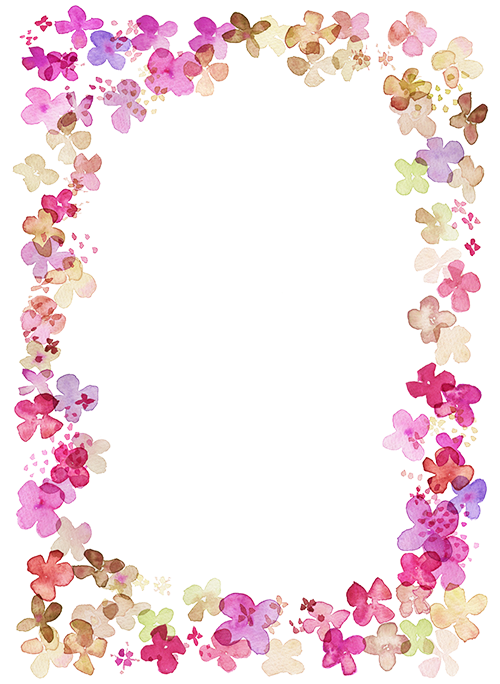十二月のクリスマス間際、デニスは英国に帰ることになった。
一月間のホームステイは、思い返せばあっという間だった。デニスが日本で望んだ滞在ができたのかどうか、私にはわからなかった。
でもデニスはリチャードや私に勧められても、帰国を早めたりはしなかった。結局、与えられた期間の最後までホームステイをして、慎ましやかに両親にお礼を言っていた。
帰りは、空港までデニスを送るのは私の役目だった。私がそうさせてほしいと父に頼んだからだった。
帰国の日は、冬の最中であるのに陽光のうららかな日だった。
私とデニスは言葉少なく電車に揺られて、次で降りるよ、とか、温かい日だね、とか、差しさわりのないことばかり言っていた。
私はきっと、デニスが帰るのをまだ実感していなかった。いつもの外出のように、帰りも一緒にデニスと電車に乗るような気がしていた。
でも空港で手続きをした後、デニスが搭乗口に向かう直前、彼は私に言った。
「僕は帰るよ、智子」
その言葉を聞いて、私は今日初めて正面からデニスを見た。
デニスは静かな目で私を見返していた。出会ったときの仮面のような冷たさはもうなかったけれど、朗らかに笑うことができるほど落ち着いてはいないようだった。
「ありがとう。君に会えてよかった」
私はその言葉にどんな別れの言葉を返せばいいのかわからず、ただ泣きそうな目で彼を見返した。
そのとき、デニスは少し屈む素振りを見せた。
けれど彼は私に触れる前に小さく苦笑して、体を離した。
代わりにデニスは右手を差し出して、きょとんとしている私から右手をすくいあげた。
その手を握りしめながら、デニスは私に言った。
「春になったら英国へおいでよ」
デニスはさよならとも、またねとも言わなかった。きっとそれが、彼にできる精一杯の別れの言葉だった。
私はぎこちなく笑って、その手を握り返す。
「……うん。行くよ。絶対行く」
それが、デニスとの最後の約束になった。
リチャードから電話をもらったのは、一月の半ばのことだった。
呆然とした自分の声が、まるで他人事みたいに聞こえた。
「……デニスが息を引き取った?」
その事実は、陰る冬の空のように私を押しつぶした。
私は短い呼吸を繰り返すばかりで、それ以上何も言えなかった。そんな私に、リチャードはぽつぽつと話す。
「だんだん弱って、言葉もわずかになっていったけど……最期は、安らかだったよ」
その光景を思い出したのか、リチャードは電話口で喉を詰まらせた。
「子どもの頃から、覚悟していたことだけど……やっぱり、つらいな」
リチャードはそう言葉を吐き出して、しばらく自分の中のこらえきれない感情に向き合っていたようだった。
「……智子さん、ありがとう」
やがてリチャードは息を吸って、私に優しい言葉を投げかける。
「あの子がそう伝えてほしいって言ってた。僕からもお礼を言うよ。君はあの子の最後の……最高の、友だちだったみたいだから」
私はまだリチャードの言葉を信じていなかった。私には死にゆくデニスを想像できなかった。
何かを考えることはできなかった。リチャードに問い詰めようとしても、言葉が沈んで形にならない。
「デニスは……」
デニスが別れ際に何と言ったか、どんな顔をしていたか、ほんの半月前のことなのに、思い出せなかった。
「デニスはね」
言葉を続けられない私に、リチャードが雨粒を落とすように声をかけた。
「亡くなる一週間前、最後の外出をしたんだ」
そっと思い出を縁取るように、リチャードは話し始める。
「少しの時間なら外出していいって医者に言われたから、僕はデニスにどこへ行きたいか訊いたんだ。そんなに遠くは行けないけれど、連れて行くよって。そうしたらデニスは、「ウェストミンスターの鐘を聴きに行きたい」と」
そこはいつか、デニスのロンドンで好きだった数少ない場所だと聞いた。たぶん私の知らない色々な思い出が詰まっているのに違いなかった。
リチャードの言葉は続く。私の心に痛む足音を残しながら、記憶を辿る。
「デニスはもう自分で歩けなかったから僕が車椅子を押して、寺院に入ったんだ。デニスはずっとぼんやりしてて、無言だった。気分が悪いのかと訊いたけど、それも聞こえてないみたいだった」
だいぶ弱っていたのだろう。痛ましい思いがして、私もうつむく。
リチャードはふいに喉を詰まらせて言う。
「だけど、鐘が鳴ったら。デニスは笑ったんだ」
リチャードは苦しそうに唇をかみしめる。
「「ああ、時間だ。智子が帰ってくる」って言うんだ」
「……私?」
一瞬、時が止まったような思いがした。
どうして私の名前が出たのか、私は考えようとして一つのことを思い出す。
リチャードは電話ごしにその事実を告げる。
「ウェストミンスターの鐘の音は、日本の学校のチャイムの音だね」
リチャードに言われて、私はこくりとうなずく。
「君の家は学校の近くだと聞いた。君は高校が終わるとすぐに帰ってきたんだって」
リチャードは言葉に詰まりながら言葉を続ける。
「……僕は」
リチャードはごくんと息を呑んで言う。
「元気になったらどこへでも連れていってやるから。デニスの好きな場所へ、日本だってまた連れて行くからって、言ったんだけど」
必死で告げたリチャードのその時の声が、聞いてもいないのに蘇るようだった。
「デニスは言ったんだ。「僕はいろんなところに行ったつもりなんだけど」」
一瞬、デニスの声が耳の近くで聞こえてくる気がした。
「……「今は智子と初めて行った、広い広い、雑貨店しか思い出せないんだ」って、笑うんだ」
リチャードはデニスの言葉を語り終えて、哀しい声で告げた。
「デニスは君のことが好きだったよ」
……デニス、私は君のことが好きだったよ。唐突に、私は自分の思いを理解した。
「好きだから、思いが伝えられなかったんだよ……」
私は張り裂けそうな思いが胸に迫るのを感じながら、リチャードの声を聞いていた。
一月間のホームステイは、思い返せばあっという間だった。デニスが日本で望んだ滞在ができたのかどうか、私にはわからなかった。
でもデニスはリチャードや私に勧められても、帰国を早めたりはしなかった。結局、与えられた期間の最後までホームステイをして、慎ましやかに両親にお礼を言っていた。
帰りは、空港までデニスを送るのは私の役目だった。私がそうさせてほしいと父に頼んだからだった。
帰国の日は、冬の最中であるのに陽光のうららかな日だった。
私とデニスは言葉少なく電車に揺られて、次で降りるよ、とか、温かい日だね、とか、差しさわりのないことばかり言っていた。
私はきっと、デニスが帰るのをまだ実感していなかった。いつもの外出のように、帰りも一緒にデニスと電車に乗るような気がしていた。
でも空港で手続きをした後、デニスが搭乗口に向かう直前、彼は私に言った。
「僕は帰るよ、智子」
その言葉を聞いて、私は今日初めて正面からデニスを見た。
デニスは静かな目で私を見返していた。出会ったときの仮面のような冷たさはもうなかったけれど、朗らかに笑うことができるほど落ち着いてはいないようだった。
「ありがとう。君に会えてよかった」
私はその言葉にどんな別れの言葉を返せばいいのかわからず、ただ泣きそうな目で彼を見返した。
そのとき、デニスは少し屈む素振りを見せた。
けれど彼は私に触れる前に小さく苦笑して、体を離した。
代わりにデニスは右手を差し出して、きょとんとしている私から右手をすくいあげた。
その手を握りしめながら、デニスは私に言った。
「春になったら英国へおいでよ」
デニスはさよならとも、またねとも言わなかった。きっとそれが、彼にできる精一杯の別れの言葉だった。
私はぎこちなく笑って、その手を握り返す。
「……うん。行くよ。絶対行く」
それが、デニスとの最後の約束になった。
リチャードから電話をもらったのは、一月の半ばのことだった。
呆然とした自分の声が、まるで他人事みたいに聞こえた。
「……デニスが息を引き取った?」
その事実は、陰る冬の空のように私を押しつぶした。
私は短い呼吸を繰り返すばかりで、それ以上何も言えなかった。そんな私に、リチャードはぽつぽつと話す。
「だんだん弱って、言葉もわずかになっていったけど……最期は、安らかだったよ」
その光景を思い出したのか、リチャードは電話口で喉を詰まらせた。
「子どもの頃から、覚悟していたことだけど……やっぱり、つらいな」
リチャードはそう言葉を吐き出して、しばらく自分の中のこらえきれない感情に向き合っていたようだった。
「……智子さん、ありがとう」
やがてリチャードは息を吸って、私に優しい言葉を投げかける。
「あの子がそう伝えてほしいって言ってた。僕からもお礼を言うよ。君はあの子の最後の……最高の、友だちだったみたいだから」
私はまだリチャードの言葉を信じていなかった。私には死にゆくデニスを想像できなかった。
何かを考えることはできなかった。リチャードに問い詰めようとしても、言葉が沈んで形にならない。
「デニスは……」
デニスが別れ際に何と言ったか、どんな顔をしていたか、ほんの半月前のことなのに、思い出せなかった。
「デニスはね」
言葉を続けられない私に、リチャードが雨粒を落とすように声をかけた。
「亡くなる一週間前、最後の外出をしたんだ」
そっと思い出を縁取るように、リチャードは話し始める。
「少しの時間なら外出していいって医者に言われたから、僕はデニスにどこへ行きたいか訊いたんだ。そんなに遠くは行けないけれど、連れて行くよって。そうしたらデニスは、「ウェストミンスターの鐘を聴きに行きたい」と」
そこはいつか、デニスのロンドンで好きだった数少ない場所だと聞いた。たぶん私の知らない色々な思い出が詰まっているのに違いなかった。
リチャードの言葉は続く。私の心に痛む足音を残しながら、記憶を辿る。
「デニスはもう自分で歩けなかったから僕が車椅子を押して、寺院に入ったんだ。デニスはずっとぼんやりしてて、無言だった。気分が悪いのかと訊いたけど、それも聞こえてないみたいだった」
だいぶ弱っていたのだろう。痛ましい思いがして、私もうつむく。
リチャードはふいに喉を詰まらせて言う。
「だけど、鐘が鳴ったら。デニスは笑ったんだ」
リチャードは苦しそうに唇をかみしめる。
「「ああ、時間だ。智子が帰ってくる」って言うんだ」
「……私?」
一瞬、時が止まったような思いがした。
どうして私の名前が出たのか、私は考えようとして一つのことを思い出す。
リチャードは電話ごしにその事実を告げる。
「ウェストミンスターの鐘の音は、日本の学校のチャイムの音だね」
リチャードに言われて、私はこくりとうなずく。
「君の家は学校の近くだと聞いた。君は高校が終わるとすぐに帰ってきたんだって」
リチャードは言葉に詰まりながら言葉を続ける。
「……僕は」
リチャードはごくんと息を呑んで言う。
「元気になったらどこへでも連れていってやるから。デニスの好きな場所へ、日本だってまた連れて行くからって、言ったんだけど」
必死で告げたリチャードのその時の声が、聞いてもいないのに蘇るようだった。
「デニスは言ったんだ。「僕はいろんなところに行ったつもりなんだけど」」
一瞬、デニスの声が耳の近くで聞こえてくる気がした。
「……「今は智子と初めて行った、広い広い、雑貨店しか思い出せないんだ」って、笑うんだ」
リチャードはデニスの言葉を語り終えて、哀しい声で告げた。
「デニスは君のことが好きだったよ」
……デニス、私は君のことが好きだったよ。唐突に、私は自分の思いを理解した。
「好きだから、思いが伝えられなかったんだよ……」
私は張り裂けそうな思いが胸に迫るのを感じながら、リチャードの声を聞いていた。