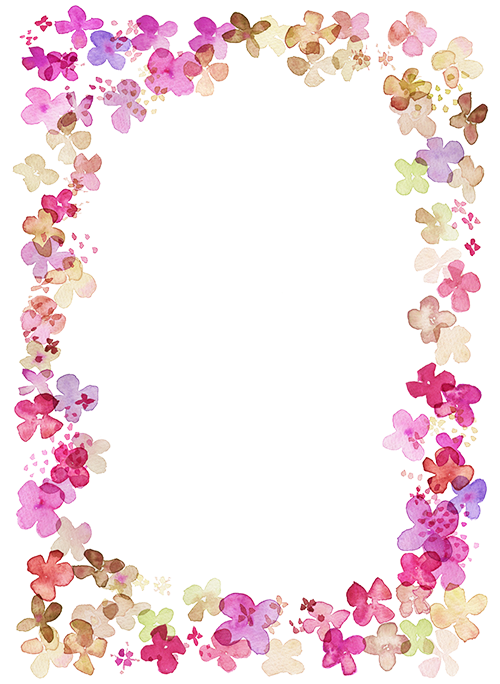リチャードはデニスが英国に帰る一週間前、日本に旅行にやって来た。
「デニス、お兄ちゃんが来てあげたよー!」
デニスの六歳年上の兄である彼は、背が高くてしっかりした体格をしているのに、子どもみたいに澄んだ緑の目が印象的な人だった。
百九十センチに届くくらいのその長身に私が啞然としていると、リチャードの方は私を見下ろして目を丸くした。
「……ちっちゃい」
「失礼な!」
思わず私が怒ると、リチャードはにこにこ笑いながら私に手を差し出した。
「怒らないで。かわいいって意味だよ。デニスから話は聞いてるんだぁ、智子さん。よろしくねー!」
「どうも」
私はその流暢すぎる日本語も腹立たしく思いながら、横を向いてリチャードと握手を交わした。
リチャードは昨日の夜、日本にやって来たばかりだった。けれど元気いっぱいで、朝デニスのところにやって来るなり言った。
「さ、行こうよ東京!」
私はその言葉にデニスが渋るのはわかっていた。
「リチャード。正直、僕は東京には行きたくないんだ。あの街は、日本の古き良きものを振り捨てて大きくなったところだろう?」
「行ってみなきゃわかんないじゃない」
リチャードはふんと笑って、デニスを外に誘った。
デニスは難しい顔をしたけれど、リチャードを見上げてつぶやく。
「……仕方ない。リチャードはせっかく旅行に来たんだからな」
そうして、私たちは三人で弾丸東京旅行に出かけた。
私の家から東京までは電車と新幹線で三時間ほどだから、今までだってデニスは行こうと思えばいくらでも行けた。けれどデニスの言う通り、彼は意図的にそこを避けていた。
リチャードは新幹線の中でもわくわくと話し続けて、目的地に着くと大きく手を広げた。
「来たよ、渋谷!」
リチャードは人だかりを楽しそうに見て、オーマイゴッドを五回くらい繰り返していた。
私がほんと明るい人だなぁと思っていると、リチャードは私の袖をくいくい引いて笑う。
「智子さーん。ハチ公の前で写真撮ろ!」
「えぇー……」
「君だってキングス・クロス駅の9と4分の3番線に来たら写真撮るでしょ。それとおんなじ!」
私はちょっと呆れながら、でも彼の言うことも一理あると思った。
リチャードに言われるままハチ公の前で写真を撮って、交差点を通って、ぎらぎら光るゲームセンターに行った。
「次あっち! でね、あれも、ここも行きたい!」
リチャードの希望でスカイツリーを上ったり、下町でカツ丼を食べたり、スーパー銭湯を堪能したりした。
仕上げに秋葉原のメイド喫茶に落ち着いて、リチャードはご満悦だった。
「日本ってエキゾチック! 僕、こんな楽しいとこ来たことないよ」
「……君のチョイスがある意味楽しいんだと言っていいと思う」
ちなみに食事中を除いてほぼ全区間、リチャードが主体的に話し続けているという賑やかさだった。
案内した私とデニスはぐったりして疲れていたけど、こんな楽しみ方もあったんだとある意味新鮮だった。
デニスはハートの描かれたオムレツを前にうなだれて言う。
「智子を風俗店に連れてきてしまった……」
「デニス、大丈夫だって。ディズニーランドみたいなものだから」
デニスなら決して案内しないところも、今日はたくさん回った。私はデニスをなだめながらリチャードに問いかける。
「メイドさんが実際にいる国の人から見たら笑えるでしょ?」
「くふふ! 日本人ってやらしーなー!」
「本当に笑われるといらっとするけど」
盛大にウケているリチャードに嫌味を言うと、彼はまたけらけらと笑っていた。
デニスと本当に兄弟なのか疑いたくなるくらい、リチャードは底抜けに明るくて元気だった。
「面白い人だなぁ、もう」
私が投げやりに言いながら笑うと、デニスがちらっと私を見た気配がした。
リチャードはふいに私とデニスを見比べて、少し困ったように眉を下げる。
「……デニスはロンドンも嫌いだからなぁ」
リチャードが飾り気なく告げた言葉は、私も聞き覚えがあった。
私はうなずいてリチャードに言う。
「うん。確かにデニスに聞いた。ロンドンはもはや、古き良き国ではないって」
デニスは苦笑しながら私の言葉に肯定を返した。
「混じってしまっているからね。変わってもいる。古いものも残ってはいるけれど、新しいものの方が凌駕している」
リチャードはそれを聞いて、多少面白くなさそうに言った。
「デニスー? ロンドンっ子の僕から一言。楽しいことを喜ぶのって、別に悪いことじゃないだろ?」
私は首を横に振って言葉を挟む。
「リチャードは、楽しいもの大好きを体現した人だけど。私はデニスの、アンティークを大事にする素朴さはいいところだと思うんだ」
「そうかぁ……」
リチャードはそう言って、それ以上ロンドンの話をすることはなかった。
帰路、相変わらずリチャードは楽しげに話し続けていた。行きと違ってデニスより私の方がよく話していたのは、今日一日でリチャードという人の明るさに感化されたからだった。
新幹線から降りた駅で、リチャードはお土産売り場で目を輝かせて言った。
「ねぇねぇ、ちょっとここで時間取っていい?」
「いいよ」
私とデニスはもう歩く元気がなくて、リチャードの自由にしてもらうことにした。
リチャードがお土産を選んでいる間、私とデニスはカフェで休憩していた。
「いつもだけど、人が多いね」
「もうすぐクリスマスだからかな」
二人で他愛ない話をしていて、ふとデニスが話題を変えた。
「君らは、仲良くなると思っていたよ」
「え?」
デニスは私の返事を待たずに続けた。
「智子もリチャードも、いろんなことに興味を持ってる。それに二人とも、真面目なんだ」
私はきょとんとして、真面目と呟いた。
彼は日本語が流暢だけど、一瞬言葉のニュアンスが違うような気がした。私は不思議そうにデニスに問い返す。
「リチャードって真面目かなぁ。何せ私はそこまで長い間一緒にいたわけじゃないし。子どもっぽい、妖精パックみたいに愉快な人じゃない?」
私は首を傾げて言葉を続ける。
「真面目なら、デニスのことじゃないの?」
「そうでもない。僕は小ずるいところがあってね」
デニスは私から目を逸らして答えた。
私はこの一月、毎日デニスと過ごしたのに、なんだかデニスが急に遠くに感じてしまった。
私は戸惑うままにデニスにたずねる。
「わからないよ、デニス。何か私が気に障ることをしたの?」
デニスは目を逸らしたまま、彼も困ったように言った。
「僕が悪い。自分がよくわからないんだ。智子が悪いわけじゃない」
それから私とデニスの間には長い沈黙が下りた。私はデニスの思いがわからなくて、それ以上の言葉を続けられなかった。
私たちの止まった時間を動かしたのは、お土産売り場から戻ってきたリチャードだった。
「お待たせー! 二人も一緒に来たらよかったのに……あれ?」
リチャードは私とデニスを見比べて、その間にある距離に気づいたらしい。
「どうしちゃったのさ。喧嘩でもした?」
デニスは首を横に振ってリチャードに返す。
「そうじゃないよ。出よう、智子。帰ろう」
「う、うん」
後半は私への言葉で、私は慌てて席を立った。
不思議そうなリチャードと言葉に迷っている私を連れて、デニスはカフェのトレイを片付けていた。
そんなとき、デニスの持ったトレイが床に落ちて音を立てた。
「デニス?」
「う……!」
デニスは胸を押さえて床にうずくまる。短い呼吸を繰り返して、顔から血の気がなくなっていく。
私は発作が起きたのだと思って、彼のポーチに手を伸ばした。
「デニス、飲んで!」
私は彼のポーチから薬を出して渡したけれど、そのときにはデニスは意識もなくぐったりとしていた。
「あ……!」
どうしようと気が動転していた。今までは発作が起きても、薬を飲めば落ち着いた。これは、今までの発作と違う。
立ちすくむ私の前に、リチャードが割り込んでデニスの様子を見た。
リチャードはデニスを抱えて、店員に向かって叫ぶ。
「救急車を呼んでください! すぐ!」
店員は慌てて踵を返すと、店の奥に入って行った。
幸い鉄道警察も来てくれて、まもなくデニスは駆け付けた救急隊員から手当てを受けることができた。
運ばれた病院の待合室で、私は母に電話をかけた。
「うん、今は落ち着いているよ。明日は一日様子を見て、問題なければ退院できるんだって。うん、うん……」
母は着替えを持ってきてくれることになって、私は通話を切るとデニスの病室に戻った。
「……デニス」
カーテンの向こうで、リチャードの声が聞こえた。彼の声は震えていて、泣いているのだとわかった。
救急隊が来るまでの間、リチャードは呼吸も忘れた様子で真っ青になってデニスを抱きしめていた。家族だから私以上に彼の病状を知っていただろうに、家族だから私以上に怖かっただろうと思った。
リチャードはにじんだ声で、すがるように言った。
「デニス……すぐ帰国して、出来る限りの治療をしよう」
デニスはそれに、首を横に振ったようだった。
「リチャードも知っているだろう? もうプライマリーの頃から宣告されていたことだ。仕方のないことなんだよ」
「そんなことない!」
リチャードはデニスのあきらめに満ちた言葉を振り払うようにして言い返した。
「違う……違う! 僕は一日だってあきらめてない! 精一杯あがこうよ、デニス! 僕ら家族はどんなことだってするって言ってるだろ!」
リチャードはデニスの手を握って嗚咽の声をもらす。
「そんな、あきらめるなんて……やだよ……ぉ」
後は言葉にならなかった。リチャードは子どものように泣きじゃくった。
デニスは自分の方が兄のように、そんなリチャードの肩をぽんぽんと叩いて宥めていた。
私はカーテンごしに二人をみつめながら、そこに私のような他人が立ち入れない家族の時間を見ていた。
残りわずかな時間を遠い異国で過ごしている弟を、きっとリチャードはどれほど心配してやって来たのだろう。
そんな兄が楽しそうにはしゃいでみせるのを、デニスはどんな思いで今日一日見ていたのだろう。
私は廊下に出て、うつむきながらつぶやいた。
「……リチャードの言う通りだ」
明日になったら、デニスに言おう。
家族の元に帰って病気を治療してほしい、と。
デニスと離れるのは想像するだけで寂しい。でも彼の家族が、ずっと英国で彼の帰りを待っている。
私は照明が落ちた廊下で一人、冷たい空気に包まれながら心に誓ったのだった。
「デニス、お兄ちゃんが来てあげたよー!」
デニスの六歳年上の兄である彼は、背が高くてしっかりした体格をしているのに、子どもみたいに澄んだ緑の目が印象的な人だった。
百九十センチに届くくらいのその長身に私が啞然としていると、リチャードの方は私を見下ろして目を丸くした。
「……ちっちゃい」
「失礼な!」
思わず私が怒ると、リチャードはにこにこ笑いながら私に手を差し出した。
「怒らないで。かわいいって意味だよ。デニスから話は聞いてるんだぁ、智子さん。よろしくねー!」
「どうも」
私はその流暢すぎる日本語も腹立たしく思いながら、横を向いてリチャードと握手を交わした。
リチャードは昨日の夜、日本にやって来たばかりだった。けれど元気いっぱいで、朝デニスのところにやって来るなり言った。
「さ、行こうよ東京!」
私はその言葉にデニスが渋るのはわかっていた。
「リチャード。正直、僕は東京には行きたくないんだ。あの街は、日本の古き良きものを振り捨てて大きくなったところだろう?」
「行ってみなきゃわかんないじゃない」
リチャードはふんと笑って、デニスを外に誘った。
デニスは難しい顔をしたけれど、リチャードを見上げてつぶやく。
「……仕方ない。リチャードはせっかく旅行に来たんだからな」
そうして、私たちは三人で弾丸東京旅行に出かけた。
私の家から東京までは電車と新幹線で三時間ほどだから、今までだってデニスは行こうと思えばいくらでも行けた。けれどデニスの言う通り、彼は意図的にそこを避けていた。
リチャードは新幹線の中でもわくわくと話し続けて、目的地に着くと大きく手を広げた。
「来たよ、渋谷!」
リチャードは人だかりを楽しそうに見て、オーマイゴッドを五回くらい繰り返していた。
私がほんと明るい人だなぁと思っていると、リチャードは私の袖をくいくい引いて笑う。
「智子さーん。ハチ公の前で写真撮ろ!」
「えぇー……」
「君だってキングス・クロス駅の9と4分の3番線に来たら写真撮るでしょ。それとおんなじ!」
私はちょっと呆れながら、でも彼の言うことも一理あると思った。
リチャードに言われるままハチ公の前で写真を撮って、交差点を通って、ぎらぎら光るゲームセンターに行った。
「次あっち! でね、あれも、ここも行きたい!」
リチャードの希望でスカイツリーを上ったり、下町でカツ丼を食べたり、スーパー銭湯を堪能したりした。
仕上げに秋葉原のメイド喫茶に落ち着いて、リチャードはご満悦だった。
「日本ってエキゾチック! 僕、こんな楽しいとこ来たことないよ」
「……君のチョイスがある意味楽しいんだと言っていいと思う」
ちなみに食事中を除いてほぼ全区間、リチャードが主体的に話し続けているという賑やかさだった。
案内した私とデニスはぐったりして疲れていたけど、こんな楽しみ方もあったんだとある意味新鮮だった。
デニスはハートの描かれたオムレツを前にうなだれて言う。
「智子を風俗店に連れてきてしまった……」
「デニス、大丈夫だって。ディズニーランドみたいなものだから」
デニスなら決して案内しないところも、今日はたくさん回った。私はデニスをなだめながらリチャードに問いかける。
「メイドさんが実際にいる国の人から見たら笑えるでしょ?」
「くふふ! 日本人ってやらしーなー!」
「本当に笑われるといらっとするけど」
盛大にウケているリチャードに嫌味を言うと、彼はまたけらけらと笑っていた。
デニスと本当に兄弟なのか疑いたくなるくらい、リチャードは底抜けに明るくて元気だった。
「面白い人だなぁ、もう」
私が投げやりに言いながら笑うと、デニスがちらっと私を見た気配がした。
リチャードはふいに私とデニスを見比べて、少し困ったように眉を下げる。
「……デニスはロンドンも嫌いだからなぁ」
リチャードが飾り気なく告げた言葉は、私も聞き覚えがあった。
私はうなずいてリチャードに言う。
「うん。確かにデニスに聞いた。ロンドンはもはや、古き良き国ではないって」
デニスは苦笑しながら私の言葉に肯定を返した。
「混じってしまっているからね。変わってもいる。古いものも残ってはいるけれど、新しいものの方が凌駕している」
リチャードはそれを聞いて、多少面白くなさそうに言った。
「デニスー? ロンドンっ子の僕から一言。楽しいことを喜ぶのって、別に悪いことじゃないだろ?」
私は首を横に振って言葉を挟む。
「リチャードは、楽しいもの大好きを体現した人だけど。私はデニスの、アンティークを大事にする素朴さはいいところだと思うんだ」
「そうかぁ……」
リチャードはそう言って、それ以上ロンドンの話をすることはなかった。
帰路、相変わらずリチャードは楽しげに話し続けていた。行きと違ってデニスより私の方がよく話していたのは、今日一日でリチャードという人の明るさに感化されたからだった。
新幹線から降りた駅で、リチャードはお土産売り場で目を輝かせて言った。
「ねぇねぇ、ちょっとここで時間取っていい?」
「いいよ」
私とデニスはもう歩く元気がなくて、リチャードの自由にしてもらうことにした。
リチャードがお土産を選んでいる間、私とデニスはカフェで休憩していた。
「いつもだけど、人が多いね」
「もうすぐクリスマスだからかな」
二人で他愛ない話をしていて、ふとデニスが話題を変えた。
「君らは、仲良くなると思っていたよ」
「え?」
デニスは私の返事を待たずに続けた。
「智子もリチャードも、いろんなことに興味を持ってる。それに二人とも、真面目なんだ」
私はきょとんとして、真面目と呟いた。
彼は日本語が流暢だけど、一瞬言葉のニュアンスが違うような気がした。私は不思議そうにデニスに問い返す。
「リチャードって真面目かなぁ。何せ私はそこまで長い間一緒にいたわけじゃないし。子どもっぽい、妖精パックみたいに愉快な人じゃない?」
私は首を傾げて言葉を続ける。
「真面目なら、デニスのことじゃないの?」
「そうでもない。僕は小ずるいところがあってね」
デニスは私から目を逸らして答えた。
私はこの一月、毎日デニスと過ごしたのに、なんだかデニスが急に遠くに感じてしまった。
私は戸惑うままにデニスにたずねる。
「わからないよ、デニス。何か私が気に障ることをしたの?」
デニスは目を逸らしたまま、彼も困ったように言った。
「僕が悪い。自分がよくわからないんだ。智子が悪いわけじゃない」
それから私とデニスの間には長い沈黙が下りた。私はデニスの思いがわからなくて、それ以上の言葉を続けられなかった。
私たちの止まった時間を動かしたのは、お土産売り場から戻ってきたリチャードだった。
「お待たせー! 二人も一緒に来たらよかったのに……あれ?」
リチャードは私とデニスを見比べて、その間にある距離に気づいたらしい。
「どうしちゃったのさ。喧嘩でもした?」
デニスは首を横に振ってリチャードに返す。
「そうじゃないよ。出よう、智子。帰ろう」
「う、うん」
後半は私への言葉で、私は慌てて席を立った。
不思議そうなリチャードと言葉に迷っている私を連れて、デニスはカフェのトレイを片付けていた。
そんなとき、デニスの持ったトレイが床に落ちて音を立てた。
「デニス?」
「う……!」
デニスは胸を押さえて床にうずくまる。短い呼吸を繰り返して、顔から血の気がなくなっていく。
私は発作が起きたのだと思って、彼のポーチに手を伸ばした。
「デニス、飲んで!」
私は彼のポーチから薬を出して渡したけれど、そのときにはデニスは意識もなくぐったりとしていた。
「あ……!」
どうしようと気が動転していた。今までは発作が起きても、薬を飲めば落ち着いた。これは、今までの発作と違う。
立ちすくむ私の前に、リチャードが割り込んでデニスの様子を見た。
リチャードはデニスを抱えて、店員に向かって叫ぶ。
「救急車を呼んでください! すぐ!」
店員は慌てて踵を返すと、店の奥に入って行った。
幸い鉄道警察も来てくれて、まもなくデニスは駆け付けた救急隊員から手当てを受けることができた。
運ばれた病院の待合室で、私は母に電話をかけた。
「うん、今は落ち着いているよ。明日は一日様子を見て、問題なければ退院できるんだって。うん、うん……」
母は着替えを持ってきてくれることになって、私は通話を切るとデニスの病室に戻った。
「……デニス」
カーテンの向こうで、リチャードの声が聞こえた。彼の声は震えていて、泣いているのだとわかった。
救急隊が来るまでの間、リチャードは呼吸も忘れた様子で真っ青になってデニスを抱きしめていた。家族だから私以上に彼の病状を知っていただろうに、家族だから私以上に怖かっただろうと思った。
リチャードはにじんだ声で、すがるように言った。
「デニス……すぐ帰国して、出来る限りの治療をしよう」
デニスはそれに、首を横に振ったようだった。
「リチャードも知っているだろう? もうプライマリーの頃から宣告されていたことだ。仕方のないことなんだよ」
「そんなことない!」
リチャードはデニスのあきらめに満ちた言葉を振り払うようにして言い返した。
「違う……違う! 僕は一日だってあきらめてない! 精一杯あがこうよ、デニス! 僕ら家族はどんなことだってするって言ってるだろ!」
リチャードはデニスの手を握って嗚咽の声をもらす。
「そんな、あきらめるなんて……やだよ……ぉ」
後は言葉にならなかった。リチャードは子どものように泣きじゃくった。
デニスは自分の方が兄のように、そんなリチャードの肩をぽんぽんと叩いて宥めていた。
私はカーテンごしに二人をみつめながら、そこに私のような他人が立ち入れない家族の時間を見ていた。
残りわずかな時間を遠い異国で過ごしている弟を、きっとリチャードはどれほど心配してやって来たのだろう。
そんな兄が楽しそうにはしゃいでみせるのを、デニスはどんな思いで今日一日見ていたのだろう。
私は廊下に出て、うつむきながらつぶやいた。
「……リチャードの言う通りだ」
明日になったら、デニスに言おう。
家族の元に帰って病気を治療してほしい、と。
デニスと離れるのは想像するだけで寂しい。でも彼の家族が、ずっと英国で彼の帰りを待っている。
私は照明が落ちた廊下で一人、冷たい空気に包まれながら心に誓ったのだった。