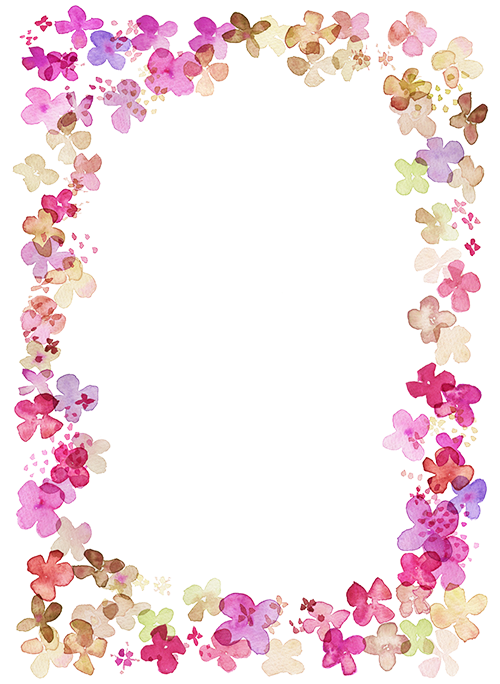デニスが旅行に行っている間、デニスが勧めてくれた英国の本を読んでいた。
私は熱心に読書をする性格ではなかったけど、デニスが来てから、彼の国のことを知りたいと英国の本を読む機会が増えた。
その中で今回私が読んだのは、シェイクスピアの『十二夜』だった。
学校から帰った後のけだるい夕暮れ時、母と二人で本の話をする日が来るとは思ってもみなかった。
「……でね、最後は主人公も公爵と結ばれてハッピーエンド。楽しくて一気に読んじゃったよ」
「デニス君は智子の趣味をよくわかっているわね」
母は私の話を聞いて、からかい交じりに言う。
「恋物語が好き。断然、ハッピーエンドが大好き」
「誰だってそうだよ」
私は少しむすっとして言い返した。
「有名だけど、シェイクスピアは難しそうじゃない。そうしたらデニスが教えてくれたんだ。「じゃあこの辺りから始めてみなよ。脚注を飛ばせばすぐに読めるよ」ってね」
そうしたら意外なほどさらさらと読めた。男装した女の子を中心としたおかしみのあるストーリーに、すぐに取り込まれた。
母は愉快そうに笑って何度もうなずく。
「小難しい脚注も飛ばしたい。デニス君はよくわかってるわ」
「もー」
私は母の軽口にむくれながら言葉を続ける。
「でもデニスだって、悲劇より喜劇の方が好きだよ」
「あら、意外」
「シャイクスピアで一番好きな作品も、『真夏の夜の夢』だったし」
私もそれをデニスから聞いたときは、意外な気持ちがした。
デニスはシェイクスピアの現存する本すべてを読んで、台詞すら空で言える。もっとマイナーなものを選んでくるかと思っていた。
私はその物語の登場人物を思い返しながら言う。
「すごくパックが好きみたい」
「妖精パック? あの悪戯っ子でハチャメチャなことをする?」
「うん。彼みたいな存在になれたら、違う世界が見えただろうなって」
パックは登場人物たちを混乱させる困った子で、けれど憎めない、どこかかわいらしい妖精だ。
「私も『真夏の夜の夢』は読んだんだ。パックの登場は、読んでいて楽しかった」
母はそれを聞いて目を細めながら言った。
「デニス君だって、あまり悲劇は見たくないのかもしれないわね」
「……そういえば」
私は少し黙ってから口を開く。
「デニスに勧められた本がもう一冊あるんだけど、手をつけられない本なんだ」
「難しい本?」
「言葉自体は易しいんだけど」
私は言葉に詰まってからぼそりと言う。
「……どう予想してもハッピーエンドじゃないんだ」
「悲劇も文学を理解するには必要よ?」
母は先生のような口ぶりで私にさとす。
「お勧めされたんだから、デニス君が留守の間に読んでみたら? 帰って来る頃にはお母さんにも感想、聞かせてね」
「うう。わかったよ」
私はちょっとうめいて、渋々母の言葉に了解した。
デニスが勧めてくれた本の名前は、『ダーバヴィル家のテス』という物語だ。
デニスに借りたその本を、私はそれから二日間かけて読んだ。
それはあまりに救いのない話だった。強姦、貧困、離れて行く恋人、主人公のテスの行き先には、いつも暗い運命しかなかった。
デニスは私に、こうも言ってくれていた。
――どうしてもというなら、最後だけ読んでごらん。
でも私は意固地になって、はじめから順々に読み進めた。
喜劇が好きなデニスが勧めたこの本を、泥沼の末に迎える最後を、どうにか見届けたかったのだった。
二日の後にデニスは父と共に帰って来たけれど、疲れていたらしくその日はすぐに眠ったようだった。
私は夜のうちに『ダーバヴィル家のテス』を読み終えて、翌日学校に行った。
高校から帰って来たら、いつものようにデニスが先に大学から帰っていた。
彼は旅行の疲れなど見せず、普段通りにリビングで新聞を読んでいた。新聞なら毎朝必ず目を通して大学に行くし、デニスは自分ではテレビをつけないからリビングにいる必要もないのに、そこで夕方に新聞を読むのは彼の癖だった。
デニスは私がリビングに入ると、ふと目を上げて笑う。
「おかえり、智子」
淡々と話す彼だけど、その一声はとても優しい。
デニスはそれから、いつものように紅茶を淹れてくれた。それを飲みながらここで話すのは、いつの間にか日常になっていた。
なんだかずっと昔から、彼とそう話していたような気分だった。私ははっと我に返って、言葉を切り出す。
「出雲大社はどうだった?」
まずは彼の非日常に耳を傾ける番だ。そう思って問いかけた私に、デニスはうなずいて答えた。
「思っていたとおり、良かった」
その日のデニスはいつもより雄弁に、旅先のことを話してくれた。
「原初の世界だった。力強くて、荒々しくて。たぶん日本の古代の神々の加護だな」
彼は旅に出る前からその歴史的価値もその景色も知っていただろう。けれどそれ以上に、彼は目にしたものを喜んでいた。
「それでいて今でも深い謎に包まれていて、故郷のストーンヘンジを思い出したよ」
彼からその名前を聞いて、私は昨晩読んだ本を思い出していた。
「『ダーバヴィル家のテス』の最後も、ストーンヘンジだったね。昨日読んだんだ」
デニスは少し驚いた風で、緑の目をまたたかせた。
「悲劇は苦手だと聞いていた。読んでくれたのか」
「うん。……あ、それより旅行の話だよ」
私はついいつものように自分の話ばかりしそうになって、慌てて言葉を挟む。
でもデニスは気にした様子もなく、穏やかに私に言葉をかけた。
「せっかく読んでくれたんだ。少しストーンヘンジの話をしよう」
デニスはそう言って、目の前に思い出すように言った。
「僕の祖先が英国に住む前からあった石群。あそこに行くと、自分のルーツについて考えさせられる」
「ルーツ?」
「起源、始まりと言うべきか。僕は自分がイングランド人だと思っているけれど」
自分が住んでいた土地のことを、彼は温かい言葉で話す。
「僕の祖先はおそらく元々グレートブリテン島には住んでいなかったはずなんだ。彼らは大陸から渡って来た」
「そうなんだ。あのね、日本人の祖先も元は今の列島に住んでなかったらしいよ」
私もデニスにそう話したら、デニスは私に問いを投げかけた。
「そう聞いている。でも君らはこの列島こそ故郷だと思っているだろう?」
「うん。そう思うよ」
私が頷くと、デニスも頷いた。
「僕もグレートブリテン島が故郷だと思ってる。そう考えると、ルーツというのは、実は血筋より地縁の方に強く結び付いているのではないかという気がする」
デニスの話すことは難しかったけど、私はじっとデニスをみつめながら聞いていた。
デニスは目を伏せてつぶやくように言った。
「だからかな。なぜか懐かしいんだ、あの石群は。僕の祖先が作ったものでも、彼らが住んでいた頃にできたものでもないはずなのに」
デニスの言葉を思い返して、自分はどうだろうと考える。
自分のルーツについて、普段意識することはない。ただ父と母がいて、その前に祖父と祖母がいる。それくらいしか日常には登場しなくて、また私自身考えもしない。
だけどもっとずっと昔に存在していた人や物を歴史で知っていて、それを見ると懐かしいと感じることがある。デニスの言いたかったことも、そういうことなのだろう。
「テスもイングランド人だったね。彼女もストーンヘンジに行って、懐かしかったのかな?」
「どうだろう」
現在の私たちは冬の最中、温かい紅茶を飲みながら遠い異国に思いを馳せる。
そういう時って、きっと幸せと言うんじゃないかな。ふとそんなことを思ってデニスを見ると、彼は目を伏せて恥ずかしそうにしていた。
「少し話し過ぎた。僕は学者でもないのに、偉そうなことを」
「いいよ、もっと話して」
私は普段聞き手に徹するデニスの話を、もっと聞きたかった。
「ストーンヘンジはどうやって作られたんだろう。石っていうけど、どんな石で出来てるんだろう? いつ頃出来たんだろう? そういうこと、デニスはきっと私より知っているはずだから」
「少しね」
デニスはそう言ったものの、そこから話し出した彼の話はとても豊かだった。
私の問いに、順番に細かく教えてくれる。その話は、私の知らないことだらけだった。
「どうして作られたのかな?」
私が一番気になったところを問うと、デニスは難しい顔をした。
「それについては色々な説がある。太陽崇拝の場所だとか、礼拝所だとか、天文台だとか、一致はしていないそうだ」
デニスがぽつりと答える。
「ただ、天文に関する場所ではあったようだね。夏至の日には、ぴったり石の並べられた方角から太陽が昇る」
「時計みたいだね。みんながそれを見ていたのかな」
ずっと古い時代に作られた、時計のように正確なしるべ。
何百年、何千年経っても、正確な時を刻むことができるように作ったのだろうか。
私がそう言うと、デニスは遠い世界を仰ぐように見て答える。
「今は風に吹かれて、石群は何もないところに立っているよ。昔は周りに何かあったのかもしれないし、なかったのかもしれない」
ただ、とデニスは言葉を続ける。
「一面、冬でも枯れない短い緑で覆われている。道の無い原野だ」
それが彼にとっての故郷なのかもしれないと思いながら、私はデニスの横顔を眺めていた。
私はふいに胸に去来した思いをつぶやく。
「私、英国に行ってみたいな」
目を戻したデニスに、私は言葉を続ける。
「日本にいる間は、私が精一杯デニスの案内をするから。私が英国に行ったら、今度はデニスが案内してくれる?」
デニスが私の言葉に答えを返すのは時間がかかった。
彼は自分の余命のことを考えたのかもしれない。あてのない約束をしたくないと思ったかもしれない。
でもデニスはふいに訪れた友だちを歓迎するように、温かく笑って答えた。
「……ああ。春になったらおいで」
私はその優しさに、少しうつむいてうなずいたのだった。
それから私とデニスは、時間を惜しむようにしていろいろな場所に出かけた。
博物館に図書館、水族館に公園、ちょっとした遠出もただの買い物もあった。
デニスは通院しながらの生活だったから、両親はあまりに頻繁な遠出は反対していた。
「ご心配をおかけしてすみません。でも今はいろいろなところを見たいのです」
両親からは時にデニスをたしなめる言葉もあったけれど、デニスはその変化を元に戻そうとはしなかった。
それから外出よりもっとたくさん、私はデニスとお互いの部屋で話をした。
私は他愛ないことをいくつもデニスに問いかけた。
「デニスはどうして他の国ではなくて、日本に来たの?」
デニスはその私の問いに淀みなく答えた。
「似ているんだ。あと、好きだからかな」
そのときデニスは短く言葉を切って、静かに目を閉じた。
「どうしてだろう。理由はいろいろ自分の中で考えた。でも何度考えてもそこに行きつくんだ。似ていて、好きなんだよ」
あるときには、私はデニスに踏み込んだことも問いかけた。
「デニス、今の生活はつらい?」
たぶん私の問いは、その先にある死が怖いかと問うようにも聞こえたと思う。
デニスは繕う風ではなく、率直に私に答えた。
「つらいときもある。死を肌で感じた、子どもの頃からずっとそうだ」
デニスは私に、子どもの頃の話をしてくれた。
「プライマリーの頃、大英博物館でミイラを見た。茶色く変色した包帯がちらっと見えただけで、身を縮こまらせた。兄の服の袖を握って震えることしかできなかった」
冷静で落ち着いて見える彼にもそんな頃があったのかと、私は意外な思いがした。
「とうとう泣き出して、兄になだめてもらった。あの頃、僕は小さな子どもだったけれど……そのときの思いは、きっと消える日は来ない」
私たちは話せば話すほど互いのことを知ったけれど、同時に迫って来る時間を意識した。
あるときのデニスの言葉は、私には遠く響いた。
「オックスフォードの中にあるボドリアン図書館には、プライマリーの頃からよく行ったよ」
そこは古い書物がたくさん詰まった、時間の結集のようなところだと言っていた。
「文字となって無限の時間が残っているんだ。じっと本をみつめていると、時間さえ遡れる気がした」
そう言ったデニスは、時間をさかのぼりたかったのだろう。
彼には時間がない。いくら過去をみつめても、未来に辿り着けないかもしれない。
けれどどうしたら未来に辿り着けるのかわからないまま、私たちはただ出かけて、話して、一緒に過ごしていた。
そんな私たちの時間に変化をもたらしたのは、ある一人の来訪者だった。
私は熱心に読書をする性格ではなかったけど、デニスが来てから、彼の国のことを知りたいと英国の本を読む機会が増えた。
その中で今回私が読んだのは、シェイクスピアの『十二夜』だった。
学校から帰った後のけだるい夕暮れ時、母と二人で本の話をする日が来るとは思ってもみなかった。
「……でね、最後は主人公も公爵と結ばれてハッピーエンド。楽しくて一気に読んじゃったよ」
「デニス君は智子の趣味をよくわかっているわね」
母は私の話を聞いて、からかい交じりに言う。
「恋物語が好き。断然、ハッピーエンドが大好き」
「誰だってそうだよ」
私は少しむすっとして言い返した。
「有名だけど、シェイクスピアは難しそうじゃない。そうしたらデニスが教えてくれたんだ。「じゃあこの辺りから始めてみなよ。脚注を飛ばせばすぐに読めるよ」ってね」
そうしたら意外なほどさらさらと読めた。男装した女の子を中心としたおかしみのあるストーリーに、すぐに取り込まれた。
母は愉快そうに笑って何度もうなずく。
「小難しい脚注も飛ばしたい。デニス君はよくわかってるわ」
「もー」
私は母の軽口にむくれながら言葉を続ける。
「でもデニスだって、悲劇より喜劇の方が好きだよ」
「あら、意外」
「シャイクスピアで一番好きな作品も、『真夏の夜の夢』だったし」
私もそれをデニスから聞いたときは、意外な気持ちがした。
デニスはシェイクスピアの現存する本すべてを読んで、台詞すら空で言える。もっとマイナーなものを選んでくるかと思っていた。
私はその物語の登場人物を思い返しながら言う。
「すごくパックが好きみたい」
「妖精パック? あの悪戯っ子でハチャメチャなことをする?」
「うん。彼みたいな存在になれたら、違う世界が見えただろうなって」
パックは登場人物たちを混乱させる困った子で、けれど憎めない、どこかかわいらしい妖精だ。
「私も『真夏の夜の夢』は読んだんだ。パックの登場は、読んでいて楽しかった」
母はそれを聞いて目を細めながら言った。
「デニス君だって、あまり悲劇は見たくないのかもしれないわね」
「……そういえば」
私は少し黙ってから口を開く。
「デニスに勧められた本がもう一冊あるんだけど、手をつけられない本なんだ」
「難しい本?」
「言葉自体は易しいんだけど」
私は言葉に詰まってからぼそりと言う。
「……どう予想してもハッピーエンドじゃないんだ」
「悲劇も文学を理解するには必要よ?」
母は先生のような口ぶりで私にさとす。
「お勧めされたんだから、デニス君が留守の間に読んでみたら? 帰って来る頃にはお母さんにも感想、聞かせてね」
「うう。わかったよ」
私はちょっとうめいて、渋々母の言葉に了解した。
デニスが勧めてくれた本の名前は、『ダーバヴィル家のテス』という物語だ。
デニスに借りたその本を、私はそれから二日間かけて読んだ。
それはあまりに救いのない話だった。強姦、貧困、離れて行く恋人、主人公のテスの行き先には、いつも暗い運命しかなかった。
デニスは私に、こうも言ってくれていた。
――どうしてもというなら、最後だけ読んでごらん。
でも私は意固地になって、はじめから順々に読み進めた。
喜劇が好きなデニスが勧めたこの本を、泥沼の末に迎える最後を、どうにか見届けたかったのだった。
二日の後にデニスは父と共に帰って来たけれど、疲れていたらしくその日はすぐに眠ったようだった。
私は夜のうちに『ダーバヴィル家のテス』を読み終えて、翌日学校に行った。
高校から帰って来たら、いつものようにデニスが先に大学から帰っていた。
彼は旅行の疲れなど見せず、普段通りにリビングで新聞を読んでいた。新聞なら毎朝必ず目を通して大学に行くし、デニスは自分ではテレビをつけないからリビングにいる必要もないのに、そこで夕方に新聞を読むのは彼の癖だった。
デニスは私がリビングに入ると、ふと目を上げて笑う。
「おかえり、智子」
淡々と話す彼だけど、その一声はとても優しい。
デニスはそれから、いつものように紅茶を淹れてくれた。それを飲みながらここで話すのは、いつの間にか日常になっていた。
なんだかずっと昔から、彼とそう話していたような気分だった。私ははっと我に返って、言葉を切り出す。
「出雲大社はどうだった?」
まずは彼の非日常に耳を傾ける番だ。そう思って問いかけた私に、デニスはうなずいて答えた。
「思っていたとおり、良かった」
その日のデニスはいつもより雄弁に、旅先のことを話してくれた。
「原初の世界だった。力強くて、荒々しくて。たぶん日本の古代の神々の加護だな」
彼は旅に出る前からその歴史的価値もその景色も知っていただろう。けれどそれ以上に、彼は目にしたものを喜んでいた。
「それでいて今でも深い謎に包まれていて、故郷のストーンヘンジを思い出したよ」
彼からその名前を聞いて、私は昨晩読んだ本を思い出していた。
「『ダーバヴィル家のテス』の最後も、ストーンヘンジだったね。昨日読んだんだ」
デニスは少し驚いた風で、緑の目をまたたかせた。
「悲劇は苦手だと聞いていた。読んでくれたのか」
「うん。……あ、それより旅行の話だよ」
私はついいつものように自分の話ばかりしそうになって、慌てて言葉を挟む。
でもデニスは気にした様子もなく、穏やかに私に言葉をかけた。
「せっかく読んでくれたんだ。少しストーンヘンジの話をしよう」
デニスはそう言って、目の前に思い出すように言った。
「僕の祖先が英国に住む前からあった石群。あそこに行くと、自分のルーツについて考えさせられる」
「ルーツ?」
「起源、始まりと言うべきか。僕は自分がイングランド人だと思っているけれど」
自分が住んでいた土地のことを、彼は温かい言葉で話す。
「僕の祖先はおそらく元々グレートブリテン島には住んでいなかったはずなんだ。彼らは大陸から渡って来た」
「そうなんだ。あのね、日本人の祖先も元は今の列島に住んでなかったらしいよ」
私もデニスにそう話したら、デニスは私に問いを投げかけた。
「そう聞いている。でも君らはこの列島こそ故郷だと思っているだろう?」
「うん。そう思うよ」
私が頷くと、デニスも頷いた。
「僕もグレートブリテン島が故郷だと思ってる。そう考えると、ルーツというのは、実は血筋より地縁の方に強く結び付いているのではないかという気がする」
デニスの話すことは難しかったけど、私はじっとデニスをみつめながら聞いていた。
デニスは目を伏せてつぶやくように言った。
「だからかな。なぜか懐かしいんだ、あの石群は。僕の祖先が作ったものでも、彼らが住んでいた頃にできたものでもないはずなのに」
デニスの言葉を思い返して、自分はどうだろうと考える。
自分のルーツについて、普段意識することはない。ただ父と母がいて、その前に祖父と祖母がいる。それくらいしか日常には登場しなくて、また私自身考えもしない。
だけどもっとずっと昔に存在していた人や物を歴史で知っていて、それを見ると懐かしいと感じることがある。デニスの言いたかったことも、そういうことなのだろう。
「テスもイングランド人だったね。彼女もストーンヘンジに行って、懐かしかったのかな?」
「どうだろう」
現在の私たちは冬の最中、温かい紅茶を飲みながら遠い異国に思いを馳せる。
そういう時って、きっと幸せと言うんじゃないかな。ふとそんなことを思ってデニスを見ると、彼は目を伏せて恥ずかしそうにしていた。
「少し話し過ぎた。僕は学者でもないのに、偉そうなことを」
「いいよ、もっと話して」
私は普段聞き手に徹するデニスの話を、もっと聞きたかった。
「ストーンヘンジはどうやって作られたんだろう。石っていうけど、どんな石で出来てるんだろう? いつ頃出来たんだろう? そういうこと、デニスはきっと私より知っているはずだから」
「少しね」
デニスはそう言ったものの、そこから話し出した彼の話はとても豊かだった。
私の問いに、順番に細かく教えてくれる。その話は、私の知らないことだらけだった。
「どうして作られたのかな?」
私が一番気になったところを問うと、デニスは難しい顔をした。
「それについては色々な説がある。太陽崇拝の場所だとか、礼拝所だとか、天文台だとか、一致はしていないそうだ」
デニスがぽつりと答える。
「ただ、天文に関する場所ではあったようだね。夏至の日には、ぴったり石の並べられた方角から太陽が昇る」
「時計みたいだね。みんながそれを見ていたのかな」
ずっと古い時代に作られた、時計のように正確なしるべ。
何百年、何千年経っても、正確な時を刻むことができるように作ったのだろうか。
私がそう言うと、デニスは遠い世界を仰ぐように見て答える。
「今は風に吹かれて、石群は何もないところに立っているよ。昔は周りに何かあったのかもしれないし、なかったのかもしれない」
ただ、とデニスは言葉を続ける。
「一面、冬でも枯れない短い緑で覆われている。道の無い原野だ」
それが彼にとっての故郷なのかもしれないと思いながら、私はデニスの横顔を眺めていた。
私はふいに胸に去来した思いをつぶやく。
「私、英国に行ってみたいな」
目を戻したデニスに、私は言葉を続ける。
「日本にいる間は、私が精一杯デニスの案内をするから。私が英国に行ったら、今度はデニスが案内してくれる?」
デニスが私の言葉に答えを返すのは時間がかかった。
彼は自分の余命のことを考えたのかもしれない。あてのない約束をしたくないと思ったかもしれない。
でもデニスはふいに訪れた友だちを歓迎するように、温かく笑って答えた。
「……ああ。春になったらおいで」
私はその優しさに、少しうつむいてうなずいたのだった。
それから私とデニスは、時間を惜しむようにしていろいろな場所に出かけた。
博物館に図書館、水族館に公園、ちょっとした遠出もただの買い物もあった。
デニスは通院しながらの生活だったから、両親はあまりに頻繁な遠出は反対していた。
「ご心配をおかけしてすみません。でも今はいろいろなところを見たいのです」
両親からは時にデニスをたしなめる言葉もあったけれど、デニスはその変化を元に戻そうとはしなかった。
それから外出よりもっとたくさん、私はデニスとお互いの部屋で話をした。
私は他愛ないことをいくつもデニスに問いかけた。
「デニスはどうして他の国ではなくて、日本に来たの?」
デニスはその私の問いに淀みなく答えた。
「似ているんだ。あと、好きだからかな」
そのときデニスは短く言葉を切って、静かに目を閉じた。
「どうしてだろう。理由はいろいろ自分の中で考えた。でも何度考えてもそこに行きつくんだ。似ていて、好きなんだよ」
あるときには、私はデニスに踏み込んだことも問いかけた。
「デニス、今の生活はつらい?」
たぶん私の問いは、その先にある死が怖いかと問うようにも聞こえたと思う。
デニスは繕う風ではなく、率直に私に答えた。
「つらいときもある。死を肌で感じた、子どもの頃からずっとそうだ」
デニスは私に、子どもの頃の話をしてくれた。
「プライマリーの頃、大英博物館でミイラを見た。茶色く変色した包帯がちらっと見えただけで、身を縮こまらせた。兄の服の袖を握って震えることしかできなかった」
冷静で落ち着いて見える彼にもそんな頃があったのかと、私は意外な思いがした。
「とうとう泣き出して、兄になだめてもらった。あの頃、僕は小さな子どもだったけれど……そのときの思いは、きっと消える日は来ない」
私たちは話せば話すほど互いのことを知ったけれど、同時に迫って来る時間を意識した。
あるときのデニスの言葉は、私には遠く響いた。
「オックスフォードの中にあるボドリアン図書館には、プライマリーの頃からよく行ったよ」
そこは古い書物がたくさん詰まった、時間の結集のようなところだと言っていた。
「文字となって無限の時間が残っているんだ。じっと本をみつめていると、時間さえ遡れる気がした」
そう言ったデニスは、時間をさかのぼりたかったのだろう。
彼には時間がない。いくら過去をみつめても、未来に辿り着けないかもしれない。
けれどどうしたら未来に辿り着けるのかわからないまま、私たちはただ出かけて、話して、一緒に過ごしていた。
そんな私たちの時間に変化をもたらしたのは、ある一人の来訪者だった。