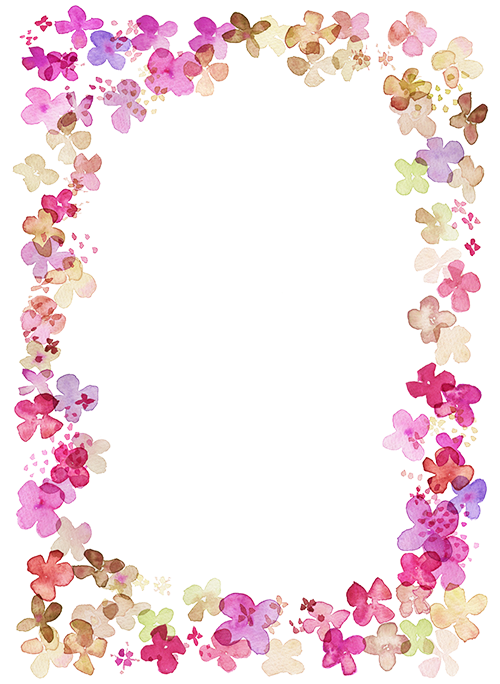彼の背負っている事実を聞いたとき、きっと忘れられない冬になる予感がしていた。
十一月の終わり、冷えてきた空気の中で日に日に陽が落ちるのが早くなる頃だった。
私は高校から帰って宿題をして、夕ご飯のために階下に降りてきた。週明けのテストは憂鬱だけど、夕食の後には新しく買った漫画を読むんだと脱力していた。
忙しなくて他愛ない日常、それに波紋を投げかけたのは、夕食の後の父の言葉だった。
「明日からホームステイする男の子について、智子に伝えておくことがある」
大学教授をしている父の縁で、明日から我が家には英国から大学生が来ることになっていた。
でもホームステイの受け入れ自体は初めてではなくて、今回の受け入れも一週間前から決まっていたことだった。
私はきょとんとして父に問いかける。
「改まってどうしたの?」
私の問いに答えたのは母だった。母はどこか憂い顔で口を開いて言った。
「直前になってごめんなさい。彼も、私たちに伝えるか迷っていたようだから」
私が首を傾げたとき、母はふいにその事実を告げた。
「明日ホームステイに来る男の子はね、余命が三か月と言われているの」
……余命と、私は思わず口にするのもためらった。
その言葉は日常で口にしていいものではなかった。けれどまもなく私の目の前に、その事実を背負った子がやって来る。
途端に、楽しみにしていたホームステイの受け入れが暮れ行く陽の色を帯びた気がした。私は思わず両親に言っていた。
「……怖いよ。私、どんな風にその子に接したらいいかわからない」
それは両親に対するというより、自分に告げた言葉だった。私の中の震えた心が、どうしたらいいか縋ったようにも聞こえた。
父は私より大人であったからなのか、それに対する答えをちゃんと持っていたようだった。父は私を静かな目で見返して言った。
「彼は限られた時間のひとときを、日本で過ごしたいと思って来る。特別なことをする必要はない。彼が何かしたいと言ったら、精一杯それに応えればいいよ」
私はごくんと息を呑んで、数度呼吸を繰り返してから答えた。
「……うん。わかった」
私はうなずいたものの、私の気持ちはまだ恐れに染まっていた。
死期の迫った非日常の存在が目の前に来て、私は私のままでいられるだろうか。もしかしたら出会ったことさえ後悔する日が来るんじゃないだろうか。
恐れて、不安で……けれど夜は否応なしに明けて、その日はやって来る。
朝、私は鏡で自分を見つめ返していた。背は低い方で、頬くらいの短い黒髪、つい不思議なものをみつけるとまじまじと見てしまう丸い瞳が年より幼く見える。
私の顔は緊張しきっていて、私は鏡の中の私にしっかりしなさいと言い聞かせた。
「……暗い顔してちゃ、その子だって嫌だよね」
まだ男の子の顔も知らない私だったけれど、単純にそう思った。
父は彼を空港まで迎えに行って、電車にも一緒に乗って家まで連れてくる。私と母は家のことをしながら時々時計を見て、その到着を待ちわびていた。
鍵が開く音が聞こえて、母と私は同時に玄関を振り向いた。私は駆け足になっては不自然だと、逸る気持ちを抑えて玄関に足を運ぶ。
玄関で初めて彼と会った私は、たぶん驚いた顔をしていた。
「初めまして。デニス・グリーンといいます。イングランドから来ました」
その流暢な日本語が意外だっただけでなく、彼は宝石のような冴えた空気をまとっていた。
さっぱりと切りそろえた金髪、にこりともしない仮面のような顔立ちの中、緑の目だけが光を放っていた。
一目見て、冷たそうな外国人だと思った。もしかして青い血が流れていたりするんじゃないかと考えたほどだった。
でもきっと、自分だってそうであるように、彼だって緊張をまとって海を渡ってきただろうと思った。
私はたぶんぎこちなく、けれどせいいっぱいの笑顔を浮かべて言った。
「福地智子です。……ようこそ」
彼は一息分だけ戸惑ってから表情を緩めてくれて、私を安心させてくれた。
それが、私とデニスの出会いだった。
デニスを迎えた初めての夕食、私ははじめ、ほとんど自分から言葉をかけることができなかった。
彼とはじめから和やかに話したのは母だった。母は今までの留学生たちと変わりなく彼に接しようと決めているようだった。
母は彼に食事を勧めながら、驚いた様子でうなずく。
「じゃあデニス君は智子と同い年なのね。大学生だと聞いていたけど、飛び級だとは知らなかったわ」
「日本では飛び級は少ないと聞きましたが、英国では周りにも相当いました。それほど珍しいものではないのです」
デニスは日本人より日本語を綺麗に話してみせた。食事の仕方だって、箸も椀も手足の延長のように扱うほど上手だった。
父は彼の食事ぶりに安心しながら彼を気遣う。
「よく食べてくれてうれしいけれど、苦手なものは無理をしなくていいよ。慣れない食事だろうから」
「ありがとうございます。ただテーブルマナーで無作法があったら、遠慮なく教えてください」
その育ちの良さは、彼から漏れ聞いた暮らしからも察しがついた。
「家庭教師を雇って練習しましたが、伝え聞いた話とは違うところもあると思うのです」
話の中で、デニスの父は英国の地方に居館を持つ家系だと聞いた。古い時代なら、彼は召使にかしずかれて過ごしていたらしかった。
「ごちそうさまでした。おいしかったです」
デニスは出された食事をきちんと完食して、丁寧に手を合わせて食事を終えた。そのそつのなさが、私には尊敬と一緒に緊張を抱かせた。
完璧すぎて、ちょっと怖かった。何を考えているのかわからなくて、私はただ横目で彼をみつめていた。
デニスはちらと私を横目で見たが、無理に私に話しかけようとはしなかった。彼には私の恐れを読み取って遠慮する繊細さもあるらしかった。
私たちはお互い構えながら一昼夜を過ごして、翌日の夕方まで何も話さなかった。
でも同じ家の中にいて、緊張しながら過ごし続けるのはお互い良くない。そう先に気づいて、沈黙を破ったのはデニスの方だった。
私がお風呂から上がって来て、彼に次だよと伝えに言った時、彼は自分から廊下に出てきて言った。
「智子さん。教えて頂きたいことがあるのですが」
デニスはそれ以上ない丁寧さで、そっと私に話しかけてきた。
「大きな雑貨店に行きたいのですが、どこかご存じですか?」
「何を探しているんですか?」
私が問い返すと、彼は言葉に詰まる素振りを見せた。
「それは……特に決まっていませんが」
デニスの困った様子に、私は彼の繊細さを見ることになった。
たぶん彼は、私とコミュニケーションを取ろうと懸命に話題をみつけて言葉をかけたんだろう。
私は不器用に差し伸べられたような手のような言葉に、柔らかな親しみを抱いた。
私はにこっと笑って言う。
「ぶらぶら歩きたい感じ? そういうときありますよね」
私は見たこともない外国から来たこの少年も、私と同じようなことを考えるんだと思った。
「明日は日曜だけど、何か予定あります?」
「いえ、特には」
「じゃ、一緒にデパートに行きませんか? 雑貨エリアが三フロアもあるところなんです」
私は彼が差し伸べてくれた手に、ぽんと親しみを返すようにして言った。
「端から端まで見ているだけで一日終わっちゃう。見ているだけでも楽しいですよ」
「僕はいいのですが、智子さんの予定には差しさわりありませんか?」
「うん……おっと。それと、もう一つ」
私は人差し指で一を作って、言葉遣いをくだけた調子に変えた。
「私のことは智子でいいよ。敬語も要らない。私たち同い年だし、これから同じ家で暮らすルームメイトなんだから」
「……そう思ってもらえるなら」
デニスは私の目を見てうなずいた。
「ぜひ連れていって。よろしく、智子」
私はその緑の瞳を見返しながら、話してみればこの人のことを理解できるかもしれないと思ったのだった。
十一月の終わり、冷えてきた空気の中で日に日に陽が落ちるのが早くなる頃だった。
私は高校から帰って宿題をして、夕ご飯のために階下に降りてきた。週明けのテストは憂鬱だけど、夕食の後には新しく買った漫画を読むんだと脱力していた。
忙しなくて他愛ない日常、それに波紋を投げかけたのは、夕食の後の父の言葉だった。
「明日からホームステイする男の子について、智子に伝えておくことがある」
大学教授をしている父の縁で、明日から我が家には英国から大学生が来ることになっていた。
でもホームステイの受け入れ自体は初めてではなくて、今回の受け入れも一週間前から決まっていたことだった。
私はきょとんとして父に問いかける。
「改まってどうしたの?」
私の問いに答えたのは母だった。母はどこか憂い顔で口を開いて言った。
「直前になってごめんなさい。彼も、私たちに伝えるか迷っていたようだから」
私が首を傾げたとき、母はふいにその事実を告げた。
「明日ホームステイに来る男の子はね、余命が三か月と言われているの」
……余命と、私は思わず口にするのもためらった。
その言葉は日常で口にしていいものではなかった。けれどまもなく私の目の前に、その事実を背負った子がやって来る。
途端に、楽しみにしていたホームステイの受け入れが暮れ行く陽の色を帯びた気がした。私は思わず両親に言っていた。
「……怖いよ。私、どんな風にその子に接したらいいかわからない」
それは両親に対するというより、自分に告げた言葉だった。私の中の震えた心が、どうしたらいいか縋ったようにも聞こえた。
父は私より大人であったからなのか、それに対する答えをちゃんと持っていたようだった。父は私を静かな目で見返して言った。
「彼は限られた時間のひとときを、日本で過ごしたいと思って来る。特別なことをする必要はない。彼が何かしたいと言ったら、精一杯それに応えればいいよ」
私はごくんと息を呑んで、数度呼吸を繰り返してから答えた。
「……うん。わかった」
私はうなずいたものの、私の気持ちはまだ恐れに染まっていた。
死期の迫った非日常の存在が目の前に来て、私は私のままでいられるだろうか。もしかしたら出会ったことさえ後悔する日が来るんじゃないだろうか。
恐れて、不安で……けれど夜は否応なしに明けて、その日はやって来る。
朝、私は鏡で自分を見つめ返していた。背は低い方で、頬くらいの短い黒髪、つい不思議なものをみつけるとまじまじと見てしまう丸い瞳が年より幼く見える。
私の顔は緊張しきっていて、私は鏡の中の私にしっかりしなさいと言い聞かせた。
「……暗い顔してちゃ、その子だって嫌だよね」
まだ男の子の顔も知らない私だったけれど、単純にそう思った。
父は彼を空港まで迎えに行って、電車にも一緒に乗って家まで連れてくる。私と母は家のことをしながら時々時計を見て、その到着を待ちわびていた。
鍵が開く音が聞こえて、母と私は同時に玄関を振り向いた。私は駆け足になっては不自然だと、逸る気持ちを抑えて玄関に足を運ぶ。
玄関で初めて彼と会った私は、たぶん驚いた顔をしていた。
「初めまして。デニス・グリーンといいます。イングランドから来ました」
その流暢な日本語が意外だっただけでなく、彼は宝石のような冴えた空気をまとっていた。
さっぱりと切りそろえた金髪、にこりともしない仮面のような顔立ちの中、緑の目だけが光を放っていた。
一目見て、冷たそうな外国人だと思った。もしかして青い血が流れていたりするんじゃないかと考えたほどだった。
でもきっと、自分だってそうであるように、彼だって緊張をまとって海を渡ってきただろうと思った。
私はたぶんぎこちなく、けれどせいいっぱいの笑顔を浮かべて言った。
「福地智子です。……ようこそ」
彼は一息分だけ戸惑ってから表情を緩めてくれて、私を安心させてくれた。
それが、私とデニスの出会いだった。
デニスを迎えた初めての夕食、私ははじめ、ほとんど自分から言葉をかけることができなかった。
彼とはじめから和やかに話したのは母だった。母は今までの留学生たちと変わりなく彼に接しようと決めているようだった。
母は彼に食事を勧めながら、驚いた様子でうなずく。
「じゃあデニス君は智子と同い年なのね。大学生だと聞いていたけど、飛び級だとは知らなかったわ」
「日本では飛び級は少ないと聞きましたが、英国では周りにも相当いました。それほど珍しいものではないのです」
デニスは日本人より日本語を綺麗に話してみせた。食事の仕方だって、箸も椀も手足の延長のように扱うほど上手だった。
父は彼の食事ぶりに安心しながら彼を気遣う。
「よく食べてくれてうれしいけれど、苦手なものは無理をしなくていいよ。慣れない食事だろうから」
「ありがとうございます。ただテーブルマナーで無作法があったら、遠慮なく教えてください」
その育ちの良さは、彼から漏れ聞いた暮らしからも察しがついた。
「家庭教師を雇って練習しましたが、伝え聞いた話とは違うところもあると思うのです」
話の中で、デニスの父は英国の地方に居館を持つ家系だと聞いた。古い時代なら、彼は召使にかしずかれて過ごしていたらしかった。
「ごちそうさまでした。おいしかったです」
デニスは出された食事をきちんと完食して、丁寧に手を合わせて食事を終えた。そのそつのなさが、私には尊敬と一緒に緊張を抱かせた。
完璧すぎて、ちょっと怖かった。何を考えているのかわからなくて、私はただ横目で彼をみつめていた。
デニスはちらと私を横目で見たが、無理に私に話しかけようとはしなかった。彼には私の恐れを読み取って遠慮する繊細さもあるらしかった。
私たちはお互い構えながら一昼夜を過ごして、翌日の夕方まで何も話さなかった。
でも同じ家の中にいて、緊張しながら過ごし続けるのはお互い良くない。そう先に気づいて、沈黙を破ったのはデニスの方だった。
私がお風呂から上がって来て、彼に次だよと伝えに言った時、彼は自分から廊下に出てきて言った。
「智子さん。教えて頂きたいことがあるのですが」
デニスはそれ以上ない丁寧さで、そっと私に話しかけてきた。
「大きな雑貨店に行きたいのですが、どこかご存じですか?」
「何を探しているんですか?」
私が問い返すと、彼は言葉に詰まる素振りを見せた。
「それは……特に決まっていませんが」
デニスの困った様子に、私は彼の繊細さを見ることになった。
たぶん彼は、私とコミュニケーションを取ろうと懸命に話題をみつけて言葉をかけたんだろう。
私は不器用に差し伸べられたような手のような言葉に、柔らかな親しみを抱いた。
私はにこっと笑って言う。
「ぶらぶら歩きたい感じ? そういうときありますよね」
私は見たこともない外国から来たこの少年も、私と同じようなことを考えるんだと思った。
「明日は日曜だけど、何か予定あります?」
「いえ、特には」
「じゃ、一緒にデパートに行きませんか? 雑貨エリアが三フロアもあるところなんです」
私は彼が差し伸べてくれた手に、ぽんと親しみを返すようにして言った。
「端から端まで見ているだけで一日終わっちゃう。見ているだけでも楽しいですよ」
「僕はいいのですが、智子さんの予定には差しさわりありませんか?」
「うん……おっと。それと、もう一つ」
私は人差し指で一を作って、言葉遣いをくだけた調子に変えた。
「私のことは智子でいいよ。敬語も要らない。私たち同い年だし、これから同じ家で暮らすルームメイトなんだから」
「……そう思ってもらえるなら」
デニスは私の目を見てうなずいた。
「ぜひ連れていって。よろしく、智子」
私はその緑の瞳を見返しながら、話してみればこの人のことを理解できるかもしれないと思ったのだった。