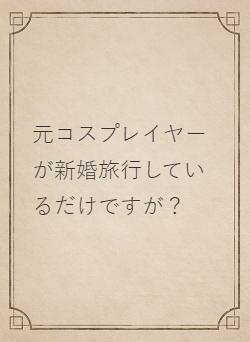・
・【火曜日の憂鬱】
・
正直高校へ行く足取りが今日は重かった。
何故なら早速今日の放課後から一緒に街を歩いて、いろいろやっていくという話になってしまったからだ。ラインでの会話でそうなってしまった。マジで文字だけのコミュニケーションもムズイ。
俺は家でゲームがしたいだけなのに。
知ってるよ、知ってる、高校生活は他人と関わることが醍醐味で、それを味わいたかった自分もいたことを。
でも何か、想像と違うんだよな、俺は本当の友達と一緒に家でゲームをしたかっただけなんだよな。
外を歩く、しかも女子と、いつあの不機嫌な顔になるか分からない女子と!
爆発するまで何も言わないで、いざ爆発したら最低最悪なことをしてくる女子と!
結局今日は時間ギリギリに登校して、席に着いた。
授業は相変わらずいつも通りって感じ。
間の休みになったその時だった。
「おはよ! 今日珍しく遅かったね! 夢限くん!」
なんと真凛さんが普通に話し掛けてきたのだ。
うわっ、何かキツイ……周りからどう思われているか心配になってきた……他のクラスメイトから何も思われていないかな、急にイジられるようになったとか思われていないかな。
女子にイジられるランクになったとか、思われたらマジでキツイ……。
でも真凛さんもすぐに他の友達のほうへ行って、俺は特にクラスメイトから怪しい視線を注がれることは無かった。
危ねぇ、真凛さんって学校でも普通に話し掛けてくるほうなの?
しかも珍しく遅かったとか、そんなに俺のこと、前段階からチェックしている感じだったの? いやそうだったみたいだけども。
ちょっと安易に教室にいるのは危険だなと思って、俺はそこから中休みになる度に、教室から出て行って、誰もいないほうに行くことにした。
それを昼休みにもやっている時に、俺は何をやっているんだという虚無感に襲われた。何この自意識過剰、キモイんじゃないか? いやでもそんなキモイ俺のことなんて誰も見ていないから大丈夫なのか? そもそも何で俺は逃げているんだ? 俺は一体何から逃げているんだ? 何で俺はずっとこうやって逃げていないとダメなんだ? ずっとずっと全てのことから逃げてきて、このまま逃げ切れるかなと思ったら、急に真凛さんに捕まってしまい、なし崩し的に一緒にゲーム作りをするようになって。
でも。
あの笑顔に一瞬救われて。
俺は何なんだ、否、真凛さんにとって俺って何なんだ、って考えることが何かキモ過ぎる、なんでも無いだろ、あえて言えばビジネスパートナー? まあそうだよな、そういうことだよな、一緒にゲームを作る契約をした人、ならば報酬が欲しいけども、でもそういうのは無いっぽい、いつかあるのかな、出来高払い? それとも友達価格? 友達じゃないのに? 何なんだ、本当どうしたんだ、俺の人生、いやもういい、教室に戻ろう、俺は教室に戻る。
戻ってくると、真凛さんはいなくて、ホッと胸をなで下ろしている自分も嫌だ。
何でこんなビクビクしないといけないんだ、でもビクビクしてしまうような人間を作り上げたのは自分だ。全部自己責任だ。自己責任なんて言葉は大嫌いだ。何でもかんでも自分のせいってそんなことないだろ。大体環境のせいだろ。環境のせいにしてもいいだろ。そう言えば誰も傷つかないだろ。自分が傷つくなんて嫌だよ。嫌だよ。もう嫌だよ。
あぁーぁ、もう、と、俺は机に突っ伏して寝ているフリをした。これもカッコ悪いのに。きっと俺は周りから指を差されて笑われているんだろうな。もういいよ、好きに笑えよ。
昼休みも終わり、授業が再開された。
もはや俺にとっては授業がオアシスだ。
生き生きと生きている。
放課後になったところで、俺は動けなくなった。
だってきっと真凛さんが俺に何かアクションを仕掛けてくるだろうから、ちゃんと返事してダサくならないようにしないといけない。
一方的に真凛さんが喋っているところを人に見られたら、一方的にイジられている人に見られてしまうだろうから。
真凛さんはどうやら他の友達の誘いを断っているみたいだ。
ヤンキーっぽい金髪ソフトリーゼントの男子・加賀美昇介や、黒ギャルで黄緑髪の鈴木瑠璃から思い切り腕を引っ張られているが、耐えていた。
なんとなく真凛さんのほうを目で追っていると、一瞬鈴木瑠璃がこっちのほうを見て、すぐに視線を逸らした。
ヤバイ、キモイヤツと目が合ったみたいな顔された。絶対そうだ。うわぁぁああ、真凛さんのほうなんて見てなきゃ良かった……最悪……なのは、鈴木瑠璃のほうか、マジでゴメンなさい……。
机に座った状態で俯いていると、横から真凛さんの声がした。
「遅くなってゴメン! 一緒に街を見て回ろうか! まずは近くの商店街から!」
俺はゆっくり首を向いて、
「いいよ、真凛さん。友達を優先しなよ」
という小さい声が出た。
すると真凛さんは俺の腕を引っ張って、こう言った。
「いこうよ! アタシはこれが楽しみで止まらなかったんだから!」
何がそんな楽しみなんだ、俺がその楽しみの中にいるのか? いや俺はただの刺身のツマみたいなもんで、いてもいなくてもどうでも良くて、とか思っていると、
「立って! 歩いて! 行こう! ゲーム作り!」
まだ教室に残っていた他のクラスメイトたちの目を感じて、このままグズっていたらキモイだろうから、スクッと立ち上がった俺は、
「じゃ、じゃあ行こうか」
とどもりながらも相槌を打って、一緒に校門を出た。
その間もずっとゲームの話をしている。
結局一方的に聞いて相槌を打っているだけだけども、何か別にそんな悪くはなくて。全部知っている話だし。
俺は真凛さんに先導されるがまま、商店街へやって来た。
ここは昔ながらの商店街で、八百屋や肉屋が未だ現役で商売をしている。小さな本屋や服屋も並んでいる。
火曜日の憂鬱、なんて思っていたけども、今は別にそんなことないなと思っていると、早速八百屋があったので、真凛さんが、
「拡張現実のRPGを作ろうと思っているんですが、何か要望は無いですかって聞いてみようっと」
と言い出して、俺は『んっ?』と思ってしまった。
いや、どうしよう、言ってもいいのかな、でも言わないと、と思っている間に真凛さんはなんと八百屋の店主さんに話し掛けてしまったのだ。
「すみません! 拡張現実のRPGを作ろうと思っているんですが、何か要望は無いですか!」
すると八百屋の店主さんは案の定、
「は? 何? というか忙しいから、野菜買う以外話し掛けないでくれ!」
と手でしっしっとするようなポーズをとられてしまった。
真凛さんは不満そうな表情になりながら、
「ちょっとぉ! 今町おこしでそういう計画があってぇ!」
「子供が適当に。何がぁ? 毛穴拡張? の現実?」
「毛穴なんて拡張しませんよ! カスが詰まっちゃうじゃないですか! 拡張現実です! ゲームです!」
「ゲームなんてやんねぇわ! 大人は仕事しているの! 子供が訳分かんないこと言うな! 現実とゲームの区別がついていないんじゃないかぁっ?」
「ちょっとぉぉおおおおおお!」
真凛さんの表情にはもはや『うっ』が出なかった。激高し過ぎていたから。
だから、
「真凛さん、ちょっと落ち着いて。一旦こっち来てください」
と何か敬語で言ってしまうと、真凛さんはかなり不服そうな表情だけども、なんとか八百屋から離れた場所に来てくれたので、もうえぇいままよといった感じで言うことにした。
「急に、そういうこと言われても、誰も分かんないです」
「ちょっと夢限くん! 敬語やめて!」
「えっと、その、とにかく、実地調査と言うから、俺たちが適当に見て回ると思ったら、要望聞くの?」
「当たり前じゃん! このゲームはみんなで作るんだから!」
「それなら根回しが必要かな、と。例えばお店屋さん用にチラシを作っておくとか、こっちのチラシは勿論、町のほうからもチラシを配っておいてもらう、とか。町が許可しているようなシールを貼ってこのチラシは公式ですよ、と伝えないと」
真凛さんは肩で息するほどに怒っていたけども、徐々に落ち着いてきて、
「分かったかもしれない……」
と言って肩を落とした。
「というわけで真凛さん、まずはチラシを作りましょう。お店屋さんの意見も聞くならば」
「だから敬語やめて! 昨日みたいに喋ろうよ!」
「いやそれは真凛さんが若干あらぶっていたから」
「アタシはもう大丈夫! 冷静沈着もち!」
俺はスルーしようかどうか迷ったけども、スルーしたら可哀想だし、何ならこのスルーで不機嫌になる可能性も否めなかったので、
「巾着もちみたいに言うな、おでんくんか」
と言っておくと、
「おでんくん面白いよね!」
と返ってきたので、合ってたと思って、ホッと胸をなで下ろした。
その後は、バイバイする流れになって、俺は真凛さんと別れ、帰ってきたところで、自分の部屋でゲームをし始めた。
あのままチラシ作りをどちらかの家で、というのも可能性としてはありえたけども、俺が「最初から根詰めても」と言ったら結構素直に引いてくれた。
何か、俺が思うに、激高したところを見られた恥ずかしさみたいなもんもあったように思える。
まあ俺みたいなもんが勝手に考えることさえおこがましいけども。
・【火曜日の憂鬱】
・
正直高校へ行く足取りが今日は重かった。
何故なら早速今日の放課後から一緒に街を歩いて、いろいろやっていくという話になってしまったからだ。ラインでの会話でそうなってしまった。マジで文字だけのコミュニケーションもムズイ。
俺は家でゲームがしたいだけなのに。
知ってるよ、知ってる、高校生活は他人と関わることが醍醐味で、それを味わいたかった自分もいたことを。
でも何か、想像と違うんだよな、俺は本当の友達と一緒に家でゲームをしたかっただけなんだよな。
外を歩く、しかも女子と、いつあの不機嫌な顔になるか分からない女子と!
爆発するまで何も言わないで、いざ爆発したら最低最悪なことをしてくる女子と!
結局今日は時間ギリギリに登校して、席に着いた。
授業は相変わらずいつも通りって感じ。
間の休みになったその時だった。
「おはよ! 今日珍しく遅かったね! 夢限くん!」
なんと真凛さんが普通に話し掛けてきたのだ。
うわっ、何かキツイ……周りからどう思われているか心配になってきた……他のクラスメイトから何も思われていないかな、急にイジられるようになったとか思われていないかな。
女子にイジられるランクになったとか、思われたらマジでキツイ……。
でも真凛さんもすぐに他の友達のほうへ行って、俺は特にクラスメイトから怪しい視線を注がれることは無かった。
危ねぇ、真凛さんって学校でも普通に話し掛けてくるほうなの?
しかも珍しく遅かったとか、そんなに俺のこと、前段階からチェックしている感じだったの? いやそうだったみたいだけども。
ちょっと安易に教室にいるのは危険だなと思って、俺はそこから中休みになる度に、教室から出て行って、誰もいないほうに行くことにした。
それを昼休みにもやっている時に、俺は何をやっているんだという虚無感に襲われた。何この自意識過剰、キモイんじゃないか? いやでもそんなキモイ俺のことなんて誰も見ていないから大丈夫なのか? そもそも何で俺は逃げているんだ? 俺は一体何から逃げているんだ? 何で俺はずっとこうやって逃げていないとダメなんだ? ずっとずっと全てのことから逃げてきて、このまま逃げ切れるかなと思ったら、急に真凛さんに捕まってしまい、なし崩し的に一緒にゲーム作りをするようになって。
でも。
あの笑顔に一瞬救われて。
俺は何なんだ、否、真凛さんにとって俺って何なんだ、って考えることが何かキモ過ぎる、なんでも無いだろ、あえて言えばビジネスパートナー? まあそうだよな、そういうことだよな、一緒にゲームを作る契約をした人、ならば報酬が欲しいけども、でもそういうのは無いっぽい、いつかあるのかな、出来高払い? それとも友達価格? 友達じゃないのに? 何なんだ、本当どうしたんだ、俺の人生、いやもういい、教室に戻ろう、俺は教室に戻る。
戻ってくると、真凛さんはいなくて、ホッと胸をなで下ろしている自分も嫌だ。
何でこんなビクビクしないといけないんだ、でもビクビクしてしまうような人間を作り上げたのは自分だ。全部自己責任だ。自己責任なんて言葉は大嫌いだ。何でもかんでも自分のせいってそんなことないだろ。大体環境のせいだろ。環境のせいにしてもいいだろ。そう言えば誰も傷つかないだろ。自分が傷つくなんて嫌だよ。嫌だよ。もう嫌だよ。
あぁーぁ、もう、と、俺は机に突っ伏して寝ているフリをした。これもカッコ悪いのに。きっと俺は周りから指を差されて笑われているんだろうな。もういいよ、好きに笑えよ。
昼休みも終わり、授業が再開された。
もはや俺にとっては授業がオアシスだ。
生き生きと生きている。
放課後になったところで、俺は動けなくなった。
だってきっと真凛さんが俺に何かアクションを仕掛けてくるだろうから、ちゃんと返事してダサくならないようにしないといけない。
一方的に真凛さんが喋っているところを人に見られたら、一方的にイジられている人に見られてしまうだろうから。
真凛さんはどうやら他の友達の誘いを断っているみたいだ。
ヤンキーっぽい金髪ソフトリーゼントの男子・加賀美昇介や、黒ギャルで黄緑髪の鈴木瑠璃から思い切り腕を引っ張られているが、耐えていた。
なんとなく真凛さんのほうを目で追っていると、一瞬鈴木瑠璃がこっちのほうを見て、すぐに視線を逸らした。
ヤバイ、キモイヤツと目が合ったみたいな顔された。絶対そうだ。うわぁぁああ、真凛さんのほうなんて見てなきゃ良かった……最悪……なのは、鈴木瑠璃のほうか、マジでゴメンなさい……。
机に座った状態で俯いていると、横から真凛さんの声がした。
「遅くなってゴメン! 一緒に街を見て回ろうか! まずは近くの商店街から!」
俺はゆっくり首を向いて、
「いいよ、真凛さん。友達を優先しなよ」
という小さい声が出た。
すると真凛さんは俺の腕を引っ張って、こう言った。
「いこうよ! アタシはこれが楽しみで止まらなかったんだから!」
何がそんな楽しみなんだ、俺がその楽しみの中にいるのか? いや俺はただの刺身のツマみたいなもんで、いてもいなくてもどうでも良くて、とか思っていると、
「立って! 歩いて! 行こう! ゲーム作り!」
まだ教室に残っていた他のクラスメイトたちの目を感じて、このままグズっていたらキモイだろうから、スクッと立ち上がった俺は、
「じゃ、じゃあ行こうか」
とどもりながらも相槌を打って、一緒に校門を出た。
その間もずっとゲームの話をしている。
結局一方的に聞いて相槌を打っているだけだけども、何か別にそんな悪くはなくて。全部知っている話だし。
俺は真凛さんに先導されるがまま、商店街へやって来た。
ここは昔ながらの商店街で、八百屋や肉屋が未だ現役で商売をしている。小さな本屋や服屋も並んでいる。
火曜日の憂鬱、なんて思っていたけども、今は別にそんなことないなと思っていると、早速八百屋があったので、真凛さんが、
「拡張現実のRPGを作ろうと思っているんですが、何か要望は無いですかって聞いてみようっと」
と言い出して、俺は『んっ?』と思ってしまった。
いや、どうしよう、言ってもいいのかな、でも言わないと、と思っている間に真凛さんはなんと八百屋の店主さんに話し掛けてしまったのだ。
「すみません! 拡張現実のRPGを作ろうと思っているんですが、何か要望は無いですか!」
すると八百屋の店主さんは案の定、
「は? 何? というか忙しいから、野菜買う以外話し掛けないでくれ!」
と手でしっしっとするようなポーズをとられてしまった。
真凛さんは不満そうな表情になりながら、
「ちょっとぉ! 今町おこしでそういう計画があってぇ!」
「子供が適当に。何がぁ? 毛穴拡張? の現実?」
「毛穴なんて拡張しませんよ! カスが詰まっちゃうじゃないですか! 拡張現実です! ゲームです!」
「ゲームなんてやんねぇわ! 大人は仕事しているの! 子供が訳分かんないこと言うな! 現実とゲームの区別がついていないんじゃないかぁっ?」
「ちょっとぉぉおおおおおお!」
真凛さんの表情にはもはや『うっ』が出なかった。激高し過ぎていたから。
だから、
「真凛さん、ちょっと落ち着いて。一旦こっち来てください」
と何か敬語で言ってしまうと、真凛さんはかなり不服そうな表情だけども、なんとか八百屋から離れた場所に来てくれたので、もうえぇいままよといった感じで言うことにした。
「急に、そういうこと言われても、誰も分かんないです」
「ちょっと夢限くん! 敬語やめて!」
「えっと、その、とにかく、実地調査と言うから、俺たちが適当に見て回ると思ったら、要望聞くの?」
「当たり前じゃん! このゲームはみんなで作るんだから!」
「それなら根回しが必要かな、と。例えばお店屋さん用にチラシを作っておくとか、こっちのチラシは勿論、町のほうからもチラシを配っておいてもらう、とか。町が許可しているようなシールを貼ってこのチラシは公式ですよ、と伝えないと」
真凛さんは肩で息するほどに怒っていたけども、徐々に落ち着いてきて、
「分かったかもしれない……」
と言って肩を落とした。
「というわけで真凛さん、まずはチラシを作りましょう。お店屋さんの意見も聞くならば」
「だから敬語やめて! 昨日みたいに喋ろうよ!」
「いやそれは真凛さんが若干あらぶっていたから」
「アタシはもう大丈夫! 冷静沈着もち!」
俺はスルーしようかどうか迷ったけども、スルーしたら可哀想だし、何ならこのスルーで不機嫌になる可能性も否めなかったので、
「巾着もちみたいに言うな、おでんくんか」
と言っておくと、
「おでんくん面白いよね!」
と返ってきたので、合ってたと思って、ホッと胸をなで下ろした。
その後は、バイバイする流れになって、俺は真凛さんと別れ、帰ってきたところで、自分の部屋でゲームをし始めた。
あのままチラシ作りをどちらかの家で、というのも可能性としてはありえたけども、俺が「最初から根詰めても」と言ったら結構素直に引いてくれた。
何か、俺が思うに、激高したところを見られた恥ずかしさみたいなもんもあったように思える。
まあ俺みたいなもんが勝手に考えることさえおこがましいけども。