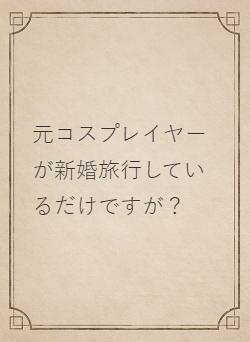・
・【天満真凛の部屋】
・
天満真凛の部屋が開くと、天満真凛が良い笑顔で顔を出してきて、
「大丈夫だよ! めっちゃ良い匂いするから嗅いでみていいよ!」
そんなこと宣言する女子、いないだろ。
絶対何らかのフレグランスを直前で撒いただけだろ。
俺はまあ会釈しながら、天満真凛の部屋へ入ると、思った以上に女子の部屋で『うっ』ってなってしまった。
あの、トラウマを作り上げた女子がリュックサックに付けていたキーホルダーのような世界観というか、端的に思えば、ハートマークがいっぱいというか。
ゲームのキャラクターのぬいぐるみもあえてハートマークをあしらった特別仕様のヤツを買ってるし。もっと世界観遵守のヤツにしろよ。
「適当に座っていいよ! むしろ座って! 立っていられると威圧感あるから! そういう身長差!」
そう言って手で促したので、座布団の上に座ると、天満真凛も丸テーブルを隔てて俺と対面に座った。
天満真凛は拳を突き上げて、
「じゃあ早速考えていこう!」
と言ったんだけども、なんというか、どう手掛かりを探っていくというか、まあそうだな、まずはこうだろうな、
「天満真凛はどんなイメージのモノを考えているんだ」
と俺が素直に聞くことにすると、天満真凛は明らかに不機嫌そうな顔をして、また『うっ』となってしまうと、
「フルネームで呼ばないでっ、距離が遠い!」
そりゃそんな急に近付くことはできないだろうと思っているんだけども、本人にそんな顔をされてしまったら、じゃあ、
「天満さん」
「苗字じゃお兄ちゃんと一緒じゃん!」
いや急に下の名前って距離を詰めすぎでは。
でも今度は頬を膨らませてプリプリと怒っている感じ。これはさすがに怖くない。だからこのまま天満さんでいけそうな気もするけども、またここから不満な方向に振り切られても困るので、ここはもう本人の意思を尊重して、
「じゃあ真凛さん」
「それでいこう! アタシ、真凛という名前が気に入っているから!」
自分の名前が好きということは両親と関係が良好なんだろうな。
まあいいや、
「じゃあ真凛さん、どんなイメージのモノを考えているんだ?」
「アタシが決めちゃっていいのぉっ?」
と尻上がりの疑問文をウザったく決めてきた天満真凛……いや脳内でも真凛さんにしよう、言い間違えると面倒そうだ。
「決めてよ。そもそも土台はあるんだろ?」
「いやあんまりできていないというか、スクラップ&ビルドというか……」
「というかさ、そんな依頼あるの?」
「依頼はあるよ!」
そう言ってちょっと目を見開いた真凛さん。
前のめりになって身を乗り出して、
「実際にこの秋葉町から依頼があるんだよ!」
でも俺は、きっと懐疑的な表情をしていたんだろう。
真凛さんは少しムッとしてから、
「お兄ちゃんはね! その道では有名なプログラマーなんだよ! だから本当ちゃんとした依頼なんだ!」
「じゃあなおさらちゃんとしないとダメだなぁ」
とただの相槌のつもりでそう言ったんだけども、真凛さんは目を輝かせて、
「分かってくれる! そうだようねぇ!」
握手のような手を差し出してきたので、どうしようと思って、でも手は引っ込めておくと、真凛さんが、
「そこも分かっておくれぇい!」
と言ってヘッドバンキングしてきて、リアクションデカいなぁ、と思ってしまった。
いやいや、というか、マジで、
「じゃあなおさら骨格はあるんだろ、それをまず俺に教えてくれよ」
真凛さんは普通にまた背筋を伸ばして座った状態になって、
「骨格もまだあってないようなもんなんだけども、アタシのイメージとしては壮大なRPGで、道端で雑魚とエンカウントして、それでレベル上げて、どんどん強くなるボスを順番に倒して最後はこの街を救うみたいな、王道のヤツを考えているよ」
今の話を聞いて、俺は正直う~んと思った。
でも言っていいのか、言ったらまた不機嫌な顔になってトラウマが想起されてしまうようなことになりそうな。
どうしよう、言うべきか、いや言うべきなんだろうな、でも、なぁ……そんなことを考えていると、真凛さんがまた身を乗り出して、こう言った。
「言いたいことがあったら何でも言ってよ! そのためのパートナーでしょ!」
と、若干への字口でそう言ったので、ここは言わないほうが不機嫌になるパターンかと思って、言うことにした。
「道端でエンカウントするって歩きスマホってこと? 媒体はスマホだよな」
「勿論闘う時は立ち止まるように指導するよ! ゲーム内でもそういう指示は出すよ!」
「でもそういうの、子供とかできないでしょ。危ないだろ」
真凛さんは眉毛を八の字にさせて、しおしおとしおれるようにうなだれた。
だから、
「歩数計と連動して、歩くだけで経験値が上がるようにしたらいいじゃん」
すると急に真凛さんの目が輝いて、
「それだ! 歩数計と連動だ! それが経験値になる! 絶対そっちのほうがいい!」
と叫んで、なんなんだコイツとは思った。
でもまあ手放しで褒めてくれて、気分が少し上がっていると、真凛さんの部屋がノックされて、あぁ! ツツモタセ! と一瞬にして青ざめると、真凛さんの兄が入ってきて一言。
「声がデカ過ぎるし、僕もそう助言しただろ、最初の部分は」
と言いながら、俺の隣に座ってきた。
真凛さんは、
「えっ? あぁ、そうだったけぇ?」
と、あからさまにとぼける感じで、あぁ、これはもしかすると俺を乗らせるために仕組んだ罠のようなもんだったのかもな、と思いつつも、同時にツツモタセ的な罠じゃなくてホッとした。
いやまだ真凛さんの兄が隣に座って突然殴ってくるとかあるかもしれないけども。いつでも怪しい動きには反応できるようにはしておこう。
でも何か、女子のこういう演技で罠を作ってくる感じ、マジで苦手だ。単純にバカにされていると思う。
真凛さんは相変わらず、えぇーぇみたいな顔をしていて、本当に腹立つ。
すると真凛さんの兄が、
「その顔、マジでやめろ。マジのミスを嘘のミスみたいにして誤魔化す癖、僕嫌いだから」
真凛さんは即座に焦りながら、
「いやそんなこと言わないでよ!」
「最悪僕にはいいけども、石破ってヤツには絶対すんなよ、絶対腹立つはずだから」
……マジのミスだったってこと? いやそういう本当のところは本人しか分かんないもんな。その本人にしか分かんないことを俺がぐちぐち考えてもしょうがないというのもあるけども、でも俺は俺で考えてしまうんだよ。女子の裏の顔というヤツを。そもそも一緒にバスに乗っていた他の男子たちも俺たちのことを馬鹿にするように誰も本当のことを言わなかったし、この世界は本当に人間の敵ばかり敵ばかり敵ばかり、マジでもう帰りたい。
でも急に帰るとアレだし、一応やるようなこと言っちゃったし、一緒に考えるしかないか、少なくても今は。
そんなことを考えていると、真凛さんが空気を変えるように、少し大きな声で、
「で! 夢限くんは何か良い案無いっ?」
すると真凛さんの兄もじっとこっちを見てきて、それはそれで『うっ』となってきた。何か新しいトラウマ形成されそう。年上から高圧的に何か言われるというトラウマが。
でもこんな易々とトラウマばっか作ってたまるかと思って、芯の食ったことを言ってやろうと思って、こう言うことにした。
「決められたボスを順番に闘うよりも、ボスのレベルは全部一定にすればいいんじゃないか? ボスって観光地とかに出てくるんだろ? なら好きに巡れたほうがいいじゃん」
すると真凛さんはう~んと唸ってから、
「それじゃあどんどん簡単にならない? 歩く度に経験値上がるんでしょ?」
「だからボスを倒すごとに、他のボス全部のレベルを上げればいい。この順番で、って運営の通り歩かされるのはダルいでしょ」
「そっか! それなら好きに観光できるもんね!」
と右手で拳を作って、左手を受け皿にして、ポンッとやった真凛さん。そういう動き、本当にするヤツいるんだ。
すると真凛さんの兄が、
「結構いいな」
と呟いて、去っていった。
なんとか怒られなくてホッと胸をなで下ろした俺。というかマジでツツモタセ的なことは無いんかい。マジでゲーム作るって話なんかい。
真凛さんは出ていく兄に、舌をベッと出していた。
いや同じゲーム作り仲間なんでしょ、プログラムしてくれるんでしょ、そんなアクション、と思っていると、また笑顔でこっちを見て、
「じゃあドンジャラ作っていこう!」
「そんなドラえもんの麻雀みたいな効果音」
とつい反射で言ってしまうと、
「ちょっとぉ! ドンジャラはしないよぉ!」
と何か照れて笑った真凛さん。
照れるようなことは無いけども、効果音が変だっただけだけども。
いやでも実際、あんま反射で喋ったら何が起きるか分からないから気を付けないとな。
余計なことを喋ると余計なことが起きるから。
さて、と思って真凛さんが次に何を喋るか待っていると、真凛さんは俺のほうをニコニコしながら見るだけで、否、若干期待感に胸を膨らませて、目を輝かせて見てくる。
これって俺が主導権を握って喋っていくヤツ……? そんなわけあるか、俺はお呼ばれされたほうだぞ。
俺はちょっと俯いて、次の言葉を引き出そうと思ったんだけども、そもそも俯くことが俺の引き出す最初の一歩ってダサくないか?
いやでも、まあいいか、もういいか、ここはとりあえず、
「で、真凛さんの意見は、何か、その」
とどもってしまい、恥ずかしかった。
でも急に司会者みたいに話を振ったことなんてないから、やり方が分からない、というより、何俺がそんなことやってんの? という自意識のせいなのかもしれない。
真凛さんは小首を傾げてから、
「むしろ夢限くんのターンだよっ?」
と言ってそんなはずは無いだろと思った。
いや俺が意見を言うターンだったのか、じゃあ何か言うか、う~、どうしよう。
今のところは(向こうが仕掛けていた乗せるだけの罠だった可能性もあるから)良かったけども、ここからは何かハズレを言いたくない。
『それはちょっと』とか言われたらマジでダサいし、すぐに家へ帰りたくなるだろう。
でもこのまま黙ってしまうことのほうがもっとカッコ悪いし、えぇい、もう言うしかない。
「まずその、ボスは一定数を倒せばラスボスに挑めることにして、全部回らなくてもいいことにしたら、どうだ? それとも、それはもう決まってる話だった?」
と何か予防線を張ってしまうところが何かダサい。
予防線を張ったことこそダサいというか。
マジで余計なこと言わなきゃ良かったのに、と鬱になっていると、真凛さんは、
「えーぇ、でも全部の観光地巡ってほしいんじゃん」
「でもほら、さすがに自分の興味無いところ行ってもしょうがないじゃん。あくまでRPGゲームは観光地としてのおまけというか、より楽しむためのモノであるべき、だと思います」
最後敬語みたいになってしまったところ、本当に弱い自分って感じで嫌だ。
どんどん声も先細りになっていって、同級生にこんな感じで、さっきまでちゃんとタメ語で喋れていたのに、あぁ、もう、何でこんなに俺は会話が下手なんだ。
いやそうか、そりゃ当たり前か、ずっと他人と会話しないで生きてきたんだから。下手に決まってる。
でも真凛さんはそんな俺の言葉尻を掴んで馬鹿にしてくるようなヤツではなくて、
「確かに……ゲームを十割全に楽しんでほしいというのはアタシのエゴだもんねぇ、まずは観光ありきだもんね! それアリかも!」
「その分、何度でも挑戦できるような構造にすれば、最終的には十割全に楽しんでもらえるんじゃないっか」
うわっ、変なところで小さい『っ』が入ってしまった。
マジでどうなってんだ俺の喉や口。ダサ過ぎる。
でも真凛さんは全然気にせず、うんうん頷きながら、
「それはいいねぇ! もっといっぱい言って! いっぱい案言って!」
何だか子犬がハシャぐようにそう言ってきた。
そんな欲されると、さすがに饒舌になってくるもので、
「ニューゲームの時は前回の武器や魔法を持っている状態で始められるとかさ」
「いいね! 絶対採用!」
「で、観光地にボスがいいよな、やっぱり。長く滞在してもいい場所だから。お店屋さんには武器や魔法を置くといいかも。あんまり買わないのに長居されても困るし、でもちゃんと一回やって来て、見てもらうキッカケにすることも観光にとっては大切なことだろうから」
と長台詞を喋った時にハッとした。
ヤバイ、調子に乗って喋り過ぎた……ほらぁ! 真凛さん、何かクスクス笑ってる!
こういうのも何かトラウマの、バスに置いてかれた時の窓から聞こえた笑い声を思い出させる……!
「夢限くん! めっちゃ良いアイデアばっかり! アタシの目には狂いが無かったよ! 最高!」
そう言って快活に笑った真凛さんに俺は何だか一瞬救われた気になってしまった。
勝手に救われた気になって本当にキモイんだけども、俺は何だかちょっとだけ、俺なんてもんが存在してもいいのかなと思ってしまった。
俺はその余韻に浸って、ちょっとボーッとしてしまっていると、真凛さんが、
「じゃ! 今の全部書き写すからね!」
と言ってメモ帳とボールペンを取り出して、書き始めた。
一応俺は俺でスマホを出して、今まで言ったことをスマホのメモ帳でまとめていると、あっ、そうだと思って、
「今度はグーグルマップでどこに何を設定するか、決めていくか」
と言うと、真凛さんは顔を上げて、キョトンとした。
いや、俺急に間違えた? そんな変なこと言ったか? と思ったところで、外を見ると、もう夕日が落ちそうになっていた。
あぁ、そうか、
「そろそろ帰る時間か。あんま遅い時間までいるの迷惑だもんな。じゃあ俺が家に帰ったら適当にグーグルマップ見て、どこに何があったほうがあたりを決めておくから・・・」
と言った俺の言葉を遮るように真凛さんはこう言った。
「ううん! 明日から実地調査だよ! 一緒に街を回って考えよう!」
俺は愕然としてしまった。
「一緒に、街を、回って、考えるぅっ?」
声に出すつもりは無かったのに、そう声に出してしまった俺。
真凛さんは屈託の無い笑顔で、
「うん! そう! その場で距離感とかを体感することが一番だよ!」
まさかそんな、街を歩かないといけないなんて……正直面倒だ、運動も苦手だから歩くのも正直嫌だ……。
でも真凛さんはもうその気といった感じで、ワクワクしている。
また不機嫌になられるのも嫌なので、
「じゃ、じゃあ、そういうこと、かっ」
と返事しておくと、真凛さんは、
「あとライン交換しておこう!」
「それはまあ」
と言って交換を普通にしたんだけども、まさか俺が同級生の、それも女子とラインを交換するなんて、と家に帰ってから考えている。
・【天満真凛の部屋】
・
天満真凛の部屋が開くと、天満真凛が良い笑顔で顔を出してきて、
「大丈夫だよ! めっちゃ良い匂いするから嗅いでみていいよ!」
そんなこと宣言する女子、いないだろ。
絶対何らかのフレグランスを直前で撒いただけだろ。
俺はまあ会釈しながら、天満真凛の部屋へ入ると、思った以上に女子の部屋で『うっ』ってなってしまった。
あの、トラウマを作り上げた女子がリュックサックに付けていたキーホルダーのような世界観というか、端的に思えば、ハートマークがいっぱいというか。
ゲームのキャラクターのぬいぐるみもあえてハートマークをあしらった特別仕様のヤツを買ってるし。もっと世界観遵守のヤツにしろよ。
「適当に座っていいよ! むしろ座って! 立っていられると威圧感あるから! そういう身長差!」
そう言って手で促したので、座布団の上に座ると、天満真凛も丸テーブルを隔てて俺と対面に座った。
天満真凛は拳を突き上げて、
「じゃあ早速考えていこう!」
と言ったんだけども、なんというか、どう手掛かりを探っていくというか、まあそうだな、まずはこうだろうな、
「天満真凛はどんなイメージのモノを考えているんだ」
と俺が素直に聞くことにすると、天満真凛は明らかに不機嫌そうな顔をして、また『うっ』となってしまうと、
「フルネームで呼ばないでっ、距離が遠い!」
そりゃそんな急に近付くことはできないだろうと思っているんだけども、本人にそんな顔をされてしまったら、じゃあ、
「天満さん」
「苗字じゃお兄ちゃんと一緒じゃん!」
いや急に下の名前って距離を詰めすぎでは。
でも今度は頬を膨らませてプリプリと怒っている感じ。これはさすがに怖くない。だからこのまま天満さんでいけそうな気もするけども、またここから不満な方向に振り切られても困るので、ここはもう本人の意思を尊重して、
「じゃあ真凛さん」
「それでいこう! アタシ、真凛という名前が気に入っているから!」
自分の名前が好きということは両親と関係が良好なんだろうな。
まあいいや、
「じゃあ真凛さん、どんなイメージのモノを考えているんだ?」
「アタシが決めちゃっていいのぉっ?」
と尻上がりの疑問文をウザったく決めてきた天満真凛……いや脳内でも真凛さんにしよう、言い間違えると面倒そうだ。
「決めてよ。そもそも土台はあるんだろ?」
「いやあんまりできていないというか、スクラップ&ビルドというか……」
「というかさ、そんな依頼あるの?」
「依頼はあるよ!」
そう言ってちょっと目を見開いた真凛さん。
前のめりになって身を乗り出して、
「実際にこの秋葉町から依頼があるんだよ!」
でも俺は、きっと懐疑的な表情をしていたんだろう。
真凛さんは少しムッとしてから、
「お兄ちゃんはね! その道では有名なプログラマーなんだよ! だから本当ちゃんとした依頼なんだ!」
「じゃあなおさらちゃんとしないとダメだなぁ」
とただの相槌のつもりでそう言ったんだけども、真凛さんは目を輝かせて、
「分かってくれる! そうだようねぇ!」
握手のような手を差し出してきたので、どうしようと思って、でも手は引っ込めておくと、真凛さんが、
「そこも分かっておくれぇい!」
と言ってヘッドバンキングしてきて、リアクションデカいなぁ、と思ってしまった。
いやいや、というか、マジで、
「じゃあなおさら骨格はあるんだろ、それをまず俺に教えてくれよ」
真凛さんは普通にまた背筋を伸ばして座った状態になって、
「骨格もまだあってないようなもんなんだけども、アタシのイメージとしては壮大なRPGで、道端で雑魚とエンカウントして、それでレベル上げて、どんどん強くなるボスを順番に倒して最後はこの街を救うみたいな、王道のヤツを考えているよ」
今の話を聞いて、俺は正直う~んと思った。
でも言っていいのか、言ったらまた不機嫌な顔になってトラウマが想起されてしまうようなことになりそうな。
どうしよう、言うべきか、いや言うべきなんだろうな、でも、なぁ……そんなことを考えていると、真凛さんがまた身を乗り出して、こう言った。
「言いたいことがあったら何でも言ってよ! そのためのパートナーでしょ!」
と、若干への字口でそう言ったので、ここは言わないほうが不機嫌になるパターンかと思って、言うことにした。
「道端でエンカウントするって歩きスマホってこと? 媒体はスマホだよな」
「勿論闘う時は立ち止まるように指導するよ! ゲーム内でもそういう指示は出すよ!」
「でもそういうの、子供とかできないでしょ。危ないだろ」
真凛さんは眉毛を八の字にさせて、しおしおとしおれるようにうなだれた。
だから、
「歩数計と連動して、歩くだけで経験値が上がるようにしたらいいじゃん」
すると急に真凛さんの目が輝いて、
「それだ! 歩数計と連動だ! それが経験値になる! 絶対そっちのほうがいい!」
と叫んで、なんなんだコイツとは思った。
でもまあ手放しで褒めてくれて、気分が少し上がっていると、真凛さんの部屋がノックされて、あぁ! ツツモタセ! と一瞬にして青ざめると、真凛さんの兄が入ってきて一言。
「声がデカ過ぎるし、僕もそう助言しただろ、最初の部分は」
と言いながら、俺の隣に座ってきた。
真凛さんは、
「えっ? あぁ、そうだったけぇ?」
と、あからさまにとぼける感じで、あぁ、これはもしかすると俺を乗らせるために仕組んだ罠のようなもんだったのかもな、と思いつつも、同時にツツモタセ的な罠じゃなくてホッとした。
いやまだ真凛さんの兄が隣に座って突然殴ってくるとかあるかもしれないけども。いつでも怪しい動きには反応できるようにはしておこう。
でも何か、女子のこういう演技で罠を作ってくる感じ、マジで苦手だ。単純にバカにされていると思う。
真凛さんは相変わらず、えぇーぇみたいな顔をしていて、本当に腹立つ。
すると真凛さんの兄が、
「その顔、マジでやめろ。マジのミスを嘘のミスみたいにして誤魔化す癖、僕嫌いだから」
真凛さんは即座に焦りながら、
「いやそんなこと言わないでよ!」
「最悪僕にはいいけども、石破ってヤツには絶対すんなよ、絶対腹立つはずだから」
……マジのミスだったってこと? いやそういう本当のところは本人しか分かんないもんな。その本人にしか分かんないことを俺がぐちぐち考えてもしょうがないというのもあるけども、でも俺は俺で考えてしまうんだよ。女子の裏の顔というヤツを。そもそも一緒にバスに乗っていた他の男子たちも俺たちのことを馬鹿にするように誰も本当のことを言わなかったし、この世界は本当に人間の敵ばかり敵ばかり敵ばかり、マジでもう帰りたい。
でも急に帰るとアレだし、一応やるようなこと言っちゃったし、一緒に考えるしかないか、少なくても今は。
そんなことを考えていると、真凛さんが空気を変えるように、少し大きな声で、
「で! 夢限くんは何か良い案無いっ?」
すると真凛さんの兄もじっとこっちを見てきて、それはそれで『うっ』となってきた。何か新しいトラウマ形成されそう。年上から高圧的に何か言われるというトラウマが。
でもこんな易々とトラウマばっか作ってたまるかと思って、芯の食ったことを言ってやろうと思って、こう言うことにした。
「決められたボスを順番に闘うよりも、ボスのレベルは全部一定にすればいいんじゃないか? ボスって観光地とかに出てくるんだろ? なら好きに巡れたほうがいいじゃん」
すると真凛さんはう~んと唸ってから、
「それじゃあどんどん簡単にならない? 歩く度に経験値上がるんでしょ?」
「だからボスを倒すごとに、他のボス全部のレベルを上げればいい。この順番で、って運営の通り歩かされるのはダルいでしょ」
「そっか! それなら好きに観光できるもんね!」
と右手で拳を作って、左手を受け皿にして、ポンッとやった真凛さん。そういう動き、本当にするヤツいるんだ。
すると真凛さんの兄が、
「結構いいな」
と呟いて、去っていった。
なんとか怒られなくてホッと胸をなで下ろした俺。というかマジでツツモタセ的なことは無いんかい。マジでゲーム作るって話なんかい。
真凛さんは出ていく兄に、舌をベッと出していた。
いや同じゲーム作り仲間なんでしょ、プログラムしてくれるんでしょ、そんなアクション、と思っていると、また笑顔でこっちを見て、
「じゃあドンジャラ作っていこう!」
「そんなドラえもんの麻雀みたいな効果音」
とつい反射で言ってしまうと、
「ちょっとぉ! ドンジャラはしないよぉ!」
と何か照れて笑った真凛さん。
照れるようなことは無いけども、効果音が変だっただけだけども。
いやでも実際、あんま反射で喋ったら何が起きるか分からないから気を付けないとな。
余計なことを喋ると余計なことが起きるから。
さて、と思って真凛さんが次に何を喋るか待っていると、真凛さんは俺のほうをニコニコしながら見るだけで、否、若干期待感に胸を膨らませて、目を輝かせて見てくる。
これって俺が主導権を握って喋っていくヤツ……? そんなわけあるか、俺はお呼ばれされたほうだぞ。
俺はちょっと俯いて、次の言葉を引き出そうと思ったんだけども、そもそも俯くことが俺の引き出す最初の一歩ってダサくないか?
いやでも、まあいいか、もういいか、ここはとりあえず、
「で、真凛さんの意見は、何か、その」
とどもってしまい、恥ずかしかった。
でも急に司会者みたいに話を振ったことなんてないから、やり方が分からない、というより、何俺がそんなことやってんの? という自意識のせいなのかもしれない。
真凛さんは小首を傾げてから、
「むしろ夢限くんのターンだよっ?」
と言ってそんなはずは無いだろと思った。
いや俺が意見を言うターンだったのか、じゃあ何か言うか、う~、どうしよう。
今のところは(向こうが仕掛けていた乗せるだけの罠だった可能性もあるから)良かったけども、ここからは何かハズレを言いたくない。
『それはちょっと』とか言われたらマジでダサいし、すぐに家へ帰りたくなるだろう。
でもこのまま黙ってしまうことのほうがもっとカッコ悪いし、えぇい、もう言うしかない。
「まずその、ボスは一定数を倒せばラスボスに挑めることにして、全部回らなくてもいいことにしたら、どうだ? それとも、それはもう決まってる話だった?」
と何か予防線を張ってしまうところが何かダサい。
予防線を張ったことこそダサいというか。
マジで余計なこと言わなきゃ良かったのに、と鬱になっていると、真凛さんは、
「えーぇ、でも全部の観光地巡ってほしいんじゃん」
「でもほら、さすがに自分の興味無いところ行ってもしょうがないじゃん。あくまでRPGゲームは観光地としてのおまけというか、より楽しむためのモノであるべき、だと思います」
最後敬語みたいになってしまったところ、本当に弱い自分って感じで嫌だ。
どんどん声も先細りになっていって、同級生にこんな感じで、さっきまでちゃんとタメ語で喋れていたのに、あぁ、もう、何でこんなに俺は会話が下手なんだ。
いやそうか、そりゃ当たり前か、ずっと他人と会話しないで生きてきたんだから。下手に決まってる。
でも真凛さんはそんな俺の言葉尻を掴んで馬鹿にしてくるようなヤツではなくて、
「確かに……ゲームを十割全に楽しんでほしいというのはアタシのエゴだもんねぇ、まずは観光ありきだもんね! それアリかも!」
「その分、何度でも挑戦できるような構造にすれば、最終的には十割全に楽しんでもらえるんじゃないっか」
うわっ、変なところで小さい『っ』が入ってしまった。
マジでどうなってんだ俺の喉や口。ダサ過ぎる。
でも真凛さんは全然気にせず、うんうん頷きながら、
「それはいいねぇ! もっといっぱい言って! いっぱい案言って!」
何だか子犬がハシャぐようにそう言ってきた。
そんな欲されると、さすがに饒舌になってくるもので、
「ニューゲームの時は前回の武器や魔法を持っている状態で始められるとかさ」
「いいね! 絶対採用!」
「で、観光地にボスがいいよな、やっぱり。長く滞在してもいい場所だから。お店屋さんには武器や魔法を置くといいかも。あんまり買わないのに長居されても困るし、でもちゃんと一回やって来て、見てもらうキッカケにすることも観光にとっては大切なことだろうから」
と長台詞を喋った時にハッとした。
ヤバイ、調子に乗って喋り過ぎた……ほらぁ! 真凛さん、何かクスクス笑ってる!
こういうのも何かトラウマの、バスに置いてかれた時の窓から聞こえた笑い声を思い出させる……!
「夢限くん! めっちゃ良いアイデアばっかり! アタシの目には狂いが無かったよ! 最高!」
そう言って快活に笑った真凛さんに俺は何だか一瞬救われた気になってしまった。
勝手に救われた気になって本当にキモイんだけども、俺は何だかちょっとだけ、俺なんてもんが存在してもいいのかなと思ってしまった。
俺はその余韻に浸って、ちょっとボーッとしてしまっていると、真凛さんが、
「じゃ! 今の全部書き写すからね!」
と言ってメモ帳とボールペンを取り出して、書き始めた。
一応俺は俺でスマホを出して、今まで言ったことをスマホのメモ帳でまとめていると、あっ、そうだと思って、
「今度はグーグルマップでどこに何を設定するか、決めていくか」
と言うと、真凛さんは顔を上げて、キョトンとした。
いや、俺急に間違えた? そんな変なこと言ったか? と思ったところで、外を見ると、もう夕日が落ちそうになっていた。
あぁ、そうか、
「そろそろ帰る時間か。あんま遅い時間までいるの迷惑だもんな。じゃあ俺が家に帰ったら適当にグーグルマップ見て、どこに何があったほうがあたりを決めておくから・・・」
と言った俺の言葉を遮るように真凛さんはこう言った。
「ううん! 明日から実地調査だよ! 一緒に街を回って考えよう!」
俺は愕然としてしまった。
「一緒に、街を、回って、考えるぅっ?」
声に出すつもりは無かったのに、そう声に出してしまった俺。
真凛さんは屈託の無い笑顔で、
「うん! そう! その場で距離感とかを体感することが一番だよ!」
まさかそんな、街を歩かないといけないなんて……正直面倒だ、運動も苦手だから歩くのも正直嫌だ……。
でも真凛さんはもうその気といった感じで、ワクワクしている。
また不機嫌になられるのも嫌なので、
「じゃ、じゃあ、そういうこと、かっ」
と返事しておくと、真凛さんは、
「あとライン交換しておこう!」
「それはまあ」
と言って交換を普通にしたんだけども、まさか俺が同級生の、それも女子とラインを交換するなんて、と家に帰ってから考えている。