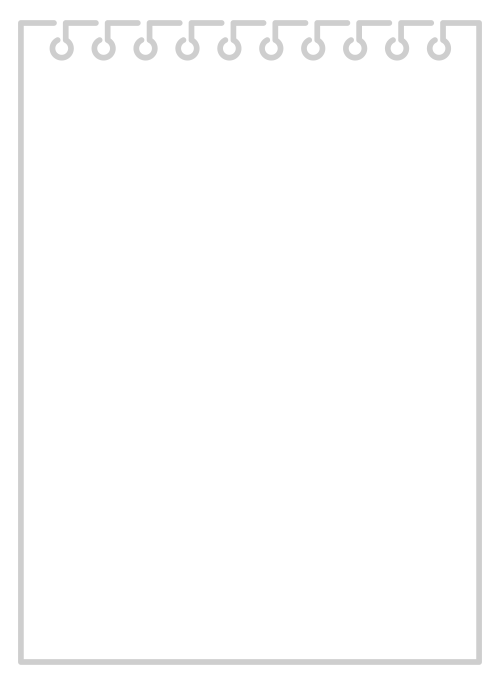何度かの調整を重ね、花火大会当日がやってきた。
『花火、見てみたいんです。』
僕は今日、燃えていた。彼女にコンテストの写真以上の花火の写真を撮って、渡してあげたいと思っていたから。
打ち上げ開始まであと一時間。普通の見物客はおそらく三十分前ごろから場所を取り始める。少し早めにカメラのセットを行い、シャッターが正確に押せるかの確認をする。大丈夫、問題ない。人が来て倒されないよう、カメラから目を離さず打ち上げられるまで待機をする。
ふと、彼女の顔が浮かんだ。
肩の下くらいまでの黒髪で、身長は低めの彼女。どこか名前のような華やかさがある。早乙女、桜子—。彼女と写真を撮れる日は来るだろうか。来年の夏は花火大会の写真撮影に同行してもらいたい、叶わぬ願いとは知らず、僕は花が咲く前の真っ黒な夜空へ期待を込めた。
打ち上げ開始まであと五分。もう多くの見物客で場所は埋まっている。最後の確認をして、秒針が脈打つのをじっと待っていた。
そろそろと夜空を見上げシャッターに指を置いた時、どこまでも黒く染まっていた夜空に花が咲いた。花火。誰が付けた名前だろう。これほどぴったりな名前はあるだろうか。
—彼女も、同じ空を見上げているのだろうか。
そんなことを考えていたら三十分程度の花火大会も一瞬にして過ぎ去った。過去になった。一人の撮影ではよく撮れた方だと思う。
「桜子ぉ、名札取ってぇー」
「めんどくさいなぁ」
そんな会話を聞き流しながら今になって実感する。彼女とは、クラスメイトだった。でも世界が違う。僕の休み時間はいつもカメラを見つめているか本を読んでいるか。それに対し、彼女は未だ覚えきれないほどの人数の友だちに囲まれている。もしかしてカメラの話できるかもと期待を込めた足取りで登校した僕が情けない。現実は甘くないどころか辛いほどだ。部活まで、何も考えず時間が過ぎるのを待とう。
やっと最後の授業の終わりのチャイムが鳴り、多くの人の愚痴やため息とともに今日の授業が終わった。
「今日もよろしくね、松乃くん」
今日からは花火大会も終わり、また学年ごとで校内を撮り合うほぼ自由時間が始まる。だから早乙女さんは僕との活動になるだろう。
…僕なんかで良いのか!?でも部長が決めたからしょうがない。早乙女さん、僕なんかでごめんなさい。悪気は無いので許してください。
二人で多くの場所の撮影をし、屋上での撮影にとりかかったとき、僕は彼女に花火の写真を渡すのを忘れていたことに気が付いた。
「早乙女さん、これ。昨日の写真なんだけど。一応データはスマホにも送ってあるから時間がある時見てみて」
「良いの!?スマホ見れてない、ごめん。今見ます。…うわぁ、すごい。花火ってすごいね。生で見てみたいなぁ」
「来年、良ければ見に行かない?撮影もあるし。」
「…松乃君だから。」
小さい声で彼女は何か言っているようだった。僕は何のことか分からない。
「松乃くんだから、言う。」
理解できない。それが素直な感想だろう。でも僕は同時に、理解したい、そうとも思った。
彼女はこう言った。
「私、夜になったら、死んじゃうの—。」
僕はなんて言えばいいのかわからなかった。時間が止まったのか、僕の鼓膜が破れたのだろうと思うほどの沈黙。しばらくして説明してくれた。
「私、不治の病って言われる病気なんだ。太陽が沈むのと同じようにだんだん体が透けていくの。それで、完全に暮れると見えなくなっちゃう。周りの声は聞こえる。私も自分では聞こえる。なのに相手には聞こえないし、自分でも見えなくなっちゃうんだ。…そんなの、死んでるよね。生きてるって言わない。私、死んじゃってるんだよ。だから、君の半分しか生きれない。だから私は、花火を生で見たことないし、撮影も同行できないんだ。ごめんね。」
「…なんで。」
「…?」
「なんで謝るの。君は悪くないよね。悪いのは病気でしょ。だから君は悪くないし、一方通行になっちゃったとしてもどちらかの思いが相手に届くなら、生きてるよ。君はずっと、生きてるよ。」
「嬉しい」
彼女は噛み締めるように言ってくれたと思う。
だとしたら、良かった、と思う。
もしも僕の写真で僕に病気のことを言おうと思ってくれたのなら。
良かったと思う。
僕の一枚の花火で、彼女に少しだけでも光を差せたのなら—。
『花火、見てみたいんです。』
僕は今日、燃えていた。彼女にコンテストの写真以上の花火の写真を撮って、渡してあげたいと思っていたから。
打ち上げ開始まであと一時間。普通の見物客はおそらく三十分前ごろから場所を取り始める。少し早めにカメラのセットを行い、シャッターが正確に押せるかの確認をする。大丈夫、問題ない。人が来て倒されないよう、カメラから目を離さず打ち上げられるまで待機をする。
ふと、彼女の顔が浮かんだ。
肩の下くらいまでの黒髪で、身長は低めの彼女。どこか名前のような華やかさがある。早乙女、桜子—。彼女と写真を撮れる日は来るだろうか。来年の夏は花火大会の写真撮影に同行してもらいたい、叶わぬ願いとは知らず、僕は花が咲く前の真っ黒な夜空へ期待を込めた。
打ち上げ開始まであと五分。もう多くの見物客で場所は埋まっている。最後の確認をして、秒針が脈打つのをじっと待っていた。
そろそろと夜空を見上げシャッターに指を置いた時、どこまでも黒く染まっていた夜空に花が咲いた。花火。誰が付けた名前だろう。これほどぴったりな名前はあるだろうか。
—彼女も、同じ空を見上げているのだろうか。
そんなことを考えていたら三十分程度の花火大会も一瞬にして過ぎ去った。過去になった。一人の撮影ではよく撮れた方だと思う。
「桜子ぉ、名札取ってぇー」
「めんどくさいなぁ」
そんな会話を聞き流しながら今になって実感する。彼女とは、クラスメイトだった。でも世界が違う。僕の休み時間はいつもカメラを見つめているか本を読んでいるか。それに対し、彼女は未だ覚えきれないほどの人数の友だちに囲まれている。もしかしてカメラの話できるかもと期待を込めた足取りで登校した僕が情けない。現実は甘くないどころか辛いほどだ。部活まで、何も考えず時間が過ぎるのを待とう。
やっと最後の授業の終わりのチャイムが鳴り、多くの人の愚痴やため息とともに今日の授業が終わった。
「今日もよろしくね、松乃くん」
今日からは花火大会も終わり、また学年ごとで校内を撮り合うほぼ自由時間が始まる。だから早乙女さんは僕との活動になるだろう。
…僕なんかで良いのか!?でも部長が決めたからしょうがない。早乙女さん、僕なんかでごめんなさい。悪気は無いので許してください。
二人で多くの場所の撮影をし、屋上での撮影にとりかかったとき、僕は彼女に花火の写真を渡すのを忘れていたことに気が付いた。
「早乙女さん、これ。昨日の写真なんだけど。一応データはスマホにも送ってあるから時間がある時見てみて」
「良いの!?スマホ見れてない、ごめん。今見ます。…うわぁ、すごい。花火ってすごいね。生で見てみたいなぁ」
「来年、良ければ見に行かない?撮影もあるし。」
「…松乃君だから。」
小さい声で彼女は何か言っているようだった。僕は何のことか分からない。
「松乃くんだから、言う。」
理解できない。それが素直な感想だろう。でも僕は同時に、理解したい、そうとも思った。
彼女はこう言った。
「私、夜になったら、死んじゃうの—。」
僕はなんて言えばいいのかわからなかった。時間が止まったのか、僕の鼓膜が破れたのだろうと思うほどの沈黙。しばらくして説明してくれた。
「私、不治の病って言われる病気なんだ。太陽が沈むのと同じようにだんだん体が透けていくの。それで、完全に暮れると見えなくなっちゃう。周りの声は聞こえる。私も自分では聞こえる。なのに相手には聞こえないし、自分でも見えなくなっちゃうんだ。…そんなの、死んでるよね。生きてるって言わない。私、死んじゃってるんだよ。だから、君の半分しか生きれない。だから私は、花火を生で見たことないし、撮影も同行できないんだ。ごめんね。」
「…なんで。」
「…?」
「なんで謝るの。君は悪くないよね。悪いのは病気でしょ。だから君は悪くないし、一方通行になっちゃったとしてもどちらかの思いが相手に届くなら、生きてるよ。君はずっと、生きてるよ。」
「嬉しい」
彼女は噛み締めるように言ってくれたと思う。
だとしたら、良かった、と思う。
もしも僕の写真で僕に病気のことを言おうと思ってくれたのなら。
良かったと思う。
僕の一枚の花火で、彼女に少しだけでも光を差せたのなら—。