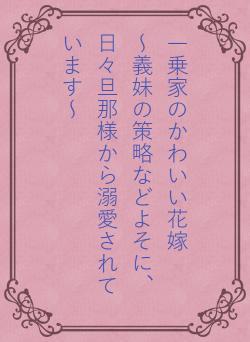『若……本当に人間から嫁を取られるんですか』
『取るも取らないも、俺が決めることじゃない』
『いくら古くからの習わしでも、もういい加減よろしいじゃないですか! そろそろ人間と決別してたって、誰も文句は言いませんよ』
近侍の灰墨が、怒ったように声を荒げて訴えていた。
『人間なんて……っ、いくら優しくしようと僕たちを化け物としか見ないじゃないですか。どうせ若の相手だって、今までのやつらと同じですよ』
今朝の灰墨との会話を思い出し、男はひとり、憂鬱な溜息を吐いた。
歩く度に地面に落ちた枯れ葉が、さくっ、さくっと鳴く。
木々に覆われた山はすっかり色を失い、空すらも灰色に淀んでいる。
「ああ……どうりで寒いはずだ」
男が木々の隙間から空を見上げれば、白い綿帽子がゆっくりと舞い落ちてきていた。
落ちてきた綿帽子を手に乗せると一瞬だけひやっとして、あっという間に熱で溶けていく。
「雪か」
ほう、と吐いた息は白く、髪色も身にまとった着物の色も黒ずくめの自分の口から出た色にしては美しすぎるな、と男は自嘲した。
男は小高い山の中でひとり佇んでおり、眼下には彼の棲まう郷が見えている。
あやかしの世界――〝常世〟に棲まうあやかしの郷の中では、鴉一族の郷は規模が大きいほうだ。
今は父が一族の長――黒王として治めているが、それもいつまで保つことか。
父は病に伏せっており、郷の中ではそろそろ代替わりをとの声がチラホラと上がっていた。特に最近は、よそのあやかしが郷の外をうろちょろしていると聞く。大方、黒王が伏せっている今ならば攻め入る隙があるかも、などと考えているのだろう。
このような状況では、いつ自分に黒王の座が回ってきてもおかしくない。
座についたらば郷の皆をまとめ、守っていくのが役目となる。
「はぁ……俺が黒王なあ……」
男は憂鬱なため息をついた。
黒王になるのが嫌なわけではない。
黒王になった者に課された〝習わし〟が煩わしいのだ。
古からの習わしで、黒王の嫁は〝花御寮〟と呼ばれる人間の娘でなければならないと決められている。
もちろん自分の母も人間であった。
母というより、自分を産んだだけの人間と言ったほうが正しいが。
彼女は自分を身ごもった時、何を思ったのだろうか。産む時、どのような思いで苦しみに耐えたのだろうか。
まあ、そんなことを知ったところで、自分にはどうしようもないが。
あやかしという存在は、人間の住まう現世では恐れられ嫌われる対象である。そのような者のところへ単身で嫁いで来る者と、どう接したら良いのか分からない。
黒王の役目は、郷を守り跡継ぎを残すことである。
父は間違いなく、その任は果たしていた。
しかし、父は幸せだったのだろうか。
両親は、夫婦だったのだろうか。
夫婦とは……なんなのか。
そんなことがばかり考えていると、「若ー!」と叫びながら山を駆け登ってくる者の姿が視界に映った。よほど慌てているのか、ぜぇぜぇと、ここまで聞こえてきそうなほど息を荒くしつつも、何度も自分を呼び続けている。
「ここにいる。なんだ」
「そちらにおいででしたか、若! 今すぐ屋敷へとお戻りください!」
嫌な予感がした。
「黒王様がご逝去なさいました!」
「ああ……」と、男は天を仰ぎ、目を閉じた。
先ほどより勢いを増した雪が、次々と顔に触れては雫となって流れ落ちていく。目尻を伝う雫だけが、ほんの少し温かい気がした。
「すぐに行くから、お前は先に戻り重役達を屋敷に集めておけ」
「かしこまりました」
ばたばたとした足音が遠ざかり聞こえなくなれば、しんしんとした静かな世界がまた戻ってくる。
「……俺の花御寮か」
期待はしていない。
どうせ今までの花御寮と同じく、異物に向けるような冷めた目で自分たちを見て、「化け物がっ!」と泣き叫んだあげく、すぐにいなくなるのだろうし。
それでも、郷の習わしは拒否できない。
「どうせなら、性格が悪い娘のほうが良い」
そうすれば、単身で常世に嫁いできてもらう罪悪感も、幾分かましになるというもの。
「口汚く罵ってくるような相手ならば、いなくなろうと、痛みも寂しさも感じないだろうしな」
男は目を開けると同時に、灰色の空に向かって片口をつり上げた。
降りしきる雪。
周囲にある針山のような枝には、うっすらと白が積もり始めている。
男は顔を正面に戻し、眼下で白くなりつつある郷に向け、ゆっくりと山を下りていく。
「……そうか、父上が……」
着物の上にまとっていた羽織を、胸の前できつくたぐり寄せる。
色のない世界は、凍えそうなほど寒かった。
◆
こうして、新たな黒王は現世より花御寮を迎え入れたのだが……。
その女は既に身籠もっていたという。
『取るも取らないも、俺が決めることじゃない』
『いくら古くからの習わしでも、もういい加減よろしいじゃないですか! そろそろ人間と決別してたって、誰も文句は言いませんよ』
近侍の灰墨が、怒ったように声を荒げて訴えていた。
『人間なんて……っ、いくら優しくしようと僕たちを化け物としか見ないじゃないですか。どうせ若の相手だって、今までのやつらと同じですよ』
今朝の灰墨との会話を思い出し、男はひとり、憂鬱な溜息を吐いた。
歩く度に地面に落ちた枯れ葉が、さくっ、さくっと鳴く。
木々に覆われた山はすっかり色を失い、空すらも灰色に淀んでいる。
「ああ……どうりで寒いはずだ」
男が木々の隙間から空を見上げれば、白い綿帽子がゆっくりと舞い落ちてきていた。
落ちてきた綿帽子を手に乗せると一瞬だけひやっとして、あっという間に熱で溶けていく。
「雪か」
ほう、と吐いた息は白く、髪色も身にまとった着物の色も黒ずくめの自分の口から出た色にしては美しすぎるな、と男は自嘲した。
男は小高い山の中でひとり佇んでおり、眼下には彼の棲まう郷が見えている。
あやかしの世界――〝常世〟に棲まうあやかしの郷の中では、鴉一族の郷は規模が大きいほうだ。
今は父が一族の長――黒王として治めているが、それもいつまで保つことか。
父は病に伏せっており、郷の中ではそろそろ代替わりをとの声がチラホラと上がっていた。特に最近は、よそのあやかしが郷の外をうろちょろしていると聞く。大方、黒王が伏せっている今ならば攻め入る隙があるかも、などと考えているのだろう。
このような状況では、いつ自分に黒王の座が回ってきてもおかしくない。
座についたらば郷の皆をまとめ、守っていくのが役目となる。
「はぁ……俺が黒王なあ……」
男は憂鬱なため息をついた。
黒王になるのが嫌なわけではない。
黒王になった者に課された〝習わし〟が煩わしいのだ。
古からの習わしで、黒王の嫁は〝花御寮〟と呼ばれる人間の娘でなければならないと決められている。
もちろん自分の母も人間であった。
母というより、自分を産んだだけの人間と言ったほうが正しいが。
彼女は自分を身ごもった時、何を思ったのだろうか。産む時、どのような思いで苦しみに耐えたのだろうか。
まあ、そんなことを知ったところで、自分にはどうしようもないが。
あやかしという存在は、人間の住まう現世では恐れられ嫌われる対象である。そのような者のところへ単身で嫁いで来る者と、どう接したら良いのか分からない。
黒王の役目は、郷を守り跡継ぎを残すことである。
父は間違いなく、その任は果たしていた。
しかし、父は幸せだったのだろうか。
両親は、夫婦だったのだろうか。
夫婦とは……なんなのか。
そんなことがばかり考えていると、「若ー!」と叫びながら山を駆け登ってくる者の姿が視界に映った。よほど慌てているのか、ぜぇぜぇと、ここまで聞こえてきそうなほど息を荒くしつつも、何度も自分を呼び続けている。
「ここにいる。なんだ」
「そちらにおいででしたか、若! 今すぐ屋敷へとお戻りください!」
嫌な予感がした。
「黒王様がご逝去なさいました!」
「ああ……」と、男は天を仰ぎ、目を閉じた。
先ほどより勢いを増した雪が、次々と顔に触れては雫となって流れ落ちていく。目尻を伝う雫だけが、ほんの少し温かい気がした。
「すぐに行くから、お前は先に戻り重役達を屋敷に集めておけ」
「かしこまりました」
ばたばたとした足音が遠ざかり聞こえなくなれば、しんしんとした静かな世界がまた戻ってくる。
「……俺の花御寮か」
期待はしていない。
どうせ今までの花御寮と同じく、異物に向けるような冷めた目で自分たちを見て、「化け物がっ!」と泣き叫んだあげく、すぐにいなくなるのだろうし。
それでも、郷の習わしは拒否できない。
「どうせなら、性格が悪い娘のほうが良い」
そうすれば、単身で常世に嫁いできてもらう罪悪感も、幾分かましになるというもの。
「口汚く罵ってくるような相手ならば、いなくなろうと、痛みも寂しさも感じないだろうしな」
男は目を開けると同時に、灰色の空に向かって片口をつり上げた。
降りしきる雪。
周囲にある針山のような枝には、うっすらと白が積もり始めている。
男は顔を正面に戻し、眼下で白くなりつつある郷に向け、ゆっくりと山を下りていく。
「……そうか、父上が……」
着物の上にまとっていた羽織を、胸の前できつくたぐり寄せる。
色のない世界は、凍えそうなほど寒かった。
◆
こうして、新たな黒王は現世より花御寮を迎え入れたのだが……。
その女は既に身籠もっていたという。