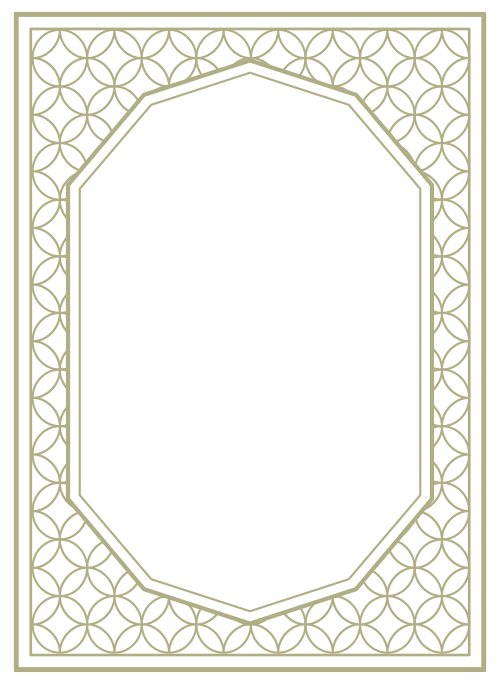都会から3時間。電車にゆられて田舎の町へと向かう。
目的地は3年前、夏休みに滞在していた親戚のおじさんの家だ。またここに来たいという俺の願いをおじさんは快く聞き入れてくれた。
俺は声変わりをしたし、背は二十センチほど高くなった。陸上部に入部して肌も焼けた。俺は『あいつ』に追いつけるくらい、男らしくなっただろうか。さて、『あいつ』はどうだろう。あの時は小柄だったけれど、『あいつ』だって成長しているはず。
けれど心の中はなにも変わらないでいてほしいと願う。なにせ『あいつ』はかつて俺と『男の友情』を分かち合った仲なのだから。
☆彡
父方の兄にあたるおじさんは町工場を営んでいた。移転することになったので、手伝う父と一緒に夏の間、住み込むことになった。俺が小学5年生の時だった。
けれどまさか電波が届かず、やりたいゲームができないとは。まじで勘弁してほしい。退屈な田舎で夏を過ごすなんて地獄に突き落とされた気分だ。
途方にくれた俺は、工場のまわりをうろついていた。あたりは風が吹けば砂埃が立つような荒れた更地だった。その更地にはすりばち状のくぼみがたくさんあった。なんだろう? ミステリーサークルにしては迫力がなく、誰かのいたずらにしては数が多くて円が綺麗すぎる。
すると隣から、するっと細い草のつるが伸びてきた。振り向くと俺よりも少し小柄な、浅黒い肌をした子供がつるを握っている。逆光で暗い顔の中、瞳だけが爛々と輝いていた。
つるの先には小さな花のつぼみがついていた。その子はいたずらっぽい顔で草のつるを凹みの中に落とし、誘いをかけるように小刻みに動かす。するとすりばちの底から何かが姿を現した。灰色をした蜘蛛のような生き物で、砂をかけてそのつぼみを落とそうとする。
蟻地獄の巣だ。はじめて見た。
虫を騙すのに成功したからか、その子は面白そうな顔で笑っていた。しばらくすると蟻地獄はつぼみが偽物だと気づいたようで、残念そうに砂の中へと戻っていった。
その子は「やってみる?」と言い、俺の答えを待たずにつるを手渡した。受け取ってしまったので試さないわけにはいかない。けれど俺が誘いをかけても、蟻地獄は誘いに乗ってこない。うまくいかない様子に、その子はまた楽しそうな顔をする。
「ははっ、簡単そうに見えるでしょ」
「くそう、俺のだけ見抜くとは……」
その子は近所に住んでいる俺と同い年の子だった。名前は「ゆうき」。大自然を相手にできそうな、かっこいい名前だと思った。
それからの毎日は、退屈とは無縁になった。ゆうきは遊び相手がいないのか、毎日俺のことを誘いにきた。俺はその誘いに喜んで乗っていた。
眺めのいい高台にある公園には、おおきなコンクリート製の『箱』が置いてあった。集めた枯れ葉が詰め込まれている。
「これで腐葉土を作っているんだって」
「腐葉土?」
「堆肥のことだよ。植物の肥料になるんだ。で、この中にさ――」
ゆうきは両手でその腐葉土を掘り起こす。大きなミミズが出てきて驚いたけれど、ゆうきは平然とミミズを掴んでいた。
「こいつを釣りの餌にするんだ」
「まじか」
「だから集めてよ」
俺は木の枝で掘り起こし、ゆうきが袋の中に詰めていった。
ゆうきの家の物置小屋には釣り竿や釣具が置いてあった。タンクトップに半ズボンの格好であぐらをかいて釣りの仕掛けをこしらえる。俺も見よう見まねで仕掛けを作る。
捕ったミミズを餌にして、近所を流れる小川に仕掛けを投げ込んでおく。ふたりで肩を並べてワクワクしながら待つと、魚がかかって竿が引っ張られ俺の心臓は跳ね上がった。
無我夢中で竿を立てて釣り上げた魚はナマズだった。キューキュー鳴く様子が可愛かったので持ち帰って飼おうと盛り上がった。けれどバケツに入れておいたらいつの間にかいなくなった。近くにいた猫がくわえていて、俺たちに気づくとあわてて逃げていった。だからその日の一番の収穫は、俺がミミズを触れる男に成長したことだった。
ゆうきは昼間、近所の森の中に忍び込み、虫が集まりそうなクヌギの木に目を付けた。おじさんの家の床下にあった梅酒を拝借し、そこに漬け込んだパイナップルを木の根元に仕掛けておく。そして夜に家を抜け出して見に行き、仕掛けた場所に蛍光灯を当てる。
ゆうきの罠の効果はてきめんで、パイナップルの上ではカブトムシやクワガタがお祭り騒ぎとなっていて、俺はその賑やかさに感動した。デパートで高値の虫は、じつは世の中にたくさんいて、しかもみんな『のんべえ』だったことにも。
ほんとうの男の子の遊びというものを、俺はゆうきから学んでいた。
俺がゆうきと一緒に遊んでいたせいか、ばあちゃんは「ゆうきちゃんも、ひろしと一緒に食べんさい」と言ってスイカを出してくれた。もちろんどっちが早く食べられるか競争になる。男はなんでも勝負したくなる性分だ。勝負はエスカレートし、あとで従兄の光之にいちゃんが「あれ、俺のぶんは?」とうろたえることになった。ふたりで顔を見合わせ、そそくさと逃げ出した。
俺は自由な世界で生きているゆうきが心底、うらやましかった。けれどゆうきもまた、俺をうらやむことがひとつだけあった。
「この帽子いいなぁ、ほしいなぁ……」
ゆうきは俺の赤い野球帽を手に取り、物欲しそうに眺めていた。
「だめだよ、父ちゃんがアメリカで買ってきてくれた、俺の宝物なんだ」
世界の至宝、メジャーリーグで活躍する大滝選手の帽子と同じデザインのもの。それだけで野球が強くなった気がする。それがきっかけで、プラスチックバットとビニールボールを持ち出しふたり野球に燃えた。けれど、帽子をかぶった俺はゆうきにさんざん打たれた。会心のあたりは偏屈なじいさんの家に吸い込まれていった。俺たちは抜き足差し足忍び足で取り返し、泥棒の気分を味わうことになった。心臓が高鳴り、じいさんの家を脱出できた瞬間にしてふたりで笑い転げた。
俺たちは思う存分、夏を謳歌していた。俺にとっては知らない世界の幕開けで、その夏がどこまでも続くと願っていた。
思い返すと、ふたりの時間はさんさんと降り注ぐ夏の太陽よりもまばゆく、夏の蝉の鳴き声よりもずっと賑やかだった。
☆彡
きっとまた、あの日とおなじ夏が来る。俺はそう信じて駅を降りた。
だからおじさんの家に行く前に寄り道をしようと思った。思い出巡りのつもりだ。
最初に町工場のあった場所を訪れる。するとその場所は開発されショッピングモールができていた。たくさんの車が出入りし、人の往来も盛んになっている。一周回ったけれど、蟻地獄の巣はどこにもなかった。町工場移転の理由が地域の開発だとおじさんが言っていたのを思い出す。
魚釣りをした小川に向かう。けれど小川はすっかり姿を変えていた。アスファルトで舗装された道となり、隅のほうに油の浮いた細い用水路があるだけだった。しかたないと思う反面、あの日の思い出に傷をつけられたような気がした。
同時に不安が沸き起こる。あいつはこの変化を悲しんでいないだろうか? 自然を失った場所でいきいきしていられるのだろうか? それに――あいつは、あの夏のあいつのままなのだろうか?
俺の足は自然と高台の公園に向かっていた。俺は三年後の夏にまた来るとゆうきに宣言していた。待ち合わせの場所はこの公園だ。ただ、日付も時間も約束なんてしていない。毎日会っていたから、来れば会えるだろうと思っている。そう信じている。大滝選手の帽子をかぶっていたから、俺のことを間違うはずはないという確信もあった。
着いた頃には日が傾き、あたりは淡いオレンジ色に染まっていた。ちいさな子供を連れた家族連れが何組かいた。日傘をさしたワンピース姿の女子に、日陰で新聞を読んでいるおじいさん、それにかつての俺と同じくらいの小学生たち。
ゆうきの姿がなかったので、俺は柵に手をかけて街を眺めていた。
風が吹いてきた。東京と違って夕方には涼しさを覚える風が吹く。空気が軽やかに流れている。
ふと、左隣にワンピースの女の子が並んでいるのに気づいた。肩よりも少し長いくらいの髪が風に舞っている。日傘のせいで顔は見えないけれど、なんとなく寂しげな雰囲気に思えた。
「こんにちは」
唐突に声をかけられてドキリとした。女の子は苦手でろくに口を聞いたことがない。それなのに見知らぬ相手との会話はハードルが高すぎる。
けれど俺は違和感を覚えた。この声は俺の記憶の中に刻まれていたものだ。
まさかと思った。否定したかった。心底、冗談だと思いたかった。けれど俺の首は自分の拒絶を振り切るように左を向いてしまう。
「――ゆうき?」
くりっとした瞳は記憶のままだけれど、肌は浅黒い日焼けの色ではなかった。
そよそよと吹く風が、自分の呼吸が、流れる時間が止まってしまった。あんなにも音の主役だったひぐらしの鳴き声さえも耳に届かなくなる。
「そうだよ、ひさしぶりだね」
やわらかな笑顔で俺の反応をうかがう。何かを言わなければいけない。そうでなければ動揺していることに気づかれてしまう。だけどうまく繕える言葉が思い浮かばない。
「驚いたっていうことは……もしかして勘違いしてた?」
相手は女子のするような小首のかしげ方で俺の顔色をうかがう。
ひさしぶりと返せばいいのか? いや、俺はきみを知らない。俺が会いにきたのは男友達だ。
全身が麻酔をかけられたような、奇妙な感覚に陥っていく。思い出の中の友情が壊されていく。確かな現実として信じていた城が、廃墟となって崩れていく。
「あー、やっぱり勘違いしてたんだ」
「あたりまえだろ!」
思わず声を荒らげている自分に気づく。ゆうきはさっと表情を曇らせた。
「ちょっとは褒めてもいいんじゃない、わたし、これでもおしゃれして待っていたんだよ」
「なんでそんな格好してんだよ!」
「きみがくるって、信じて毎日待っていたのに、それひどいんじゃない」
「男の友情はどこに消えたんだ? 最初からなかったのか?」
大切な宝物を奪われたような怒りがふつふつと湧いてくる。俺の苛立ちにゆうきは困ったような顔をし、髪をかきあげて口を尖らせる。
「……だってさ、しょうがないじゃん」
「なにがしょうがないんだよ。男らしいお前はどこに行っちまったんだよ!」
「そう言われたって……中学に入れば制服もあるし、身体だって女の子らしくなるし」
思い詰めたような顔をしたので、俺ははっとなった。ひょっとしてと思いおそるおそる尋ねる。
「もしかして、心と身体の性別がちがうとかいう……」
「ううん、そういうんじゃないよ。わたしが好きだったことが、女の子よりも男の子が好きだったことだっただけ」
乾いた言葉でそう言った後、ただそれだけなのにね、と付け加えた。
「女の子には、虫と遊ぶなんて気持ち悪いよって言われて。男の子には、女子は足手まといだから嫌だって言われてさ。だからクラスののけ者だったんだ、わたし」
「あ……」
ずっと俺と一緒に過ごしていたのは、友達がいなかったからなのか。つまりゆうきは夏の間、周囲の否定から身を隠して、自分自身でいられる場所を探していたのだ。
「男の子みたいなことするのって、恥ずかしいことなのかなぁ……」
「……それは親に言われたことなのか」
「うん……。女の子らしくないことはやめなさいって」
ゆうきはきっと、まわりから常識の『らしさ』を求められていたのだろう。
「ひろしだけは、そういうの気にしないひとだと思ってたんだ」
俺はその言葉に、心底打ちのめされた。俺はゆうきにとって唯一の、『自分らしさ』を肯定してくれるひとだったはずだ。その願いを、俺は今ここで壊してしまったのだ。
「だからきみにどうしても会いたかった。きみがわたしのことをどう思っていたのか、確かめたかったんだ」
涙を浮かべるゆうきに、俺は何も言い返せないでいた。ゆうきはため息をひとつついてからぽつりとこぼす。
「でも勘違いだったら仕方ないかぁ……」
ああ、もしもゆうきの見た目が女子でも、心が男子であってくれたのなら。純粋に俺との関係を男の友情だと思ってくれていたのなら。
友情は友情のままで色褪せることなどなかったはずなのに。
あの日の夏は、幻想で、虚像で、蜃気楼のようなものだったのだろうか。
俺が混迷するなか、ゆうきが突然視線を空へ向けた。
「あっ、そうだ!」
それから振り向き、ひとつの提案を持ちかける。
「ねえ、あのときできなかったこと、もう一度挑戦してみない?」
「できなかったこと……?」
思い返すと、ゆうきとふたりで成し得なかったことが、たしかにひとつだけあった。カブトムシを捕りに行った時、森の中で見かけた鳥の捕獲だ。
天然のチャボ。ニワトリに似ているけれど、それよりも小型で、木々の間を自由に飛び回る鳥。俺はそいつを無性に捕まえたくなった。男の狩猟本能が駆り立てられたのだ。
結局、空を飛ぶ相手はふたりがかりでも太刀打ちできなかった。けれどふたりが大人になれば捕まえられるかもしれないとも思った。だから再戦を誓って拳を合わせた。
☆彡
翌日、ゆうきと俺は森の入り口で待ち合わせをした。ゆうきは長袖のシャツとジーパン姿で、つんとしたすまし顔で現れた。すこしだけ男らしく見えた。
ふたりで顔を見合わせ無言でうなずく。かつて戦友だったゆうきは、この日だけ俺の前に戻ってきた。
「準備はいい?」
「ああ、今度こそ捕まえてやる」
風に揺れる森の中で目を凝らして周囲を見回す。けれどチャボの姿はどこにも見当たらない。
気持ちを落ち着かせ、身体の感覚を研ぎ澄ます。遠くの方で、かさり、と風とは違う音が聞こえた。俺よりもゆうきのほうが先にその存在に気づいた。
「いたよ、あそこだ」
目を凝らすと焦げ茶色の鳥の姿があった。岩の上に飛び乗りあたりを見回している。
息を止めて身をひそめる。風の向きを利用して匂いを消し、目と目が合わないよう注意深く近づく。
けれど足音を完全に消すことはできなかった。チャボは俺の存在に気づいて驚き、一気に逃げ出してしまう。
「ひろし、あいつを追うよ」
「ああ、もちろんだ」
チャボは森の奥へ飛び込むように逃げてゆく。俺は目を見開き、一瞬たりともその姿を見失わなかった。
ゆうきの足は岩や木の根を避けながら俊敏に動く。俺の心臓は新鮮な森の空気を吸い込み高鳴っていた。チャボを捕まえるためには、その素早さに勝ることが不可欠だった。
急な斜面にさしかかり、枝や蔦との闘いが始まる。ゆうきは優れたバランス感覚で自然の障害物をかわしてチャボを追う。やっぱり『あいつ』は『あいつ』だったと思いながら、俺も負けじと草木を割って進む。
「ゆうき、俺は左から回り込む。おまえは反対側を!」
「了解!」
ゆうきは風を裂くように森の中を駆ける。
チャボは一瞬、足を止めた。作戦に気づいたのか、ふたりを確かめた後、翼をはためかせた。そして木の枝へと向かって飛んでいってしまった。
「くそっ……!」
逃げられたと悔しがったとき。神風とでも言うべき強風が吹いてきた。チャボが飛び乗った枝はひどく揺れ、留まっていられないようだった。揺れの弱い、低くて太い枝に降りてきた。
「あそこなら届くかも」
それを見たゆうきは迷わず木に飛びつき登り始めた。ゆうきの目には、チャボを捕まえるための燃えるような情熱が宿っている。
ゆうきは軽やかに枝へと移り、チャボとの距離を縮めてゆく。えいっ、と手を伸ばして捕まえようとする。同時にチャボも羽を広げて飛び立った。けれどゆうきの手がチャボの羽をかすめ、チャボはバランスを崩す。
「いまだ、ひろし!」
「おう!」
俺は全身全霊を込めて飛び上がり、空中でチャボの足を捉えた。地面に降りたと同時にチャボの上に草のつるを重ねて閉じ込める。
「はぁ、はぁ、はぁ……」
ゆうきは木からゆっくりと降りてくる。俺もゆうきも肩で息をしていた。興奮と達成感で全身から汗が吹き出し、手は震えっぱなしだ。森を舞台に繰り広げられた追いかけっこは、ふたりの勝利で幕を閉じた。
「やったな、ゆうき!」
「まさか捕れるなんて思わなかったよ」
「無理だと思ってたのかよ!」
笑いながら足元を見ると、チャボは草のつるに閉じ込められ、恐怖に怯えた顔をしていた。
「おまえを食ったりしないから。ただ捕まえられるか挑戦してみただけだ」
ゆうきは仰向けになって頭上を見上げる。いつの間にか風は落ち着きを取り戻していた。息を整えてぽつりとつぶやく。
「……やっぱり、男の子ってイイネ」
「だろう? 俺はゆうきに出会ってそう思えたんだ」
「生きたいように生きられるのって、なんだか羨ましいなぁ……」
「そっか、そうだよなぁ」
達成感が背中を押したのか、ゆうきはとつとつと心情を吐露しはじめた。
「正直、あの頃の無邪気な関係が懐かしくて愛おしいよ。それのに、わたしはだんだん女の子になっていく。ひろしとおなじではなくなって、きみの言う『男の友情』を裏切るしかなくなっちゃうんだ」
その言葉に、ゆうきがチャボを捕まえようと提案した理由も痛いほど伝わっていた。
それは、ふたりの夏をここで終わらせるためだ。
永遠に続くわけではない男の友情を、悔いなく締めくくろうと思ったに違いない。
ああ、俺はなんで気づかなかったのだろう。ゆうきは俺が想像できないくらいの、途方もない苦しみを抱えていたことに。そしてこの3年間、抗えない変化にさらわれてゆく自身の心を、必死でつなぎ止めていたはずなのに。
「じゃあ逃がしてあげようか」
ゆうきがそう言ったので、ふたりでチャボを抱きかかえ空に向かって掲げる。チャボは翼をはためかせ、森の中へと飛んで逃げていった。ゆうきは黙ってその姿を見送っていた。
いつまでも、いつまでも。
☆彡
駅のホームは閑散としていて、俺以外の人の姿はなかった。鳥のさえずりだけが響いている。
ふと、柵の向こうにゆうきの姿を見つけた。ゆうきは電車通り沿いの街路樹に登り、黙って俺を見下ろしていた。俺も何も語らずゆうきを見上げていた。男同士なら、別れの言葉なんてさほどいらないはずだ。
「まもなく二番線に電車がまいります」
無言のふたりの間に電車が流れ込んでくる。ゆうきの姿が遮られた。電車に乗り込み、奥の座席から木の上を見上げる。
ゆうきはいつの間にか、大きな裁ちバサミを手にしていた。ウエストバッグが半開きになっている。ハサミを目の前に突き出し、それを首の後ろ回した。俺はまさか思った。
あたりの音が消え、一閃の音が響く。
――じゃきん。
ゆうきは躊躇なく自身の髪を断ち切った。迷いや葛藤を振り切るかのように。荒々しく、潔く。
女の子の証でもある髪の切れ端を、空に向かって舞い上げる。それを風が遠くへ運んでいった。
泣きそうな顔で笑ったゆうきを見て、『あいつ』はやっぱり『あいつ』のままだったと、俺は胸が締めつけられた。
俺は無意識に帽子を脱ぎ、ゆうきの方に向かって投げ飛ばしていた。大滝選手の帽子を風が運んでゆうきの元へ送り届ける。ゆうきは驚いた顔をしたが、持ち前の運動神経でそれを掴み取る。
それからゆうきに向かって指を3本、突き立ててみせる。
――3年後、また会いにくる。
かつて悩んでいたはずのゆうきは、いまだに迷子のままだった。自然の中を駆け抜けたふたりの夏を、ゆうきも記憶から消せるはずなんてなかった。だから3年後のゆうきだって、自分のあり方を迷い続けているに違いない。
ゆうきに男の子を忘れることを諦めさせてしまったのは、この俺自身だ。それなら――。
俺はゆうきの未来の選択を見届けなくちゃならない。人生で選べる道なんて、ひとつしかないのだから。
そして変わりゆくふたりの関係がどんな風景になるのか、俺はまだ想像できっこない。
男の友情は生きているのか、はたまた違う感情に蝕まれてしまうのか。怖いけれど、知らなくちゃならない。その答えはふたりで探さないと見つからないものだから。
たとえ次に出会う夏が終わるころ、違った痛みが待っていたとしても。
【了】
目的地は3年前、夏休みに滞在していた親戚のおじさんの家だ。またここに来たいという俺の願いをおじさんは快く聞き入れてくれた。
俺は声変わりをしたし、背は二十センチほど高くなった。陸上部に入部して肌も焼けた。俺は『あいつ』に追いつけるくらい、男らしくなっただろうか。さて、『あいつ』はどうだろう。あの時は小柄だったけれど、『あいつ』だって成長しているはず。
けれど心の中はなにも変わらないでいてほしいと願う。なにせ『あいつ』はかつて俺と『男の友情』を分かち合った仲なのだから。
☆彡
父方の兄にあたるおじさんは町工場を営んでいた。移転することになったので、手伝う父と一緒に夏の間、住み込むことになった。俺が小学5年生の時だった。
けれどまさか電波が届かず、やりたいゲームができないとは。まじで勘弁してほしい。退屈な田舎で夏を過ごすなんて地獄に突き落とされた気分だ。
途方にくれた俺は、工場のまわりをうろついていた。あたりは風が吹けば砂埃が立つような荒れた更地だった。その更地にはすりばち状のくぼみがたくさんあった。なんだろう? ミステリーサークルにしては迫力がなく、誰かのいたずらにしては数が多くて円が綺麗すぎる。
すると隣から、するっと細い草のつるが伸びてきた。振り向くと俺よりも少し小柄な、浅黒い肌をした子供がつるを握っている。逆光で暗い顔の中、瞳だけが爛々と輝いていた。
つるの先には小さな花のつぼみがついていた。その子はいたずらっぽい顔で草のつるを凹みの中に落とし、誘いをかけるように小刻みに動かす。するとすりばちの底から何かが姿を現した。灰色をした蜘蛛のような生き物で、砂をかけてそのつぼみを落とそうとする。
蟻地獄の巣だ。はじめて見た。
虫を騙すのに成功したからか、その子は面白そうな顔で笑っていた。しばらくすると蟻地獄はつぼみが偽物だと気づいたようで、残念そうに砂の中へと戻っていった。
その子は「やってみる?」と言い、俺の答えを待たずにつるを手渡した。受け取ってしまったので試さないわけにはいかない。けれど俺が誘いをかけても、蟻地獄は誘いに乗ってこない。うまくいかない様子に、その子はまた楽しそうな顔をする。
「ははっ、簡単そうに見えるでしょ」
「くそう、俺のだけ見抜くとは……」
その子は近所に住んでいる俺と同い年の子だった。名前は「ゆうき」。大自然を相手にできそうな、かっこいい名前だと思った。
それからの毎日は、退屈とは無縁になった。ゆうきは遊び相手がいないのか、毎日俺のことを誘いにきた。俺はその誘いに喜んで乗っていた。
眺めのいい高台にある公園には、おおきなコンクリート製の『箱』が置いてあった。集めた枯れ葉が詰め込まれている。
「これで腐葉土を作っているんだって」
「腐葉土?」
「堆肥のことだよ。植物の肥料になるんだ。で、この中にさ――」
ゆうきは両手でその腐葉土を掘り起こす。大きなミミズが出てきて驚いたけれど、ゆうきは平然とミミズを掴んでいた。
「こいつを釣りの餌にするんだ」
「まじか」
「だから集めてよ」
俺は木の枝で掘り起こし、ゆうきが袋の中に詰めていった。
ゆうきの家の物置小屋には釣り竿や釣具が置いてあった。タンクトップに半ズボンの格好であぐらをかいて釣りの仕掛けをこしらえる。俺も見よう見まねで仕掛けを作る。
捕ったミミズを餌にして、近所を流れる小川に仕掛けを投げ込んでおく。ふたりで肩を並べてワクワクしながら待つと、魚がかかって竿が引っ張られ俺の心臓は跳ね上がった。
無我夢中で竿を立てて釣り上げた魚はナマズだった。キューキュー鳴く様子が可愛かったので持ち帰って飼おうと盛り上がった。けれどバケツに入れておいたらいつの間にかいなくなった。近くにいた猫がくわえていて、俺たちに気づくとあわてて逃げていった。だからその日の一番の収穫は、俺がミミズを触れる男に成長したことだった。
ゆうきは昼間、近所の森の中に忍び込み、虫が集まりそうなクヌギの木に目を付けた。おじさんの家の床下にあった梅酒を拝借し、そこに漬け込んだパイナップルを木の根元に仕掛けておく。そして夜に家を抜け出して見に行き、仕掛けた場所に蛍光灯を当てる。
ゆうきの罠の効果はてきめんで、パイナップルの上ではカブトムシやクワガタがお祭り騒ぎとなっていて、俺はその賑やかさに感動した。デパートで高値の虫は、じつは世の中にたくさんいて、しかもみんな『のんべえ』だったことにも。
ほんとうの男の子の遊びというものを、俺はゆうきから学んでいた。
俺がゆうきと一緒に遊んでいたせいか、ばあちゃんは「ゆうきちゃんも、ひろしと一緒に食べんさい」と言ってスイカを出してくれた。もちろんどっちが早く食べられるか競争になる。男はなんでも勝負したくなる性分だ。勝負はエスカレートし、あとで従兄の光之にいちゃんが「あれ、俺のぶんは?」とうろたえることになった。ふたりで顔を見合わせ、そそくさと逃げ出した。
俺は自由な世界で生きているゆうきが心底、うらやましかった。けれどゆうきもまた、俺をうらやむことがひとつだけあった。
「この帽子いいなぁ、ほしいなぁ……」
ゆうきは俺の赤い野球帽を手に取り、物欲しそうに眺めていた。
「だめだよ、父ちゃんがアメリカで買ってきてくれた、俺の宝物なんだ」
世界の至宝、メジャーリーグで活躍する大滝選手の帽子と同じデザインのもの。それだけで野球が強くなった気がする。それがきっかけで、プラスチックバットとビニールボールを持ち出しふたり野球に燃えた。けれど、帽子をかぶった俺はゆうきにさんざん打たれた。会心のあたりは偏屈なじいさんの家に吸い込まれていった。俺たちは抜き足差し足忍び足で取り返し、泥棒の気分を味わうことになった。心臓が高鳴り、じいさんの家を脱出できた瞬間にしてふたりで笑い転げた。
俺たちは思う存分、夏を謳歌していた。俺にとっては知らない世界の幕開けで、その夏がどこまでも続くと願っていた。
思い返すと、ふたりの時間はさんさんと降り注ぐ夏の太陽よりもまばゆく、夏の蝉の鳴き声よりもずっと賑やかだった。
☆彡
きっとまた、あの日とおなじ夏が来る。俺はそう信じて駅を降りた。
だからおじさんの家に行く前に寄り道をしようと思った。思い出巡りのつもりだ。
最初に町工場のあった場所を訪れる。するとその場所は開発されショッピングモールができていた。たくさんの車が出入りし、人の往来も盛んになっている。一周回ったけれど、蟻地獄の巣はどこにもなかった。町工場移転の理由が地域の開発だとおじさんが言っていたのを思い出す。
魚釣りをした小川に向かう。けれど小川はすっかり姿を変えていた。アスファルトで舗装された道となり、隅のほうに油の浮いた細い用水路があるだけだった。しかたないと思う反面、あの日の思い出に傷をつけられたような気がした。
同時に不安が沸き起こる。あいつはこの変化を悲しんでいないだろうか? 自然を失った場所でいきいきしていられるのだろうか? それに――あいつは、あの夏のあいつのままなのだろうか?
俺の足は自然と高台の公園に向かっていた。俺は三年後の夏にまた来るとゆうきに宣言していた。待ち合わせの場所はこの公園だ。ただ、日付も時間も約束なんてしていない。毎日会っていたから、来れば会えるだろうと思っている。そう信じている。大滝選手の帽子をかぶっていたから、俺のことを間違うはずはないという確信もあった。
着いた頃には日が傾き、あたりは淡いオレンジ色に染まっていた。ちいさな子供を連れた家族連れが何組かいた。日傘をさしたワンピース姿の女子に、日陰で新聞を読んでいるおじいさん、それにかつての俺と同じくらいの小学生たち。
ゆうきの姿がなかったので、俺は柵に手をかけて街を眺めていた。
風が吹いてきた。東京と違って夕方には涼しさを覚える風が吹く。空気が軽やかに流れている。
ふと、左隣にワンピースの女の子が並んでいるのに気づいた。肩よりも少し長いくらいの髪が風に舞っている。日傘のせいで顔は見えないけれど、なんとなく寂しげな雰囲気に思えた。
「こんにちは」
唐突に声をかけられてドキリとした。女の子は苦手でろくに口を聞いたことがない。それなのに見知らぬ相手との会話はハードルが高すぎる。
けれど俺は違和感を覚えた。この声は俺の記憶の中に刻まれていたものだ。
まさかと思った。否定したかった。心底、冗談だと思いたかった。けれど俺の首は自分の拒絶を振り切るように左を向いてしまう。
「――ゆうき?」
くりっとした瞳は記憶のままだけれど、肌は浅黒い日焼けの色ではなかった。
そよそよと吹く風が、自分の呼吸が、流れる時間が止まってしまった。あんなにも音の主役だったひぐらしの鳴き声さえも耳に届かなくなる。
「そうだよ、ひさしぶりだね」
やわらかな笑顔で俺の反応をうかがう。何かを言わなければいけない。そうでなければ動揺していることに気づかれてしまう。だけどうまく繕える言葉が思い浮かばない。
「驚いたっていうことは……もしかして勘違いしてた?」
相手は女子のするような小首のかしげ方で俺の顔色をうかがう。
ひさしぶりと返せばいいのか? いや、俺はきみを知らない。俺が会いにきたのは男友達だ。
全身が麻酔をかけられたような、奇妙な感覚に陥っていく。思い出の中の友情が壊されていく。確かな現実として信じていた城が、廃墟となって崩れていく。
「あー、やっぱり勘違いしてたんだ」
「あたりまえだろ!」
思わず声を荒らげている自分に気づく。ゆうきはさっと表情を曇らせた。
「ちょっとは褒めてもいいんじゃない、わたし、これでもおしゃれして待っていたんだよ」
「なんでそんな格好してんだよ!」
「きみがくるって、信じて毎日待っていたのに、それひどいんじゃない」
「男の友情はどこに消えたんだ? 最初からなかったのか?」
大切な宝物を奪われたような怒りがふつふつと湧いてくる。俺の苛立ちにゆうきは困ったような顔をし、髪をかきあげて口を尖らせる。
「……だってさ、しょうがないじゃん」
「なにがしょうがないんだよ。男らしいお前はどこに行っちまったんだよ!」
「そう言われたって……中学に入れば制服もあるし、身体だって女の子らしくなるし」
思い詰めたような顔をしたので、俺ははっとなった。ひょっとしてと思いおそるおそる尋ねる。
「もしかして、心と身体の性別がちがうとかいう……」
「ううん、そういうんじゃないよ。わたしが好きだったことが、女の子よりも男の子が好きだったことだっただけ」
乾いた言葉でそう言った後、ただそれだけなのにね、と付け加えた。
「女の子には、虫と遊ぶなんて気持ち悪いよって言われて。男の子には、女子は足手まといだから嫌だって言われてさ。だからクラスののけ者だったんだ、わたし」
「あ……」
ずっと俺と一緒に過ごしていたのは、友達がいなかったからなのか。つまりゆうきは夏の間、周囲の否定から身を隠して、自分自身でいられる場所を探していたのだ。
「男の子みたいなことするのって、恥ずかしいことなのかなぁ……」
「……それは親に言われたことなのか」
「うん……。女の子らしくないことはやめなさいって」
ゆうきはきっと、まわりから常識の『らしさ』を求められていたのだろう。
「ひろしだけは、そういうの気にしないひとだと思ってたんだ」
俺はその言葉に、心底打ちのめされた。俺はゆうきにとって唯一の、『自分らしさ』を肯定してくれるひとだったはずだ。その願いを、俺は今ここで壊してしまったのだ。
「だからきみにどうしても会いたかった。きみがわたしのことをどう思っていたのか、確かめたかったんだ」
涙を浮かべるゆうきに、俺は何も言い返せないでいた。ゆうきはため息をひとつついてからぽつりとこぼす。
「でも勘違いだったら仕方ないかぁ……」
ああ、もしもゆうきの見た目が女子でも、心が男子であってくれたのなら。純粋に俺との関係を男の友情だと思ってくれていたのなら。
友情は友情のままで色褪せることなどなかったはずなのに。
あの日の夏は、幻想で、虚像で、蜃気楼のようなものだったのだろうか。
俺が混迷するなか、ゆうきが突然視線を空へ向けた。
「あっ、そうだ!」
それから振り向き、ひとつの提案を持ちかける。
「ねえ、あのときできなかったこと、もう一度挑戦してみない?」
「できなかったこと……?」
思い返すと、ゆうきとふたりで成し得なかったことが、たしかにひとつだけあった。カブトムシを捕りに行った時、森の中で見かけた鳥の捕獲だ。
天然のチャボ。ニワトリに似ているけれど、それよりも小型で、木々の間を自由に飛び回る鳥。俺はそいつを無性に捕まえたくなった。男の狩猟本能が駆り立てられたのだ。
結局、空を飛ぶ相手はふたりがかりでも太刀打ちできなかった。けれどふたりが大人になれば捕まえられるかもしれないとも思った。だから再戦を誓って拳を合わせた。
☆彡
翌日、ゆうきと俺は森の入り口で待ち合わせをした。ゆうきは長袖のシャツとジーパン姿で、つんとしたすまし顔で現れた。すこしだけ男らしく見えた。
ふたりで顔を見合わせ無言でうなずく。かつて戦友だったゆうきは、この日だけ俺の前に戻ってきた。
「準備はいい?」
「ああ、今度こそ捕まえてやる」
風に揺れる森の中で目を凝らして周囲を見回す。けれどチャボの姿はどこにも見当たらない。
気持ちを落ち着かせ、身体の感覚を研ぎ澄ます。遠くの方で、かさり、と風とは違う音が聞こえた。俺よりもゆうきのほうが先にその存在に気づいた。
「いたよ、あそこだ」
目を凝らすと焦げ茶色の鳥の姿があった。岩の上に飛び乗りあたりを見回している。
息を止めて身をひそめる。風の向きを利用して匂いを消し、目と目が合わないよう注意深く近づく。
けれど足音を完全に消すことはできなかった。チャボは俺の存在に気づいて驚き、一気に逃げ出してしまう。
「ひろし、あいつを追うよ」
「ああ、もちろんだ」
チャボは森の奥へ飛び込むように逃げてゆく。俺は目を見開き、一瞬たりともその姿を見失わなかった。
ゆうきの足は岩や木の根を避けながら俊敏に動く。俺の心臓は新鮮な森の空気を吸い込み高鳴っていた。チャボを捕まえるためには、その素早さに勝ることが不可欠だった。
急な斜面にさしかかり、枝や蔦との闘いが始まる。ゆうきは優れたバランス感覚で自然の障害物をかわしてチャボを追う。やっぱり『あいつ』は『あいつ』だったと思いながら、俺も負けじと草木を割って進む。
「ゆうき、俺は左から回り込む。おまえは反対側を!」
「了解!」
ゆうきは風を裂くように森の中を駆ける。
チャボは一瞬、足を止めた。作戦に気づいたのか、ふたりを確かめた後、翼をはためかせた。そして木の枝へと向かって飛んでいってしまった。
「くそっ……!」
逃げられたと悔しがったとき。神風とでも言うべき強風が吹いてきた。チャボが飛び乗った枝はひどく揺れ、留まっていられないようだった。揺れの弱い、低くて太い枝に降りてきた。
「あそこなら届くかも」
それを見たゆうきは迷わず木に飛びつき登り始めた。ゆうきの目には、チャボを捕まえるための燃えるような情熱が宿っている。
ゆうきは軽やかに枝へと移り、チャボとの距離を縮めてゆく。えいっ、と手を伸ばして捕まえようとする。同時にチャボも羽を広げて飛び立った。けれどゆうきの手がチャボの羽をかすめ、チャボはバランスを崩す。
「いまだ、ひろし!」
「おう!」
俺は全身全霊を込めて飛び上がり、空中でチャボの足を捉えた。地面に降りたと同時にチャボの上に草のつるを重ねて閉じ込める。
「はぁ、はぁ、はぁ……」
ゆうきは木からゆっくりと降りてくる。俺もゆうきも肩で息をしていた。興奮と達成感で全身から汗が吹き出し、手は震えっぱなしだ。森を舞台に繰り広げられた追いかけっこは、ふたりの勝利で幕を閉じた。
「やったな、ゆうき!」
「まさか捕れるなんて思わなかったよ」
「無理だと思ってたのかよ!」
笑いながら足元を見ると、チャボは草のつるに閉じ込められ、恐怖に怯えた顔をしていた。
「おまえを食ったりしないから。ただ捕まえられるか挑戦してみただけだ」
ゆうきは仰向けになって頭上を見上げる。いつの間にか風は落ち着きを取り戻していた。息を整えてぽつりとつぶやく。
「……やっぱり、男の子ってイイネ」
「だろう? 俺はゆうきに出会ってそう思えたんだ」
「生きたいように生きられるのって、なんだか羨ましいなぁ……」
「そっか、そうだよなぁ」
達成感が背中を押したのか、ゆうきはとつとつと心情を吐露しはじめた。
「正直、あの頃の無邪気な関係が懐かしくて愛おしいよ。それのに、わたしはだんだん女の子になっていく。ひろしとおなじではなくなって、きみの言う『男の友情』を裏切るしかなくなっちゃうんだ」
その言葉に、ゆうきがチャボを捕まえようと提案した理由も痛いほど伝わっていた。
それは、ふたりの夏をここで終わらせるためだ。
永遠に続くわけではない男の友情を、悔いなく締めくくろうと思ったに違いない。
ああ、俺はなんで気づかなかったのだろう。ゆうきは俺が想像できないくらいの、途方もない苦しみを抱えていたことに。そしてこの3年間、抗えない変化にさらわれてゆく自身の心を、必死でつなぎ止めていたはずなのに。
「じゃあ逃がしてあげようか」
ゆうきがそう言ったので、ふたりでチャボを抱きかかえ空に向かって掲げる。チャボは翼をはためかせ、森の中へと飛んで逃げていった。ゆうきは黙ってその姿を見送っていた。
いつまでも、いつまでも。
☆彡
駅のホームは閑散としていて、俺以外の人の姿はなかった。鳥のさえずりだけが響いている。
ふと、柵の向こうにゆうきの姿を見つけた。ゆうきは電車通り沿いの街路樹に登り、黙って俺を見下ろしていた。俺も何も語らずゆうきを見上げていた。男同士なら、別れの言葉なんてさほどいらないはずだ。
「まもなく二番線に電車がまいります」
無言のふたりの間に電車が流れ込んでくる。ゆうきの姿が遮られた。電車に乗り込み、奥の座席から木の上を見上げる。
ゆうきはいつの間にか、大きな裁ちバサミを手にしていた。ウエストバッグが半開きになっている。ハサミを目の前に突き出し、それを首の後ろ回した。俺はまさか思った。
あたりの音が消え、一閃の音が響く。
――じゃきん。
ゆうきは躊躇なく自身の髪を断ち切った。迷いや葛藤を振り切るかのように。荒々しく、潔く。
女の子の証でもある髪の切れ端を、空に向かって舞い上げる。それを風が遠くへ運んでいった。
泣きそうな顔で笑ったゆうきを見て、『あいつ』はやっぱり『あいつ』のままだったと、俺は胸が締めつけられた。
俺は無意識に帽子を脱ぎ、ゆうきの方に向かって投げ飛ばしていた。大滝選手の帽子を風が運んでゆうきの元へ送り届ける。ゆうきは驚いた顔をしたが、持ち前の運動神経でそれを掴み取る。
それからゆうきに向かって指を3本、突き立ててみせる。
――3年後、また会いにくる。
かつて悩んでいたはずのゆうきは、いまだに迷子のままだった。自然の中を駆け抜けたふたりの夏を、ゆうきも記憶から消せるはずなんてなかった。だから3年後のゆうきだって、自分のあり方を迷い続けているに違いない。
ゆうきに男の子を忘れることを諦めさせてしまったのは、この俺自身だ。それなら――。
俺はゆうきの未来の選択を見届けなくちゃならない。人生で選べる道なんて、ひとつしかないのだから。
そして変わりゆくふたりの関係がどんな風景になるのか、俺はまだ想像できっこない。
男の友情は生きているのか、はたまた違う感情に蝕まれてしまうのか。怖いけれど、知らなくちゃならない。その答えはふたりで探さないと見つからないものだから。
たとえ次に出会う夏が終わるころ、違った痛みが待っていたとしても。
【了】