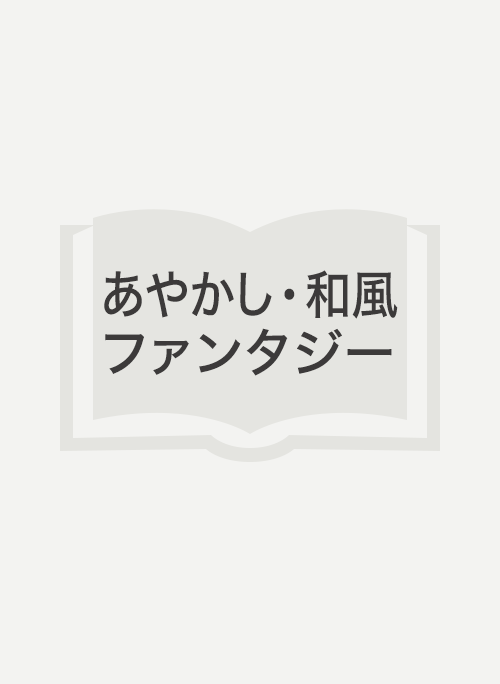「那美の力が他者に気づかれないように澄宮雪葉が封印したからだ」
「お母さまが……!?どうして綺世さまが母を知っているのですか?」
綺世の口から聞く、母の名前に驚きを隠せない。
それは他の三人も同じようで普段は堂々としている立ち振る舞いだが、互いに顔を見合わせて動揺している様子がうかがえる。
「私が澄宮雪葉と会話したのは彼女の魂が天界に迎え入れられた際。彼女は巫女の中でも稀有な力、未来予知を宿していた」
「未来予知!?そんなこと私は知らないわ!」
それまで黙っていた継母が声を荒げる。
他の二人も様子を見る限り、同じようだ。
綺世は呆れたように、ため息をつくと淡々と話を続けた。
「当たり前だ。未来予知の力があると知ればお前たちが悪用すると恐れたからだ。それは愛娘である那美に対しても同じ。自らの命が長くは保たないと知った澄宮雪葉は那美の夢想以外の力を封じた」
「お母さまが……」
時々、無能な自分を恨むこともあった。
由緒正しき家に生まれ、普通の巫女にすらなれない自分は蔑まれても仕方ないと。
星巫女の姉を支え、邪魔をしないように影で生きていくのだと全てを諦めていた。
しかし知らないうちにずっと助けられ、見守られていたのだ。
胸がじんわりと温かくなってそっと手を添えた。
「私と那美が出逢うと知っていた彼女は大切な娘を守ってほしいと託したんだ。今まで黙っていてすまない」
憂いを帯びている綺世に那美は首を横に振った。
「謝らないでください。こんなわたしを想ってくれていた人が二人もいる、それだけで幸せですから」
「……ありがとう、那美」
素直な想いを伝えると綺世の表情に笑顔が戻る。
しかしそこで穏やかな空気を壊すような美桜の声が中庭に響く。
「本当に妹が姫巫女で白龍さまの花嫁だとしても要領も悪く、教養も無いのではその立場には相応しくありません!」
幸せな夢から覚めるような言葉にズキリと胸が痛む。
反論も出来ない姉の正しい意見に黙り込む那美。
(……そうだ。たとえわたしが姫巫女や花嫁でもそれに見合うものがない。綺世に逢えて浮かれていたのね)
本当ならば夢だけでなく現実でも綺世の隣にいたい。
でもその気持ちだけでは龍王である彼と同じ未来を歩むことは不可能。
「綺世さま、わたしは貴方に相応しくないです。だから──」
口から出るのは本音とは真逆の言葉。
必死に気持ちを押し殺して紡ぐ。
『一緒にはいられない』そう伝えようとしたとき、綺世が那美を引き寄せ腕の中へ閉じ込めた。
「私は那美が良いのだ。他の誰でもなく」
「でも、わたしなんかが隣にいたら綺世さまのご迷惑になります……!」
「そんなことは絶対にない。那美の優しさや笑顔にどれだけ救われたことか。出逢ってから君を想わなかった日は一日もないよ」
「あ、やせさま……」
耳に届く声も温かな体温も全てが那美にとって大好きなもので失いたくない。
静かに涙を流す那美の頭を撫でながら、綺世は耳元で囁いた。
「那美の本当の気持ちを教えて?」
綺世や母の想いは一歩を踏み出すこの日の為にあったのだと今分かる。
もう家族に縛られずに自由に生きる。
胸に強い決意を固めた那美は顔を上げ、綺世をまっすぐ見つめた。
「わたしは……綺世さまとずっと一緒にいたいです」
決意を宿した瞳に綺世は笑顔で頷くと頬に手を伸ばし、涙を拭う。
「それでは那美、この家を出て私と翡翠の町で暮らさないか?」
「翡翠って確か、龍さまとその花嫁が暮らすっていう……」
『ああ』と頷く綺世。
龍と花嫁が暮らす町、翡翠。
通常、二人が想いを通わせても巫女を天界へ連れて行けない為、特別な結界が貼られた町へ住むことになる。
巫女本人の同意があれば、生家を離れてすぐにでも共に暮らすことが出来るのだ。
そして那美の中ですでに答えは決まっていた。
(わたしはこのまま、この家にいても幸せになれない)
澄宮家という鳥籠から抜け出して恋い慕う人の傍にいたいという想いが芽生えたのだ。
「お、お待ちください!那美は大事な娘で──」
「お前には聞いていない」
『大事な娘』などと父の口から聞いたこともない。
那美が姫巫女だと分かったから、その力欲しさに止めているのだろう。
しかし父の本性を知っている綺世は彼の願いも即座に却下する。
「那美!貴方は家族を見捨てたりしないわよね!?」
継母はまるで脅迫するような言い方だ。
以前までだったら自分の考えも意見も言えずに飲み込んでいた。
でも今は違う。
綺世が前へ進む勇気を与えてくれた。
那美は静かに深呼吸をすると綺世を見つめた。
「わたしは綺世さまと翡翠の町へ行きます」
綺世は嬉しそうに目を細めて頷くと呆然とする三人に視線を移す。
「細かな手続きについては後日、使いの者をこちらに送る。そして今まで那美を傷つけた罰も一本の落雷で済むと思うな。覚悟しておけ」
「そんな……」
「これは決定事項だ」
「……っ。は、い」
美桜は唇を軽く噛むと俯いてしまって、その表情を伺うことは出来なかった。
そして屋敷の一部を壊され、対応に追われている使用人たちが当主の指示を仰ぎに来ると、三人は足元をよろめかせながら行ってしまった。
先ほどまで騒がしかった中庭に静けさが戻る。
「早速だがこれから共に翡翠の町へ行くか?那美がすぐにでも私と宮で暮らせるように準備は整えているが」
「まさか綺世さま、わたしがそう答えると見越して準備を?」
「ああ。夢で那美は私と別れるとき、寂しそうにしていたから。勿論、私も同じだけど」
「わたし、そんなに顔に出ていますか?」
慌てて赤く染まった両頬を手のひらで隠す那美を見て綺世はくすりと笑った。
「表情がころころ変わって可愛いよ」
「かわっ……!?」
夢でも何度か愛を囁いてくれていたが慣れることはない。
恥ずかしさを必死に堪える那美の手に綺世は自分の手を重ねた。
「それで、どうする?今日から私と暮らすか?」
真剣な綺世の瞳と声に次第に落ち着きを取り戻す。
すでに答えは決まっていて悩むことは無かった。
夢でしか逢えなかった彼と少しでも長くいたい──。
「はい。よろしくお願いします」
「こちらこそよろしく頼む。ずっとこの日を待ち望んでいた。これから先、必ず那美を守り抜いて愛すと誓うよ」
存在を確かめるように抱きしめられて胸が高鳴る。
那美は綺世と歩む幸せな未来を想像しながらそっと彼の背中に腕を回したのだった。
「お母さまが……!?どうして綺世さまが母を知っているのですか?」
綺世の口から聞く、母の名前に驚きを隠せない。
それは他の三人も同じようで普段は堂々としている立ち振る舞いだが、互いに顔を見合わせて動揺している様子がうかがえる。
「私が澄宮雪葉と会話したのは彼女の魂が天界に迎え入れられた際。彼女は巫女の中でも稀有な力、未来予知を宿していた」
「未来予知!?そんなこと私は知らないわ!」
それまで黙っていた継母が声を荒げる。
他の二人も様子を見る限り、同じようだ。
綺世は呆れたように、ため息をつくと淡々と話を続けた。
「当たり前だ。未来予知の力があると知ればお前たちが悪用すると恐れたからだ。それは愛娘である那美に対しても同じ。自らの命が長くは保たないと知った澄宮雪葉は那美の夢想以外の力を封じた」
「お母さまが……」
時々、無能な自分を恨むこともあった。
由緒正しき家に生まれ、普通の巫女にすらなれない自分は蔑まれても仕方ないと。
星巫女の姉を支え、邪魔をしないように影で生きていくのだと全てを諦めていた。
しかし知らないうちにずっと助けられ、見守られていたのだ。
胸がじんわりと温かくなってそっと手を添えた。
「私と那美が出逢うと知っていた彼女は大切な娘を守ってほしいと託したんだ。今まで黙っていてすまない」
憂いを帯びている綺世に那美は首を横に振った。
「謝らないでください。こんなわたしを想ってくれていた人が二人もいる、それだけで幸せですから」
「……ありがとう、那美」
素直な想いを伝えると綺世の表情に笑顔が戻る。
しかしそこで穏やかな空気を壊すような美桜の声が中庭に響く。
「本当に妹が姫巫女で白龍さまの花嫁だとしても要領も悪く、教養も無いのではその立場には相応しくありません!」
幸せな夢から覚めるような言葉にズキリと胸が痛む。
反論も出来ない姉の正しい意見に黙り込む那美。
(……そうだ。たとえわたしが姫巫女や花嫁でもそれに見合うものがない。綺世に逢えて浮かれていたのね)
本当ならば夢だけでなく現実でも綺世の隣にいたい。
でもその気持ちだけでは龍王である彼と同じ未来を歩むことは不可能。
「綺世さま、わたしは貴方に相応しくないです。だから──」
口から出るのは本音とは真逆の言葉。
必死に気持ちを押し殺して紡ぐ。
『一緒にはいられない』そう伝えようとしたとき、綺世が那美を引き寄せ腕の中へ閉じ込めた。
「私は那美が良いのだ。他の誰でもなく」
「でも、わたしなんかが隣にいたら綺世さまのご迷惑になります……!」
「そんなことは絶対にない。那美の優しさや笑顔にどれだけ救われたことか。出逢ってから君を想わなかった日は一日もないよ」
「あ、やせさま……」
耳に届く声も温かな体温も全てが那美にとって大好きなもので失いたくない。
静かに涙を流す那美の頭を撫でながら、綺世は耳元で囁いた。
「那美の本当の気持ちを教えて?」
綺世や母の想いは一歩を踏み出すこの日の為にあったのだと今分かる。
もう家族に縛られずに自由に生きる。
胸に強い決意を固めた那美は顔を上げ、綺世をまっすぐ見つめた。
「わたしは……綺世さまとずっと一緒にいたいです」
決意を宿した瞳に綺世は笑顔で頷くと頬に手を伸ばし、涙を拭う。
「それでは那美、この家を出て私と翡翠の町で暮らさないか?」
「翡翠って確か、龍さまとその花嫁が暮らすっていう……」
『ああ』と頷く綺世。
龍と花嫁が暮らす町、翡翠。
通常、二人が想いを通わせても巫女を天界へ連れて行けない為、特別な結界が貼られた町へ住むことになる。
巫女本人の同意があれば、生家を離れてすぐにでも共に暮らすことが出来るのだ。
そして那美の中ですでに答えは決まっていた。
(わたしはこのまま、この家にいても幸せになれない)
澄宮家という鳥籠から抜け出して恋い慕う人の傍にいたいという想いが芽生えたのだ。
「お、お待ちください!那美は大事な娘で──」
「お前には聞いていない」
『大事な娘』などと父の口から聞いたこともない。
那美が姫巫女だと分かったから、その力欲しさに止めているのだろう。
しかし父の本性を知っている綺世は彼の願いも即座に却下する。
「那美!貴方は家族を見捨てたりしないわよね!?」
継母はまるで脅迫するような言い方だ。
以前までだったら自分の考えも意見も言えずに飲み込んでいた。
でも今は違う。
綺世が前へ進む勇気を与えてくれた。
那美は静かに深呼吸をすると綺世を見つめた。
「わたしは綺世さまと翡翠の町へ行きます」
綺世は嬉しそうに目を細めて頷くと呆然とする三人に視線を移す。
「細かな手続きについては後日、使いの者をこちらに送る。そして今まで那美を傷つけた罰も一本の落雷で済むと思うな。覚悟しておけ」
「そんな……」
「これは決定事項だ」
「……っ。は、い」
美桜は唇を軽く噛むと俯いてしまって、その表情を伺うことは出来なかった。
そして屋敷の一部を壊され、対応に追われている使用人たちが当主の指示を仰ぎに来ると、三人は足元をよろめかせながら行ってしまった。
先ほどまで騒がしかった中庭に静けさが戻る。
「早速だがこれから共に翡翠の町へ行くか?那美がすぐにでも私と宮で暮らせるように準備は整えているが」
「まさか綺世さま、わたしがそう答えると見越して準備を?」
「ああ。夢で那美は私と別れるとき、寂しそうにしていたから。勿論、私も同じだけど」
「わたし、そんなに顔に出ていますか?」
慌てて赤く染まった両頬を手のひらで隠す那美を見て綺世はくすりと笑った。
「表情がころころ変わって可愛いよ」
「かわっ……!?」
夢でも何度か愛を囁いてくれていたが慣れることはない。
恥ずかしさを必死に堪える那美の手に綺世は自分の手を重ねた。
「それで、どうする?今日から私と暮らすか?」
真剣な綺世の瞳と声に次第に落ち着きを取り戻す。
すでに答えは決まっていて悩むことは無かった。
夢でしか逢えなかった彼と少しでも長くいたい──。
「はい。よろしくお願いします」
「こちらこそよろしく頼む。ずっとこの日を待ち望んでいた。これから先、必ず那美を守り抜いて愛すと誓うよ」
存在を確かめるように抱きしめられて胸が高鳴る。
那美は綺世と歩む幸せな未来を想像しながらそっと彼の背中に腕を回したのだった。