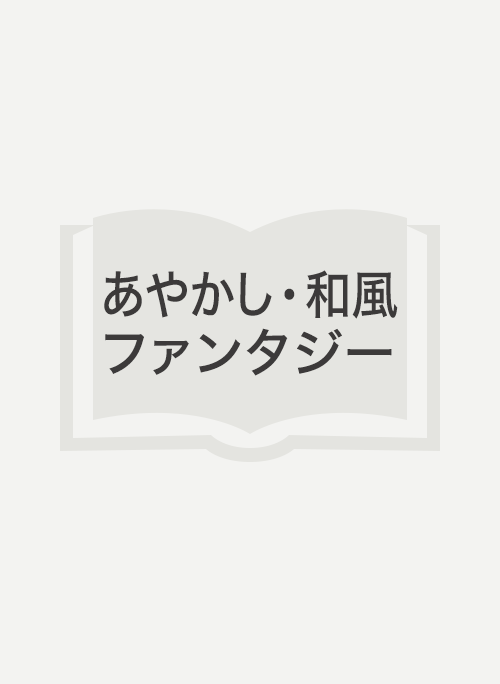「舞ったのはお前だけではない。私は那美の舞に導かれて地上に降り立ったのだ」
「なっ……!それは本当なの?」
美桜が殺気を含んだ瞳をこちらに向ける。
那美は突き刺すような視線に恐怖を感じながら、やっとのことで頷いた。
「は、はい。部屋の中で……」
「何ということだ!お前は舞を習得していないだろう!その上、巫女装束も纏わないで勝手に龍夜の儀を執り行うとは!澄宮家の人間として恥ずかしくないのか!?」
「龍夜の儀を行ったつもりはっ」
「貴方の不安定な舞のせいで美桜さんの舞が邪魔された。それで白龍さまが勘違いをなされてしまったのね」
「ち、違っ──」
次々と浴びる怒号に思わず後ずさりをする。
儀式の邪魔をするつもりなどまったく無かった。
しかし彼らは聞く耳を持たず、どんどんと話を進めていて入る余地が無い。
(誤解なのに……。わたしはただ自由に舞ってみたくて……)
いないもの同然に扱われるのはもう慣れているはずなのに、悲しみが押し寄せて逃げるように固く瞳を閉じた。
そして一段と強い夜風がおさまったとき。
「貴様ら死にたいのか?」
綺世の怒りの声が中庭に響いたかと思うと、一閃の稲妻が少し離れた屋敷に落ちた。
「きゃあー!!」
「うわぁ!!」
「何事!?」
三人は強烈な音に耳を塞ぐが那美には何故か小さく聞こえ動揺する。
「今のは……?それに音も……」
数回、瞬きをしていると綺世が優美な笑みを浮かべながらこちらに振り向いた。
「那美を傷つけたから罰を与えたんだ。ここで働く使用人たちには怪我をさせないように調整して落としたから大丈夫」
雷の音が那美だけに小さく聞こえたのは綺世の力によるもので驚かせたくなかったからという理由らしい。
(あの辺りってお父さま達の部屋があるところよね……)
呆気にとられながら遠くへ視線を向けると落雷が起きた場所は跡形もなく崩れ、煙が立っている。
使用人達が騒ぐ声が聞こえ、屋敷の一部を失った両親は膝から崩れ落ちている。
「で、でも私は強き力を持つ星巫女です!どうして無能の妹が花嫁に?到底納得できません!」
その場に一度、沈黙が訪れたあと美桜は眉をつり上げ、不服そうに綺世に訴える。
焦りさえも滲ませている彼女を綺世は一瞥すると手を伸ばし、那美の肩を引き寄せた。
(あ……)
服越しからでも分かる体温に胸が高鳴る。
しかし二人が距離を近づけたことで美桜の表情は悔しそうに歪んだことが分かりハッと戻される。
その問いの答えは那美も知りたかったこと。
そっと顔を上げて綺世の言葉を待っていると一呼吸置いて彼は口を開いた。
「那美は無能などではない。正真正銘の姫巫女だ」
「姫巫女……!?」
「え……?わたしが……?」
衝撃の事実に綺世以外の全員が驚きを隠せない。
それも当然だった。
巫女の力は通常、物心つく頃に目覚める。
しかし十七になっても、その傾向が見られなかったのに突然、巫女の最高位である姫巫女だと言うのだ。
(そういえば夢でも、わたしのことを姫巫女だって……)
別れ際に言った彼の一言、あれは聞き間違いではなかったのだ。
「まさか……。おい那美!もしや夢で白龍さまとお逢いしていたのか!?」
「は、はい」
怒鳴り声にも近い父の声に驚いて身体をびくりと震わせながらもこくりと頷く。
父から家事の言いつけ以外でこうして話しかけられたのは久しぶりかもしれない。
しかし那美の中で両親は絶対的な存在だと心得ている為、嬉しさの感情は無い。
「それはただの夢ではない。姫巫女特有の力の一つ、夢想だ」
「夢想、ですか?」
「貴方はそんなことも知らないの?」
「も、申し訳ありません」
「澄宮葉月、死ぬ覚悟ができているようだな」
「……っ」
那美を責めた継母を今にも殺してしまいそうな目つきで睨みつけている綺世。
巫女の素質が無いと決めつけられていた為、当然のごとく教養など皆無。
しかしその言い訳を家族のせいにしたくない。
(天奈女学院に通えなかったとはいえ、自分に出来ることがあったかもしれない)
後悔に加え、無知であることが途端に恥ずかしくなって、ただ謝ることしか出来ない。
顔に影を落とす那美を見て気持ちを汲み取ったのか小さく細い手に自らの手を重ねた。
「気に病むことは無い。これから知っていけば良い」
「綺世さま……。でも信じられないのです。わたしなんかが姫巫女だなんて」
憧れていた巫女。
そう知れて嬉しいはずだが気持ちは晴れない。
そもそも巫女の素質があったのならばどうして幼い頃に力が目覚めなかったのか謎が残る。
「私はずっと那美に秘密にしていたことがある」
「秘密?白龍さまであるということ以外にですか?」
「ああ。何故、今まで表向きで力が目覚めなかったのか──」
無数の星が降る夜、那美は優しくも儚い秘密を知るのだった。
「なっ……!それは本当なの?」
美桜が殺気を含んだ瞳をこちらに向ける。
那美は突き刺すような視線に恐怖を感じながら、やっとのことで頷いた。
「は、はい。部屋の中で……」
「何ということだ!お前は舞を習得していないだろう!その上、巫女装束も纏わないで勝手に龍夜の儀を執り行うとは!澄宮家の人間として恥ずかしくないのか!?」
「龍夜の儀を行ったつもりはっ」
「貴方の不安定な舞のせいで美桜さんの舞が邪魔された。それで白龍さまが勘違いをなされてしまったのね」
「ち、違っ──」
次々と浴びる怒号に思わず後ずさりをする。
儀式の邪魔をするつもりなどまったく無かった。
しかし彼らは聞く耳を持たず、どんどんと話を進めていて入る余地が無い。
(誤解なのに……。わたしはただ自由に舞ってみたくて……)
いないもの同然に扱われるのはもう慣れているはずなのに、悲しみが押し寄せて逃げるように固く瞳を閉じた。
そして一段と強い夜風がおさまったとき。
「貴様ら死にたいのか?」
綺世の怒りの声が中庭に響いたかと思うと、一閃の稲妻が少し離れた屋敷に落ちた。
「きゃあー!!」
「うわぁ!!」
「何事!?」
三人は強烈な音に耳を塞ぐが那美には何故か小さく聞こえ動揺する。
「今のは……?それに音も……」
数回、瞬きをしていると綺世が優美な笑みを浮かべながらこちらに振り向いた。
「那美を傷つけたから罰を与えたんだ。ここで働く使用人たちには怪我をさせないように調整して落としたから大丈夫」
雷の音が那美だけに小さく聞こえたのは綺世の力によるもので驚かせたくなかったからという理由らしい。
(あの辺りってお父さま達の部屋があるところよね……)
呆気にとられながら遠くへ視線を向けると落雷が起きた場所は跡形もなく崩れ、煙が立っている。
使用人達が騒ぐ声が聞こえ、屋敷の一部を失った両親は膝から崩れ落ちている。
「で、でも私は強き力を持つ星巫女です!どうして無能の妹が花嫁に?到底納得できません!」
その場に一度、沈黙が訪れたあと美桜は眉をつり上げ、不服そうに綺世に訴える。
焦りさえも滲ませている彼女を綺世は一瞥すると手を伸ばし、那美の肩を引き寄せた。
(あ……)
服越しからでも分かる体温に胸が高鳴る。
しかし二人が距離を近づけたことで美桜の表情は悔しそうに歪んだことが分かりハッと戻される。
その問いの答えは那美も知りたかったこと。
そっと顔を上げて綺世の言葉を待っていると一呼吸置いて彼は口を開いた。
「那美は無能などではない。正真正銘の姫巫女だ」
「姫巫女……!?」
「え……?わたしが……?」
衝撃の事実に綺世以外の全員が驚きを隠せない。
それも当然だった。
巫女の力は通常、物心つく頃に目覚める。
しかし十七になっても、その傾向が見られなかったのに突然、巫女の最高位である姫巫女だと言うのだ。
(そういえば夢でも、わたしのことを姫巫女だって……)
別れ際に言った彼の一言、あれは聞き間違いではなかったのだ。
「まさか……。おい那美!もしや夢で白龍さまとお逢いしていたのか!?」
「は、はい」
怒鳴り声にも近い父の声に驚いて身体をびくりと震わせながらもこくりと頷く。
父から家事の言いつけ以外でこうして話しかけられたのは久しぶりかもしれない。
しかし那美の中で両親は絶対的な存在だと心得ている為、嬉しさの感情は無い。
「それはただの夢ではない。姫巫女特有の力の一つ、夢想だ」
「夢想、ですか?」
「貴方はそんなことも知らないの?」
「も、申し訳ありません」
「澄宮葉月、死ぬ覚悟ができているようだな」
「……っ」
那美を責めた継母を今にも殺してしまいそうな目つきで睨みつけている綺世。
巫女の素質が無いと決めつけられていた為、当然のごとく教養など皆無。
しかしその言い訳を家族のせいにしたくない。
(天奈女学院に通えなかったとはいえ、自分に出来ることがあったかもしれない)
後悔に加え、無知であることが途端に恥ずかしくなって、ただ謝ることしか出来ない。
顔に影を落とす那美を見て気持ちを汲み取ったのか小さく細い手に自らの手を重ねた。
「気に病むことは無い。これから知っていけば良い」
「綺世さま……。でも信じられないのです。わたしなんかが姫巫女だなんて」
憧れていた巫女。
そう知れて嬉しいはずだが気持ちは晴れない。
そもそも巫女の素質があったのならばどうして幼い頃に力が目覚めなかったのか謎が残る。
「私はずっと那美に秘密にしていたことがある」
「秘密?白龍さまであるということ以外にですか?」
「ああ。何故、今まで表向きで力が目覚めなかったのか──」
無数の星が降る夜、那美は優しくも儚い秘密を知るのだった。