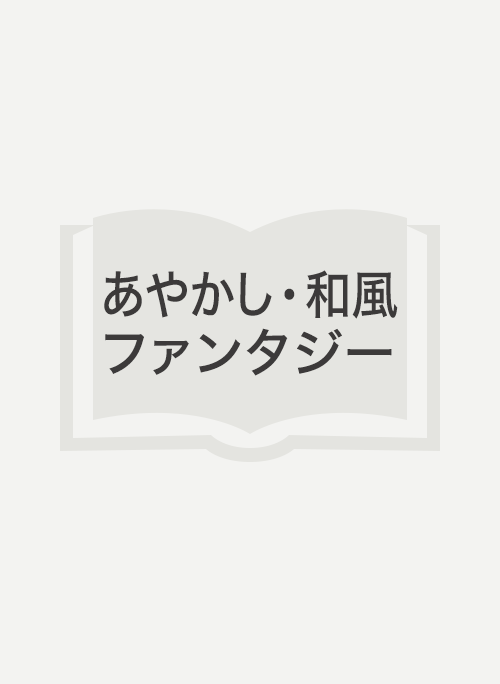微かに光の気配を感じて瞼を開く。
寝室で寝ていたはずなのに視界に入るのは色鮮やかな花畑と透き通るほど美しい湖。
このような状況に置かれても特に驚きはしない。
もう何度も経験しているから。
「那美」
低く艶やかな声が耳に届く。
自分の名を呼んでいることに気がついた少女はゆっくりと振り返った。
「綺世さま」
少し離れた場所に優しい笑みを浮かべた青年が立っている。
肩まで伸びた絹のような髪にシミ一つない肌、赤い瞳は長い睫毛に縁取られており、まるで精巧に作られた人形のよう。
綺世、と少女に自分の名を呼ばれた青年は、さらに嬉しそうに宝石のような瞳を細めた。
二人は引き寄せられるように歩み寄る。
すぐに触れられるほど近づくと綺世は手を伸ばし目の前にいる少女、那美の頬に触れた。
手から伝わる体温がじんわりと広がり、久しぶりに感じる温もりが嬉しくて那美は微笑む。
「こうして逢うのは久しいな。変わりはないか?」
「はい。わたしは大丈夫です。綺世さまは──」
「嘘だろう」
「……!」
絢世の表情が笑みから、こちらの真意を探るような真剣なものへと変わった。
那美はギクリとして視線を逸らす。
嘘など本当はつきたくない。
いつも自分の身を案じてくれている彼に素直でいたい。
しかし心のどこかにもうこれ以上、心配させたくないという思いもあって、本音とは反対の言葉を口にしてしまう。
「……申し訳ありません」
嘘をついてしまったことに罪悪感を感じて謝ると綺世は首を横に振った。
「私に心配をかけたくなかったのだろう?優しいな、那美は。……だからこそいつかその心体が壊れてしまわないか私は恐れているのだ」
気遣うような眼差しを向けられ、本心を隠すこと自体が彼を苦しめてしまうと気がついた那美はそっと口を開いた。
「今日も家族からお前は無能で邪魔な存在だと言われました。少し傷つきましたが、でもそれは本当のことだから……」
昼間の出来事が脳裏に浮かぶ。
父親と継母、そして姉の怒号や暴言がまだ鮮明に焼き付いていて耳から離れない。
幼かった頃は恐ろしさや悲しさで毎日のように泣いていたが、すでに涙は枯れ果てて、しばらくそれは頬を伝っていない。
成長するにつれ、自分はそう言われても仕方ない存在なのだと気がついたから。
「そのようなことは絶対にない」
強く言い切るように綺世が放ったあと、那美は引き寄せられ彼に抱きしめられた。
急な行動に一瞬、何が起こったのか分からなかったが、片耳から感じる心臓の音に自分は綺世の腕の中にいるのだと理解した。
それが不思議と嫌ではなくて突き放すことはせず、そのまま次の言葉を待った。
「そんな戯れ言など聞かなくて良い。那美は不要な子ではないよ」
「綺世さま……」
実母が亡くなってから、綺世だけが味方でいてくれた。
継母だけでなく、血が繋がっている父親や姉でさえも虐げ始めてきたときはつらかったが、こうして夢で逢う綺世との時間がひとときの幸せ、希望だった。
「すぐに守ってあげられなくて本当にすまない」
「謝らないでください。こうして綺世さまに逢うだけで心が軽くなりますから」
安心させるように、微笑むと綺世の表情に少しだけ明るさが戻った。
それは嘘ではなく、確かな事実。
本当はずっとこのまま二人の時間を過ごしたい。
しかし、このひとときも残りわずかだと知らせるように花びらが舞い始める。
「名残惜しいが時間のようだな」
「はい……」
抱きしめる腕の強さが弱まり、一歩下がる。
(綺世さまと次に逢えるのはいつだろう)
一抹の寂しさを覚え、彼の着物の裾を無意識に握った。
それに気がついた綺世は那美の腰に手を添えて再度、引き寄せた。
もう二人の距離は完全に無くなり、洋服と着物が擦れる音が那美の鼓動を跳ねさせた。
吸い込まれそうな瞳には頬を染めた自分が映っている。
「あと少しなんだ」
「え……?」
言葉の意味が分からず、那美は首を傾げる。
綺世も説明することなく、ただ微笑みをたたえるだけ。
きょとんとしている那美を愛おしげに見つめ、握る手に僅かに力を加える。
「必ず君を迎えに行く。だから信じて待っていて、私の姫巫女、そして花嫁──」
『姫巫女』『花嫁』という言葉に疑問に思ったのも束の間、辺りが眩い光に包まれて那美は瞳を閉じた。
寝室で寝ていたはずなのに視界に入るのは色鮮やかな花畑と透き通るほど美しい湖。
このような状況に置かれても特に驚きはしない。
もう何度も経験しているから。
「那美」
低く艶やかな声が耳に届く。
自分の名を呼んでいることに気がついた少女はゆっくりと振り返った。
「綺世さま」
少し離れた場所に優しい笑みを浮かべた青年が立っている。
肩まで伸びた絹のような髪にシミ一つない肌、赤い瞳は長い睫毛に縁取られており、まるで精巧に作られた人形のよう。
綺世、と少女に自分の名を呼ばれた青年は、さらに嬉しそうに宝石のような瞳を細めた。
二人は引き寄せられるように歩み寄る。
すぐに触れられるほど近づくと綺世は手を伸ばし目の前にいる少女、那美の頬に触れた。
手から伝わる体温がじんわりと広がり、久しぶりに感じる温もりが嬉しくて那美は微笑む。
「こうして逢うのは久しいな。変わりはないか?」
「はい。わたしは大丈夫です。綺世さまは──」
「嘘だろう」
「……!」
絢世の表情が笑みから、こちらの真意を探るような真剣なものへと変わった。
那美はギクリとして視線を逸らす。
嘘など本当はつきたくない。
いつも自分の身を案じてくれている彼に素直でいたい。
しかし心のどこかにもうこれ以上、心配させたくないという思いもあって、本音とは反対の言葉を口にしてしまう。
「……申し訳ありません」
嘘をついてしまったことに罪悪感を感じて謝ると綺世は首を横に振った。
「私に心配をかけたくなかったのだろう?優しいな、那美は。……だからこそいつかその心体が壊れてしまわないか私は恐れているのだ」
気遣うような眼差しを向けられ、本心を隠すこと自体が彼を苦しめてしまうと気がついた那美はそっと口を開いた。
「今日も家族からお前は無能で邪魔な存在だと言われました。少し傷つきましたが、でもそれは本当のことだから……」
昼間の出来事が脳裏に浮かぶ。
父親と継母、そして姉の怒号や暴言がまだ鮮明に焼き付いていて耳から離れない。
幼かった頃は恐ろしさや悲しさで毎日のように泣いていたが、すでに涙は枯れ果てて、しばらくそれは頬を伝っていない。
成長するにつれ、自分はそう言われても仕方ない存在なのだと気がついたから。
「そのようなことは絶対にない」
強く言い切るように綺世が放ったあと、那美は引き寄せられ彼に抱きしめられた。
急な行動に一瞬、何が起こったのか分からなかったが、片耳から感じる心臓の音に自分は綺世の腕の中にいるのだと理解した。
それが不思議と嫌ではなくて突き放すことはせず、そのまま次の言葉を待った。
「そんな戯れ言など聞かなくて良い。那美は不要な子ではないよ」
「綺世さま……」
実母が亡くなってから、綺世だけが味方でいてくれた。
継母だけでなく、血が繋がっている父親や姉でさえも虐げ始めてきたときはつらかったが、こうして夢で逢う綺世との時間がひとときの幸せ、希望だった。
「すぐに守ってあげられなくて本当にすまない」
「謝らないでください。こうして綺世さまに逢うだけで心が軽くなりますから」
安心させるように、微笑むと綺世の表情に少しだけ明るさが戻った。
それは嘘ではなく、確かな事実。
本当はずっとこのまま二人の時間を過ごしたい。
しかし、このひとときも残りわずかだと知らせるように花びらが舞い始める。
「名残惜しいが時間のようだな」
「はい……」
抱きしめる腕の強さが弱まり、一歩下がる。
(綺世さまと次に逢えるのはいつだろう)
一抹の寂しさを覚え、彼の着物の裾を無意識に握った。
それに気がついた綺世は那美の腰に手を添えて再度、引き寄せた。
もう二人の距離は完全に無くなり、洋服と着物が擦れる音が那美の鼓動を跳ねさせた。
吸い込まれそうな瞳には頬を染めた自分が映っている。
「あと少しなんだ」
「え……?」
言葉の意味が分からず、那美は首を傾げる。
綺世も説明することなく、ただ微笑みをたたえるだけ。
きょとんとしている那美を愛おしげに見つめ、握る手に僅かに力を加える。
「必ず君を迎えに行く。だから信じて待っていて、私の姫巫女、そして花嫁──」
『姫巫女』『花嫁』という言葉に疑問に思ったのも束の間、辺りが眩い光に包まれて那美は瞳を閉じた。