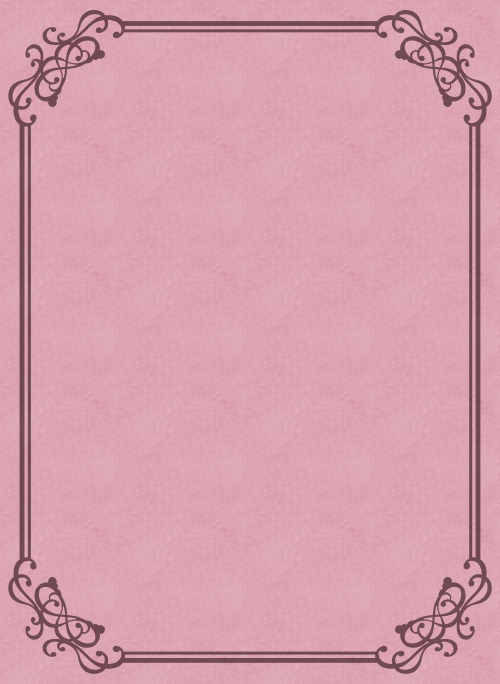行く道中、僕の頭は君のことでいっぱいだったからか、つくまでに、そんなに時間がかかった気はしなかった。
「兄ちゃんついたよ」
「あぁ」
僕は、車を降りて、一本の松葉杖なんかなくても、僕はきっと歩けるだろうと、僕は思うが、念の為持たされた松葉杖を僕は使う。
式場に向かうのは僕一人。
少し来るのが遅くて、みんなとゆるく庭で話しながら、ブーケトスをする時間みたいだ。
君を見つけるのは簡単で、白いレースをまとったきれいな横顔と、幸せそうな笑顔で違う男の隣にいる君を見たらやっぱり許せなくて。
どうしても綺麗な君が許せなくて。
僕はショルダーバックから、あるものをゆっくりと取り出して、君に近づいていった。
君は僕に気づいてくれる?
僕の気持ちわかってくれる?
君がいたからここまでこれたんだよ。
君がいなきゃ、きみが、きみが、
ごめんね
君が僕に気付いた瞬間に
松葉杖を捨てて
君に抱きつくように
僕は君をカッターナイフで刺した。
君はさされたお腹をうなりながら抑えた。
周りから聞こえる、大量の悲鳴と叫び声。
これで一緒だから。関係ないよね?
真っ白なウエディングドレスが、赤く染まっていく。
落ちた甘い花束の香りと、婚約者の引きつる苦しそうな顔。
君が悪い。
君が僕から離れるから
「…ほんっとは、幸せにしてッ、あげたッ、かった、私が、やっ、ぱり、幸せにできなかったから、苦しめちゃッ、たね」
君は僕に刺されたというのに、こんなに血が出てるのに、なんで僕に話すの?
僕にも刺さなきゃ、刺さなきゃ、…君が手を離してくれないから、だれかに、止められる、その前に早く
「このひとを、しなせないで、おねがい、わたしは、いいッ、から」
君は婚約者にそう言った。
「わかったから、もう喋るな、お腹の子が」
「え、お腹の子?…お腹の子がって…妊娠してるの、君が僕から離れて、なんで幸せになろうとするの、なんで、僕は、君だけじゃなくて、僕の子は」
騒ぎを駆けつけてきた弟も僕を引き止めに来た。
「兄ちゃん、なんてことして」
そういって君から切り離された僕は遠ざけられ。
「やめて!ぼくもしぬから、君のとこ行くから、やめて、きみがさきにいっちゃう」
鳴り響く2つのサイレンの音が、僕の焦らせた。
僕の手は血だらけで、君の血が、どんどん乾いて、擦っても取れなくて、君が悪いのに、僕は悪くない、君が悪い。
僕が君と一緒になるためには必要なことなのに。
みんなが遠ざける。
ぼくがいけないの?
.
.
.