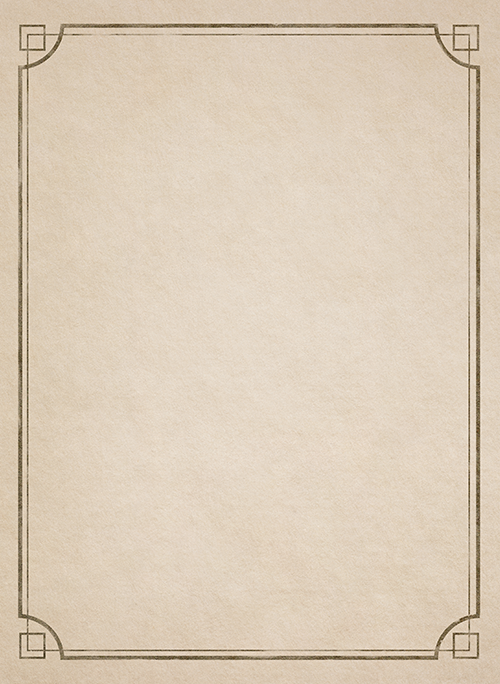現するのが最適だろう。
僕がついさっき通ってきたあの車道に、一台のバイクが姿を見せた。それも僕の時と同じ方角だった。
運転手の顔は、フルフェイスタイプのヘルメットを被っているので見えない。男性か女性か、年齢がどのくらいなのかも判別がつかなかった。彼、或いは彼女の乗っているマシンは、バイクに詳しくない僕にも高価な事がわかった。手入れがしっかりとされている。緑に塗装されたボディには傷も汚れも付いてはいない。顔を近づけたら、反射して顔が映り込むはずだ。
山の上まで届くほどの走行音を響かせながら、バイクはすぐに視界から消えた。僕と同じように、駐車場にバイクを停め、山を登ってくるのだろうか。もし登ってくるのだとしたら、公園はあまり広くないので展望台にはすぐ気づくはずだ。気づかれて仕舞えば、風景は僕だけのものとは言えなくなる。否応なく風景という財産が見知らぬ他人と共有される事になるだろう。
もちろん、この場所は誰か個人の所有物ではない。公園に立ち入り、ベンチや展望台といった設備を使用する権利は誰にでもある。僕のような子供でも使用できるし、歩行動作がままならない老人が犬の散歩のために利用するのも間違った行為ではない。けれど、叶うのならば、展望台だけは僕に占拠させてほしい。
身勝手な要求であるのは、誰の目にも明らかだ。だから僕は要求を口にだす真似はしないし、同じ道路を辿って入ってきたバイク乗りには、「僕は景色を堪能しました。次はあなたの番です」などと言ってこの場を大人しく開け渡さすべきなのだ。あくまでバイク乗りが公園に入ってきたら、という話だが。
今にヘルメットを脱いで顔を露わにした彼、もしくは彼女が、僕の元へとやってくるのかもしれない。
なんとなく後ろにある階段が気になって、僕は振り返った。そして息を呑んだ。
階段を上り切った場所に、一人の少女が立っていた。
少女は、僕がリュックサックに詰め込んだのと同じブレザーを着ていた。つまり、僕と同じ学校の生徒。肩に届くかどうかという長さに揃えられた黒髪が、僕の髪と同様、風によって荒れ狂っている。だが彼女は、動き回る髪には全く意識を向けていなかった。恐怖とか、怯えと言った感情を内包したまま動けずに立っている。
目は肉食獣に睨まれたウサギのようだし、胸の前で組んだ指が忙しなく動いている様からは落ち着きなど微塵も感じ取れない。だが、僕の顔を見ている。瞳はしっかりと、僕の顔を向いている。何かはわからないが、明確な目的があってこの場にいるのだという気配が感じ取れた。
少女の顔には、見覚えがあった。僕が中学校の頃、一年生の時だけ同じクラスだった生
僕がついさっき通ってきたあの車道に、一台のバイクが姿を見せた。それも僕の時と同じ方角だった。
運転手の顔は、フルフェイスタイプのヘルメットを被っているので見えない。男性か女性か、年齢がどのくらいなのかも判別がつかなかった。彼、或いは彼女の乗っているマシンは、バイクに詳しくない僕にも高価な事がわかった。手入れがしっかりとされている。緑に塗装されたボディには傷も汚れも付いてはいない。顔を近づけたら、反射して顔が映り込むはずだ。
山の上まで届くほどの走行音を響かせながら、バイクはすぐに視界から消えた。僕と同じように、駐車場にバイクを停め、山を登ってくるのだろうか。もし登ってくるのだとしたら、公園はあまり広くないので展望台にはすぐ気づくはずだ。気づかれて仕舞えば、風景は僕だけのものとは言えなくなる。否応なく風景という財産が見知らぬ他人と共有される事になるだろう。
もちろん、この場所は誰か個人の所有物ではない。公園に立ち入り、ベンチや展望台といった設備を使用する権利は誰にでもある。僕のような子供でも使用できるし、歩行動作がままならない老人が犬の散歩のために利用するのも間違った行為ではない。けれど、叶うのならば、展望台だけは僕に占拠させてほしい。
身勝手な要求であるのは、誰の目にも明らかだ。だから僕は要求を口にだす真似はしないし、同じ道路を辿って入ってきたバイク乗りには、「僕は景色を堪能しました。次はあなたの番です」などと言ってこの場を大人しく開け渡さすべきなのだ。あくまでバイク乗りが公園に入ってきたら、という話だが。
今にヘルメットを脱いで顔を露わにした彼、もしくは彼女が、僕の元へとやってくるのかもしれない。
なんとなく後ろにある階段が気になって、僕は振り返った。そして息を呑んだ。
階段を上り切った場所に、一人の少女が立っていた。
少女は、僕がリュックサックに詰め込んだのと同じブレザーを着ていた。つまり、僕と同じ学校の生徒。肩に届くかどうかという長さに揃えられた黒髪が、僕の髪と同様、風によって荒れ狂っている。だが彼女は、動き回る髪には全く意識を向けていなかった。恐怖とか、怯えと言った感情を内包したまま動けずに立っている。
目は肉食獣に睨まれたウサギのようだし、胸の前で組んだ指が忙しなく動いている様からは落ち着きなど微塵も感じ取れない。だが、僕の顔を見ている。瞳はしっかりと、僕の顔を向いている。何かはわからないが、明確な目的があってこの場にいるのだという気配が感じ取れた。
少女の顔には、見覚えがあった。僕が中学校の頃、一年生の時だけ同じクラスだった生