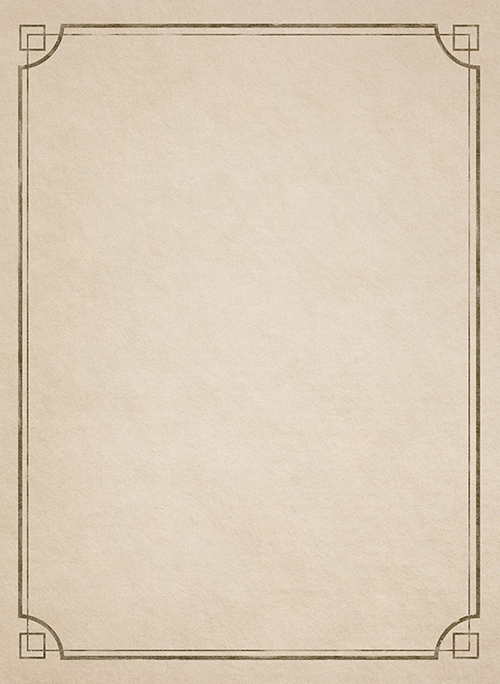僕は咄嗟に左右を見渡した。もしかすると、僕以外に展望台へ立ち寄っていた『砂川くん』がいるのかもしれない。景色に見惚れ、気づいていないだけで別の砂川が存在しているのかもしれないと思った。だがそれはありえない。こんな狭いスペースで他に誰かがいれば、気が付かないはずがないのだ。実際に、展望台には僕と金城瑠夏の他には誰もいない。
瑠夏の言っている砂川くんとは、間違えるはずもなく僕の事だ。状況を飲み込むために、少しだけ時間が必要だった。
僕が目の前で起こった事象の整理に努めていると、急に瑠夏が顔だけを上げた。「返事はまだか」と言っているような気がした。
「あの、へ、返事とか……」
しっかりそう言われてしまった。だが僕には答えようがない。まさか、卒業式の日に昔仲が良かった女の子に告白されるとは、思っても見ないからだ。
「返事と言われても、いまいち状況が飲み込めないんだ。金城さんだよね? 中一の時にクラスが同じだった」
「はい! 覚えててくれたんだね!」
体を起こして、嬉しそうに笑う金城瑠夏。忘れるわけがない。あの出来事を境に、僕の暮らしは大きく変わったのだ。どれだけ忘れようとしても、恐らくは死ぬまで忘れる事はないだろう。
「うん、覚えてるよ。でもどうして、金城さんが僕に告白するの? 何かのイタズラ?」
僕は瑠夏の背後に視線を向けて言った。階段の下に彼女の仲間数人が潜んでいて、飛び出すタイミングを待ち侘びているような気がした。
瑠夏は慌てた様子で両手を振った。
「違う、違うよ。これは、私の本当の気持ちなの。イタズラとかじゃないよ」
「でも、信じられない。僕の事が好きだなんて。一体、いつから?」
僕が訊くと、瑠夏の顔はにわかに紅潮していった。俯いて自分の足元を見つめた。両の手は背中で組まれ、もじもじと体全体を動かす。なんだか、こっちまで気恥ずかしくなってくる。
「中学校の、頃から。一年生の時に、私に話しかけてくれたでしょ?」
「うん、そうだね。確か、読んでる本の事で質問とかしてたんだっけ」
「すごく嬉しかったの。私、人見知りがすごくて誰からも声をかけてもらえなかったんだ。最初だけは、別の場所から引っ越してきたからって話しかけてもらえたんだけど、時間が経ってくると誰も私に興味をもたなくなったの。もちろん、会話に積極的じゃない私が悪いんだけど、でも当時は、どうすることもできなくてすごく苦しかった」
瑠夏は顔をあげて、遠くに見える街の方に視線を向けた。僕とは目を合わせられないか
瑠夏の言っている砂川くんとは、間違えるはずもなく僕の事だ。状況を飲み込むために、少しだけ時間が必要だった。
僕が目の前で起こった事象の整理に努めていると、急に瑠夏が顔だけを上げた。「返事はまだか」と言っているような気がした。
「あの、へ、返事とか……」
しっかりそう言われてしまった。だが僕には答えようがない。まさか、卒業式の日に昔仲が良かった女の子に告白されるとは、思っても見ないからだ。
「返事と言われても、いまいち状況が飲み込めないんだ。金城さんだよね? 中一の時にクラスが同じだった」
「はい! 覚えててくれたんだね!」
体を起こして、嬉しそうに笑う金城瑠夏。忘れるわけがない。あの出来事を境に、僕の暮らしは大きく変わったのだ。どれだけ忘れようとしても、恐らくは死ぬまで忘れる事はないだろう。
「うん、覚えてるよ。でもどうして、金城さんが僕に告白するの? 何かのイタズラ?」
僕は瑠夏の背後に視線を向けて言った。階段の下に彼女の仲間数人が潜んでいて、飛び出すタイミングを待ち侘びているような気がした。
瑠夏は慌てた様子で両手を振った。
「違う、違うよ。これは、私の本当の気持ちなの。イタズラとかじゃないよ」
「でも、信じられない。僕の事が好きだなんて。一体、いつから?」
僕が訊くと、瑠夏の顔はにわかに紅潮していった。俯いて自分の足元を見つめた。両の手は背中で組まれ、もじもじと体全体を動かす。なんだか、こっちまで気恥ずかしくなってくる。
「中学校の、頃から。一年生の時に、私に話しかけてくれたでしょ?」
「うん、そうだね。確か、読んでる本の事で質問とかしてたんだっけ」
「すごく嬉しかったの。私、人見知りがすごくて誰からも声をかけてもらえなかったんだ。最初だけは、別の場所から引っ越してきたからって話しかけてもらえたんだけど、時間が経ってくると誰も私に興味をもたなくなったの。もちろん、会話に積極的じゃない私が悪いんだけど、でも当時は、どうすることもできなくてすごく苦しかった」
瑠夏は顔をあげて、遠くに見える街の方に視線を向けた。僕とは目を合わせられないか