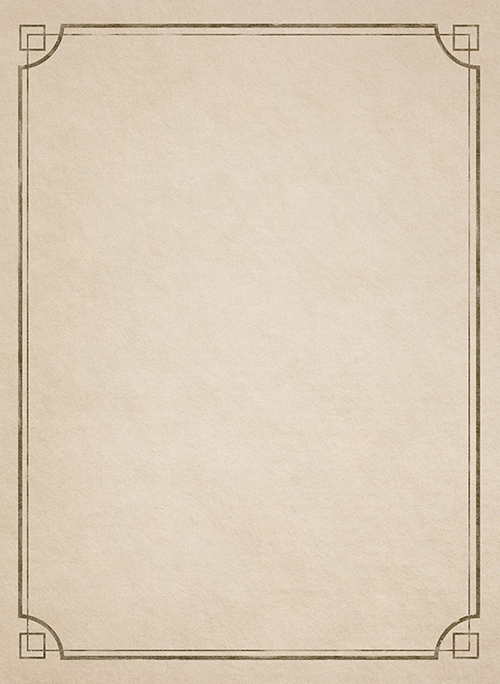るまで、ただ待つのが懸命な判断だと思えたのだ。
結論から言って、その判断は間違いだった。噂が否定されなかった事で、周囲は言い当てられて黙るしかないのだと考え始めたのだ。『恋人イジり』が、時間経過とともにより多くなった。誰もが、二人は付き合っているのだと言う噂話を真実だと思い込んでいった。
いつしか僕は、噂がなんだと言って気にしないフリを続けるのも難しくなっていった。仲の良かった友人たちも、僕と距離を取るようになったし、僕も彼らから距離を取るようになった。
ある日の放課後、偶然瑠夏と二人きりで教室で当番に割り当てられた清掃をしている時に彼らが教室を覗き見していた。「キスをするのか?」「ハグをするのか?」などと小さな声で呟き、ニヤニヤと笑みを浮かべていた。手にしていた箒で威嚇し、追い払ったが、それきり彼らとの交友は絶たれた。どちらかが宣言したりはせずに、ごく自然に。
二年生と三年生では、それぞれクラス替えがあったが、元々が三クラスしかない小さな学校だったので、かつてのクラスメイトたちの何人かは必ず同じ組に分けられた。金城瑠夏とだけは再び同じクラスにはならなかったが、十分、噂の内容は継続された。
歳を重ねるごとに、ある程度学校内で恋人ができる生徒は増えていったものの、それだけでは僕と瑠夏に向けられる奇異の目は無くならなかった。
だから僕は、学年が上がるごとに誰とも口を聞かないようになっていった。
今、目の前には件の金城瑠夏がいる。僕の特別な場所に足を踏み入れて、しっかり目を合わせている。僕に会いにきたのだと言いたげだ。けれど、彼女は一向に話を切り出そうとはしなかった。固く閉じられた唇が時折動こうとするが、結局元に戻って固く結ばれる。
景色を眺めにきたのではないようだが、ならわざわざここへ来た目的はなんだろうか。
道を歩いていて、知っている人が立ち寄ったから追いかけてみた、と言うような場所ではない。ここは学校から離れているのに加えて、商業施設が一つもないド田舎だ。気分で立ち寄る人など、おそらく一人としていないのではないか。
卒業式が終わって、体育館から僕の後を追ってきたのかとも考えたが、あり得る話ではない。そんな間柄ではない。
僕がありえそうな可能性を頭の中で探っていても、一向に瑠夏は口を開かなかった。彼女が今立っている場所から退いてくれなければ、階段を降りて帰宅できない。僕が帰るためには瑠夏のアクションが必要な訳だが、肝心の本人がどうもしないのでは話にならない。
如何にしてこの事態を突破すべきか、という議題に脳が移りかけた時、ようやく瑠夏が言葉を発した。
「あの、砂川くんの事がすっ、好きなんです。付き合ってください!」
腰を折って頭を下げる瑠夏に対し、僕の方は口を開けて呆然とする他なかった。金城瑠夏は、たった今何を言ったのだろう。好きと言ったか。誰の事を好きと告白したのか。
結論から言って、その判断は間違いだった。噂が否定されなかった事で、周囲は言い当てられて黙るしかないのだと考え始めたのだ。『恋人イジり』が、時間経過とともにより多くなった。誰もが、二人は付き合っているのだと言う噂話を真実だと思い込んでいった。
いつしか僕は、噂がなんだと言って気にしないフリを続けるのも難しくなっていった。仲の良かった友人たちも、僕と距離を取るようになったし、僕も彼らから距離を取るようになった。
ある日の放課後、偶然瑠夏と二人きりで教室で当番に割り当てられた清掃をしている時に彼らが教室を覗き見していた。「キスをするのか?」「ハグをするのか?」などと小さな声で呟き、ニヤニヤと笑みを浮かべていた。手にしていた箒で威嚇し、追い払ったが、それきり彼らとの交友は絶たれた。どちらかが宣言したりはせずに、ごく自然に。
二年生と三年生では、それぞれクラス替えがあったが、元々が三クラスしかない小さな学校だったので、かつてのクラスメイトたちの何人かは必ず同じ組に分けられた。金城瑠夏とだけは再び同じクラスにはならなかったが、十分、噂の内容は継続された。
歳を重ねるごとに、ある程度学校内で恋人ができる生徒は増えていったものの、それだけでは僕と瑠夏に向けられる奇異の目は無くならなかった。
だから僕は、学年が上がるごとに誰とも口を聞かないようになっていった。
今、目の前には件の金城瑠夏がいる。僕の特別な場所に足を踏み入れて、しっかり目を合わせている。僕に会いにきたのだと言いたげだ。けれど、彼女は一向に話を切り出そうとはしなかった。固く閉じられた唇が時折動こうとするが、結局元に戻って固く結ばれる。
景色を眺めにきたのではないようだが、ならわざわざここへ来た目的はなんだろうか。
道を歩いていて、知っている人が立ち寄ったから追いかけてみた、と言うような場所ではない。ここは学校から離れているのに加えて、商業施設が一つもないド田舎だ。気分で立ち寄る人など、おそらく一人としていないのではないか。
卒業式が終わって、体育館から僕の後を追ってきたのかとも考えたが、あり得る話ではない。そんな間柄ではない。
僕がありえそうな可能性を頭の中で探っていても、一向に瑠夏は口を開かなかった。彼女が今立っている場所から退いてくれなければ、階段を降りて帰宅できない。僕が帰るためには瑠夏のアクションが必要な訳だが、肝心の本人がどうもしないのでは話にならない。
如何にしてこの事態を突破すべきか、という議題に脳が移りかけた時、ようやく瑠夏が言葉を発した。
「あの、砂川くんの事がすっ、好きなんです。付き合ってください!」
腰を折って頭を下げる瑠夏に対し、僕の方は口を開けて呆然とする他なかった。金城瑠夏は、たった今何を言ったのだろう。好きと言ったか。誰の事を好きと告白したのか。