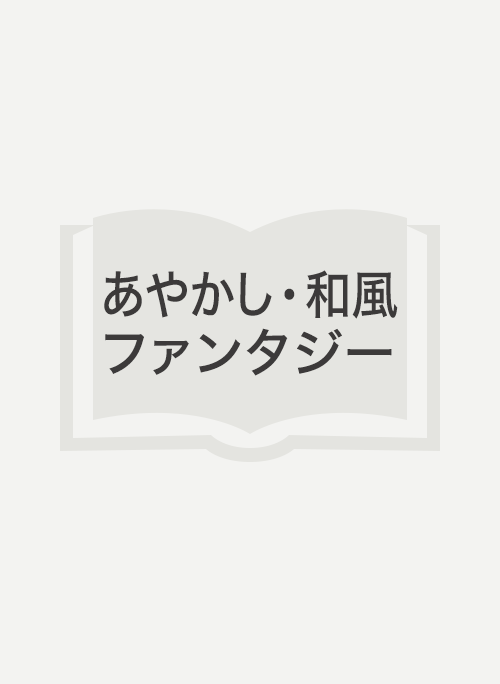――――――よく、晴れた夏の空。しかしそのうだるような暑さの中……。
「……お、おはよう」
「……。……行くぞ」
この男は相変わらず氷点下で羨ましい。
体温は……大丈夫だと思うが、この低気圧。氷点下0のニコリともしない表情。
朝の挨拶をしてもろくに返しもせず、家から出てきたぼくの顔を見るなりぶっきらぼうにそう告げる。
本当に紅葉は……昔からずっと変わらないんだから。ん……昔?どこか気になる感覚を覚えつつも……。
紅葉がすたすたと歩き始めるのに、遅れまいと続こうと駆け出そうと……したところだった。
「ちょっとちょっと――――――っ、お兄ちゃんっ!待っちなさあぁぁ――――――いっ!」
元気な妹の声が響き、早速ドタバタと音をたてながら、妹がドアから勢いよか飛び出してきた。
「……命。ちゃんとカギ、閉めろよ?」
父さんも母さんも朝が早い。朝食はある程度作っていってくれるけど、盛り付けと弁当詰めるのは俺の仕事である。妹を台所に入れるわけにはいかないからな。
こうして、お弁当を忘れずに鞄に詰め込んで。
妹に私も弁当と言われ、いや給食あるだろと言えば、今日はお弁当デイだと言われ、大急ぎで妹の弁当もこしらえて、朝から大急ぎだ。
……ったく、それくらい昨日のうちに言っとけよ~~。しかし、ぼくもお兄ちゃんなので我慢である。
そうして妹の寝癖を直して、ツインテールに結んでやって。まだ鞄の中の整理をしている妹を中に残し、早々と準備を終えて出発したぼく。そしてぼくに続いて、遅れて出てきた妹がカチャリと、鍵を閉めたのを確認する。
「弁当忘れてないよな?」
一応、確認。
「あっ!!」
……『あっ!!』じゃないからあぁぁっ!もぅ……。慌てて家の鍵を開けて、弁当をとってきた妹の代わりにドアの鍵をがチャリと閉める。
うん、これでよし!
「それじゃ、行ってらっしゃい」
いつもの朝。学校へ向かう妹に手を振れば。
「行ってきま――――すっ!」
ラジャっと敬礼する妹。中学生は相変わらず元気で羨ましいな。
「あ、紅葉お兄ちゃんも、行ってきまぁ~~すっ!」
ぼくの向こうの紅葉に向かって、妹が腕をぶんぶんと振る。先へ行っているはずの紅葉をパッと振り返ってみれば。ぼくがついて来ないからか、進んだ先の途中で立ち止まり、不機嫌そうに振り返っていた。
これも、いつも通り。そう、いつもの朝の日常である。とっとと先に行ってもいいのに、結局は待つんだよな……こいつは。優しいのか、何なのか、それとも是が非でもリングパワーを吸いたいのか、よく分からない。
いや、リングパワーってなんだ。リングパワーって。それはEPA専用用語ではない。ただのぼくの妄想である。
そして紅葉が小さく「あぁ」と言うと、妹は逆方向に元気に走り出していく。……さすがは陸上部。陸上女子である。
「車には気を付けろー」
そう叫べば、後ろ向きに手を振って走り去って行った。
因みに紅葉が挨拶を返す女子は……多分妹くらいだ。妹がそれを知ったら喜びそうだな。
本気で付き合いたいとか言い出したら困るから、言わないけど。別に紅葉に特別な感情があるわけじゃない。ただ単に、危険があるかもしれない特殊体質とリングの世界に、妹を巻き込みたくないだけだ。
そうして妹を見送り、再び紅葉を見やれば……。素っ気なく顔をそらして、また歩き出していた。
はぁ……全く、仕方がない。ぼくが駆け足で追い付くと、あとはいつも通りの登校風景だ。
高校へ続くなだらかな坂を上り、高校に近付くにつれ、だんだんと同じ制服の高校生たちが増えていく。やはりその中で思うのは……。
「ねぇ、あのひとイケメン!」
「カッコいい~!」
「知らないの?1年の奥宮くんだよ」
「声かけてみようかなぁ~~」
紅葉を見て、明らかに色めき立つ女子たち。まぁ、紅葉はとにかくモテるのだ。顔がいいからな。あと、文武両道だし。英語も帰国子女かってくらいペラペラしゃべるし、体育の授業だって紅葉がチームに入れば勝利間違いなし!
でも中身は無愛想で1ミリも笑わない冷血男ですよ~と思いつつも、何故かそう言う黄色い声に胸がざわざわしてしまう。
ぼくがよくある黒髪黒目の平凡顔だからだろうか。つまりこれは、ジェラシー?いやいや、紅葉ほどのイケメンにジェラシー溜めることがまず烏滸がましいって。
――――――ぼくは平凡でいい。そう、平凡がいい。
紅葉のリングでいられればそれでいいのだ。ワイシャツ越しに、制服の下にさげた指輪の感触を確かめる。大丈夫、まだここにある……紅葉のペアリングの証が。
「……おい」
「はぇっ!?」
気が付けば、紅葉がむすっとしながらぼくの正面に立っていた。そしてその周りで何故かキャーキャー叫ぶ女子たち。イケメンは立っているだけでも絵になるんだな。
「早く来い。……周りが騒がしい」
あ――――……。ぼく、考え事をしている間にいつの間にか立ち止まってたんだ……。
そう、そうだよね。紅葉は騒がしいのを好まない。静寂を好む。紅葉は無口であまり語ろうとしないが、いつものあの時間を過ごしていればなんとなく分かってくる。
――――――そしてぼくの側にいる理由。特殊体質のこともあるだろうけど、一番はこれだろう、絶対に。紅葉が男友だちと一緒に歩いていると遠慮する女子も多いから。たまに気にせずアタックしてくる女子もいるが、紅葉はファンサービスとか皆無だから。むしろファンいるの分かってる!?自分のルックスの価値理解してるぅっ!?あぐっ、ガツガツ行く系女子たちに精神面を強く保つコツを教えてもらいたいほどである。まぁここまでのぼくが言いたいことはだな。つまりぼくは体のいい女子避けなのだと言うことだ。
そして周りに集まってきた女子たちは多分……ぼくが離れた隙に突撃しようとしたのかなと思う。しかしそんなのお構い無しに進む紅葉に置いていかれないように駆け出す。
胸の中に沸き起こる良く分からない高揚感と、寂しさを感じつつも、紅葉と共に、見えてきた校舎を目指していく。
――――――そして、下駄箱。
ガチャン、と扉を開ける紅葉。この下駄箱は紅葉が無駄に特殊体質の力を使って、毎日封じている。外からは空気しか通らぬよう、手紙の一枚も紛れ込まぬよう。
小学生の時はまだましだったが、中学生くらいから下駄箱を開けると常に羨ましいほどの恋文やらお菓子などの贈り物び~~っしり。周囲にはバレていないが、その度に紅葉の機嫌がものっそい悪くなるのだ。
しかも一度、怒りに任せて下駄箱の中ごと発火能力で燃やしたもんだから……当然の如く中履きごと、燃え尽きていた。
その恐ろしい一件以来、下駄箱の扉を開けられないようにすればいいんじゃないかとのぼくのアイディアで、こうして空気以外は入らないようにしているのだ。空気は入れる。うん、換気はしないとヤバいからね。
それにそれくらいならたいした力の使用量ではないそうなので良かった。
――――――ぼくの心の平穏のためにも。
そして素早く靴を履き替え下駄箱を再び開かないように閉じた紅葉は、急かすようにぼくを見る。
「あぁ、うん!待って!」
急いで靴を履き替え、紅葉を追い掛けたことは、言うまでもない。
※※※
「ねぇ、秋雨、お願いっ!クラスメイトでしょ!?」
ぼくは今まさに、クラスの女子から手渡されようとしている手紙に、思わず眉を寄せる。
因みに秋雨とは、ぼくの苗字のことだ。
「秋雨、奥宮くんと仲いいでしょ!?これ、奥宮くんに渡してよ!」
その、つまりは紅葉宛ての恋文ってことか……。ふぅ。さすがはイケメン。女子にモテモテだ。
当然、紅葉といつも一緒にいるぼくに仲立ちを頼もうと言う女子も出てくるのだ。
それに嫉妬しているわけじゃないんだ、断じて。これには深い事情があるのだ。
「ごめん、それはちょっと」
「な……っ、何でよ――――っ!」
うぉ――――ぅ。女子高生の迫力は、妹にも勝る。思わず身をのけ反りそうになるものの、我慢、我慢。耐えろ、ぼく。
別に、それは意地悪とか、そう言うのじゃない。以前、女子にどうしてもと頼まれて紅葉に恋文を渡したら……。
紅葉が突如眉間に皺を寄せ、鋭く睨み付けてきたと思えば……発火能力で恋文を一瞬で燃やしてしまったのだ。
『二度とこんなもの持ってくるな』
あの時の紅葉の怒りようはとんでもないレベルだった。どうしてあそこまで怒るのか、まるで分からなかったけど。
後日恋文を託してきた女子に誤って紛失してしまったことを告げたら、当然のことながら大激怒された。まぁ、最後は女子も自分で渡さなかったこちらも悪かったからと和解を申し出てくれたから良かったものの……。
「大切なものは、自分で渡したほうが……いいんじゃないのかな」
そう付け加えれば……。
「んもぅっ!意味分っかんないっ!」
ぷりぷり怒って行ってしまった。
「一回失くしてるやつに頼むなよ」
「あはは――――」
ほかのクラスメイトの笑い声が響き……。
「あんた最っ低っ!!」
と、こちらを振り返った先程の女子に叫ばれた。……いや、何でぼくがそんなことを言われにゃぁならんのだ。全ては……読みもせずに燃やした紅葉が悪くないか。ほんと意味分からんのはぼくの方だ。
因みに恋文紛失事件に対する妹の見解はーー『恋文を失くしたお兄ちゃんも悪いけど、お兄ちゃんを小間使いに出すのは、妹の私だけの権利!』だ、そうだ。
「おい」
「はぇ?」
ふと振り向けば、紅葉がぼくの後ろに立っていた。渦中のイケメンの登場に女子たちが色めき立つ。
「……今日は早退する」
そう短く言って……紅葉は颯爽と身を翻し、帰っていく。多分ひと目につかないところでテレポートする気だろう。突然のことのようで、じつはこう言うことはよくある。そう、EPAの任務だ。もちろんこう言う時は下校は別々だから、また終わった頃にぼくに会いに来るのだ。抱き締めてもらいに。その凍てついた身体を温めるために。
――――――けど。
最近の紅葉の頻繁な任務が気になったぼくは……。昼休みになると早々に弁当を平らげ……、とある場所に向かった。
「篠田先生!」
かたや、高校の校舎の隅。普通の研究室に見えるその場所は、普通の生徒には知られていない顔がある。
「あぁ、秋雨か。どうした?奥宮はもう行ったんじゃないのか?」
研究室の奥から顔を出したメガネを掛けた男性が、篠田疾風先生だ。大学から高校に出向で来ていると言う『設定できた』のこの日本史教師は、学内にこうして研究室を借りていた。だが、こうしてこの錦矢高校にやってきたのには、秘密がある。
「それは、……そうなんですけど」
「ならどうした?もしかして、リングのことで相談か?」
篠田先生は特殊体質とリングのことを知っている。篠田先生自身も特殊体質で、EPAのエージェントだからだ。
こうして錦矢高校に赴任してきたのも、研究室を借りているのも、全てはEPAの根回しあってのことだった。
そして篠田先生はこの高校のある錦矢市を取り持つEPAの支部長を勤める。
無論紅葉もここの支部所属。他支部への出張もあるようではあるものの……ぼくはただ、紅葉からいついつ帰ると言われるだけ。そして任務が終われば、身体を提供するだけだ。もし本当に心配事があれば篠田先生を訪ねる。篠田先生は篠田先生で、答えられる範囲で答えてくれるし。
それに篠田先生は自身もペアリングを持っている。篠田先生のところも男同士だけど、常に共にいるために同棲し、パートナー登録までしたと言うから……。特殊体質とリングはなかなか離れられない存在なのだと分かる。
紅葉はレンタル家族まで派遣してもらって、ぼくの隣の家に引っ越して来たんだもんな。
特殊体質も生きるために必死なのである。
まぁ、そんなこともあってリングと共に暮らしている篠田先生はリングに対しても詳しい。無論EPAとしての知識もあるだろうし。
でも今日篠田先生に会いに来たのは、そう言うことじゃないんだ。
「あの、紅葉のことなんですけど」
「奥宮がどうかしたか」
「……最近、多いような気がして……。ぼくに、そのー、抱き付いて……来るのが」
すごく語弊があるような言い方な気がするが、事情を知っている篠田先生なら問題ないだろう。
篠田先生だって、同じ穴の狢である。
「奥宮のリングを務めることが、苦痛になったか?」
「……それはっ」
苦痛か、と聞かれると、何故か迷うぼくがいる。ぼくはただ、抱き締め、抱き締め返されるだけだ。そこに感情などない。ぼくは紅葉を抱き締め、紅葉はただ、生きるためにぼくを抱き締め返す。そうしなければ、自分が自分じゃなくなる。紅葉が紅葉じゃなくなるんだ。そして自我を失った紅葉は……ほかのエージェントたちに始末されることになってしまう。
「まぁ、一般人として生きているお前には酷かも知れないし、理解できないことも多いだろうが……」
そうだ。多くのリングは一般人だ。特殊体質でも何でもない。いや、特殊体質を癒せる時点である意味特殊体質かもしれないが。
特殊体質がリングを必要とする反面、リングは別に特殊体質を必要としていない。
特殊体質がいなくても、特殊体質を抱き締めなくても、普通に生きていける。
「でも俺たちは……特殊体質はペアリングがいなければ生きられない。紅葉も、お前がいなければ生きられない。やがて心の病がその身を蝕み、自我を失い、暴れることしかできなくなる。そうなれば、俺たちエージェントがそれを始末するしかない」
「それは、その、分かっています」
否、分かっていない。言葉では理解していても、どうやってそうなるのか、実際はどうなるのかを知りもしない。紅葉がそうなるなんて、知りたくない。
「特に奥宮は……あいつは、特殊体質の中でも特別だ」
「特別?」
「特別強い力、様々な超常能力。類を見ない最強の特殊体質。それがあいつだ。だからこそ、多くの特殊任務に駆り出される。しかもあいつは早くにリングを見つてペアリングとなった。そうなれば、紅葉の回復は問題なく行われる。そしてEPAは惜しみ無くあいつを使えるわけだ」
「……えっ」
早くに、見付けたって……。
紅葉がぼくと出会ったのは、小学生の時のはず。紅葉があのレンタル家族と共に隣の家に越してきた以上、その頃からEPAに所属、もしくは管理されていたと言うこと。そしてぼくというペアリングを見付けてしまったから……。
「だから紅葉は」
少なくとも、ぼくに抱き付かなくてはならなくなった中学生の時から……。
「ぼくのせいで、まだ高校生なのに、連日任務に出ているってことですか……?」
ぼくと出会ってしまったから……。ぼくと出会わなければ、紅葉はこんな過酷な生活を強いられることはなかったんだ……。
リングが見つからなければ、紅葉は……。
「おい、秋雨、何か勘違いを……っ」
篠田先生が何か言いかけた時だった。
ガランッ、ドンッ。
乱暴に研究室の扉が開き、その先にはひどく虚ろな、しかししっかりとぼくを見つめている紅葉がいたのだ。
「紅葉、任務は……」
「終わった」
えっと……もう?そう聞こうとしたその時。
ガバッ
強引に抱き締められる。その体温はいつも以上に冷たくて、凍えるようで。
「あ、ぅ……、もみっ」
何か言葉をかけようとすれば。
「黙れ」
氷点下よりも低い、冷たい声がズシンと心に深く降り積もる。
「おい、とっとと回復してもらえ。お前今日、どんな無茶をした。ヤバいぞ」
え……紅葉が……。やっぱりこの凍えようは……。
篠田先生のその言葉を最後に、景色は見慣れない建物の中に移動する。ここ、どこだ……。
わから、ない。
寒くて寒くて……凍えそうな……。
紅葉をこんなにしたのは、間違いなく、ぼくだ。あぁ、紅葉。ごめん……ぼくの、せいで、こんなになって……。
寒くて寒くて凍えそうな中、必死に紅葉の背中に腕を伸ばし、抱き締める。
「……ごめん、ね」
かすれ出た声は、果たして紅葉に聞こえたのか、聞こえていないのか。
涙で歪んだ視界の端に、ぼくの写真が見えた気がした……。紅葉はぼくを怨んで……いたのかな。
涙が頬を伝ったのか、そのまま凍ってしまったのか……。その答えをぼくは、知らない。