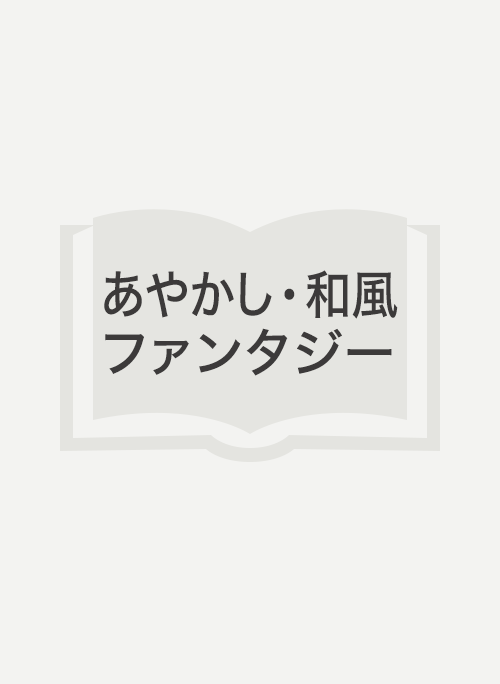その身に何を望むのか。
ぎゅ……っと、その身体を抱き締める。
そうして抱き締める時、その身体はとても冷たくて……。だけどゆっくりと体温が戻っていくのが分かった。
そしてその体温を名残惜しく思いつつも、それが離れていくのをじっと耐える。
そして抱擁を解いた目の前には……部屋の窓から射し込む夕陽色に照らされた、色素の薄い髪と瞳の少年。
顔立ちは整っており、肌の血色が感じられない。だが、確かに体温は温かく、確実に元に戻っている。
そしてじっと見つめ合う、何かを確かめ合うような、いつもの時間。
部屋には無音の大音響を奏でているかのように夕陽が降り注ぐが……その音色はひどく、切なく。そして物悲しい。この調べを、ぼくはどこかで聞いた気がするんだ……。
こんなにも、温もりを確かめあっても、抱き締めあっても……。
――――――ぼくたちは、恋人同士ではない。
「……」
沈黙に耐えかねたように口を開くのは、いつもぼくの方だ。
「もう……いいの?紅葉」
ぼくはそっと口を開き、彼の名を呼ぶ。
「あぁ、浬」
抑揚のないその声が、ぼくの名前を呼ぶ。
だけどぼくと言う存在を認識してくれているんだって分かるから……嬉しくもあり、切なくもなる。
ぼくはその先に、行くことができない。
「……もぅ、帰るの?夕飯は……」
「……いい」
そう、素っ気なく答えた紅葉は……ぼくの部屋からフッと消え失せる。
……家に、帰ったのだろう。紅葉が来るのはいつも突然で、こうしてぼくを抱き締め体温が戻っていくと帰っていく。
紅葉が来たら教えてとせがむ妹にも教えられない、2人だけの時間。でも、一線は越えてはいけないんだ。
ぼくたちはただ、家が隣同士と言うだけで……。
小さな頃から家が隣同士だった。紅葉はルックスはいいくせに無口で、他人に興味がなくて。だけど、ぼくと妹が家の外で遊んでいれば不思議とやってきたから、一緒に遊んでいた。
妹はその頃から紅葉のファンである。妹は俺と紅葉をよくある幼馴染みとしか思っていないし、あわよくば紅葉の彼女の座を狙っている……。
しかし、紅葉はどうあっても妹の手を取らないだろう。その事実にホッとしているのは兄としてなのか……。それとも口には出せないこの思いのせいか……。
妹も、ぼくの両親だって、紅葉の本当は知らない。
――――――奥宮紅葉。
その正体は、EPA(Extrasensory Perception Agency)ー特殊能力捜査部隊ーのエージェントである。
だがEPAの実態を、エージェントの実態を……その全てをぼくは知らない。
ただ、知っていることは。この日本には一般人には知られていない異能を持つ存在……特殊体質と呼ばれる人間がいること。
しかしその中にはその異能を使い犯罪を行うもの、暴走させてしまい一般人を危険に巻き込んでしまうものもいる。
そう言ったものたちを取り締まり、それから彼ら特殊体質にしか扱えない未曾有の事態に対応するのがEPAである。
それが政府機関なのか、警察機関なのか、民間機関なのか……それとも世界的機関なのか。それは多分……エージェントや一部のリングしか知らないのだろうな。
そしてEPAに取って大切な存在が、リングと呼ばれる存在。
リングとは特殊体質ごとに存在すると言われる人間のことだ。昨今流行りのゲームやアニメで例えるならば、いわゆるヒーラーと呼ばれる存在に近いと思う。
特殊体質はその力を無限に使えるわけではない。力を使うごとに心を病が蝕み、暴れ、狂人化して……最期には廃人のようになってしまう。
そんな状況から回復させ、特殊体質を元に戻すのが、リングと呼ばれる存在だ。
回復させる方法は、みんな同じ。いたって簡単だ。
先程のようにリングが特殊体質を抱き締めればいい。ただ、それだけだ。
側にいたり、手を握ったりでもいい。
特殊体質はその力を放出していなくとも、日々気付かぬうちに力を漏れ出している。だからただそばにいるだけでも、特殊体質としてはホッとするのだろう。
だけど……。ここ数年のようにひどく消耗した紅葉を回復させるには、抱き締めてやるしかない。
これはただひとり、ぼくにしかできない役割だ。
特殊体質にとってのリングが誰でもいいと言うわけではないのだ。
特殊体質は、ひとりとして同じ体質がないのが厄介なところ。
似ていたとしても、違う。
同じような体質でも、一方で効果のあるリングはもう一方では全く機能しないのだ。
その上数多くの体質を併せ持つ複合型特殊体質なら、なおのこと。
長い時間、研究を重ねて導きだした答えはーー、リングをその特殊体質を癒せるか。その特殊体質に適合するかは、特殊体質ごとに異なる。つまりは特殊体質毎にそれぞれのリングが必要なのである。
その特殊体質の力を使うにはリングが必要だし、さらに自身に適合するリングを見付けられなければ、特殊体質は須く病んでいく。
なるべく力を使わないようにしても、生きていく上でどうしてもその力は滲み出るものなのである。だからこそ……特殊体質にはリングが不可欠なのだ。
なら、リングを集めて特殊体質に会わせれば……と言う方法も考えられた。
だがリングを判別できるのは特殊体質だけだ。そしてその特殊体質に適合するリングは、特殊体質自身にしか分からない。
――――――中にはリングの気配を辿って、海を渡ってくる特殊体質もいるようだが……実際どうなんだか。もしそんなことができるとしたら……テレポートが使えるもみじとか。
いや、まさかね。
だが、制約もあれば時に救いもある。
聖女ーーもしくはホーリーリングと呼ばれる存在だ。
ホーリーリングは全ての特殊体質に適合すると言われる特別なリング。リングのいない、いつ自我を失うか、狂うか分からない中生きる特殊体質にとっては、まさに夢のような……いや、女神のような存在なのだろう。
まぁぼくは実際に会ったことがあるわけではないので、そんな神の御業のようなことができるリングが本当に存在するのか……。真偽は不明瞭である。
だがひとつ明らかなのは……ぼくが紅葉の唯一のリングだと言うことだけである。
こうしてぼくたちのように適合し、特殊体質のリングとなった人間は……【ペアリング】と呼ばれ、適合した特殊体質からひとつの指輪を渡される。
ぼくも持っている。普段は制服の下にチェーンを通して首から下げている。今は部屋着だからこの通り……だな。
そしてチェーンの先にぶら下がるリングをそっと摘まみ上げる。これが、紅葉とのペアリングの証。
銀色の、無機質な輪っか。まるで紅葉の存在そのものを象徴するかのようなリング。これには紅葉の特殊体質によって生み出される力が込められているのだそうだ。
ぼくには全く分からないけど……だけどこれがぼくの身を守ることにもなる。特殊体質者はこの指輪を感知できるから。
だからこそ特殊体質の間ではこの証を持っている人間には不干渉とするのが暗黙のルールなのだそうだ。
――――――これを肌身放さず持ち歩け……そう、紅葉に言い付けられて。さすがに指にはつけられないから、せめてこうして首からさげている。
そしてこのリングに力を込めたその主は、身に付けたリングがいつ、どこにいるのかをいつでも感知する。
だからこそ紅葉はいつも突然ぼくの前に現れる。紅葉にはぼくの居場所がいつも分かるし、紅葉にはいつでもぼくの前に現れることのできる力がある。まるで……テレポートみたいだな。
いや、まさにテレポートなのだけど。
だけど誰でもテレポートが使えるわけじゃない。ここまで自由自在と言うのは、なかなかないらしい。ぼくは紅葉の特殊体質の全てを知らない。それがすごいのか、どうなのか……一度紅葉に聞いてはみたものの、『知らん』と言われてしまった。
しかし最近は、テレポートしてくる頻度が特に高いな……。ぼくは抱き締めるだけだから負担は一切なのだが。
だけどぼくの元にテレポートしてくる、抱擁を求めてくると言うことは、その分力を使ったと言うことだ。
その度に抱き締める、紅葉の身体はとても冷たくて、凍えるようだった。
だがしかし、紅葉は生きるために、自我を保つために……人間であるために必死にしがみつく。
そこに温かな感情はない。愛などない。何もない。あるのはただ、生きようとする生存本能のみである。
この凍てついた身体を抱き締めて、温めて……温ためて……。
その体温がだんだんと戻ってきてやっと……ぼくは一安心できるのだ。
だがそれは、抱き締める分だけ、凍えた紅葉の体温の分だけ、エージェントとして任務に駆り出されていると言うことだ。まだぼくと同じ16歳。高校1年生だと言うのに。
――――――大丈夫かな、紅葉。
紅葉が帰って、暫く部屋のなかで考え込んでいた。やがて部屋に射し込んでいた西陽と共に残響も立ち消えて……。
部屋に暗闇と本当の静寂が降りてくる。
――――――夕飯に、するか。
とぼとぼと下の階に降りれば、中学生の妹がテレビを眺めながら、お菓子を摘まんでいた。
「ねぇ、お兄ちゃん!」
「なんだ?命」
エプロンをつけて台所に入ろうとすれば。
「最近、紅葉お兄ちゃん来ないね」
「そう……かな?」
まぁぼくの前には毎日のように現れるし、登下校は不思議と今も一緒である。
そこだけは小学生の頃から変わらない。小学生の頃は手を繋いで、側にいることで紅葉の特殊体質が落ち着いていたことは分かる。だからこそ紅葉は、ずっとぼくといた。
最近は毎日のように抱擁をせがんでくる。側にいるだけじゃ、全く足りてない。いつも、まるで浴びるように、貪るように抱き締めてくる。そこに特別な感情がないとしても。ただ生きるためだからだとしても。
……ぼくには、それを拒むことができない。
紅葉はぼくとなるべくいるために、ぼくと同じ高校に入った。
だからか高校への登下校も、いつも一緒だ。
しかも妹は紅葉に会いたくて、毎日早起きしている。高校と中学はまるで方向が違うから、家の前でさよならなのだけど。ほんと、女子中学生の活力が羨ましい。
「命も毎日会ってるだろ、朝」
「朝だけじゃんっ!紅葉お兄ちゃんがうちに遊びに来ないじゃんっ!」
そんな駄々を捏ねられても。紅葉には任務があるのだろうし……。
しかし……それはあれか?幼い頃はうちの前に遊びに来ていたからか?
いやでもあれも紅葉がぼくのことを自分のリングだと認識し、側にいたにすぎない。
たまに手を繋いでいるのを妹が羨ましがり、ぼくと紅葉の手を無理矢理放そうとしたら是が非でも離れないほど強く握られたのは衝撃だったが。
最後には妹が泣き出してしまい、観念してぼくが手を繋ごうと言ったら、『紅葉お兄ちゃんがいいの!』とキレられて兄心が傷付いたのは……余談だが。
中学生に上がった頃には手を繋ぐことはなくなったけど。でもある日、数日家を留守にしていた紅葉が突然ぼくの前にやってきて、抱き締めて来た時。
――――――期待してしまったんだ。
ぼくは……ずっと……。どうしてか、遠い昔から抱く、懐かしい感情。
妹にもひた隠していた思いを自覚してしまった。
だけどすぐに打ち明けられた。EPAのこと。紅葉の特殊体質のこと。そしてリングのこと。ぼくが紅葉のリングで、ペアリングとならねばならないこと。
『勘違いをするな。これは……お前がリングだからにすぎない』
そう言われたことが、ショックで……。同時に悟ってしまったのだ。紅葉がどうしてぼくたち兄妹に、いや、ぼくに近付いたのか。
『それが、紅葉のためなんだもんな……!大丈夫。ぼくたち、友だちだもんな!』
あんなこと、言わなければ良かった。
紅葉の短い『あぁ』と言う頷きを聞くくらいなら。
「お兄ちゃん?」
「え、あぁ、何?」
妹の呼び掛けに慌てて返せば。
「最近、おじさんとおばさんたちも見ないね。えっと、ずっと海外勤務なんだっけ?」
「……あぁ、そうだな」
そう言うことに、なっている。でも俺は聞かされていた。本当はそんなひと、いないんだって。
妹やぼくの両親が、紅葉の両親だと思っているおじさんとおばさんは、必要な時だけ紅葉の両親を勤めるためのEPAからの派遣員なんだって。いわゆるレンタル家族である。まぁ一応辻褄を合わせるために同じひとが派遣されてくるらしい。
普段は海外勤務だって言う設定だから、スーツケースで帰ってきても不思議でもないし。
紅葉は色々と謎だけど、少なくとも紅葉は孤独で、そして本当の家族と呼べる存在がいない。
ただお互い中学生の時は、紅葉をうちに招いて、ついでに夕飯食べさせてあげていたけれど、高校に入ってからはめっきり来なくなった。
あの広い一軒家で、紅葉がどう過ごしているのかを、俺は知らない。
妹だって知らない。ぼくも妹も、紅葉は家にいれてくれないから。妹の電撃訪問だって頑なに拒否するんだ、あいつ。
でも中学校の家庭訪問の際はさすがにレンタル家族が派遣されてきて、対応していたようだけど。小学校の時は気が付かなかったことも、中学生になって分かったこともある。
――――――ぼくだけが知る紅葉のあの体温も。
「お兄ちゃん。紅葉お兄ちゃんに、うちに夕飯食べに来るよう誘っといてよ」
「……え、何で」
「何でって、紅葉お兄ちゃん、まだ高校生じゃん!おじさんおばさんは普段留守だし」
まぁ……レンタル家族だからな。
「だからお夕飯くらい食べさせてあげなきゃ……!」
「作るのお兄ちゃんだぞー」
妹はそこら辺はからっきしなので、台所に立つことを禁じられている。
「それでも、だよ!……あ、それともお兄ちゃん、紅葉お兄ちゃんと喧嘩したんじゃないよね……っ!?」
妹がはっとして口を手で隠す。
「……してないよ」
「じゃぁなんでさ?」
「今度誘っとくから」
「うん、絶対だよ?お兄ちゃん!」
妹は満足げに笑うと、再びテレビに目を戻して、お菓子をボリボリ食べ始めた。
夕飯、食べられなくなっても知らないぞー。
でもま、仕方がない、か。今日みたに、誘っても来ないだろうけどね。
両親とも仕事で遅いから、夕飯はぼくが作ることになっている。
あれこれ紅葉のことを考えつつフライパンを握り、料理を仕上げる。
よし、今日はハンバーグ定食だな。
そうして完成してみれば、命ったら、ぼくの気も知らないで。
やったやったと浮かれながら、大喜びでハンバーグにがっつく肉食系妹にーー少しだけ救われたのは、内緒である。
……言ったら、調子に乗るからな。