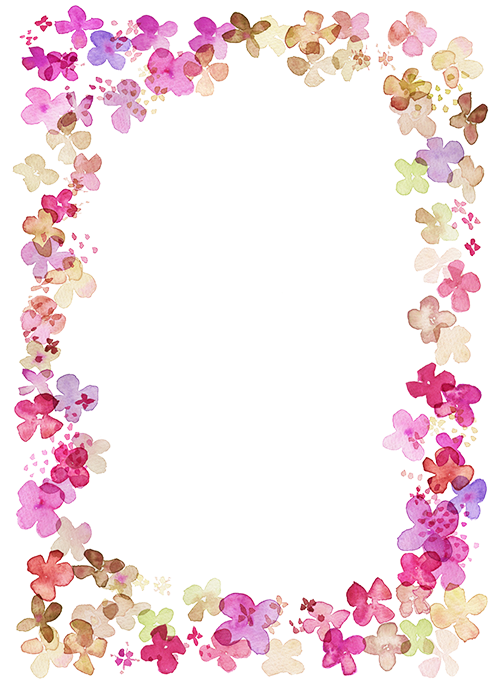照り付ける陽光を遮るには、パーカーのフードでは心もとない。
ショートパンツから伸びる足が火傷を追ったようにひりひりする。
気怠さを感じながら、出来るだけ早く爪先を前に出した。
いくらも歩かないうちに眩暈がして、人目につかない橋の下でしゃがみ込む。眼前が暗い。海の中で揺蕩うような意識の中で、冷や汗の浮かぶ額を袖で拭う。これではとても歩けない。
浅はかな考え外に出て、行き倒れそうな己のひ弱さを情けなく思う。
それでもここにいて見つかりさえしなければ、夜になったら逃げられる筈だ。太陽は真上で恨めしいほど輝いている。直接見てしまったら目が潰れてしまいそうに。
マヤは学校でテスト用紙と睨めっこしている時間だ。それでも午前だけで帰宅する。私が部屋にいないと分かったらどうするだろう。どうもしないかもしれない。
マヤの部屋の隅でそうしていたように膝を抱える。昨晩降った雨のせいで、川には濁流が走っていた。
道端で立ち止まっているより随分涼しい。
意識して酸素を取り込み、ぼうっと川の向こう岸を眺める。大きな犬をつれた婦人が大股で歩いていた。手の平で膝を擦る。思ったより肌が乾燥していた。
六日血を飲まないだけで堪えられない体になってしまったのか。甘やかされ、それに甘えていた事実を憎らしく思う。しかし同時にこれならすぐに死ねるかもしれないという期待感が生まれた。コンスタントに血を摂取することに慣れてしまった体に、飢餓はよく効くような気がした。
現に今だって、空腹感と倦怠感に襲われ、瞼が重くなっていた。ひどく疲れているのに、幸福な夢の中にいるような心地がする。
このまま目が覚めませんように。
祈りながら、眠気に身を任せた。
目が覚めたのは、胸や腹を這い回る熱いものを感じたからだった。
ぞわそわと鳥肌が立ち、その正体を確かめるために下を向くと、茶色い手がパーカーの中を弄っていた。反射的に後ろを振り向く。
小鼻の横に盛り上がった黒子のある、栄養を失ったような長髪を振り乱す中年男性が、私を両足の間に挟んで座っていた。
「や……っ」
肘を振って体を離そうとするも、太い指は離れなかった。それどころか、パーカーの中に着ているシャツの下に、無理矢理手を滑り込ませる。欲を帯びた体温が伝わってきて、全身が粟立った。
ガサガサの手の平が臍のあたりを撫で、徐々に上へと上っていく。
叫び出したい衝動に駆られたが、頭の真ん中にマヤの顔が浮かび、下唇の裏を噛んで堪えた。
そうだ、死ぬんだった。
死んでいいんだった。
もう、止める奴はいない。
体の緊張を解くと、両方の乳房を鷲掴みにされ、パンをこねるように揉みしだかれた。その先の突起を摘ままれ、痛覚が刺激され声が漏れる。途端に、過去同じようなことを沢山の異性にされていたことを思い出した。
彼らは金額を提示し、血をねだると容易に提供してくれた。そういうプレイが好きなんだね、と不可解なことを言うので、理解できないまま曖昧に頷いた。体中を撫で、舐め上げ、股の間に指を入れると、股間のものを取り出してそれを埋めた。粘膜を擦られ、臓器を抉り出される不快感を、天井の四隅を順番に見ながらやり過ごした。
そういうことをする人間の血は、大概が腐臭がして、栄養を摂る為だけに飲んでいた。そういうものだと思っていた。
その味だけ知っていれば良かったのに。
男の薄汚れた衣服から、体臭を濃縮させたような匂いが漂ってくる。吐き気がした。
十匹の大きなムカデが這っている。そのうちの五匹が太腿に触れた。ショートパンツの裾から内部に侵入し、下着を捲る。深いところへ進もうとするので、思わず足を閉じた。
がつっ、と耳元で音がして、頬に痛みと熱が走った。
横向きに倒れると、強い力で正面を向かされ、男は切羽詰まったような顔を、私の足の間から覗かせた。再び服の上から股間を撫でられる。男の荒い鼻息が太腿に触れる。
口の中から血の味がした。
滑稽だ。思えばずっとそうだ。
奪った分だけ奪われる。因果応報だ。
男の手がショートパンツを引き下ろそうと手を掛ける。
橋の裏は規則的に鉄骨が入り組んでいた。ホテルで天井の四隅を眺めていたのと同じく、これを見ていればいずれは終わる。願わくば、そのまま殺してくれれば。
考えていると、いきなり男の気配が消えた。
砂袋を殴るような音が何度も繰り返され、急いで視線を向ける。
白いYシャツの後ろ姿が、体を折り曲げ転がる男の体をサッカーボールのように蹴っていた。男がうめき声を上げる。額から血が滲んでいた。
私は震えて力の入らない体を起こし、乱暴をはたらく背中に抱きついた。
「や、やめて……!」
振り返ったマヤは無表情で私を一瞥に、足元の男の腹を思いきり蹴った。吐き散らした赤い唾がマヤのスニーカーを汚す。再び足を後ろに振り上げるので、マヤの背中に額を押し付けながら叫んだ。
「死んじゃうから!やめて!」
橋の下で私の声が反響する。
マヤは動きを止めて、困ったような、悲しんでいるような表情で私を見つめた。
「何で止める」
湖の水が凍るような温度で、マヤは問う。
「だって……そんなにしたら死んじゃうから」
「死んでもいいだろ」
「マヤが、悪者になる」
「別にいいよ」
あまりにも無垢で、あっけらかんとしているので、恐ろしくなった。
男は動かなくなっていた。本当に死んでしまったのではと首筋に指をあてると、確かな拍動を感じて安堵した。
「お前、怪我……」
マヤは私を見て、すぐに男に視線を移し、今度は膝を垂直に上げた。無邪気な子どもが蟻を潰すような仕草に、硬い腕を掴む。
「駄目だってば!」
マヤの足は静かに地を踏んだ。
「……顔色悪いな。帰るか」
腫れて痺れたようになっている頬に触れて、マヤは倒れている鞄を掴んだ。
「おぶる?」
「……大丈夫」
強がりだった。芯の抜けている足に力を入れる。
生まれたての仔馬のように不安定に歩を進めると、マヤが私の正面に背を向けてしゃがんだ。
「そんなんじゃいつまで経っても着かねえよ」
不本意だが最もだと思い直し、素直に跨る。軽々と立ち上がったマヤの背中は温かかった。
「顔隠しとけ」
言われた通り、日陰から出る前にフードを被り直す。緑の騒ぐ土手を上る揺れを感じていると、頭がぼんやりしてきて、抵抗する間も無く柔らかな闇に落ちた。
マヤの背中の大きさを、いつか忘れられる日はくるだろうか。
ショートパンツから伸びる足が火傷を追ったようにひりひりする。
気怠さを感じながら、出来るだけ早く爪先を前に出した。
いくらも歩かないうちに眩暈がして、人目につかない橋の下でしゃがみ込む。眼前が暗い。海の中で揺蕩うような意識の中で、冷や汗の浮かぶ額を袖で拭う。これではとても歩けない。
浅はかな考え外に出て、行き倒れそうな己のひ弱さを情けなく思う。
それでもここにいて見つかりさえしなければ、夜になったら逃げられる筈だ。太陽は真上で恨めしいほど輝いている。直接見てしまったら目が潰れてしまいそうに。
マヤは学校でテスト用紙と睨めっこしている時間だ。それでも午前だけで帰宅する。私が部屋にいないと分かったらどうするだろう。どうもしないかもしれない。
マヤの部屋の隅でそうしていたように膝を抱える。昨晩降った雨のせいで、川には濁流が走っていた。
道端で立ち止まっているより随分涼しい。
意識して酸素を取り込み、ぼうっと川の向こう岸を眺める。大きな犬をつれた婦人が大股で歩いていた。手の平で膝を擦る。思ったより肌が乾燥していた。
六日血を飲まないだけで堪えられない体になってしまったのか。甘やかされ、それに甘えていた事実を憎らしく思う。しかし同時にこれならすぐに死ねるかもしれないという期待感が生まれた。コンスタントに血を摂取することに慣れてしまった体に、飢餓はよく効くような気がした。
現に今だって、空腹感と倦怠感に襲われ、瞼が重くなっていた。ひどく疲れているのに、幸福な夢の中にいるような心地がする。
このまま目が覚めませんように。
祈りながら、眠気に身を任せた。
目が覚めたのは、胸や腹を這い回る熱いものを感じたからだった。
ぞわそわと鳥肌が立ち、その正体を確かめるために下を向くと、茶色い手がパーカーの中を弄っていた。反射的に後ろを振り向く。
小鼻の横に盛り上がった黒子のある、栄養を失ったような長髪を振り乱す中年男性が、私を両足の間に挟んで座っていた。
「や……っ」
肘を振って体を離そうとするも、太い指は離れなかった。それどころか、パーカーの中に着ているシャツの下に、無理矢理手を滑り込ませる。欲を帯びた体温が伝わってきて、全身が粟立った。
ガサガサの手の平が臍のあたりを撫で、徐々に上へと上っていく。
叫び出したい衝動に駆られたが、頭の真ん中にマヤの顔が浮かび、下唇の裏を噛んで堪えた。
そうだ、死ぬんだった。
死んでいいんだった。
もう、止める奴はいない。
体の緊張を解くと、両方の乳房を鷲掴みにされ、パンをこねるように揉みしだかれた。その先の突起を摘ままれ、痛覚が刺激され声が漏れる。途端に、過去同じようなことを沢山の異性にされていたことを思い出した。
彼らは金額を提示し、血をねだると容易に提供してくれた。そういうプレイが好きなんだね、と不可解なことを言うので、理解できないまま曖昧に頷いた。体中を撫で、舐め上げ、股の間に指を入れると、股間のものを取り出してそれを埋めた。粘膜を擦られ、臓器を抉り出される不快感を、天井の四隅を順番に見ながらやり過ごした。
そういうことをする人間の血は、大概が腐臭がして、栄養を摂る為だけに飲んでいた。そういうものだと思っていた。
その味だけ知っていれば良かったのに。
男の薄汚れた衣服から、体臭を濃縮させたような匂いが漂ってくる。吐き気がした。
十匹の大きなムカデが這っている。そのうちの五匹が太腿に触れた。ショートパンツの裾から内部に侵入し、下着を捲る。深いところへ進もうとするので、思わず足を閉じた。
がつっ、と耳元で音がして、頬に痛みと熱が走った。
横向きに倒れると、強い力で正面を向かされ、男は切羽詰まったような顔を、私の足の間から覗かせた。再び服の上から股間を撫でられる。男の荒い鼻息が太腿に触れる。
口の中から血の味がした。
滑稽だ。思えばずっとそうだ。
奪った分だけ奪われる。因果応報だ。
男の手がショートパンツを引き下ろそうと手を掛ける。
橋の裏は規則的に鉄骨が入り組んでいた。ホテルで天井の四隅を眺めていたのと同じく、これを見ていればいずれは終わる。願わくば、そのまま殺してくれれば。
考えていると、いきなり男の気配が消えた。
砂袋を殴るような音が何度も繰り返され、急いで視線を向ける。
白いYシャツの後ろ姿が、体を折り曲げ転がる男の体をサッカーボールのように蹴っていた。男がうめき声を上げる。額から血が滲んでいた。
私は震えて力の入らない体を起こし、乱暴をはたらく背中に抱きついた。
「や、やめて……!」
振り返ったマヤは無表情で私を一瞥に、足元の男の腹を思いきり蹴った。吐き散らした赤い唾がマヤのスニーカーを汚す。再び足を後ろに振り上げるので、マヤの背中に額を押し付けながら叫んだ。
「死んじゃうから!やめて!」
橋の下で私の声が反響する。
マヤは動きを止めて、困ったような、悲しんでいるような表情で私を見つめた。
「何で止める」
湖の水が凍るような温度で、マヤは問う。
「だって……そんなにしたら死んじゃうから」
「死んでもいいだろ」
「マヤが、悪者になる」
「別にいいよ」
あまりにも無垢で、あっけらかんとしているので、恐ろしくなった。
男は動かなくなっていた。本当に死んでしまったのではと首筋に指をあてると、確かな拍動を感じて安堵した。
「お前、怪我……」
マヤは私を見て、すぐに男に視線を移し、今度は膝を垂直に上げた。無邪気な子どもが蟻を潰すような仕草に、硬い腕を掴む。
「駄目だってば!」
マヤの足は静かに地を踏んだ。
「……顔色悪いな。帰るか」
腫れて痺れたようになっている頬に触れて、マヤは倒れている鞄を掴んだ。
「おぶる?」
「……大丈夫」
強がりだった。芯の抜けている足に力を入れる。
生まれたての仔馬のように不安定に歩を進めると、マヤが私の正面に背を向けてしゃがんだ。
「そんなんじゃいつまで経っても着かねえよ」
不本意だが最もだと思い直し、素直に跨る。軽々と立ち上がったマヤの背中は温かかった。
「顔隠しとけ」
言われた通り、日陰から出る前にフードを被り直す。緑の騒ぐ土手を上る揺れを感じていると、頭がぼんやりしてきて、抵抗する間も無く柔らかな闇に落ちた。
マヤの背中の大きさを、いつか忘れられる日はくるだろうか。