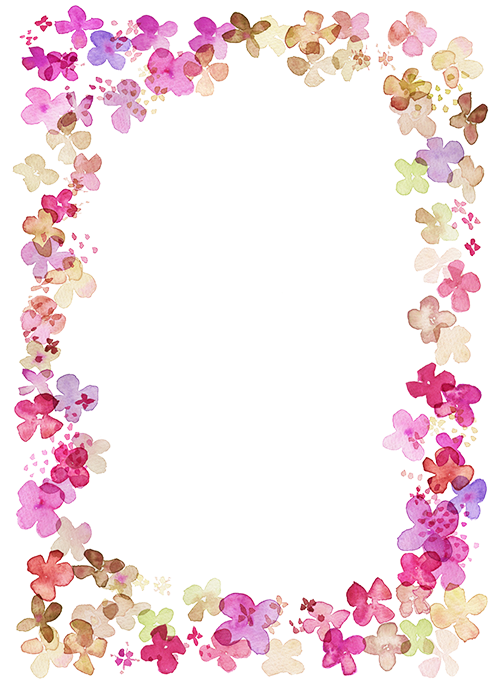死んでいるのかと疑うほど寝息が静かなので、四つん這いで背後に近付く。
豆電球のほのかで柔らかな明かりの下で、幅の広い肩は正常に上下していた。
それだけを確認して少しだけ身を引く。ちらと見えた瞼は廃れた商店街のシャッターのように下がりきっていた。
水野マヤはいつも私に背を向けて眠る。
まるで弱点を曝されているようで、気分が悪い。私が危害を加えないことを妄信しているような、そんな不用意さが、嫌いだ。
寝首をかくことが出来て、生存を確認できるこの距離にいると、ふとした瞬間に泣きたくなる。
目の前が滲んで、鼻を啜る。マヤが起きてしまってはいないかと顔を覗くと、その横顔に影が出来た。
溜息をついて恐る恐る体を離そうとした時だった。
「……ッ」
腕が伸びてきた腕に胸元を掴まれた。
体が浮き、全身に衝撃を感じた時には柔らかな敷布団の上に倒れていた。痛みに瞑ってしまっていた目を開くと、鼻先にはマヤの二つの瞳が光っていた。
「眠れないのか」
静寂を震わせないように気を使っているような声量でマヤが問う。先程まで寝ていたそれらしい掠れた声だった。マヤと向き合うように横向きの体勢になった私が体を起こそうとすると、腕を掴まれ引き倒された。落下地点にはマヤの腕があって、望まない腕枕をされてしまった。
それどころか、背に腕を回され、肩甲骨の真ん中を、子をあやすように叩かれた。秒針よりもゆっくりなリズムと手の平のぬくもりに、首を絞められたように呼吸が苦しくなった。
「腹、膨れなかったか?」
耳に直列に繋がれたようにマヤの声が届いて、芋虫のように体を丸めた。するとマヤの肩口に額を押し付けるようなかたちになってしまい、慌てて離れようとすると、頭の下に敷いていたマヤの手が私の後頭部を引き寄せた。
「お前いつ寝てんの?」
頭頂部にマヤの熱い息がかかる。
「吸血鬼って寝なくても死なねえの?」
マヤの図太い呼吸の音も、太鼓を鳴らすような心臓の音も聞こえる。
首から甘い匂いがする。
その香しさに惹きつけられて、口腔内がしとどに濡れた。喉が鳴る。
「まだ足りねえならもっと」
「要らない。要らないから離してよ」
私が声を上げると、マヤはますます両腕に力を込めた。屈強な肩に口が塞がれる。マヤの顔は見えない。マヤの胸に腕を突っ張っても、体同士は糊を付けたように離れなかった。
「ここから出て行ったらどうすんだ、お前。死ぬのか?」
ぼそぼそと独り言のようにマヤが呟く。何故か少しだけ笑っているような色もあって、抵抗さえ出来ない自分が惨めに思えて、マヤの薄いシャツを握った。
「公園のトイレで寝泊りしてたって言ったよな。またそういう生活に戻るのか?知らねえオヤジについて行って血と金貰ってたって言ったよな?なあ」
ははっ、と本当に声を出してマヤは笑った。セミの抜け殻を見つけた子どものような笑い方だった。
ざらざらと窓の外で葉の擦れ合う音がする。
「そんなざまで幸せかよ」
どん、と乱暴に叩いても、マヤの体はびくともしなかった。
自分の荒い呼吸音がよく聞こえた。
何もかも五月蠅くて煩わしくて、他人の腐った口を塞げないのならば、せめて自分の呼吸の音も心臓の音も止めてしまいたいのに。この男がそれをさせない。
悔しくて涙が溢れた。
止めどないそれを、マヤのシャツに染みさせてやった。
ああ、いやだ。死にたい。
マヤの首から生き生きとした拍動を感じる。
苛々する。
「ずっとここにいればいい」
マヤの低い声が水滴のように降ってくる。肘を伸ばすと、漸くマヤの体から離れることが出来た。何度か咳をして、濡れた目を拭う。マヤは眉を寄せて、自嘲するように口の端を上げていた。
「血は吸い放題だし、風呂にも入れるし、悪くねえだろ?死にたくなる理由あるか?」
逃げようとすると、今度は左の手首を捕らえられた。マヤの手は大きくて厚い。柔道部で鍛えた体に叶うはずもなかった。
「なあ、お前に死なれると後味が悪いんだよ」
宥めるように抑えた声に虫唾が走った。
「あんたに何が分かる!勝手に助けただけのくせに!」
思わず声を荒げた。喉の奥から感情が噴出する。マヤの硬い胸を、握った拳で思いきり叩いた。
「もう私に関わるな!私が生きてようが死んでようがあんたには関係ないだろ!」
どん、どん、どん。
肋骨の中で殴打の音が響いた。
それでもマヤは動かない。そして私の手首を掴む力も弛めなかった。
マヤが一度瞼を伏せ、虚を見るような瞳で私を見た。
「関係ない」
沼の中に匙でも投げ、それを見送るような粘着質な間ができる。
「けど、……死なれたら、困る」
マヤが眼球を入れ替える為の瞬きをしたのだと思った。鋭い視線に射貫かれて、動揺した。そうしてるうちに手首が解放され、私は逃げることを許可された。
なのに、マヤは逃げる私を追ってはこないだろうという確信を持ってしまって、何故か体が動かなくて、私は敷布団の上に顔を埋めて、金縛りにあったようにじっとしていた。
「また泣かせた。すまん」
沈んだ声をともに、再び頭に体温が降ってくる。もう抵抗はしなかった。
「ちゃんと寝てくれ」
声と体温が離れていき、髪の間から様子を窺うと、マヤは反対の壁の前に横になっていた。
フローリングよりましとはいえ、直に触れる畳は、骨の出ているところには特に硬く感じ、不快なことだろう。どうしてこの布団を使わないのだろう。居た堪れなくなり、立ち上がった。
「それ、使えよ」
「……要らない」
「あっそ」
マヤは転がったまま動かない。
「こっちに寝たら」
「要らねえ」
私は部屋の隅に座り、冷たい壁に寄り掛かった。マヤから移った体温を冷やすのに丁度良かった。
布団は空になったまま、マヤはいつもの時間に目を覚ました。
私はそれをぼんやり見ていた。
豆電球のほのかで柔らかな明かりの下で、幅の広い肩は正常に上下していた。
それだけを確認して少しだけ身を引く。ちらと見えた瞼は廃れた商店街のシャッターのように下がりきっていた。
水野マヤはいつも私に背を向けて眠る。
まるで弱点を曝されているようで、気分が悪い。私が危害を加えないことを妄信しているような、そんな不用意さが、嫌いだ。
寝首をかくことが出来て、生存を確認できるこの距離にいると、ふとした瞬間に泣きたくなる。
目の前が滲んで、鼻を啜る。マヤが起きてしまってはいないかと顔を覗くと、その横顔に影が出来た。
溜息をついて恐る恐る体を離そうとした時だった。
「……ッ」
腕が伸びてきた腕に胸元を掴まれた。
体が浮き、全身に衝撃を感じた時には柔らかな敷布団の上に倒れていた。痛みに瞑ってしまっていた目を開くと、鼻先にはマヤの二つの瞳が光っていた。
「眠れないのか」
静寂を震わせないように気を使っているような声量でマヤが問う。先程まで寝ていたそれらしい掠れた声だった。マヤと向き合うように横向きの体勢になった私が体を起こそうとすると、腕を掴まれ引き倒された。落下地点にはマヤの腕があって、望まない腕枕をされてしまった。
それどころか、背に腕を回され、肩甲骨の真ん中を、子をあやすように叩かれた。秒針よりもゆっくりなリズムと手の平のぬくもりに、首を絞められたように呼吸が苦しくなった。
「腹、膨れなかったか?」
耳に直列に繋がれたようにマヤの声が届いて、芋虫のように体を丸めた。するとマヤの肩口に額を押し付けるようなかたちになってしまい、慌てて離れようとすると、頭の下に敷いていたマヤの手が私の後頭部を引き寄せた。
「お前いつ寝てんの?」
頭頂部にマヤの熱い息がかかる。
「吸血鬼って寝なくても死なねえの?」
マヤの図太い呼吸の音も、太鼓を鳴らすような心臓の音も聞こえる。
首から甘い匂いがする。
その香しさに惹きつけられて、口腔内がしとどに濡れた。喉が鳴る。
「まだ足りねえならもっと」
「要らない。要らないから離してよ」
私が声を上げると、マヤはますます両腕に力を込めた。屈強な肩に口が塞がれる。マヤの顔は見えない。マヤの胸に腕を突っ張っても、体同士は糊を付けたように離れなかった。
「ここから出て行ったらどうすんだ、お前。死ぬのか?」
ぼそぼそと独り言のようにマヤが呟く。何故か少しだけ笑っているような色もあって、抵抗さえ出来ない自分が惨めに思えて、マヤの薄いシャツを握った。
「公園のトイレで寝泊りしてたって言ったよな。またそういう生活に戻るのか?知らねえオヤジについて行って血と金貰ってたって言ったよな?なあ」
ははっ、と本当に声を出してマヤは笑った。セミの抜け殻を見つけた子どものような笑い方だった。
ざらざらと窓の外で葉の擦れ合う音がする。
「そんなざまで幸せかよ」
どん、と乱暴に叩いても、マヤの体はびくともしなかった。
自分の荒い呼吸音がよく聞こえた。
何もかも五月蠅くて煩わしくて、他人の腐った口を塞げないのならば、せめて自分の呼吸の音も心臓の音も止めてしまいたいのに。この男がそれをさせない。
悔しくて涙が溢れた。
止めどないそれを、マヤのシャツに染みさせてやった。
ああ、いやだ。死にたい。
マヤの首から生き生きとした拍動を感じる。
苛々する。
「ずっとここにいればいい」
マヤの低い声が水滴のように降ってくる。肘を伸ばすと、漸くマヤの体から離れることが出来た。何度か咳をして、濡れた目を拭う。マヤは眉を寄せて、自嘲するように口の端を上げていた。
「血は吸い放題だし、風呂にも入れるし、悪くねえだろ?死にたくなる理由あるか?」
逃げようとすると、今度は左の手首を捕らえられた。マヤの手は大きくて厚い。柔道部で鍛えた体に叶うはずもなかった。
「なあ、お前に死なれると後味が悪いんだよ」
宥めるように抑えた声に虫唾が走った。
「あんたに何が分かる!勝手に助けただけのくせに!」
思わず声を荒げた。喉の奥から感情が噴出する。マヤの硬い胸を、握った拳で思いきり叩いた。
「もう私に関わるな!私が生きてようが死んでようがあんたには関係ないだろ!」
どん、どん、どん。
肋骨の中で殴打の音が響いた。
それでもマヤは動かない。そして私の手首を掴む力も弛めなかった。
マヤが一度瞼を伏せ、虚を見るような瞳で私を見た。
「関係ない」
沼の中に匙でも投げ、それを見送るような粘着質な間ができる。
「けど、……死なれたら、困る」
マヤが眼球を入れ替える為の瞬きをしたのだと思った。鋭い視線に射貫かれて、動揺した。そうしてるうちに手首が解放され、私は逃げることを許可された。
なのに、マヤは逃げる私を追ってはこないだろうという確信を持ってしまって、何故か体が動かなくて、私は敷布団の上に顔を埋めて、金縛りにあったようにじっとしていた。
「また泣かせた。すまん」
沈んだ声をともに、再び頭に体温が降ってくる。もう抵抗はしなかった。
「ちゃんと寝てくれ」
声と体温が離れていき、髪の間から様子を窺うと、マヤは反対の壁の前に横になっていた。
フローリングよりましとはいえ、直に触れる畳は、骨の出ているところには特に硬く感じ、不快なことだろう。どうしてこの布団を使わないのだろう。居た堪れなくなり、立ち上がった。
「それ、使えよ」
「……要らない」
「あっそ」
マヤは転がったまま動かない。
「こっちに寝たら」
「要らねえ」
私は部屋の隅に座り、冷たい壁に寄り掛かった。マヤから移った体温を冷やすのに丁度良かった。
布団は空になったまま、マヤはいつもの時間に目を覚ました。
私はそれをぼんやり見ていた。