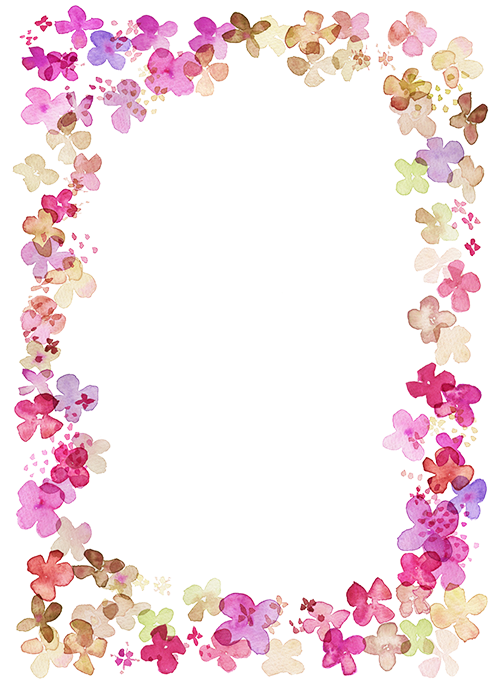風呂から上がると、真っ黒い塊が部屋の隅で両膝を抱えて俯いていた。
五月に入った途端気温がぐんと上がり、密閉した部屋はもやもやとした暑さが漂っている。清潔になったばかりの体には、再び汗が滲んだ。
距離を取ったままそれに声を掛ける。
「なあ」
僅かに上げた顔は青白くて、唇だけが妙に赤い。淀んだ真っ黒い瞳がこちらを向く。長い黒髪が聞き分けよく揺れた。
「飲めるか?」
片足に体重を乗せないようにゆっくりと近付くと、逃げ場を失った小動物のようにますます縮こまる。
それ、ゼンは俺と関わることを望まない。
ゼンの前でしゃがみ込み、顔を覗くように近付けると、再び膝に顔を埋めた。
「無理矢理飲まされるのと、自分から飲むの、どっちがいい?」
自分でもひどい台詞だと思う。
脅すような問いに体を跳ねさせたゼンは、聞き取れないくらい小さな声で何かを呟いた。
「何?」
「……嫌だ」
弱った子猫を思い起こさせるような声を鼓膜が拾う。
「何が?」
「……どっちも」
「そうか。じゃあ、これはどうすろ?」
俺はその場に胡坐をかいて、折り畳みの座卓に手を伸ばした。置いていたカッターを手に取る。
その刃を二の腕の内側の柔らかい皮膚に当てて力を籠め、素早く横に引いた。鋭い痛みと共に、傷口が熱を発したように熱くなると、鮮度のいい肉が口を開いた隙間から窺えた。そこからすぐに血液が滲んで、つうと二の腕の外側まで伝う。
首から下げていたフェイスタオルで雫が落ちるのを抑え、ゼンを見ると、喉ぼとけが上下していた。
下唇の裏を噛んで、堪えるようにに眉根を寄せる。華奢な肩がぶるぶる震えていた。
「要らないならいい」
傷を見せつけ、わざと溢れる血はそのままに、零れるものだけを受け止める。ゼンは下を向き、嫌々するように何度も首を横に振った。
「嫌だ。それ、しまってよ」
黒い瞳が俺を見据え、声を震わせる。
「何で?」
「……我慢出来なくなる。飲みたくない」
「我慢しなくていい」
「嫌だ。死にたい。生きていたくない」
この部屋に来て、食事を与える度、ゼンはその言葉を吐く。
たった一か月の付き合いだが、拾った生き物が死を望むなんて気持ちが悪い。とはいっても人間でないゼンの生存本能は本人の意思に反して強く、この先の展開については確信に近い予想がついていた。
「ほら」
傷付けた腕をゼンの目の前に差し出す。
光を吸い込むような瞳が揺れた。操られているように、鼻先が腕を突くくらいの位置まで寄ってくる。釣り堀で餌を垂らした時に似ているといつも思う。
ゼンが泣きそうに顔を歪めながら、恐る恐るといった様子で真っ赤な舌を伸ばす。
「ちゃんと飲めよ」
言った瞬間、柔らかく湿った感触が皮膚にあたり、べろりと傷口を舐め上げた。
静電気を受けたように痛みが走る。
閉じかけていた傷を抉じ開けるような舌使いに、仰け反りそうになる体を拳を握って堪えた。
血の跡を舐めていた舌は、やがて赤ん坊がするように傷を吸い始めた。ちゅうちゅうと吸い取られ、
その唇の動きに腹の底の方が重くなる。擽ったいだけでない感情を抱いてしまう自分自身を律しようと大きく息を吸うと、口を離したゼンが顔を上げた。真っ直ぐに見てくる瞳と唇が、絵の具を塗ったように赤い。
「……ごめん、なさい」
ゼンの濃い下睫毛が濡れ始める。瞳の色は漆黒に戻っていた。
握っていたタオルでゼンの唇を拭ってやると、瞑った瞳から涙が一粒零れた。
同情をしないわけではない。
生物の血を取り込まないと生きられないなんて、その対象となる我々人間の脅威であり、架空のもとと遠ざけたいほど気味の悪い存在だ。他に姿を露わにしている吸血鬼がいるのかどうかは知らないが、正体を隠しながら人間社会で生きるのは苦労することだろう。
それでも人間よりも欲深く生を求め、それを得る力を持ち、人間を魅了する美しさを持つ。
それが『吸血鬼』、らしい。
図書館から借りた本からの受け売りだが。
しかし、ゼンには何故か生きる気力がない。鋭い犬歯もなく、備え持っている筈の魅了の性質もない。唯一あるのは、唾液に治癒成分が含まれているという特殊体質だけで、身体能力が高いわけでもないようだ。血を飲まなければ死ぬのに、飲みたくないという。
気付くとケロイド状の瘢痕だけを残し、二の腕の傷は無くなっていた。
「もうやめてよ。放っといて」
ゼンが黒いパーカーの袖で目元を擦った。少女の姿の吸血鬼は濡れた声で続ける。
「死にたいの。もう嫌なの」
たった六畳の部屋が湿っていく。
血塗れになったタオルを座卓に放り投げ、ゼンの小さな頭に手を乗せた。俺よりも低い体温が手の平から伝わる。
人間と変わらない姿かたち。
ゼンは吸血鬼だが、目の前で命が失われるのを見過ごすのは気が引けた。その辺でミミズが干乾びようとしているのを見るのは何てことはないというのに、人間に似ているというだけで情が湧く。ただ、それだけの理由で拾ってきた。
「せっかく助けてやったのに、そんなこと言うな」
思ったより不機嫌なそうな声が出た。伸ばしていた手を、ゼンの頭から頬に滑らせる。涙の跡を拭き取るように動かすと、ゼンは微かに身動ぎをした。
「別に出て行くななんて言ってない。嫌なら逃げればいい」
ゼンは恨みがましそうに俺を見て、再び三角座りをして、に顔を下げた。
俺は立ち上がり、畳を踏みしめ、通学用の鞄から英語の教科書とノートを取り出した。座卓に乗っているタオルを退かし、教科書類をそこに広げる。携帯で時間確認すると、21時を回ったところだった。
「もう寝るなら電気消すけど」
教科書を捲りながら問う。「寝ない」と離れたところから聞こえたのを確認してペンを走らせた。
ゼンが眠る姿を見たことがない。寝ているのかどうかも分からない。そもそも睡眠が必要な体ではないのかもしれない。死にたくて体を痛めつけているのかもしれない。
本人が何も喋らないので真相は分からない。
「マヤ」
ふいに名前を呼ばれて視線を上げた。大きな瞳がこちらを向いていた。
「あなたの血は美味しい」
言いながら首を傾げる様子に、同じように首を傾けた。疑問形なのかそれは。
彼女のことは、いまだに知らないことだらけだ。
知っているのは『死にたがりの吸血鬼』であるということだけ。
それ以外は何も知らない。
五月に入った途端気温がぐんと上がり、密閉した部屋はもやもやとした暑さが漂っている。清潔になったばかりの体には、再び汗が滲んだ。
距離を取ったままそれに声を掛ける。
「なあ」
僅かに上げた顔は青白くて、唇だけが妙に赤い。淀んだ真っ黒い瞳がこちらを向く。長い黒髪が聞き分けよく揺れた。
「飲めるか?」
片足に体重を乗せないようにゆっくりと近付くと、逃げ場を失った小動物のようにますます縮こまる。
それ、ゼンは俺と関わることを望まない。
ゼンの前でしゃがみ込み、顔を覗くように近付けると、再び膝に顔を埋めた。
「無理矢理飲まされるのと、自分から飲むの、どっちがいい?」
自分でもひどい台詞だと思う。
脅すような問いに体を跳ねさせたゼンは、聞き取れないくらい小さな声で何かを呟いた。
「何?」
「……嫌だ」
弱った子猫を思い起こさせるような声を鼓膜が拾う。
「何が?」
「……どっちも」
「そうか。じゃあ、これはどうすろ?」
俺はその場に胡坐をかいて、折り畳みの座卓に手を伸ばした。置いていたカッターを手に取る。
その刃を二の腕の内側の柔らかい皮膚に当てて力を籠め、素早く横に引いた。鋭い痛みと共に、傷口が熱を発したように熱くなると、鮮度のいい肉が口を開いた隙間から窺えた。そこからすぐに血液が滲んで、つうと二の腕の外側まで伝う。
首から下げていたフェイスタオルで雫が落ちるのを抑え、ゼンを見ると、喉ぼとけが上下していた。
下唇の裏を噛んで、堪えるようにに眉根を寄せる。華奢な肩がぶるぶる震えていた。
「要らないならいい」
傷を見せつけ、わざと溢れる血はそのままに、零れるものだけを受け止める。ゼンは下を向き、嫌々するように何度も首を横に振った。
「嫌だ。それ、しまってよ」
黒い瞳が俺を見据え、声を震わせる。
「何で?」
「……我慢出来なくなる。飲みたくない」
「我慢しなくていい」
「嫌だ。死にたい。生きていたくない」
この部屋に来て、食事を与える度、ゼンはその言葉を吐く。
たった一か月の付き合いだが、拾った生き物が死を望むなんて気持ちが悪い。とはいっても人間でないゼンの生存本能は本人の意思に反して強く、この先の展開については確信に近い予想がついていた。
「ほら」
傷付けた腕をゼンの目の前に差し出す。
光を吸い込むような瞳が揺れた。操られているように、鼻先が腕を突くくらいの位置まで寄ってくる。釣り堀で餌を垂らした時に似ているといつも思う。
ゼンが泣きそうに顔を歪めながら、恐る恐るといった様子で真っ赤な舌を伸ばす。
「ちゃんと飲めよ」
言った瞬間、柔らかく湿った感触が皮膚にあたり、べろりと傷口を舐め上げた。
静電気を受けたように痛みが走る。
閉じかけていた傷を抉じ開けるような舌使いに、仰け反りそうになる体を拳を握って堪えた。
血の跡を舐めていた舌は、やがて赤ん坊がするように傷を吸い始めた。ちゅうちゅうと吸い取られ、
その唇の動きに腹の底の方が重くなる。擽ったいだけでない感情を抱いてしまう自分自身を律しようと大きく息を吸うと、口を離したゼンが顔を上げた。真っ直ぐに見てくる瞳と唇が、絵の具を塗ったように赤い。
「……ごめん、なさい」
ゼンの濃い下睫毛が濡れ始める。瞳の色は漆黒に戻っていた。
握っていたタオルでゼンの唇を拭ってやると、瞑った瞳から涙が一粒零れた。
同情をしないわけではない。
生物の血を取り込まないと生きられないなんて、その対象となる我々人間の脅威であり、架空のもとと遠ざけたいほど気味の悪い存在だ。他に姿を露わにしている吸血鬼がいるのかどうかは知らないが、正体を隠しながら人間社会で生きるのは苦労することだろう。
それでも人間よりも欲深く生を求め、それを得る力を持ち、人間を魅了する美しさを持つ。
それが『吸血鬼』、らしい。
図書館から借りた本からの受け売りだが。
しかし、ゼンには何故か生きる気力がない。鋭い犬歯もなく、備え持っている筈の魅了の性質もない。唯一あるのは、唾液に治癒成分が含まれているという特殊体質だけで、身体能力が高いわけでもないようだ。血を飲まなければ死ぬのに、飲みたくないという。
気付くとケロイド状の瘢痕だけを残し、二の腕の傷は無くなっていた。
「もうやめてよ。放っといて」
ゼンが黒いパーカーの袖で目元を擦った。少女の姿の吸血鬼は濡れた声で続ける。
「死にたいの。もう嫌なの」
たった六畳の部屋が湿っていく。
血塗れになったタオルを座卓に放り投げ、ゼンの小さな頭に手を乗せた。俺よりも低い体温が手の平から伝わる。
人間と変わらない姿かたち。
ゼンは吸血鬼だが、目の前で命が失われるのを見過ごすのは気が引けた。その辺でミミズが干乾びようとしているのを見るのは何てことはないというのに、人間に似ているというだけで情が湧く。ただ、それだけの理由で拾ってきた。
「せっかく助けてやったのに、そんなこと言うな」
思ったより不機嫌なそうな声が出た。伸ばしていた手を、ゼンの頭から頬に滑らせる。涙の跡を拭き取るように動かすと、ゼンは微かに身動ぎをした。
「別に出て行くななんて言ってない。嫌なら逃げればいい」
ゼンは恨みがましそうに俺を見て、再び三角座りをして、に顔を下げた。
俺は立ち上がり、畳を踏みしめ、通学用の鞄から英語の教科書とノートを取り出した。座卓に乗っているタオルを退かし、教科書類をそこに広げる。携帯で時間確認すると、21時を回ったところだった。
「もう寝るなら電気消すけど」
教科書を捲りながら問う。「寝ない」と離れたところから聞こえたのを確認してペンを走らせた。
ゼンが眠る姿を見たことがない。寝ているのかどうかも分からない。そもそも睡眠が必要な体ではないのかもしれない。死にたくて体を痛めつけているのかもしれない。
本人が何も喋らないので真相は分からない。
「マヤ」
ふいに名前を呼ばれて視線を上げた。大きな瞳がこちらを向いていた。
「あなたの血は美味しい」
言いながら首を傾げる様子に、同じように首を傾けた。疑問形なのかそれは。
彼女のことは、いまだに知らないことだらけだ。
知っているのは『死にたがりの吸血鬼』であるということだけ。
それ以外は何も知らない。